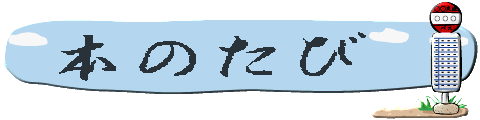
☆ 本のたび 2025 ☆
学生のころから読書カードを作っていましたが、今時の若者はあまり本を読まないということを聞き、こんなにも楽しいことをなぜしないのかという問いかけから掲載をはじめました。
海野弘著『本を旅する』に、「自分の読書について語ることは、自分の書斎や書棚、いわば、自分の頭や心の内部をさらけ出すことだ。・・・・・自分を語ることをずっと控えてきた。恥ずかしいからであるし、そのような私的なことは読者の興味をひかないだろう、と思ったからだ。」と書かれていますが、私もそのように思っていました。しかし、活字離れが進む今だからこそ、本を読む楽しさを伝えたいと思うようになりました。
そのあたりをお酌み取りいただき、お読みくださるようお願いいたします。
また、抜き書きに関してですが、学問の神さま、菅原道真公が49才の時に書いたと言われる『書斎記』のなかに、「学問の道は抄出を宗と為す。抄出の用は稾草を本と為す」とあり、簡単にいってしまえば学問の道は抜き書きを中心とするもので、抜き書きは紙に写して利用するのが基本だ、ということです。でも、今は紙よりパソコンに入れてしまったほうが便利なので、ここでもそうしています。もちろん、今でも、自分用のカードは手書きですし、それが何万枚とあり、最高の宝ものです。
なお、No.800 を機に、『ホンの旅』を『本のたび』というわかりやすい名称に変更しました。最初は「ホンの」思いつきではじめたコーナーでしたが、こんなにも続くとは自分でも本当に考えていませんでした。今後とも、よろしくお願いいたします。
No.2499『雑草は踏まれても諦めない』
この本は、今年の大人の休日倶楽部パスを利用して出かけたとき、読む本がなくなり、近くの本屋さんで買い求めた1冊です。ですから、自宅に帰ってくると、読みたい本がたくさんあるので、つい後回しになってしまいました。
そろそろ年末なので、1年の部屋のほこりを掃除しようと思い、これを見つけ、今年求めた本は今年のうちに読んでみようと思ったのです。
このような植物関係の本はいろいろと読んでいて、この本に書かれている内容も、どこかで読んだようなものも載っていました。それでも表現が違ったりすると、これはおもしろいと思って、改めて植物のすごさを感じました。
たとえば、パイオニアプランツについての説明で、「何でもそうだが、1から2を作ることよりも、ゼロから1を生み出すことのほうがはるかに難しい。パイオニアプランツが進出する不毛の大地も決して生存に適しているとは言えない。土は固く、根の成長を妨げる。水や栄養分も十分ではない。しかし、パイオニアプランツたちは様々な知恵を発達させ、その環境に挑んできた。これらの植物が根を張ることで土は細かくなり、通気性や保水性が改善されていく。枯死した茎や葉は分解されて肥料になり、土を豊かにしていく。そして、そこには次第に多くの昆虫や小生物が棲みつき、土地はだんだんと豊かな土地になっていくのである。しかし、不毛の土地を開拓したパイオニアたちは、そこに自分たちの楽園を築くことはできない。雑草たちの繁栄は長くて数年である。豊かになった土地には、次々と力のある植物が侵入して、パイオニアたちは追いやられてしまうのである。」と書いてあります。
たしかに、道路を造るために新しく切り拓いた斜面などは、最初は土だけしかないのに、年ごとにいろいろな草たちが入り込み、いつしか土が見えなくなってきます。最近は、最初から網をかぶせて、斜面に強い草などの種を蒔くこともありますが、それだってほとんどが雑草です。
これを初めて知ったのは50年ほど前で、シャクナゲを始めたころに、シャクナゲの青々とした葉にシラカバの白い幹は目立つだろうなと思い、北海道からシラカバの種を取り寄せ、実生をしました。その小苗を小町山自然遊歩道のあちこちに植えましたが、最初のうちこそ元気でしたが、だんだんと他の植物たちに負けてしまい、今では数本しか残っていません。さらに、シラカバの根は横に伸びるらしく、シャクナゲの浅根とかち合ってしまい、良くないと後から知りました。若い時は、見た目が先行しますが、後からいろいろと知ってくると、なるほどと思うことがあります。
また、植物には少しずつストレス耐性をつけることが知られていて、「植物には「ハードニング」と呼ばれる作用がある。これは、ストレスを受けることによって耐性がついていくことを示す。植物の体は多くの水分を含んでいるため、突然気温が零度以下になると、体内の水分が凍って大きなダメージを受けて枯れてしまう。しかし、ここでハードニングが機能する。徐々に寒さを経験していった植物は、冬季の低温下でも耐凍性を発揮するのである。強い一撃を一気に受けると耐えることはできないが、弱い一撃を少しずつ受けることによって、厳しい環境に対する耐性を獲得していくのである。人間が負荷をかけた筋肉が発達することによって強くなるのと同じである。」と書いてあります。
そういえば、高山植物を見ると、背が低く、葉なども厚い毛などで保護されています。特に印象に残っているのは、ブータンに行った時に出合ったノビレ・ダイオウで、外側を包むような苞葉には有害な紫外線を吸収するフラボノイド色素があるといいます。そして、葉緑素はなく、透けるような半透明なので太陽光を通し、内部は外気温より5℃シーほど高いそうです。そこに花を咲かせるのです。ここは温かいので、虫たちも寄ってくるので、花粉も媒介できます。現地では、これを生のままでも食べるそうで、小さいときに食べたスカンポのような味がしました。
このときに採取してきた種を帰国してから蒔くと、芽が出てきました。しかし、花が咲き、種子が実るとその株は枯れてしまうそうで、今でもそのまま花を咲かせずに鉢植えになっています。
下に抜き書きしたのは、第4章「雑草と生きる」に書いてあった雑草学者のベーカーさんの「理想的な雑草の特徴」です。
よく読むと、これが人間の生き方にも相通ずるものがあるように感じたので、ここに載せることにしました。たかが雑草ですが、されど雑草です。もともとは、雑草という分類は、植物額にはないようです。この本に、ニンジン畑にジャガイモが生えたら、それは雑草かという話しが載っていました。たしかに、ニンジンだけを育てようとすればジャガイモは邪魔なものになりますから、雑草といえなくもありません。しかし、ニンジンだけでなくジャガイモも収穫できればこれもいいと考えれば、雑草ではなくなります。
つまり、人間が雑草と思えば雑草になり、この植物の花もきれいだから育てようとすれば、それは雑草ではなくなります。つまり、「雑草とは人間が雑草扱いしてはじめて雑草となる」というわけです。
今年はの本を読んで終わりですが、来年も雑草に負けないような強い生き方をしようと思っています。良いお年をお迎えください。
(2025.12.31)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 雑草は踏まれても諦めない(中公新書ラクレ) | 稲垣栄洋 | 中央公論新社 | 2012年10月10日 | 9784121504326 |
|---|
☆ Extract passages ☆
1 種子に体眠性を持ち、発芽に必要な環境要求が多要因で複雑である
2 発芽が不斉一で、埋土種子の寿命が長い
3 栄養成長が速く、速やかに開花にいたることができる
4 生育可能な限り、長期にわたって種子生産する
5 自家和合性であるが、絶対的な自殖性ではない
6 他家受粉の場合、風媒かあるいは虫媒であっても昆虫を特定しない
7 好適環境下においては種子を多産する
8 不良環境下でも幾らかの種子を生産することができる
9 近距離、遠距離への巧妙な種子散布機構を持つ
10 多年性である場合、切断された栄養器官からの強勢な繁殖力と再生力を持つ
11 多年性である場合、人間が攪乱する範囲より深い土中に体眠芽を持つ
12 種間競争を有利にするための特有の仕組みを持つ
(稲垣栄洋 著『雑草は踏まれても諦めない』より)
No.2498『ハツカネズミと人間』
だいぶ昔、ジョン・スタインベックの小説を読んだことがありますが、今ではほとんど覚えていません、かろうじて「怒りの葡萄」だけは印象に残っています。
この本は新訳ですが、この前に大門一男さんや大浦暁生さんの訳もあるそうです。最初に出版されたのは、1937年2月で、その翌々年の4月14日に「怒りの葡萄」が出版されました。出た当時は、戯曲化もされ、ニューヨークのブロードウェイで上演もされたそうです。
ということは、高く評価されたようで、だからこそ、今でも新訳が出てくるのだと思いますが、時代背景としては1937年は大恐慌時代で、フランクリン・ルーズベルトがニューディール政策を掲げたときでもあります。日本では、この年に発生した支那事変が、それからの日本に暗い影を落としたときでもあります。
この本は小説なので、抜書きすることはなるべく控えますが、毎回、「Extract passages」に抜書きしているので、それだけはご理解ください。
主人公はジョージとちょっと間抜けなレニーの話しです。場所の設定はカリフォルニア州モントレー郡ソルダード付近で、労働者として農家で働くコンビです。レニーはハツカネズミだけでなく、ウサギやすべすべした可愛いものが好きで、有り余る体力でいじり回すので、つい殺してしまいます。そこからいろいろな問題が起こり、ついには農場から逃げてしまうことになります。
日にちにすれば数日程度ですから、これが戯曲化されれば、どのような舞台設定がされるのか、ちょっと興味があります。
素人目にしても、インパクトのある内容ですから、見応えのあるものになりそうです。もし、機会があれば、ぜひ見てみたいと思います。
文庫本で180ページほどですから、機会があれば読んでもらいたいと思います。時代的には古い昔のアメリカですが、このような時代を経て、今のアメリカがあると思えば、それなりに有意義ではないかと思うんです。
下に抜き書きしたのは、第4章に出てくる黒人の馬屋番、クルックスの話しです。
そういえば、マザー・テレサは、「人から声を掛けられない、話し相手がいないほど寂しい事はない」とよく話されたそうです。また、「人は貧しさを体験しなければ、本当の奉仕は出来ない」とか、「裸の人に衣服を着せる時は、人間としての尊厳を着せてあげましょう」とか、いろいろな言葉を残しています。
だいぶ昔、カルカッタ(現在はコルカタといいます)に行ったときに、ぜひ会いたいと思い、訪ねたことがあります。
ただ、残念なことに、外国に出かけているとのことでしたが、その道の途中で見かけた癩病に罹って手先に巻いた包帯に血膿がにじんでいるのを見て、あらためてすごいことをしていることを実感しました。
(2025.12.28)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| ハツカネズミと人間(講談社文庫) | ジョン・スタインベック 著、齊藤 昇 訳 | 講談社 | 2023年9月15日 | 9784065327319 |
|---|
☆ Extract passages ☆
「所詮これは黒い奴のぼやきさ。それも、俺のように背骨が潰れて背中が曲がった黒い奴のな。だから、何の意味もねえ。わかるか?まぁ、いずれにしても、アンタは覚えねえだろうが。そういうのはしょっちゅう見てる――1人の男がもう1人の男に話すけど、相手が耳を傾けていなくても、それを埋解していなくても、構わねえんだ。大事なのは、そいつがもう1人と話をしてるという事実だ。別に話してなくても、一緒にそこに座ってるだけでもいい。どっちでも同じこった、なあ、そうだろ」彼は次第に気持ちを高ぶらせて、思わず片膝を叩いた。「まぁ、ジョージはアンタに、くだらねぇことを話すかもしれんが、そんなことはどうでもいい。大事なのは、話してるってことだ。傍にそれを聞く相手がいるということなんだよ。それだけでいいんだ」そう言うと彼は口をつぐんだ。
(ジョン・スタインベック 著『ハツカネズミと人間』より)
No.2497『言葉にすれば願いは叶う』
副題は「私に勇気をくれる英語フレーズ」で、著者はアメリカのマウント・ホリヨーク大学を卒業後、通信社やNPOなどに勤務し、フリーランスの同時通訳者だそうです。そして、2010年にコロンビア大学でコーチングの資格をとり、さらには2023年に倉敷市の大原美術館の理事に就任したそうです。
私も、だいぶ前から黙って実行することもいいかもしれないけど、ある意味、言葉にして誰かに伝えることも大切だとよく話します。たとえば、今年の6月下旬から津軽三十三観音札所詣りに行ったのですが、今年はクマが出るかもしれないと思い、距離的に一番大変で山のなかの第25番札所の梵珠山松倉観音堂は今回は諦めようと思っていましたが、たまたま青森の方がいらっしゃって、しかもその札所の近くということで、話しをして、一緒にお詣りしました。これなどは、話してみないことには、できないことでした。
この本のなかで、ロバート・ケネディが、
Some men see things as they are and say,Why.
I dream things that never were and say Why not.
(人は物事を見て"Why"というけれど、私はこれまでに起こりえなかったことを夢見て"Why not"と言う)
「これは、アイルランドの劇作家であり思想家のジョージ・バーナード・ショーの言葉を、ロバート・ケネディが引用したものだそうです。ケネディはこの言葉を通して、厳しい現実はあるけれど、"why(なぜだ|どうして、こんなことになるんだ!)''と嘆くよりも、いまだ成し得ていなe「夢」を描いて、"Why not(なぜそうならないと言えるのだ?"というメッセージを伝えたかったのだと思います。」と書いています。
つまり、思い通りにならないことを、これからの目指す目標にしてしまうような態度こそが大切だと思います。
また、この本には、旅を意味する"travel"と"journey"の違いも出ていました。「"travel"は、物理的に場所を移動するという意味が強いのに対し、"journey"は、旅のブロセスやそこで得られる経験などの中身に重きを置くニュアンスを持ちます。……"journey"の語源は、「日記」や「記録」を意味する"journal"だそうです。そう考えると、「旅」を表す言葉であっても"journey"は「物理的な移動」より、旅で得る経験や旅の中身のニュアンスが強い、というのが何となくしっくりきます。」といいます。
これを読むまでは、"travel"のほうが"trouble"に近いので冒険的な意味合もあるのかなと思っていましたが、それは違うようです。そういえば、関野吉晴さんの「グレートジャーニー 人類5万キロの旅」などを読んでみると、やはりこの本の解釈のほうがしっくりきます。
そういえば、よくポジティブとかネガティブというような話しをしますが、それを実験で確かめた人がいるそうです。「人為的に楽観的な気持ちと悲観的な気持ちをつくり出すために、被験者に楽しい映画、悲しい映画を見せたあと、1.新しいアイデアを出す作業、2.緻密で正確さを要する作業、をそれぞれやってもらったそうです。楽しい映画を観て気持ちが明るく楽観的になっている時は、アイデアはたくさん出る一方、緻密な作業にはミスが頻発したそう。逆に、悲しい映画を観て悲観的な気持ちになっている時には、アイデアはなかなか出てこないけれど、正確さを求められる作業ではミスが少なかったというのです。人が楽観的であるか、悲観的であるかというのは、その人の特性であると同時に、その時の気分によっても変化するというのは興味深いところです。楽観的、悲観的のどちらが良いということではなく、作業内容によつてそれぞれの特性が活かされるという話には何か安心感を覚えます。そして人の特性は後天的に変えられる部分も多く、気持ちで変化するというのも、言われてみれば納得です。」とあり、よくもって生まれた性格のように考えられがちなのですが、これは後天的なもので、いくらでも変えられると聞けば、そのほうが悲観的にならずにすみそうです。
下に抜き書きしたのは、第2章「願いを叶える言葉」のなかにあったものです。
アンドレアス・ハイネッケは、ジャーナリストですが、その同じ職場に目の見えない同僚がいたそうですが、とても優秀な人だといいます。ある日、突然停電が起こり、真っ暗な中でみんながパニックになったとき、彼だけは落ち着いてみんなを導き助けたのだそうです。
それをヒントにして生まれたのが、この「タイアログ・イン・ザ・ダーク」です。
もう、1週間もすれば新しい年を迎えます。来年は、この"The sky ls the limit"を肝に銘じ毎日を送りたいと思いました。
(2025.12.25)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 言葉にすれば願いは叶う | 田中慶子 | 婦人之友社 | 2025年5月15日 | 9784829210758 |
|---|
☆ Extract passages ☆
ダイアログ・イン・ザ・ダークを訪れた人は、暗闇が服装や持ち物、年齢や肩書などの情報を取り払ってくれるからこそ成り立つ、対等なタイアログ(対話)の楽しさを知ります。……
ハイネッケの口ぐせは、"The sky ls the limit"。これは英語で時々聞く表現で、直訳すると「空が限界」です。空は果てしなくどこまでも続きます。「空が限界」とは、「限界なんてない。何でもできる!」という意味なのです。
(田中慶子 著『言葉にすれば願いは叶う』より)
No.2496『AIに看取られる日』
この題名を見て、さらにお医者さんが書いたと知り、読んでみたくなりました。副題は、『2035年の「医療と介護』で、あと10年ほどでAIが医療の現場にも入り込んでくるというのです。
でも、考えてみれば、現在でも患者さんに向かうより、パソコンの画面に向かっている医師が多いと聞くし、そこにはいろいろな情報が書いてあり、すでにある程度のAIの利用もあると思います。たとえば、薬の情報などでも、診察結果からAIがたくさんの薬のなかから絞り込んでくれれば、判断もすみやかにできそうです。あるいは、薬を使いすぎる場合などは、それを制限するように働くこともありそうです。
だとすれば、AIをそんなに目の敵にしなくても、使っていけばいいと私は思います。ただ心配なのが、最近多くなったマルウェアなどの脅威です。もし乗っ取られれば、治療どころではなくなり、個人情報まで盗まれてしまいます。人間のつくったものに絶対ということはないので、限りなく安全で心配のないシステムが必要です。この本にも、自動運転の車の話しが出てきますが、たしかに流れはそのように進むのかもしれませんが、これも同じことで、限りなく安全であることが前提です。
もちろん、医療や介護においても、同じことです。この本では、「2035年には、AIは日常的な介護業務の大部分を人間よりも正確かつ効率的に担うようになると思われます。食事の準備、服薬管理、排泄の手伝い、そして夜間の見守り。現在、多くの人手を要しているタスクが、自律型ロボットやAIシステムによって行われます。AIは狭義のバイタルデータ(体温、脈拍、血圧など)だけでなく、顔の表情や声のトーン、身体の微細な動きから、利用者の感情や精神状態を読み取り、適切なタイミングで声かけをしたり、サポートを提供したりできるようになるのです。特に「看取り」の局面では、AIが多岐にわたる役割を果たす可能性があります。AIは、患者さんの過去の医療記録、生活習慣、心理状態、そして家族との関係性などの膨大なデータを解析し、残された時間をより豊かに過ごすための最善のサポートを提案するでしょう。」と書いてあります。
たしかに、これらの流れは後戻りできないことのようですが、それでも、ほんとうにそのように進んで行っていいのかと思います。そういえば、だいぶ前の話ですが、ある個人医院にいったときに、たいしたことのない病気でしたが、診察の後に薬を処方する段階で、透明なファイルに薬の説明書が入っていて、それを見ながら、どれにしようかという感じで見ていたことがあります。おそらく、間違いのないようにという思いからのことでしょうが、ちょっと不信感を感じました。
そういう場合などには、AIが最適な薬をあっという間に選んでくれたほうが信頼感はあります。あるいは、つい惰性で毎回同じように薬を出されるよりは、その都度、しっかりと判断して出してくれれば、そのほうがいいと思います。
そういえば、「医師の診断精度は経験や知識に左右されます。しかし、AIは膨大なデータから学習し、常に最新の医学知識を取り入れます。疲労や感情に左右されず、昨日飲みすぎたとか、恋人と喧嘩して落ち込むことも(まだ)ありません。24時間、365日安定した診療を提供できるのです。もちろん、医療にはAIだけでは代替できない人間的な側面も存在します。しかし、診断や治療計画といった領域では、AIがその能力を最大限に発揮するでしょう。AIが医師の「道具」から「パートナー」へ、さらには「主役」へと変化していく過程は、すでに始まっているといっていいでしょう。」とあり、素人としては、AIが補助役ならいいけど、主役になれば、ちょっと嫌な感じがします。
ただ、この後に書いてあるところを読むと、むべなるかなと思いました。現在の医師不足や地域の不均衡など、さまざまな問題を抱えながら、ほとんどがそのままの状態になっています。AI診療なら、地方の小さな医院でも、名医といわれる医師の診断を受けることも可能になります。あるいは、遠く離れたところから、手術することもできます。そう考えれば、それもいいことだとは思います。
下に抜き書きしたのは、第4章「AIは医療問題を解決するか」に書いてあったものです。
まさしく、上で取り上げた問題で、これからはこれらを抜きに医療問題を考えることはできないと思います。
ただ、すべてをAIに任せきることは当分はできないし、生身のお医者さんでないと対応できないこともあります。その間のところに、進むべき道はありそうな気がします。
(2025.12.22)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| AIに看取られる日(Asahi Shinsho) | 奥 真也 | 朝日新聞出版 | 2025年9月30日 | 9784022953346 |
|---|
☆ Extract passages ☆
AI技術を活用して保険診療の効率化を図り、医師一人あたりの診療能力を飛躍的に向上させることで、現在の医師不足問題を根本的に解決すべきです。保険診療で扱う範囲をいまよりもシンプルにし、AI診断支援で質の高い医療を効率的に提供する。そうした新しい医療制度への転換こそが、日本の医療の未来を切り拓きます。
美容外科などの自由診療については、社会的に必要な医療分野への人材確保を阻害しない範囲で、適切な規制のもとで運営されるべきでしょう。
(奥 真也 著『AIに看取られる日』より)
No.2495『作家とランチ』
この本は、もともと「日本児童文学」の2023年1・2月号から2024年11・12月号に連載された「作家とLunch」の12編のインタビュー記事に書き下ろしの2編を加えたものだそうです。
だから副題が「インタビュー・児童文学の13人」で、日本児童文学者協会の編になっています。この本を読んではじめて知ったのですが、児童文学というのは絵本などばかりではなく、けっこう裾野が広いと思いました。
この本の「解説」で日本児童文学者協会理事長の藤田のぼるさんは、「児童文学というジャンルは、大人の書き手が、子どもの言葉で子どもに向かって(その意識のレベルは様々だとしても)物語を提出する、という、ある意味不思議なジャンルです。ひこ・田中さん風に言えば、「変態」ということになりますが、そこでひこさんも語っているように、まさに「それによってしか見えてこない世界」というものがあり、そこに惹かれて、それぞれの書き手が作品世界を紡いでいるのだと思います。」と書いています。
そういえば、わが息子の1人が、那須正幹さんの「ズッコケ三人組」という本を好きで、たしか全巻読んだと思います。私は大事にしている本だと知っていたので、まったく読まなかったのですが、今思えば、借りて読んでみたかった思います。
また、山形出身の最上一平さんのインタビューに出てくる筋ジストロフィー症の子どもと友だちとの関係などは、児童だけでなく、大人にとっても大切な関係のような気がします。身障者と健常者というだけでなく、そこには人と人との関係性もあり、とても大切なことだと感じました。それは、「じつは筋ジスを患っている子が今住んでいるところの近くにいたんです。あるとき、その子と何人かの友だちが学校から帰ってくるところを見たことがあるんですね。その子のカバンをほかの子が持ってあげたりしていましたが、見ている限り、周りの子がお世話をしているという感じではありませんでした。わいわい騒ぎながらそれぞれ楽しそうにして歩いていて、その関係っていいなと思ったんです。それで、自分なりにどんな友だち関係が作れそうか考えてみました。なんでもその子の思いを優先していくような関係だったら、おもしろくないし、友だちとしてうまくいかないと思います。そうかといって、病気のことをまったく無視することができるかと言ったら、それも無理なことです。」と書いています。
よく、健常者と身障者との関係性が話題になることがありますが、子どもならそれらを気にせずに成り行きに任せるようにしているようです。それが自然だし、大切なことだと思います。
それは子どもだからこそで、大人になってからだと、つい構えてしまいがちです。
そういえば、書いたものでも、もし間違っているかもしれないとか、もっていい表現があるかもと思いがちです。私は原稿を頼まれると、サッと書いて、しばらく寝かせておいてから、〆切のまえにもう1度見なおすことをします。
これは作家の方も同じようで、内田麟太郎さんは、「ほんとうは、書いたものをすぐに発表するのは、恥ずかしいんです。全部が成功作ならいいんだけど、なかには書いてすぐに直したいなと思うものもあって。実際、直すこともあるしね。だけど、この恥を引き受けないと、行きたいところには行けないから。子どもの遊びがそうでしょ?失敗するかもしれないから今日は野球しなぃ、じゃなくて、絶えずやっていく。そのなかで少しずつ目標ににじり寄っていく。そんなに力まず、書いていけばいいんじゃないかと思いますね。」といいます。
そうか、「子どもの遊び」だと思えば気楽だし、ダメだったら、次に少しでもいいものを書けばそれでよしと思えば、何ごとにもチャレンジできそうです。先ずは、やらないよりやってしまう、それがもしいいものではなかったとしても、次は少しでもいいものを書こうと思えばそれでいい、とこの話を聞いて納得しました。
下に抜き書きしたのは、第6回目の令丈ヒロ子さんのところに出てきた話しです。
おそらく、何かを創作したいと思うと、必ず突き当たる問題が、このオリジナリティということです。既に誰かが書いているのではないかとか、何となく誰かの真似をしているのではないかと不安になります。
私は写真をよく撮るのですが、同じ場所から同じ季節にとっても、まったく違うものにしか写せません。というのは、気象条件、とくに太陽の光りなどは刻々と変化しますし、むしろ同じに撮ろうとしてもできません。毎年同じ花を撮っても、撮るたびに新たな発見があります。だから楽しいのです。
そういう意味では、科学論文とは違うので、自分が書きたいと思うように書き、撮りたいと思うように撮ればいいと私は思っています。
(2025.12.19)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 作家とランチ | 日本児童文学者協会 編 | りょうゆう出版 | 2025年10月23日 | 9784910675091 |
|---|
☆ Extract passages ☆
私が美術大学で教えている学生にはオリジナリティの呪いにかかっている人がけっこういるんです。読んだもの見たものから影響を受けるのが怖いとかね。彼らに言うんです。どんなものを作ってもあなたという人のオリジナルの作品であることに間違いはないのだから、影響をどんどん受けるといい。ありきたりになるのも怖がらないでいいって。それから落ち込むことは大切だって。一度とことん落ち込んだ方が、早く現実に向き合えるんじやないかなって思います。
(日本児童文学者協会 編『作家とランチ』より)
No.2494『人生後半にこそ読みたい秀歌』
俳句も好きですが、たまには和歌や短歌を読んでみたいと思っていて、たまたま目にしたこの本を読むことにしました。
この本は、もともとは「一冊の本」の2022年4月号から2024年3月号まで掲載したものに、さらに「中年は人生後半への入口」を書き下ろし、大幅に加筆し配列も変えたそうです。たしかに、読んでいて流れがよくわかり、楽しめました。
この本のなかで、「年齢を意識するとき、今日の自分は、これまででいちばん齢をとった自分だと思うか、今日の自分は、これからの自分のなかでいちばん若い自分だと思うか、」という話しがありましたが、私は今日の自分をいつも中心に考えています。つまり、今の自分が若いと思っているということです。
そういえば、1ヶ月ほど前の大祭の挨拶で、私はまだまだ若いという話しをしました。これは考え方次第ですが、100歳の方から比べればまだまだ若いというのは間違いない事実です。どっちみち、誰にも迷惑をかけることもないので、若いと思っていたほうが元気でいられます。
永田 紅という歌人が『日輪』という歌集のなかに、「人はみな馴れぬ齢を生きているユリカモメ飛ぶまるき曇天」という歌があるそうです。
この歌は、作者がまだ二十歳のころの作品だそうですが、たしかに、人というのは自分の年齢に慣れないうちに、確実に年を重ねていきます。だから、馴れない齢を生きるしかないわけで、この歌は心に染みいかのように感じました。
私が二十歳のころのことを思い出すと、年齢のことなどほとんど考えたこともなく、毎日毎日をただ楽しく暮らしていたように思います。それでも、No.2492『本が生まれるいちばん側で』に書いたように、詩などを少し書いたりすると、今の状況だけでなく、将来のことなどを考えたときにそれらしいことを考えたこともあります。
そういう意味では、歌とか詩などをつくるというのは、自分の人生を考えるきっかけにはなると思います。
それから年齢を考えるのは、大きな病気などをしたときです。現在、病気のなかで怖いものはガンのようで、早めに見つかれば大丈夫だとはいわれても、やはり怖いです。このガンですが、漢字で書くと「癌」で、その使い分けが書いてありました。私もわからなかったので、ここに載せますと、「身体の表面や胃や腸を始めとする各臓器の表面を覆っている細胞を「上皮細胞」と呼びます。この上皮細胞に発生する悪性腫瘍を「癌」、正式には「癌腫」と呼びます。一方、骨や筋肉、脂肪組織などにできる腫瘍は、骨肉腫、平滑筋肉腫など、「肉腫」と呼ばれます。また自血病や悪性リンパ腫など血液系細胞に発生するものを「血液がん」と呼びます。本来、漢字の「癌」は上皮組織の腫瘍にのみに用い、ひらがなの「がん」は、悪性腫瘍全体を指すときに用いるとされているのですが、一般社会ではこの区別はほとんど知られていないでしようし、使い分けられてもいないようです。」と書いています。
著者は、さすが細胞生物学者ですから、その使い分けははっきりとしています。
また、私の興味は、この本のなかの旅についての歌にもありました。私はどちらかという旅、それも一人旅が好きですが、この本には、「人はなぜ旅に出たいと思うのか。もちろん知らない土地を訪れて、これまでにない体験をしたいという欲求もあるでしょうが、単なる物見遊山以上の意味もあるでしょう。世界が一冊の本なら、旅行をしない人はその1ページ目しか読まないようなものだなどという言葉もあったような気がしますが、日常世界の狭さを開け放ち、大きな視野と世界を開いてくれるものとして、旅は人生に大きな意味を持ち、また楽しみを与えてくれるものでもあります。」とあり、なるほどと思いました。
たしかに自分の目で見てみたいとか、珍しいものを食べてみたいとか、いろいろな理由はあるでしょうが、私にとっても旅は大きな意味のある行動だと思っています。そして、自分が年を重ねて、まったく動けなくなったとしても、その旅に出かけたときのことを思い出し、楽しめるのではないかと今から想像しています。
下に抜き書きしたのは、第2部「老いの先へ」の「孤のなかに己を見る」に書いてありました。
たしかに、生まれてくるときもほとんどの人はひとりですし、亡くなるときは間違いなくひとりです。でも、これはみなわかっているはずですが、いざ亡くなる前になるとどう思うかはわかりません。
そういう意味では、年を重ねるとボケますが、それは亡くなる先のことを思い煩うことがないようにとの計らいかもしれません。つまり、人間というのは、うまくできているような気がします。
(2025.12.16)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 人生後半にこそ読みたい秀歌 | 永田和宏 | 朝日新聞出版 | 2025年4月30日 | 9784022520517 |
|---|
☆ Extract passages ☆
どっちみちどちらかひとりがのこるけどどちらにしてもひとりはひとり
夏秋淳子 朝日歌壇 2023・12・10
この作者はすでに伴侶を亡くしている。先立たれて、いまはひとりぼっち。日々、連れ合いのいない寂しさを痛感しない日はないが、しかし、とまた考えるのです。二人居るのが伴侶なら、夫婦は最後は、「どっちみちどちらかひとりがのこる」以外ないのだ、と。いまは残された者として、自分がひとりの寂しさを託っていますが、逆だったら夫が自分と同じ寂しさを感じていたのだろうとも。「どちらにしてもひとりはひとり」生きていく以外ないではないか、とも思ったのでしょう。どこか箴言風な一首でもあります。
(永田和宏 著『人生後半にこそ読みたい秀歌』より)
No.2493『恋する文化人類学者』
文庫本にしては厚めで、ページ数も386もありました。それでも、なんとなく興味を引く題名だったので読み始めると、とてもおもしろかったです。
というのも、自分の体験から書いていることもあり、文化人類学者の書いてものとしては深くて、なかなか知ることのできない内容でした。そういえば、結婚式のときのカメラマンの立ち位置としては、私もカリマンタンのイスラム教の結婚式に参列したときに経験したのですが、「この部屋は「花嫁の部屋」と呼ばれ、そこにはいることができるのは花嫁と親族関係あるいは友人関係にある女性だけで、完全に男子禁制となる。例外はビデオ・写真撮影をするカメラマンで、思い出を映像。画像として残したいという欲求は伝統的慣習よりも強いことがよくわかり、なんとなくほほえましい。」と書いてあります。
私の場合は、カメラマンの立場で結婚式に出たのではなく、新郎の知人という立場なので、イスラム社会では見知らぬ男性が女性の写真を撮ることは厳禁です。ただ、そこにいたカメラマンより、ちょっとだけいいカメラとレンズを持っていたので、カメラマンから推薦され、両家の了解をもらえたのです。だから、日本でもおなじみの新婦が両親に別れの感謝と挨拶をしますが、それが式場の白い布に囲まれたところで行われます。だから、声だけは聞こえるのですが、その様子はほとんどわかりません。
すると、カメラマンから入れといわれ、その囲いのなかに入ると、新婦が父の膝元に頭をつけて泣きじゃくりながら別れを惜しんでいました。それでも、言葉がわからないので、あまり切迫感を感じないまま、写真をたくさん撮らせてもらいました。
それを見ていた参列の女性たちにも、結婚式の途中で写真を撮ってくれと頼まれ、途中でホテルの部屋に戻り電池を替えなければならないほど撮りました。後日、それらの写真を新郎側に送ったのですが、誰が誰なのかは、今もわかりません。でも、夢中で何時間も撮ったことだけは今も思い出します。
この本を書こうと思った著者の動機は、「人類の多様性を尊重したいからである。私はさまざまに異なる人々がいっしょに生きることをすばらしいと思う。肌の色、国籍、宗教、言葉、食文化、音楽……世界はあきらかに「違う」人々で満たされている。しかし各々は「同じ」民族や国民として集まろうとする。それ自体は至極当然なことである。だが異なる人々が集う場に身をおいてみたなら、その刺激的な雰囲気のおもしろさをわかってもらえるだろう。色も形もさまざまな顔。まっすぐだったり縮れていたりする髪の毛。ある者は民族衣装をまとい、ある者はジーパンにTシャツ。さまざまな言葉が頭上を飛び交うなか、ときには片言の、あるいはペラペラの外国語で、ときには身ぶり手ぶりでコミュニケーションをとってゆく。そんなとき、私は心地よい興奮に包まれる。」といいます。
たしかに、世界には、数え切れないほどの人たちがいて、いろいろな違いもあります。私自身も、どちらかというと辺境といわれるところに何度も足を運びましたが、そのたびごとに世界は広いと思いました。そして、たとえば、40年ほど前に訪れたブータンでは、宗教がしっかりと根付き、そのなかで生活をしていました。おそらく、今ではそうとうな変化はしたと思い、また行ってみたいと思いますが、その当時のまま心にとどめて置きたいと考えることもあります。
そういえば、海外に出かけるときには、ビザの問題がありますが、著者は奥様の「ニャマのビザ問題を通して、私はひとつのことを学んだ。人は内体をもち、肉体には魂が宿り、心を通して喜びや悲しみを感じる。このレベルにおいてすべての人は平等である。いっぽう現代の世界においてすべての人は原則としてひとつの国家に属すが、すべての国家は平等ではない。富や権力は先進国と呼ばれる一部の国々に偏っている。ビザの問題はこの不平等な上下関係を反映しているのだ。「上」対「上」では、たがいにビザは免除される。「上」から「下」へは、ビザは免除されるか、あっても簡単に取得できる。ところが「下」の人間が「上」の国家に入ろうとすると、ビザの壁が立ちはだかる。「人類」は平等とされるが、国家間の不平等を反映する「諸国民」はけっして平等ではない。」と書いてあり、日本人ではなかなかわかりないビザも問題もあることに気づかされました。
それでも、ネパールからインドに入国するときには、カトマンドゥのインド大使館で何時間も待たされて、数日後にビザをもらったことがあり、そのときのことを思い出しました。
下に抜き書きしたのは、第3章「声の文化、音の文化」に書いてあったものです。
この文章を見て、だからこそ、昔の社会がそのまま最近まで続いていたのではないかと思いました。たしかに、文字がなければ、伝える方法は、口伝えなどの声や音を使うしかなく、それだって長い時間のなかでは少しずつ変わっていくことも考えられます。
しかし、文字で残す場合は、施政者の一言で、急激に変化することもあり、まったく否定されることだってあります。
だとすれば、文化人類学者にとっては、アフリカという地域は古き文化を知るためには絶好のところのような気がします。しかも、そこで見初めた女性と結婚したとすれば、通りすがりの人には絶対に見せないものをありのままに見えると思います。そうでなければ、結婚だって認めないでしょう。しかも、結婚して子どもが生まれ、その成長を見届けるならば、異文化間結婚で多文化にいたる流れも体験したことで、それらも興味のあることです。
この本は、もともと世界思想社から『恋する文化人類学者 結婚を通して異文化を理解する』という題名で刊行されていたものを、文庫化することになり、補章「ラブ・ロマンスのゆくえ」が追加され、さらに楽しい読みものになったと思います。
(2025.12.13)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 恋する文化人類学者(角川ソフィア文庫) | 鈴木裕之 | KADOKAWA | 2024年3月25日 | 9784044008086 |
|---|
☆ Extract passages ☆
アフリカのほとんどの社会は文字をもたなかった。アラブ人が人口の大半を占める北アフリカ諸国ではアラビア文字を使うが、サハラ砂漠以南の黒人の国々、通称「ブラック・アフリカ」においては、 エチオピアのアムハラ社会のような一部の例外をのぞき、その歴史において固有の文字をもつことはなかった。このような社会を「無文字社会」(「むもんじしゃかい」と発音)と呼ぶ。アフリカでは植民地化の過程でフランス語や英語を通してアルファベットが普及し、独立後もおおくの国では旧宗主国の言葉を公用語としたため、公文書、新聞、雑誌などでフランス語や英語が使用されてい
る。タンザニアではアフリカの言語であるスワヒリ語を公用語としたが、その文字はローマ字表記とならざるをえない。
(鈴木裕之 著『恋する文化人類学者』より)
No.2492『本が生まれるいちばん側で』
じつは、恥ずかしながら、大学生のころに自分で詩集を出したくて、池袋の東武デパートのなかの書店に聞きに行ったことがあります。もちろん、自費出版しかないと思ってたのですが、それには学生にしてはとても高額だったこともあり、相談をしただけで終わってしまいました。
つぎは、コロナ禍のときで、ほぼ毎日、小町山自然遊歩道に行き植物の写真を撮っていたので、小さな写真集でも作ろうと思い、いろいろと調べると、しまうまプリントの「フォトブック」というのを見つけました。それだと1部からでも注文でき、スクエアサイズ、72ページで858円からでした。これだと手軽にできそうだと思い、3部頼むと、欲しいという方もいて、その次には20部にしました。
でも、それもコロナ禍が過ぎると、仕事も忙しくなり、それからは本を作ろうとは考えませんでした。むしろ、本が好きなので、自分専用の本のしおりをつくり、先月も雲南省の百花嶺で撮ってきた「コーヒーの花と実」というのが出来上がりましたが、今まで10種類ぐらいは製作しました。
この「本が生まれるいちばん側で」を読むと、本をつくる心構えから、実際の製作過程間で詳しく書いてあり、つくりたいという気持ちがふつふつと湧いてきました。この本には、『「自分のためにつくる本」はちがう。読者や社会は見ない。まず、とことん自分に集中する。自分の思い描くかたちに自由にまとめる。そして、だれかを食わせる必要もない。だから「売れそう」とか「目立ちそう」とか、ほかの本と比べて考える必要がない。マーケットを見ずに、自分の哲学や思想、世界観をピュアに表現し尽くすのみ。つまり、内容、タイトル、デザイン、仕様(本のつくり)、制作費、部数、売り方――自分の「こうしたい」だけが「正解」となる。だから多種多様で、個性豊かで、アイデンティティを詰め込んだユニークな本ができあがる。』と書いてあります。
つまりは、本の注文住宅のようなもので、わが家を建てるときも、設計士さんととことん話し合い、実際に建てるときでも建築士さんとも出来上がるまでとことん細部まで煮詰めました。そのおかげか、今でも不自由なところはほとんどなく、快適に暮らしています。最初は、直接、建築士さんにお願いして、設計の分を安くしようとも思ったのですが、今は、設計代や管理料を払っても、それ以上の効果があったと思ってます。
やはり、本をつくるといっても、素人ではわからないところも多く、紙を選ぶとしてもすごい種類があります。昔、絵ハガキをつくろうと思い、印刷屋さんにお願いしたら、先ずは紙を選んでくださいといわれ、すごい紙の見本帳をいただいたことがあります。もちろん、それを見ただけではわからず、結局はこちらの希望を伝え、印刷してもらいました。
そういえば、紙といえば、本をつくるにはとても大事な要素ですが、紙を見ただけではわからないことも多いようです。そこで、束見本といって、その選んだ紙を裁断し、製本して、どのような感じになるかを見てもらうのだそうです。
そうして実際の本の形が見えると、やはりそのモノを通して「好き・嫌い」がはっきりとわかるようで、ここで違和感を感じ、変更する方も少なくないそうです。
私もそうですが、頭の中で考えるのと、実際にモノとして見て触ってみるのとでは、まったく違います。これは大賛成です。
下に抜き書きしたのは、第3章『「できない」のない本づくりを実現するために』に書いてありました。
これはとても大切なことで、本を作るというのは、その人にとっては夢を実現すると同じことです。だとすれば、安い高いだけではなく、気持ち良くつくらなければ、意味がありません。
そのためには、もっともっといい写真を撮り、しっかりした原稿を書くようにしなければならないと、改めて思いました。
(2025.12.9)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 本が生まれるいちばん側で | 藤原兄弟 著、田中裕子 聞き手・文 | ライツ社 | 2025年9月23日 | 9784909044648 |
|---|
☆ Extract passages ☆
本づくりには、たくさんの人がたずさわっている。紙屋、インキ屋、製本会社、箔押しや型抜きなどをしてくれる加工会社……。印刷会社だけがんばっても絶対にいいものはつくれない。それぞれの持ち場で力を合わせて「一緒にモノをつくっている」という感覚があるからこそ、はじめてつくり手さんによろこんでもらえる。
じつはというか、藤原印刷は消して安い会社じゃない。「値下げ競争の輪に入らない」というのは決めていて、それは社員たちや協力会社のみなさんのがんばりを買い叩くようなことをしたくないからだ。
(藤原兄弟 著『本が生まれるいちばん側で』より)
No.2491『オランダは、「自由の国」だったか』
おそらく、『アンネの日記』を知らない人は少ないと思いますが、では読んだことがあるかといわれれば、図書館などであちこち拾い読みしたという記憶しかありません。この本を読んでから、ぜひ最初から読んでみたいとは思いました。
この「世界史のリテラシー」というシリーズも始めてで、NHKの「100分de名著シリーズ」は読みやすく、写真もあるので何冊か読み、今も持っています。読んで見ると、たしかにアンネ・フランクの生まれや育ち、どのようにして隠れ家生活をしたかとか、ドイツ占領下のオランダでユダヤ人が過ごしていたかいうことがよくわかります。それだけでなく、アンナと女優のオードリー・ヘップバーンが会ったということはなかったそうですが、同い年というだけでなく、オードリー自身が「アンネは私の魂の姉妹なのです」というぐらいの精神的なつながりがあると初めて知りました。
また、この本では、アンネのことだけでなく、オランダは本当に「自由の国・寛容の国」なのかや、小川洋子さんのアンネについての思いなどにも触れています。小川さんの著書は、「博士の愛した数式」など数冊しか読んではいないのですが、これは映画化もされたので、これは観ました。それらを考え合わせると、『アンネの日記』は世界中の方々に大きな影響を与えたということがわかります。
ナチスドイツ軍がオランダに侵攻したのは、1940年10月で、ドイツが1945年5月に降伏するまでの4年半の凄惨さ、特にユダヤ人にとっては生死をかけた一方的な迫害です。なぜオランダは、それをゆるしたのかということにもこの本は踏み込んでいます。
その隠れ家生活は、「アンネたちの隠れ家生活は、食べ物の買い出しと貯蔵に始まります。缶詰、油、バターなどを買い込み、少しずつ消費していくのです。1日の過ごし方も計画的です。各自に仕事を割り振り、自学自習、作業、料理などを次々こなしていきました。日課には柔軟体操もありました。」と書いています。
つまり、「他者と完全に切り離された生活を送ったわけではありません。協力者のオランダ人たちから仕事を依頼され、内職に励むこともありました。また、通信教育を受けて英語やフランス語を学ぶことで、学校の授業内容を補っていたのです。本は図書館から借りることができました。」ともあります。
だとすれば、この前のコロナ禍のときのヨーロッパなどの街全体のロックアウトと似たような状況だったと思います。日本の場合は、それよりも緩く、不要不急の外出は出来なかったけれど、リモートで仕事をすることもあり、サービス業は大きな影響がありましたが、それでもアンネのときのような精神的迫害までは感じることも少なかったと思います。いつ、誰が、急に強制収容所に送られ、殺害されるかわからないというような切迫した状況は、考えるだけでも恐ろしい時代です。
今、コロナ禍のときのことを思い出すと、孫たちは学校にも行けず、買いものも1人で出かけて家族6人分の食料などを買い込んでくると、山のようになります。しかも、図書館も閉鎖され、楽しみの読書も制限されたときには、困りました。
それでも、ナチスドイツ軍の侵攻で恐怖の生活を考えれば、比較にもなりません。その死を考えなければならない状況下で、小さな子どもたちだけでもなんとか強制収容所に送られる前に別な場所に隠そうという動きがあったそうです。そこはオランダ北部のスネークという都市で、複数の協力者がいたそうです。「このスネークで現地協力者の中核となったのは、キリスト教の聖職者たちです。しかもプロテスタント、カトリック双方の聖職者が積極的に協力したことが重要でした。信徒コミュニティを率い、地域社会で信頼を得ていた彼らは、現地のコーディネート役としてうつてつけでした。牧師、神父という役割上、彼らは地域社会のどこに誰が住み、誰が信頼できる人物かを知り抜き、潜伏場所を提供してくれそうな人物の目星をつけ、依頼してくれたからです。プロテスタントではメスダフ牧師、カトリックではヤンセン神父が代表格でした。」とあります。
これを読むと、日本の宗教家と違い、いかに聖職者たちが地域社会に溶け込んでいたかがよくわかります。もちろん、ここでも潜伏生活をせざるをえないわけで、その間の生活必需品や生活費なども定期的に届けなければなりません。もし子どもが病気をすることもありますし、それらさまざまなトラブルにも対処しなければならないので、相当な信頼関係がなければ続かないと思います。でも、それらを続けて支援したという話しを読み、それだけでもこの本を読んでよかったと思いました。
下に抜き書きしたのは、第4章「後世に与えた影響」に書いてあったものです。
これを読むと、今、現在もロシアによるウクライナ侵攻においても、なぜヨーロッパの国々がウクライナを支持し援助するのかがよくわかります。日本では、距離的に遠いだけでなく、第二次世界大戦後に一時的に占領されたものの、それほどの迫害を受けなかったからなのか、ヨーロッパの人たちとの温度差を感じます。
やはり、人間というものは、しっかりと謝罪し反省をしないと、思い切って前には進めないと思いました。
(2025.12.6)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| オランダは、「自由の国」だったか(世界史のリテラシー) | 水島治郎 | NHK出版 | 2025年10月5日 | 9784144073342 |
|---|
☆ Extract passages ☆
2020年1月、アウシュヴィッツ強制収容所が解放されて75周年を迎えたことを記念し、オランダ・アムステルダムにおける追悼式典が行われたさい、マルク・ルッテ首相が、はじめて公式にユダヤ人やロマ、シンティヘの迫害について、オランダ政府の過ちを認め、次のように謝罪を行ったのです。
「最後の生存者の方々が生きておられるうちに、本日私は、政府を代表し、当時の政府の行為につき、謝罪します。ホロコーストほど凄惨で酷いことを表現する言葉はないということをこの身に感じながら謝罪します」
ルッテ首相はこの追悼演説において、ほとんどの政府職員が「占領当局が彼らに求めたことを実行」したこと、政府のなかで抵抗した者は散発的にすぎなかったこと、その結果、政府機関が「法と安全の護り手」としての役割を果たすことができなかったと明言し、政府を代表して謝罪を表明しました。
(水島治郎 著『オランダは、「自由の国」だったか』より)
No.2490『古代人の教訓』
表紙絵が、いかにも古代エジプトのようで、副題が「視野が広くなる、世界最古の教え」と書いてあり、「仕事や日常の悩みに効果的! 人生に役立つ古代エジプト人の知恵」ともありました。
古代エジプトの遺跡は、行って見たことはありませんが、イギリスの大英博物館に膨大なコレクションがあり、2度ほど見たことがあります。よく、こんなにも大きな遺物を持ち帰ったと思いましたが、ひとつひとつに魅入ったことも事実です。
だから、この表紙絵を見て、読んだみたいと思いました。
この本を読んで、古代エジプトの人たちの教訓だとしても、今の時代も同じような問題があり、それら教訓が生かせるような気がしました。たとえば、「宰相プタハホテプの教訓」ですが、そこには「その男が名声ある人物の側にいるなら、たとえあなたがその男の昔の卑しい身分を知っていたとしても、その過去ゆえに軽蔑することのないようにしなさい。その男が得たものに相応しい尊敬の念を抱くべきです。富は勝手に向こうからやって来るものではないのです」というのがあるそうです。
このプタハホテプとは、古王国時代第5王朝の王イセシ(ジェドカラー)のときの宰相で、彼が老年にさしかかったのを基に、息子に語った37の格言だそうです。
それでも、今では考えられないような格差社会のなかで、このような話しが伝えられるというのは、やはり、これが正しい教訓だからです。いつの時代でも、卑しい身分だとしても、すごい努力をして上に立つ人はいます。日本でも、羽柴秀吉は日本を統一して太閤になったわけのですが、心の奥底に出自の悩みがあり、だからこそ、「その男が得たものに相応しい尊敬の念を抱くべき」だというのは確かなことです。
そして、今でもそうですが、「富は勝手に向こうからやって来るものではない」というのは、ある意味では真理に近いものがあります。だからこそ、後世まで残ってきたように思います。
また、『「夏がやって来た」などと言って浮かれるな。すぐに冬がやって来るのだから。夏の間に薪を集めておかなかった者は、冬に暖をとることができない者だ。(「アンクシェションクイの教訓」より)』なども同じで、イソップ物語の「アリとキリギリス」と同じような話しです。
そういえば、イソップ寓話集のなかに、「蝉と蟻」というのがあるそうで、これはおもしろいと思ったので、ここに引用します。
『「冬の一日、蟻は夏の間に溜めこんだ穀物を穴倉から引っぱり出して、乾かしていた。腹をすかせた蝉が来て、露命をつなぐため、自分にも食物を少し恵んでくれ、と頼みこんだ。「夏の間、一体何をしていたのかね」と尋ねると、「怠けていたわけではない。忙しく歌っておりました」と蝉は答える。蟻は笑って、小麦をしまいこみながら言うには、「夏に笛を吹いていたのなら、冬には踊るがいい」』(イソップ寓話集、中務哲郎訳、岩波書店)、とありました。
たしかに、この話しなどは、なんの説明もなくてもすぐ理解できますし、やはりいつの時代でも、先を見据えて準備をすることが大切です。
今年は、異常気象だけではなく、地震なども多く、いつ災害に見舞われるか不安です。でも、毎日を不安のなかで暮らすより、実際にそうなったときのことを考え、日頃の備えが大切です。
また、だいぶ昔のエジプト人でも、やはり水がなければ生活できないし、だからこそナイル川沿いに文明も開かれました。それを、「アニの教訓」では、「永眠しているあなたの父と母に水を捧げよ。もし神々があなたの行いを目にしたならば、彼らは「受け入れた」と告げるだろう。死者を忘れてはならない。そうすればあなたの息子はあなたのために同じことをしてくれるだろう。」といいます。
このアニという人は、書記のなかでも下級の神殿付きの書記であったそうですが、写本がいくつか発見されていて、エジプトだけではなく、ロンドンやパリ、ベルリンなどにも残っているそうです。ということは、それをなるほどと思って受け入れた人たちがいるわけで、おそらく日本人のなかにも、お盆などにお墓詣りをするときに、お墓に水をかける風習などを思い起こすかもしれません。
世界は広いといいながらも、どこかで深く結びついているようです。
今の政治の世界でも、演説のうまい人や、しっかりと答弁できる政治家がマスコミにも登場します。この本のなかにも、「メリカラー王への教訓」がのっていて、「雄弁に語れるようになりなさい。そうすれば、あなたは強くなるだろう。王の強さはその舌にあるからだ。言葉はどんな戦闘能力よりも強力であり、心を読める者を出し抜くことは誰にもできないのだ。ゆえにあなたは王座に安らかに座っていられるであろう。」とあります。
これは父親であるケティ王が、後継者の息子メリカラーに王の心得を述べているのだそうですが、これなども、いつの時代にも大切なことだと思います。とくに、最近は失言で政界から離れざるをえなくなったりしますが、今は人の揚げ足をとるようなことを平気でしますから、要注意です。
下に抜き書きしたのは、第1章「コミュニケーション 人類最大の悩みは、いつの時代も人間関係」に書いてありました。
たしかに、人は1人では生きられないので、必ず人との交わりが必要で、そこにいろいろな問題が生まれてきます。あまり強い欲望に引っ張られても困るし、だからといって、まったく欲望も覇気もなければ、目標を立てることすらできません。
人との関係がうまく行けば、スムーズにことが運びます。
この文章のなかで、「欲望強き者は、墓をもつことすらかなわないでしょう」という言葉は、いかにも古代エジプト人らしい表現だと思いました。また彼らは、インド人のように輪廻転生を信じていたようで、それでビラミットのような墓をつくったのかもしれません。
(2025.12.3)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 古代人の教訓(ポプラ新書) | 大城道則 | ポプラ社 | 2025年8月5日 | 9784591186763 |
|---|
☆ Extract passages ☆
あなたがよい生活を望むのならば、あらゆる邪心を捨て去りなさい。欲望から身を守るのです。欲望こそは直らぎる病なのです。欲望の下に親友はやって来ません。両親や兄弟を仲たがいさせ、妻と離婚することにも繋がるのです。欲望こそが避けるべき存在なのです。人は正義に仕えるならば長生きし、正義の道を歩むならば幸福が訪れるものなのです。欲望強き者は、墓をもつことすらかなわないでしょう。(「宰相プタハホテプの教訓」より)
(大城道則 著『古代人の教訓』より)
No.2489『生きるもののおきて』
岩合光昭さんの写真集は何冊か見ていますから、これも読んだかもしれないと思いながら、読み始めました。もちろん、写真は何度か見ているものもありましたが、文章は初めてのような気がしました。
たとえば、「水遊びはともかく、泥遊びは大好きなようだ。ゾウは暑さに弱いのだろう。大きなからだを泥の中に転がして、いろいろな動きをする。人が「これがゾウの形」と思っているイメージを見事に覆す。まるで宇宙遊泳のように踊ったり、泥の中にお座りしたり、見た日よりもからだが柔らかい。こうした遊びをいつまでもやっているのはオスだ。100キロほどもあるバオバブの木の枝を鼻で持ち上げて振り回したりする。ゾウに限らず、おもしろいことをするのは大抵オスだ。なぜなら、暇だから。「暇」といっては失礼だが、メスは出産・子育てに費やす時間・エネルギーが大きいためか、あまり無駄な動きはしないのだ。」という話しなどは、もし読んだとすれば覚えているはずです。たしかに、人間の場合でも同じようで、「おもしろいことをするのはオス」です。だから、男はいつまでたっても幼児性が残っているなどといわれるのかもしれません。
この本は、たくさんのカラー写真が掲載されていて、読みながら見ながら、つい何度も見比べたりもしました。たとえば、ライオン家族の文章や写真は、何回見ても、よくこんなにも近くで撮れるものだと思います。私も思うのですから、多くの人たちも同じように思うらしく、著者に対する質問も多いそうです。
それに対する答えは、「人間が、いかに間違った「常識」にとらわれているか、ひとつ例をあげよう。「ライオンは人を見ると襲う」と多くの人がそれを信じているのではないか。ぼくが最も「 多く受ける質問の一つは、「ライオンにあんなに近づいてこわくはないんですか」というものだ。それは、一般的にライオンが人に危害を加えると信じられている証拠だろう。でも、ぼくは一度だってライオンに襲われたことも、「襲われる」という危険を感したこともない。まれに「ライオンに襲われる!」というニュースを見ることがある。これはよく聞いてみると野生のライオンではなく、人に飼われていたり、あるいは、なんらかのかたちで人と関わりのあるライオンである場合がほとんどだ。野上のライオンと飼われているライオンとの違いは、食べ物を自力で得るか、餌をもらっているかということだろう。」と書いています。
そういえば、少し前の話になりますが、サルが山から下りてきて、田畑が荒らされて困るからというので、山と人の住む里との間に境界をつくり、いわゆる棲み分けのようなバッファーゾーン(緩衝地帯)をつくろうという動きがありました。その根拠になったのが、昔は石積みの「鹿垣」もあったとか、その向こう側に「熊留めの木」という栗や柿を植えていたからといいます。
しかし、野生動物たちは、いったん人間が栽培している栗や柿を食べてその味を知ったら、むしろ、山には帰らなくなってしまうのではないかと私は思いました。
案の定、現在は収穫もされない柿の木には、近くに居着いてしまった猿が食べていますし、特に今年などは熊もそれらを食べに山から下りてきているようです。たしかに、自然のようにこまめに草刈りなどをしないし、管理放棄地がふえてしまうと、その境界線も不明確になり、人の生活圏に動物が侵入しやすくなってしまいました。
熊の場合は、今年はブナの実などが大凶作で、食べものをさがして里だけでなく、町中にまで出没して、人的被害も多数出ています。おそらく、これは今年だけの問題ではなく、これからますます大きな問題になると思います。
ちょっと話しがズレてしまいましたが、著者に対する質問に、毎日動物を見ていて飽きないですか、というものもあるそうです。それに対して、「いつも車の中から動物たちを見ていた。車を降りると、人間はとても小さい。視線の高さが動物たちに近くなっているのだった。そうやって見ていると、いつもと違って見えてくる。よく、「毎日動物を見ていて退屈しないんですか。毎日見ていても同じ動物でしょ」と聞かれるが、同じに見えることはまったくない。小さな発見がいくつもあって、飽きることなんてないのだ。」と明確に答えています。
ただ、つらいと思うこともあるそうで、写真のシャッターチャンスがくるまで、何日も何ヶ月も待ち続けることもあるそうです。
そういえば、私もある人に、毎年同じような花の写真を撮って飽きないですかといわれたことがありますが、私の場合も飽きるということはありません。花の場合は、必ず毎年咲くとは限らないし、多く咲くこともあれば、あまり咲かないときもあります。天気だって、日々違うので、撮れ方方だって変わってきます。たとえば、白い花の場合は、天気が良すぎると花色が飛んでしまいますし、紅葉のときなどは、太陽が射してくれないと際立ちません。だから、毎年同じように撮っても、まったく違う写真になることもあります。だから、おもしろいのです。
下に抜き書きしたのは、「あとがき」に書いてありました。
そういえば、ほとんどの科学的真理といわれるものは、自然を見つめたところから発見されますし、さまざまな論証も自然界から見つけられることが多いような気がします。たしかに著者のいうように「予測がつかない」ことが多々ありますが、その煩雑ななかに微妙な流れがあったりすると、おもしろい発見につながります。
私も、先日は旅行先でずっと雲の流れを見ていましたが、それだけでも楽しかったです。
(2025.11.30)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 生きるもののおきて(ちくま文庫) | 岩合光昭 | 筑摩書房 | 2010年6月10日 | 9784480427182 |
|---|
☆ Extract passages ☆
自然の中にいると、予測のつかないことがおきる。ヒトの判断が及ばないこともある。そこが一番おもしろい。はまってしまうと抜けられない、底無し沼のような魅力だ。そこでは、肩書きだとか格好だとかは何の意味も持たない。だからこそ、都会に住む人が自然の世界へ旅すると、同じ場所に何度も行くリピーターになることが多いのだろう。
「見ること」を深めるには並大抵の勢力ではすまないと思う。しかし、野生動物、そして自然とヒトとの関係は、そこからはじまるのだ。
それを教えてくれたのは、ほかでもない、世界中で出会った多くの野生動物たちだ。
(岩合光昭 著『生きるもののおきて』より)
No.2488『まっすぐに生きる勇気』
初めて知る名前でしたが、「ナチ党が1933年以前において非常に巧妙だったのは、労働者には「労働者のための政党」として、農民には「農民のための政党」として、小ブルジョワには「小ブルジョワのための政党」として自らを見せかけたことだった。それが可能だったのは、彼らがすべての人に嘘をついていたからだ。」という文章を見つけ、それから経歴を見ると、「パリのユダヤ系の家庭に生れ」たことを知り、読んでみたくなりました。
このことは、政治史を読むときにも参考になり、おそらく、この嘘の流れは今の政治にもつながっているようです。だれが考えてもおかしなことを、平気でいかにも本当のことのようにいうのは、マスコミの報道でもよくわかります。
この本は、著者の本のいいところを抜書きしたもののようで、その生い立ちだけでなく、労働者の実態分析のために工場労働に従事したこともあると知り、ますます読んでみたくなりました。
「はじめに」のところで、シモーヌ・ヴェイユについての紹介がありますが、「戦時下に34歳という若さで亡くなったため、彼女は生前に自分が書いた本を手にすることはできなかった。つまり彼女はまったく無名のまま亡くなったのである。ただ戦後になり、『根をもつこと」がまず出版され、またアルベール・カミュ(『異邦人」「ベスト」)がヴェイユを高く評価したことにより、1950年代に次々と出版が進んだ。彼の尽力によって『抑圧と自由』『歴史的政治的著作集』『労働の条件」などの著作が世に出たのである。そして『重力と恩寵』や『神を待ちのぞむ』がベストセラーになったこともあって、シモース・ヴェイユは死後数年のうちにフランスで広く知られるようになったのであった。」と書いてありました。
たとえば、労働そのものについても、自分が工場労働に1年以上も従事したからこそ理解できたもので、頭のなかだけで考えて理解できるものではないということを教えられました。それは、「疲労は、いつのまにか私に工場にいる本当の理由を忘れさせ、私はこういう生活がもたらす最大の誘惑、つまり苦しみをまぬかれる唯一の方法である「もうなにも考えない」という誘惑に負けそうになる。記憶や思考の断片が戻ってきて、自分もまた考える存在だったことを思い出せるのは、土曜の午後と日曜だけだ。外的な状況に振り回されている自分に気づき、恐怖に襲われる。たとえば、もしいつか、週末休みもなく仕事をするような外的状況を強いられたら、それは実際いつでも起こりうることだが、私はおそらく(少なくとも自分自身の目には)家畜のように従順であきらめきった存在になってしまうことだろう。」という文章です。
私自身、疲れてもうなにも考えたくないという状況になったことがないので、この言葉はちょっとショックでした。おそらく、今よりももっと古い時代には、一般庶民は疲れ切って、何も考えられず、家畜のように従順であきらめきった存在だったのではないかと思います。
そういえば、歴史書というのは、ほとんどが為政者側からのものだけで、一般庶民の側から書いてものはないようです。おそらく、考えることも書くこともできずに、ただ毎日働いて眠るだけだと思うと、ちょっと遣り切れないものがあります。ただ、そのことだけを考えても、今の世に生まれて良かったと思います。
それでも、現在も戦争状態のところがあり、それを報道などで知ると、今も日々の生活に疲れて、何も考えられなくなっているところがあります。やはり、戦争という暴力は、絶対に許せるものではないとこの本を読みながら思いました。
下に抜き書きしたのは、「神への愛のために学びを善く用いる事についての考察」に書いてあったものです。
たしかに、知性を導くためには学ぶ歓びがなければ続かないし、そうしたいという欲求も大切です。欲求がなければ、その目的も定まらないので、そのうちに迷ってしまいます。
これは確かだ、と感じました。
(2025.11.27)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| まっすぐに生きる勇気 | シモーヌ・ヴェイユ 著、鈴木順子 訳 | ディスカヴァー・トゥエンティワン | 2025年8月23日 | 9784799332016 |
|---|
☆ Extract passages ☆
知性を導くことができるのは、欲求しかない。欲求が存在するには、楽しさと歓びがなければならない。
知性は、歓びの中でしか育たず実も結ばない。学ぶ歓びは、走者に呼吸が必要なように、学習にとって必要不可欠である。歓びの欠けているところに学生は存在しない。
(シモーヌ・ヴェイユ 著、鈴木順子 訳『まっすぐに生きる勇気』より)
No.2487『静かに生きて考える』
森 博嗣さんの本は、何冊か読んでいるのはどこかに共感する部分があるからです。その全てがよいとは思っていませんし、これはまったく共感できないというところも多々ありますが、それでも読んでみたいと思います。
たとえば、「なにかもやもやするときに、深呼吸をして、身近にある自然に目を向けてほしい。植物でも動物でも良い。風景でも星空でも良い。あなたは、静かに生きることができるはず。すべての人間は自然に生まれ、自然に死んでいく。生きている間だけ、ちょっとやかましいけれど、無理に騒ぐようなことでもない。怒ったり、嘆いたり、笑ったりするよりも、黙って周囲を眺めている方が、ずっと人間らしい。」と書いてあるところなどは、私も同じようにしているのではないかと思いました。
でも、書いてあるような生活ができるのは、作家として書いているので、その印税などが入ってくるからで、一般の人も同じようなことをしたいと思っても、なかなかできそうもありません。そんなことをいえば、著者から、私と同じようにすればといわれてしまいそうですが、平凡な普通の人たちにとってはできそうもありません。ほとんどの人たちは、自分の好きなことをして暮らせれば、そうしたいと思ってはいます。
でも、好きなものはいつでも手に入れ、好きな工作を時間を忘れてできるかといえば、難しいです。私も半分引退しているようなものですが、それでも時間は制限されますし、好きなことだけをしているわけには行かないのです。それでも、以前よりは、今日は天気が良くなりそうだからといって、車で写真を撮りに出かけられるようになりました。だから、何をするという目的意識は必要だと思います。
よく、子ども時代には、したいことが次々と出てきて、家庭の事情とか体力的な問題などでできないこともありますが、それでも好奇心があり、なんでも知りたがります。著者は、大人になるとその「知りたがること」を失ってくるといいます。著者は、「子供が、どんなものにも興味を抱くのは、なにも知らないからである。すなわち、「無知」という強みを持っている。知らないことがあるから、人間は知りたくなる。」といいます。
では、なぜ大人になるとそうではなくなるのかというと、「どうせ知っても大して面白くない」ことを知っているからだといいます。たしかに、今思えば、子ども時代に勉強したことが役立っているかといえば、それほどでもありません。数学の定理などをいくら知ってていても、ほとんど役に立ちそうもありません。でも、考え方として、たとえば地球温暖化などについても、地球の仕組みなどを知っていれば理解は早まります。異常気象などについても、その原因が多岐にわたるといっても、筋道を立てて考えることはできます。
だとすれば、「どうせ知っても大して面白くない」とは思っても、知るということはとても大切なことだと思います。
また、著者は、一人遊びが好きなようですが、たしかに孤独というのも大切なことです。「一人でいると、感情の起伏が大きくなるだろう。他者と接するときには、きっと誰でも我慢をして、感情を押し殺しているはず。そんな時間ばかりだと、だんだん感情が鈍くなるのでは?一人なら、自分に正直でいられるし、自分がどう感じるかを見ることで、人間というものの綺麗なところも汚いところも、一番正確に観察でき、人間が理解できるだろう。この理解が、自分以外に対しても役に立つ。孤独の時間は、とても大事なもので、できるだけ多く一人の時間を持ち、有意義に使ってほしい。一人で考える時間が、人を成長させるだろう、とも思っている。」書いていますが、このことは間違いないと思います。
私は一人旅で、このようなことをよく経験します。一人になるからこそ、見えたりわかったりすることがあります。
下に抜き書きしたのは、「知らないから楽しい」のところに書いてました。
今まで経験したことがないことや、初めて知ったことなどをすることは、本当に楽しいことです。そういえば、私も30年ほど前に自分でパソコンを作り始めたときのことを思い出します。現在使っているパソコンは、システムが古くなり、Windoes11に更新できないそうです。
そこで、歳を重ねても、この古くなった自作のパソコンを快適に動くシステムに作りかえようと思いました。この本を読んで、本当に良かったと思います。
(2025.11.25)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 静かに生きて考える | 森 博嗣 | KKベストセラーズ | 2024年1月20日 | 9784584139943 |
|---|
☆ Extract passages ☆
新しい発想は、知らない人や、やったことのない人の頭から生まれてくる。既知で体験済みであると、発想が制限されるからだ。これは、斬新な発見や発明が、若い人によって成されることでも明らかである。知っているほど、やり尽くしているほど、新しいアイデアが生まれにくい。逆にいえば、知識や経験を度外視して、まったく白紙にして考えることができれば、最高の思考といえる。
歳を取っても、自分の知識に立脚せず、自分の経験を活用しないような思考を心がけることがよろしい。稚拙であれ、未熟であれ、幼稚であれ、ということ。
知らないことが馬鹿なのではない。知ろうとしないことが本当の馬鹿である。
(森 博嗣 著『静かに生きて考える』より)
No.2486『良寛にまなぶ「無い」のゆたかさ』
この本は、もともとは春秋社の「良寛の呼ぶ聲」という題名で出版されたものを、文庫化されました。文庫本なので、ときおり、旅行のときなどにもって行き読んでいたのですが、なかなか読み終わらなかったものです。
というのも、あちこちに和歌や漢詩が載っていて、そのところどころでとまってしまいます。ちょうど、当山の例大祭が11月19日ですので、このときに読み切ってしまおうと考えたのです。
だから、それまでは、良寛の和歌や漢詩などの出典を調べたりしましたが、それではいつまで経っても読み終わらないので、ここで先ずは区切ろうと思いました。しかし、そのところどころの風景などが頭をよぎり、つい思い出したり、自分の撮った写真などを見かえすので、いつものような読書とはまったく違いました。
そういえは、「良寛はよほどにザクロが好きだったし、無邪気によろこびを表現した人だったのだ。そしてその表現があまりに正直だから、そこに思いがけぬ滑稽味、ユーモアが生じて、こういうなんでもない歌にも人柄があらわれることになる。こういう歌に接するとそこにザクロを食うことに夢中になっている良寛がいて、少しも気取らず、あるがままにいるのがわかり、あらためてその人が好きにならずにいられなくなる。」という箇所を見つけました。たまたま、そのときは、先月の10月23から24日にかけて新潟に行ったときで、「廻転寿司 佐渡弁慶 ピア万代店」のすぐ近くにあった「みなとのマルシェピアBandai」でザクロを見つけ、買ってしまいました。
この佐渡弁慶のお寿司もおいしかったのですが、買ったザクロもほんのりとした甘みがあり、とてもおいしかったです。
この時も、この『良寛にまなぶ「無い」のゆたかさ』をもって入ったのですが、やはり、旅の一番の思い出は食べものかもしれません。もちろん、本もそのひとつです。
そのとき読んだなかで、まさに天真に任すというような漢詩の解説で、「とくにこの中の、疲れたら足を伸ばして眠り、元気があるときは履をはいて托鉢に出かけるというところがいい。一所定住して、やはり漂泊中とは違ったやわらかさが出てきているのである。草の庵とはいえそこは住むところに違いなく、誰はばかることなくのびのびと足を伸ばすことができる。そして良寛にとってはこの、ゆったりと足を伸ばしていられるという何でもない状態がほとんど幸福を意味するほどの満足感を与えたらしく、何度もそのことのしあわせをうたっている。われわれは長い飛行機の旅のあと、足をながながと仲ばして寝ることがいかに快いかを知るくらいのものだが、どういう理由でか良寛にとってはそれがこの世の至福の時であったかのようである。」と書いてありました。
この漢詩を読んだのは、越後に戻ってからのことですが、なんとなく五合庵を思い出しました。
私が今回泊まったのは、ここから15㎞どしか離れていない燕三条のビジネスホテルでしたが、バストイレつきの部屋で快適な空間だったので、五合庵とは比べようもありませんが、足を伸ばして休むということに関しては、同じではないかと思いました。
ただ、町中にあるホテルとは違い、山中にある草庵は、まさに自然のまっただ中にあります。この本には、「そういう生存に身を置くからこそ、自然は、字宙は、彼の中に入ってくる、鳥も猿も鹿も、渓声も、屋根の風も、すべてが彼と共にある。そしてこのゼロ・レベルから見ると、生きてあることのよろこび、人恋しさ、人の情のうれしさ、四季の変化、すべてが最も敏感に体験されるのでもある。もし彼がぬくぬくと保護された生に身を置いたら、天地自然とともに呼吸するこの境地は失われてしまうであろう。草庵の生だからこそあらゆる感覚も研ぎすまされ、よろこびも悲しみも、苦しみも幸福も深いのである。」書いてあり、たしかにこれではまったく違うと感じました。
むしろ、わが家のほうが、鳥も猿も近くまで来るし、小町山自然遊歩道に行けば季節の花や吹き抜ける風などを感じることができます。それでも、今の生活と良寛さんが生きていた時代とはまったく違うので、比べようもないのですが、このような本を読むことにより、少しでも身近に感じることはできると思いました。
下に抜き書きしたのは、第5章「良寛の漢詩」のなかに出てきたものです。
その漢詩のなかに、「優游又優游」という語句があり、良寛さんが「遊」よりも「游」という字を好んでいたということが書いてありました。そういえば、私が初めて遊印を作ったときには、「清游」という文字を選びましたが、このときにはまだ良寛さんがこの字が好きだったことは知りませんでした。
この文章は、唐木順三『良寛』筑摩書房に出てきますが、この本は30年以上も前に読み、今も持っていますが、ほとんど忘れかけていました。それで、改めて、ここの載せることにしました。
(2025.11.21)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 良寛にまなぶ「無い」のゆたかさ(小学館文庫) | 中野孝次 | 小学館 | 2000年12月1日 | 9784094050515 |
|---|
☆ Extract passages ☆
「良寛が遊より游の字を好んだことは、泛として自由に、波のまになに動き流れる境を好んだことを示しているが、それは同時にまた、晩来(老来)殊に流れるもの、リズミカルに流れ動くもの、音楽的なもの、時間的な流動を好んだことに通じるだろう。禅の究極所は、透明な氷の世界のように塵ひとつ動かない「佳妙の地」、即ち超時間、無時間の世界として表象されていると同時に、水潺々の処としても表象されているのである。」(唐木順三『良寛」筑摩書房)
(中野孝次 著『良寛にまなぶ「無い」のゆたかさ』より)
No.2485『言葉のトランジット』
コロナ禍があってから、海外に行く機会はなくなり、トランジットを経験することもなくなりました。これは飛行機の場合は、同じ飛行機にそのまま乗り、燃料補給や機体の点検などのために短時間立ち寄ることです。だから、ある程度、遠距離でないとないわけで、イギリスに行った時などは、デンマークのコペンハーゲンで経験しましたが、今はロシアのウクライナ侵攻でこの航空路は使えないそうです。
この本は、最初は「群像web」に2023年6月15日から2025年5月20日まで掲載したそうで、それをまとめたようです。題名通り、旅について多く書いてありますが、旅好きにとっては、納得できることも多かったと思います。
たとえば、「旅行にはさまざまな形がある。遠いところへ出かけて新しいものを求めるのもあれば、すでに何度も訪れたところへ戻り、同じバターンを繰り返すのもある。旅館を訪れることは後者に当たるだろう。どのような部屋に泊まり、どのような食事をし、どのような浴場に浸かるかは、出発するまでもなくだいたい想像がつく。新しさよりも、自分がすでに知っているテーマのバリエーションを求めている。儀式のように、その反復には安心させるものがある。」と書いてます。そういえば、私も若いときには、なぜ同じようなところに旅に出るのか、ちょっと不思議でしたが、このように想像できるというか、ある意味、安心感があるというのも旅の良さかもしれないと思うようになりました。
そういえば、昔は定宿というのがあり、行きつけの旅館でわが家に帰ってきたような雰囲気を感じるというのを聞いたことがあります。旅館の側でも、そのような常連を大切にしていたこともあったようです。しかし、最近では夕食が豪華になり、毎夕同じものも出すこともためらわれ、3泊以上は断るという旅館もあるそうです。
私にとっても、行きつけの宿があれば気安く利用できるし、なんの心配もないので、憧れるときもありますが、まだ今まで行ったことのないところに行きたいという気持ちもあるようです。
話しは変わりますが、今のネット社会のなかで、学習する人たちは、瞬時にいろいろなメディアが手に入るので恵まれているという話しがのっていました。この本のなかに、「彼らが置かれている環境の利便性は否定できない。効率的に学習しているし、少し羨ましくさえ思う。だが一方疑間が浮かぶ。当時の自分がこれほど白由に日本語にアクセスできたなら、そこまで掘り下げたくなっただろうか。教科書や、集めた文化の欠片で、別の言葉と文化のあり方が垣問見えた。垣間見えたからこそ、興味が湧いたのかもしれない。次に何が見えてくるのか、言葉と距離の壁の向こう側に何が待っているのか。そんな単純な好奇心が常に原動力になっていた気がする。」ということです。
たしかに指摘されているように、たしかに便利にはなったかもしれませんが、この世の中はいろいろなことが重なり合っています。最近は、生成AIなどについてもいろいろな問題が出ていますが、この『本のたび』でも何度もとりあげていますが、出てきた答えが本当かどうかはわかりません。つまり、わかっていないと使えないということでもあります。たとえば、英訳でも、それがおかしいかどうかというのは、それなりに英語の素養がなければ判断できないということです。わからないから使うというのでは、間違ってしまうことも多いと思います。
著者も、最初のほうで、「AIという呼び方はするけれど、今流行っているシステムが意識を持つ人工知能だというわけではない。まるで人間が書いたような文章を出力する能力はあるのだが、それはいうなれば数学的なトリックだ。ユーザーが質問を入力すると、システムはその文章に関連する単語を探し出してくる。次に来るはずの単語を統計学的に決定し、そしてまた同じプロセスを繰り返す。出力された文章は、最初から最後まで書かれたものではない。データベースやレポジトリーから掻き集めた(盗んだ)文章を分解して分析し、それぞれの断片を再利用することで、あってもおかしくないような、平均的な文章を提示しているわけだ。」といいます。
私も基本的には、このような考えに近いと思います。おそらく、これからますます情報をかき集めて文章を解析すれば、だんだんと良くなることとは思いますが、そこに斬新さとか独創性というのはないような気がします。
下に抜き書きしたのは、「言葉の出島」に書いてありました。
これなども、外国人だから、英語のネイティブだからこそ思いつくことで、たしかに和製英語はそのままでは英語圏の人たちには通じないことが多いと聞きます。それを「言葉の出島」と表現するのは、とてもおもしろいと思いました。
(2025.11.17)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 言葉のトランジット | グレゴリー・ケズナジャット | 講談社 | 2025年8月19日 | 9784065404263 |
|---|
☆ Extract passages ☆
私のマイナンバー、あなたのマイナンバー、みんなのマイナンバー。もしマイナンバーを直訳して、「わたしの番号」と名付ければ、誰しも違和感を覚えるはずだが、和製英語にすると、 マイカーやマイホームなどと同様に、すんなりとうけ入れられる。和製英語というものは、そんな特殊な領域だ。日本語の一部でありながらも、「本物の」日本語とは一定の距離が保たれ、通常の規定の外にある。新しいもの、グローバルなもの、まだ定かでないものを安全に扱うために隔離された空間を提供する。いわば、言葉の出島のようなものだ。
(グレゴリー・ケズナジャット 著『言葉のトランジット』より)
No.2484『杉山アナの(アンチ)巨人、大鵬、玉子焼き』
私たち世代は、どちらかというと「巨人、大鵬、玉子焼き」で、今はそれほど野球や相撲を見ませんが、子どものころはあまり娯楽がないので、初めてテレビがわが家に入ると、相撲やプロレスなどもよく見ました。
しかも、近くにはテレビがないので、隣近所からも集まり、みんなで見ていた記憶があります。
この題名の、「杉山アナの(アンチ)巨人、大鵬、玉子焼き」ですが、語り手が元NHKアナウンサーの杉山邦博さんで、聞き手が相撲ジャーナリストの荒井太郎さんです。そして、「巨人、大鵬、玉子焼き」というべきところを、巨人の前に(アンチ)がついていて、それがちょっと気になり読み始めました。
杉山さんの出身は、福岡県ですから、野球が好きでも巨人ではない、それが(アンチ)という但し書きが入っている理由のようですが、むしろ正直な感じがして好ましいと思いました。
そういえば、この「巨人、大鵬、玉子焼き」を初めて使ったのは、作家でのちに経済企画庁長官も務めた堺屋太一氏だそうで、この本のなかにも書かれています。時は1961(昭和36)年で、通商産業省(現在の経済産業省)の官僚のときの経済報告の記者会見の席で話したようです。この年は、ソ連のガガーリンが人類初の有人宇宙飛行をしたり、この本にも書かれている大鵬と柏戸が同時に横綱昇進を成し遂げました。
この本では、「昭和36年九州場所に柏戸、大鵬が同時に横綱に昇進して、一直線の相撲が大変魅力的だった柏戸さんが、昭和44年名古屋場所で引退するまで8年。大鵬さんが土俵の円を無限に使いこなすような四つ相撲で10年、ともに綱を張って、それぞれ違うスタイルで土俵をけん引してきました。大鵬さんの引退で明白に一つの時代が終わりを告げましたね。」と書いてあります。さらに、大鵬に優勝インタビューした杉山アナが、「一番印象に残っているのが、優勝インタビユーを私は何度もしましたけど、「優勝おめでとうございます」と言うと、どんな場合でも最初の一言は「おかげさんで」なんです。真っ先にその言葉から入るんです。これはやはりほかの人にはなかったですね。大鵬さんの人柄が滲み出ていました。これには生い立ちとか、いろいろな苦労をなさったこともあったんでしょうけど、その「おかげさんで」という言葉に大鵬さんの思いが込められていると思います。ですから柏戸さんに対しても「柏戸関がいたおかげで、自分がある」といつもおっしゃっていましたから。優勝回数は、特に後年は大きく開いてまるっきり違いますけど、柏戸関がいるから自分があるという思いは常に持っていましたよ。」と話していたそうで、私も山形県出身ということもあり柏戸ひいきでしたので、この言葉は印象に残りました。
この本を読んで、相撲の世界のことで初めて知ったことも多く、現在は相撲中継はNHKだけですが、もとは民放もしていたそうです。それが、「大鵬は優勝回数をどんどん伸ばしていきます。そのうちに相撲ファンもどうせ見なくたっていいや、また人鵬が勝つに決まっている。テレビも見なくていいやつて感じでテレビ離れが進んでいったんですよ。それで民放の相撲中継の視聴率も上がらなくなって、一抜けた、二抜けたといった具合に、民放がどんどん大相撲から撤退していく。昭和41年初場所限りで日本テレビの大相撲放送が終了して、民放局はすべて撤退したわけです。」と書いてあり、やはり独り勝ちというのは、見ていてもつまらなくなってしまうと思いました。
これはどんなことでも同じで、誰がどんなチームが勝つかわからないからこそおもしろいんです。もし、大谷翔平が毎回ホームランを打つと思えば、それほど見なくなるのではないかと思います。あの名選手でさえスランプに苦しめられるからこそ、それから立ち直ったときの素晴らしさが際立つような気がします。
どんな人にも、調子の良いときもあれば、悪いときもあります。それが人生ですから、つねに調子の良いときばかりでは、見ているほうだって彼だから当然だと思いながらも、どこかでつまらなさを感じてしまうと思います。
下に抜き書きしたのは、第1章「"臨場感を共有する"時代へ」に書いてありました。
やはり、戦争で負けた悲哀みたいなものも感じますが、このようなときを乗り越えてきたからこそ、今の大相撲があるのだと思います。すでに、終戦まえにも日本軍部に両国国技館は風船爆弾の工場として接収されていましたから、昭和19年5月の本場所が後楽園球場で行われたりもあったそうです。
いつの時代も、戦争となれば、それが最優先されますから、いかに平和が大切かがわかります。
(2025.11.13)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 杉山アナの(アンチ)巨人、大鵬、玉子焼き | 相撲ファン編集部 編 | 大空出版 | 2025年7月30日 | 9784867480144 |
|---|
☆ Extract passages ☆
終戦後の昭和20年10月26日、相撲協会は連合軍から国技館接収の通達を受け、接収日が同年の12月26日に決まった。接収に先立ち、戦後初の本場所は11月16日から晴天10日間で開催されたが、当時の相撲協会幹部は進駐軍に楽しんでもらおうと、土俵を従来の直径15尺から16尺に広げて熱戦を目論んだが、食糧不足で痩せ細った力士にとっては不評だった。休場中の横綱双葉山はこれを不服として引退を表明したといわれている。結局、16尺土俵は1場所で姿を消し、翌場所からはもとの15尺土俵に戻った。
(相撲ファン編集部 編『杉山アナの(アンチ)巨人、大鵬、玉子焼き』より)
No.2483『世界は知財でできている』
たしかに、今の時代は、知財、つまり知的財産でこの世界は動いています。では、この知的財産とは何かというと、この本では、ざっくりいえば、「人間の知的活動によって生み出された財産的な価値を持つ情報」などのこと、と書いています。
この人間の知的活動というのが大切なようで、たとえば、象が絵を描いたとしてもそれは著作権は生まれないそうです。そのつながりで考えれば、生成AIは著作者にはなれないそうです。つまり、動物が描いた絵と同じで、生成AIにも思想や感情がないし、つまりは人間が関わることなくAIが自分で生成した画像や文章や音楽にも著作権は発生しないそうです。ちょっと意地悪くいえば、あっちこっちのいいところをかき集めてつくったようなもので、そこに独創性はほとんど感じられないと私も思います。
ただ、いくら以前のことやものから集めたとしても、それはそれなりに参考にはなると思いますが、そのなかには明らかに間違っているものや誤解しやすいものも含まれているので、そのまま通用するかどうかの判断は大切です。
その生成AIは著作者にはなれないという例のひとつとして、この本では、「2022年2月、米国のコンピュータ科学者であるステイーヴン・ターラー氏が、自身が開発した画像生成AI「Creativity Machine」が創作したとする「A Recent Entrance to Paradise」(楽園への最近の入り口)という作品について、著作者の欄に「Creativity Machine」と記載して米国著作権局に著作権登録申請をしたところ、「人間による著作ではない」との理由から登録が認められなかった。ターラー氏はそれを不服として連邦地方裁判所に提訴したが、敗訴している。」といいます。
そういえば、この本の「おわりに」のところで、著者は、よく忙しいなかで本を書く時間が取れましたねといわれ、さらに「生成AIでも使ったのですか?」と聞かれたりもしましたそうです。そこで、「生成AIは一切使っていません。たしかに、最近は生成AIを使っている筆者もいるでしょうし、早く書き進めるには、それが効率的でしょう。ただ、法律や技術に関係する内容になってくると、生成AIが不正確な文章を作り出すことが非常に多いことから、まったく安心することができません。そのような理由から本書は引用部分を除いて、私が自ら書き起こしています。また、生成AIの文章には、「もともと知識のない人が参考文献をたくさん引っ張り出してきて、そこにある文章を組み合わせて、何となくそれらしい文章を作っている」という印象があります。生成AIに頼り切るのは大変危険なように思います。」と書いていて、それは私もその通りだと思っていますが、著者同様にこれからますます生成AIが発展していけば、どうなるかはわかりません。
私も遊びでChatGPTを使ってみたことはあるのですが、当たり障りの文章で、明らかに間違っていると思われるものもありました。ただ、大切な資料としては使えませんが、世の中だからこんなこともあるかもしれないと思うこともありました。よくニュース原稿をAIが読むこともありますが、以前と比べて格段になめらかになったようですが、それでも聞いていると違和感を感じることもあります。これとて、現在のスピードで改良されれば、本当のアナウンサーが読んでいるようになるのかもしれません。
これら現在のAIブームを牽引しているのは、「やはり2024年のノーベル物理学賞の受賞対象ともなった「人工ニューラルネットワーク」による「機械学習」や「デイープラーニング」であろう。これにより画像認識、音声認識、自然言語処理などに関する技術が飛躍的に向上し、AIの応用範囲の拡大や生成AIの登場へとつながっていった。」と書いています。
数字の上でも、2024年10月に特許庁がまとめた「AI関連発明の出願状況調査」で出ていましたが、AI関連発明の出願件数は2014年以降に急激に増加しており、2022年の出願件数は約10,300件だそうです。だとすれば、今後はその知的財産を護ることも必要で、著作権も多種多様になっていくのではないかと思いながら読みました。
そういえば、今年の読書週間10月27日から11月9日までの2週間で、今年の標語は「こころとあたまの、深呼吸。」だそうです。どんな難しい本でも、ゆっくりと深呼吸をするような感じで読めば、なんとなくわかってくるような気がします。
下に抜き書きしたのは、第6章「ところ変われば……「知財」の国際問題」に書いてあったものです。
よく話題に上るのは、シャインマスカットですが、これはもともと日本の農研機構が2006年に品種登録をしたものですが、これは日本の育成者権は国内でしか制限できないようです。つまり国ごとに権利が独立しているので、植物新品種の保護に関しては「植物の新品種の保護に関する国際条約」があり、それによると加盟国ごとに品種登録をする必要があるそうです。
これらは、もう少し簡略化し、ある国連の機関に登録するとすべての国に有効だというようなシステム作りが必要ではないかと思いました。
(2025.11.10)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 世界は知財でできている(講談社現代新書) | | 稲穂健市 | 講談社 | 2025年8月20日 | 9784065407868 |
|---|
☆ Extract passages ☆
……各国ごとに保護の事情が異なることから、まずは種苗の海外流出を防ぐことがポイントとなるだろう。特に一代限りの「一代交配種(F1)」であれば、親種を厳重に管理すべきである(たとえば、夕張メロンの親種は金庫で保管されている)。また、増殖可能であっても栽培が難しい品種であれば、その育成方法などのノウハウが流出しないように対応していくことも重要だ。
次に各国でもなるべく早めに育成者権を確保して権利行使ができる状態を作っておくことが必要である。それに加えて、海外で模倣品が出回っていないかモニタリングするための仕組みを作ることで権利を形骸化させないことも重要だ。
(稲穂健市 著『世界は知財でできている』より)
No.2482『イカの恋、タコの愛』
岩波科学ライブラリーの1冊ですから、科学的な本だとは思うのですが、題名がいかにもハウツー本みたいです。それでも、イカ刺しは大好きなので、読んで見ようと思いました。表紙には、「風変わりな恋の駆け引きから目が離せない!」と書いてありました。
読んで見ると、今まで知らなかったイカやタコの話しがたくさん載っていて、とてもおもしろかったです。
たとえば、イカとタコの違いは、「ほとんどのイカは常に水中を遊泳しながら餌となる動きの速い魚やエビ類に狙いを定める。すばやく逃げる相手に対して、イカはスナイパーのように離れた位置から狙いすました触腕の一撃で、相手を捕獲する。触腕は他の腕より長く伸びる一方で、吸盤は掌部と呼ばれる先端部分にしかない。獲物を捕まえる部位だけに吸盤を集めた、まさに捕獲に特化した腕というわけだ。触腕で餌をつかむことに成功したら、餌の体重が自分より軽い場合は相手を引き寄せ、重い場合は自分から近づき、先端から付け根までびっしり吸盤のある残り8本の腕で動けないようにしっかりと体を固定する。一方、海底を這いずり回るタコは触腕をもたない代わりに、腕の間に傘膜と呼ばれる河童の水かきのような膜が張っている。これを広げて餌が隠れていると思われる石などを包み込むように獲物を捕まえる、イカとは違い、岩などの隙間に隠れるカニや貝を捕まえるためには、狙いすました一撃よりも、投網をうつように狙いなど関係なく周りを取り囲んでしまう大胆な捕まえ方のほうが適しているのだろう。そういう摂餌戦略上の違いが、タコが触腕を必要とせず、腕の本数が8本にとどまっている理由なのかもしれない。」とあり、なるほどと思いました。
では、あの墨を吐くのは、敵から逃れることかなと思っていたら、それだけではなく、繁殖のときに使う種類もいるそうで、今まで、あまり研究されてこなかったこともあり、詳しくはわからないことも多いそうです。
たとえば、日本の小型コウイカ類のエゾハリイカでは、求愛ディスプレイのときに、雄は墨を自分の背後に放出して、その暗く濁ったその前で身体を白く変色させるそうです。つまり、より自分を目立たせるためにも墨を使っているそうです。
そうすれば、自分を目立たせるたけではなく、おそらくまわりも見えなくなり、他に雄がいたとしても気にならなくなるかもしれません。
また、オーストラリア沿岸に分布するヒヨウモンダコの仲間の1種であるブルーラィンオクトパスは、「なんと、雄が雌にマウンティングの体勢で交接するやいなやすぐに雌の体に噛みつくのである。すると雌の呼吸速度は急速に遅くなり、10分ほどで完全に停止し、体の色も真っ白に変化する。いわゆる昏睡状態になるのだ。その間に雄はせっせと精子を渡し終える。1時間ほどの交接が終わるころ、ようやく雌は呼吸をしはじめ、正気を取り戻す。」といいます。
このようなことは、他の昆虫などでも知られていますが、まさかタコの仲間がするとは思ってもいませんでした。この研究をしているクイーンズランド大学の Chung 博士は、雄が雌に比べてだいぶ小さいので、共食いを避けるためではないかといいます。また、致死量の高いフグ毒のようなものだとしても、このことで雌は死ぬことはほとんどないそうで、この毒に対する耐性を持っているのではないかとも書いています。
著者は、このことを「雄による毒の口づけ」と書いていますが、おもしろい表現です。
下に抜き書きしたのは、第2章「精子のバトンの受け渡し――頭足類の繁殖方法」にあったものです。
この頭足類というのは、その姿からきているようで、まさに頭に足がついているような生きものです。「しかし、巨大な頭部と思われがちな体のパーツは、実際のところは胴体であり、中に詰まっているのは脳みそではなく、心臓や鰓、胃、肝臓、すい臓といった臓器である。脳は大きな目の間に収まっているので、頭部はあくまでも両眼が位置するあたりに留まる。つまり、特徴的な8、もしくは10本の足は頭から直接生えていることになり、これを表して頭足類と呼ばれるわけである。」と書いています。
(2025.11.6)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| イカの恋、タコの愛(岩波科学ライブラリー) | 佐藤成祥 | 岩波書店 | 2025年8月20日 | 9784000297363 |
|---|
☆ Extract passages ☆
イカもタコも繁殖期は一生に一度といわれている(これを一回繁殖という)。しかし、一生に一度といっても、迎えた繁殖期における産卵の仕方は2タイプに分かれる。繁殖期の中で1回しか産卵を行わないものもいれば、繁殖期間に何度か産卵を繰り返し行うものもいる。イカでいうと、ヤリイカ科やアカイカ科のような数日から1週間ほどと比較的短い期間に少ない回数で多量の卵を産むタイプが前者寄りで、コウイカ科のように1カ月ほどの長期間にわたり、だらだらと少数の卵を何度も産むタイプが後者にあたる。一方、タコの産卵はいずれも長期間の卵保護を行う必要があるので、ほとんどの種が前者のタイブで、産卵回数においてはイカほとせの違いは見られない。
(佐藤成祥 著『イカの恋、タコの愛』より)
No.2481『「私のなかにみんながいる」?』
副題は、「AI・ロボットと教育哲学」ということで、神林照道氏の「私のなかにみんながいる」という設問から、AIとロボットの専門家がそれに答えるという対談というか鼎談を記録したものです。
そして、出版社をみてみると、「今人舎」で、住所は東京都国立市になっています。企画・編集は稲葉茂勝氏で「NPO法人子ども大学くにたち」の理事長で、子どもジャーナリストという肩書きです。この本に出てくる国立学園小学校は、私立の小学校だそうで、だからこそ自由な校風があり、独特な教育もできるのではないかと思います。
山形県内では、あまり私立小学校はなじみがないのですが、都会では入学が難しいという話しを聞いたことがあります。よく、お受験などといわれるのも、このような私立小学校です。
そもそも、この小学校の校長をしていた神林照道氏の「私のなかにみんながいる」という話しに興味を持ったロボット工学の淺間一氏が、神林氏の自宅を訪ねるところからこの本は始まります。
ロボットと一口に行っても、いろいろなロボットがあるそうですが、この「私のなかにみんながいる」という考え方は、「協調ロボット」にもつながると淺間氏は感じたそうです。
この本には、『「協調ロボツト」の「協調」という言葉には、「邪魔しない協調」と、「助け合う協調」の2種類があります。とくに難しいのが、後者の「助け合う協調」です。人間にたとえると、自分ができること(能力)が決まっているとすると、それ以上のことを要求されたとき、自分では解決できないと判断します。そんなとき、だれかとチームを組むことで、自分の力を増大させる。これは私のなかでは、自分と他人の境界が拡がっていくようなイメージだったのです。本来、ロボットが自分で制御(コントロール)できるのは、アクチュエータ、人間でいうと、自分の筋肉だけです。でも、協調すること、すなわち、コミュニケーションをとることによって、自分が扱えるものやできることが増えていく。そこには、自分が拡がっていくような状態があるわけです。』と書いています。
これは、ロボットだけの話しではなく、人間にも同じようなことがあります。よく三人寄れば文殊の知恵などといいますが、1人ではできないことも、お互いに協力することによって大きなことができるようになります。その決め手は、やはりコミュニケーションです。
そう考えれば、人間もロボットもAIも、みな同じように思えますが、そこには厳然とした違いがあるそうです。
SF作家のアイザック・アシモフという人が、「ロボツト3原則」というものを提案したそうです。それは、
第1条:ロボットは人間に危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。
第2条:ロボットは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第1条に反する場合は、このかぎりではない。
第3条:ロボットは前掲第1条および第2条に反するおそれのないかぎり、自己を守らなければならない。
ということです。たしかに、ロボットもAIも人間を無視して勝手に動いたとしたら、やはり恐怖です。それを防ぐためにも、これらの「ロボツト3原則」は必要です。
下に抜き書きしたのは、第5章「神林先生から子どもたちと保護者の方へのメッセージ」に書いてありました。
国立学園では、「21世紀を生き抜く子どもを育てる」ということを目標に掲げ、具体的には「自ら考え、自ら学び、自ら行動する」ことを教育目標にしているそうです。だからこそ、たとえ失敗したからといってそれが悪いことではなく、そこから何かを導き出すことが大切だといいます。
だとすれば、過保護や過干渉は子どもの将来を考えると、育児放棄に等しいと神林氏はいいます。
では、生き抜く力というのはどういうことかというと、『「生きる」でなく「生きぬく」とは、
ア、自ら考え、自ら学び、自ら行動する。そして、自らを自ら振り返ることのできる子ども。
イ、「優しさ」「たくましさ」「かしこさ」は、大切なことの順番。だから、「かしこさ」を、最初に位置づける実践は誤りだと考えている。
ウ、学校は失敗するところだと考え、日々の学校生活に挑戦する「失敗を恐れない」子ども。』
と答えています。すると、淺間氏は「それらのことは、私たちの研究でも言えることなんです。ロボットも、失敗から学び、学習し、状況に応じてきちんと動けるようにすることがとても重要です。」と話しました。
国立学園では、ペーパーテストでも、答えは1つとは限らず、2つ以上あることもあるそうです。つまり、どうしてそういう答えになったのかをきちんと答えられなければならないということです。下の抜書きしたところをじっくりと読めば、「間違うことが成長の原動力になる」ということが理解できると思います。
(2025.11.2)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 「私のなかにみんながいる」? | 神林照道・白井克彦・淺間 一 | 今人舎 | 2024年10月10日 | 9784910658155 |
|---|
☆ Extract passages ☆
うちの教師によく言ってきたのは、間違うということは自分を成長させるんだということを、どうしたら子どもたちに理解させてやれるか、そこを上手に指導してほしいと。「正しいか正しくないか」式に勉強させられた子の場合、テストで間違うと落ち込んでしまうのです。
泣いてしまう子どももいます。これからいろいろな知識を覚え、それを知恵にしようという子が、テストの答えを間違えたと泣き出す、だれがどう考えてもおかしいことです。
なぜ、間違うことがプラスになるのか、成長の原動力になるのかというと、間違うことによって初めて、どうして間違ったのかを考えることができるのです。
(神林照道・白井克彦・淺間 一 著『「私のなかにみんながいる」?』より)
No.2480『私にふさわしいホテル』
10月23~24日と、新潟県内に行ったので、そのときに持っていった1冊です。いくら車で出かけたといっても、荷物が増えると大変です。旅は、身軽が一番で、本を持って行くのは文庫本で決まりです。
しかも、この本は、久しぶりの小説なので、気軽に楽しめて、ところどころで休みながら読んでも筋はつながります。また、そんなに身構えなくても、気軽に読めるのも楽しいです。
内容は、なるべくなら読んで欲しいのですが、簡単に紹介すると、新進女性作家がいろいろな障壁にもめげず、しっかりと文学賞をとりながら歩んでいく、痛快ともいえるものでした。もちろん、実際とは違うと思いますが、もしかしてあるかもしれない、というようなことが次々に起こります。たとえば、嫌みな批評家にパーティー会場で罵倒されたり、担当の編集者とのバタバタ劇や、嫌いな小説家とのとんでもない軋轢など、数えれば切りがないほどです。
でも、主人公は、それらにもめげず、着々と自分の立場を自分でつくっていきます。それが読んでいても笑えたり、そこまでしなくてもと思ったりしながら、読んでしまいました。
この作品は、もともと扶桑社より平成24年10月に刊行され、平成27年12月に文庫化されました。小説としては珍しく参考文献が載っていて、常盤新平『山の上ホテル物語』白水社、です。私も学生のころはお茶の水駅近くのこのホテルの近くを通っていたのですが、その当時から文筆家のホテルとして有名でした。いつかは泊まってみたいと思ってましたが、惜しいことに2024年2月13日より休館になってしまいました。
そういえば、この本に出てくるパークハイアットには、ある企業の招待で泊まったことがあり、その部屋の広さにびっくりしたり、たまたま東京都庁を見下ろすようなところにバスルームがあったのを今でも思い出します。
この本のなかで、文学賞の選考にはいろいろな圧力があるような話しが出てきますが、解説の石田衣良さんによると、「2ちゃんねるの文芸板のように政治的陰謀説で文学賞の選考など行われていないし、裏駆け引きなどすくなくとも伝統ある文学賞ではまず考えられない。それは数々の賞の選考に携わったぼく自身が証言できる。だいたい我がままで自分の読みに揺るぎない自負をもつ複数の作家の意見が、容易に誘導できるはずがないのだ。賞の主催社だろうが、版元だろうが関係ない。文学賞も選考会も生きものなのである。」とありますが、この解説の通りだと私も思っています。
それよりおもしろかったのは、この小説の影の主人公ともいうべき東十条宗典が、この解説を書いている石田衣良本人によると、自分ではないかといいます。それを出てくる小説の題名や内容から照らし合わせて推察していますが、なるほどと思わせる説得力があります。
そして、「作家という仕事は、いつか書けなくなるその日がくるまで、暗闇のなかで全力投球を続けることなのだろう。この本を読んで、ひとりの書き手がそう思わされたという事実。それは『私にふさわしいホテル』という洒落たタイトルのこの小説に、ものを創る人間の心のある深度まで届く力があったということなのかもしれない。本好きなら、怖いもの見たさで読み始め、最後は小説への揺るぎない信仰を後光のように浴びてもらいたい。」と結んでいます。
たしかに小説は虚構の世界かもしれませんが、最初から最後まで虚構でかためるというのはかえって難しいと思います。どこかに自分の幼少時の体験や今までの経験が混ざっているような気がします。そんなことを考えながら、読み終わりました。
下に抜き書きしたのは、第4話「私にふさわしい聖夜」にあった下積み時代の思い出です。
どんな人にも下積みらしきものはありますが、小説家の下積みというのは、まさにこのようなものかもしれないと思いました。
しかし、小説を抜書きしたり、内容を明かしてしまうと、読む楽しさがなくなると困るので、今回はしないことにしました。興味のある方は、自分で本を読んでほしいと思います。10月27日から11月9日までの2週間が読書週間で、今年の標語は「こころとあたまの、深呼吸。」だそうです。ジャンルを問わず、いろいろな本を読んでほしいと思います。
(2025.10.30)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 私にふさわしいホテル(新潮文庫) | 柚木麻子 | 新潮社 | 2012年12月1日 | 9784101202419 |
|---|
☆ Extract passages ☆
今回は抜書きをしませんでした。
(柚木麻子 著『私にふさわしいホテル』より)
No.2479『上杉鷹山』
副題は、「富国安民」の政治で、私たち米沢の人たちは、鷹山公と親しみを込めていいます。おそらく、学校などでも副読本などを使って鷹山公のことは教えていると思いますが、今は少子化で小中学校の統合が進み、現在はどのようになっているかはわかりません。
上杉神社に行くと、NHK「天地人」放映をきっかけに「上杉景勝公と直江兼続公主従像」が建っていますが、「上杉鷹山公之像」は、建っている姿と座っている姿の2基建っています。上杉神社の一之鳥居近くにあるのが建っている姿で、その脇には、有名な「なせば成る なさねば成らぬ 何事も 成さぬは人の なさぬなりけり」という名言が彫られた石板が添えられています。この像を製作したのは、高岡市の田畑功氏で、小野川温泉の甲子大黒天本山の甲子大黒天像も製作しました。田畑氏は、日展会員でもあり、北村西望賞も受賞したことがあり、私もその工房を訪ねたことがあります。
上杉鷹山の学問の師匠といえば細井平洲が有名ですが、それを結びつけたのが竹俣当綱です。いつも「政治は学問に基づいて行われなければならない」と考えていたそうで、本を読むことも好きで、読書ノートもつけていたようです。それは「竹俣は、鷹山と出会う少し前、30歳前後から読書ノートを作り、様々な書物の抜粋や要約を書き込んで学んだ。そのノートには、教訓的な仮名草子である『智恵鑑』『分類画本良材』や『絵本童の的』のような絵入り本(教訓書)、『通俗武王軍談』『通俗忠義水滸伝』といった読本までが書き写されている。竹俣は、学者然として四書五経といった儒学の古典を諳んじたり、高度な内容の儒学書を読みこなしていたわけではない。むしろ、通俗的とさえいえる読み物や絵入り本の類を好んで読み、自己を形成していったのだ。」と書いてあることからもわかります。
私も学生のころから読書カードをつくっていますから、50年以上は続けていることになります。今では、そのカードも相当数になり、置き場にも困るぐらいですが、なかなか捨てられません。むしろ、私の宝物のようです。
鷹山の寛政の改革をみると、一番難しいのは質素倹約よりも荒廃した人の心をいかに奮い立たせることが大切かがよくわかります。すべてを失って路頭に迷う人たちにとって、一時的な救済はほとんど何も残しません。そこで必要なことは、「国を富まし、民を足らしむる事」の前提として、多くの人たちにそれがなぜ必要なことなのかを教導することです。だから莅戸善正の嫡男の莅戸政以は、富国を「藩政の最優先課題だとしながらも、領民の負担増につながる年貢増徴策や、専売制による商品流通の過程からの富の吸い上げは主張せず、むしろ、民衆に通俗道徳的な倫理・規範を浸透させること、すなわち「風俗教化」によって、「富国」と「安民」を同時に実現することを構想した。」といいます。
つまり、この本の副題の「富国安民」の政治を目指したということです。
いつの時代もそうですが、人々から搾れるだけ搾り取ろうとする為政者は、長くは続きません。だからこそ、上杉鷹山が米沢藩の藩主になったころは、「金気を抜くには『上杉』と書いた紙を貼るとよい」と噂されていたのに、この寛政の改革をしてからは、「天下の富強の国」とさえいわれるようになったそうです。
幕末ころに米沢藩を訪れた永山徳夫は、「米沢藩士たちは、平生農民と変わらないくらしを送っていることによって壮健。屈強な身体を持っており、それは汲み取るべきいにしえの風習なのだ、と。」と書いていて、むしろそれは、「米沢藩士たちのくらしぶりは、幕末期にかけて、武士の気高さを失った行為としてではなく、むしろ、見習うべき身体的屈強さをもたらす営為として高く評価されるようになっていたのだ。」といいます。
これは改革の始まった当時の七家騒動を考えると、そのときの武士の気位の高さがよくわかりますが、改革を推し進めていくと、それほど人の心も変わっていくのかというぐらい、変化します。おそらく、これは時代的な流れもあると思いますが、それが明治になるとひ弱な武士より、体力的に勝る人たちが主流になっていくのは当然かもしれません。
下に抜き書きしたのは、第3章「名君像の形成と『翹楚』」に書いてあったものです。
この本では、この莅戸善正が書いたこの『翹楚』をなんども取り上げています。その内容も箇条書きにして56条一覧も掲載してますが、今、私たちが鷹山公として記憶している内容がほとんどです。つまり、おそらくは今の鷹山公につながるほとんどが、この本の影響といっても過言ではなさそうです。そして、その当時でも、この本は「P107」とあり、相当な影響を及ぼしていたようです。
最近では、あまり知られていないようで、もっと手軽に読めるようにしてもらいたいと思いました。
(2025.10.28)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 上杉鷹山(岩波新書) | 小関悠一郞 | 岩波書店 | 2021年1月20日 | 9784004318651 |
|---|
☆ Extract passages ☆
上杉鷹山の日頃からの言行を描き、18世紀末以降、各地の大名家や藩校、昌平坂学問所の学者などに広汎に流布して、上杉鷹山・米沢藩政を政治論議の基準に押し上げていった明君録『翅楚篇』。士民の視線や「教化」という政策課題を意識しつつ、養老や孝行の徳日実践に努める鷹山の姿は、その「安民」への思いがいかに深いものだったのかを強く印象づける。著者の荏戸善政が、米沢藩の寛政改革を遂行するにあたって、「民利」優先の改革政策を打ち出したことは偶然とは言えまい。
(小関悠一郞 著『上杉鷹山』より)
No.2478『トーベ・ヤンソンの夏の記憶を追いかけて』
トーベ・ヤンソンという名前を聞いてもわからないという方がいるかもしれませんが、「ムーミン」といえば知らない方はほとんどいないと思います。彼女は、その「ムーミン」シリーズの産みの親で芸術家としても知られています。
私自身も図書館などで拾い読みをした程度で、子どもの読み物という程度の認識でしたが、この本を読んで、これはもう一度、しっかりと読んでみなくてはならないと思いました。
また、フィンランドというと、美しい湖水地方とかフィンランド式サウナや、ロヴァニエミにあるサンタクロース村ぐらいしか知らなかったのですが、この本には、たくさんの写真も載っていて、あらためて首都のヘルシンキなどの古い街並みを知りました。
「ムーミン」の著者のトーベ・ヤンソンについても、略歴すら知らなかったのですが、この本によると、「1950年代、トーベは、幼い頃からの画家でありたいという願いと、加熱していくムーミンビジネスの間で苦しんでいた。その前には舞台監督のヴィブイカ・バンドレルという女性L激しい恋に落ちたことで、自分のセクシャリティが揺らぎ、悩みを抱えていた時期もあったようだ。トゥーリッキは、繊細なトーベを受け止め、ビジネスとの付き合い方をアドバイスした。それによってトーベは創作の危機を脱し、ムーミンシリーズが文学的に深められる契機となった傑作『ムーミン谷の冬』を書き上げることができた。最終的にトーベの生涯の伴侶になったトゥーリッキは女性だったが、トーベ自身も書いているように、性別ム々ではなく、「その人に恋したかどうか」が大切だったのだと思う。何よりも私が感じ入ったのは、トゥーリッキがトーベと同じように自由や旅を愛し、芸術と創作を自分の人生の中で最も重要なものとして位置づけていたことだった。」と書いてありました。
もちろん、今ならそれほど驚くこしではないのですが、その当時は、近くの人たちはどのように感じていたのかはわかりません。今では、人それぞれですし、どちらかというと、人の数だけセクシャリティはあると考えられるようになってきました。まさにセクシャリティは、個人の性のあり方の問題です。
でも、風評などを気にしなければ、しかも、人里離れた孤島で夏を過ごせば、自分たちの生き方をそのまま続けられます。それこそが、貴重な時間であり、空間だったのではないかと思います。
現在は、その島、つまりクルーヴハルに芸術家に限り、トーベたちが造ったコテージを貸し出しているそうで、今回はそこで過ごした1週間を中心にまとめています。おそらく、ムーミン好きにはたまらない話しではないかと想像します。
著者も、そのクルーヴハルのコテージで、人生にとって貴重な瞬間があったといいます。
それは、「東の空にはいつの間にか羽根のようなふんわりとした白い雲が高く浮かんでいた。そして、あたりがはっと明るくなったかと思うと、水平線に伸びていた雲から太陽が顔をのぞかせた。その瞬間、後から振り返っても本当に不思議なのだが、私の中でもう長いことずっと、何度も何度も同じところを堂々めぐりしていた迷いのようなものが、そのときふっと消えてなくなった、そうか、何も恐れることはないんだ、と私は心の底から理解した。人生の中では、時には失敗することだってあるかもしれない、後戻りはできないこともあるかもしれない。けれど、それは恐れたって仕方のないことなのだ。大切なのは、自分がどこへ進んでいくのかを自分自身が決めることなのだ。自分が本当は何を望んでいるのかだけを、きちんとわかつていればいいのだ、と。」と書いています。
私も旅先でいろいろな体験をしますが、いつもの日常と違い、ほんとうの偶然との出合いのように思い、頭のなかですっきりと考えがまとまったりします。そして、後から考えると、やはりその一瞬が自分にとって大切なことだったと思うのです。
下に抜き書きしたのは、第3章「小さな島での一週間」に出てくるものです。
たしかに、自分たち以外誰もいない小さな島で、電気も水もない生活をすれば、いろいろなことを考えます。
私も、今月初めに津軽三十三観音札所詣りをしましたが、ほとんど誰とも会わず、1人で観音堂でお詣りしていると、太陽や雲の動きや風の流れを感じます。特に今年は、あちこちにクマが出没するので、それに対する恐怖感もあります。
でも、そのような孤独感のなかだからこそ、今までの自分を振り返ったり、これから先のことを考えたりできます。むしろ、そのようなところが、人間には必要ではないかとさえ思えます。
そういう意味では、この本は、トーベ・ヤンソン夏の記憶を追いかけながら、自分自身を追っかけ見つめ直すきっかけになるような気がしました。
(2025.10.25)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| トーベ・ヤンソンの夏の記憶を追いかけて | 内山さつき | 東海教育研究所 | 2025年9月2日 | 9784924523531 |
|---|
☆ Extract passages ☆
長いこと日々の仕事に追われるままでいると、自分が本当は何をしたいのか、わからなくなっていってしまう。自分がしたいことを追求するためには、ときにはリスクを取らなければならないこともあるけれど、そのリスクと向き合う恐怖から、私はずつと目を逸らし続けていた。そして日々押し寄せてくる仕事の影に、問題を見ないようにする自分を隠していた。島に来て、これから自分はどう進んでいけばよいのだろうと考える時間が増えた。トーベのようには才能も勇気も、エネルギーもないけれど、女性が仕事を持って芸術家として生きるのが今よりもっと過酷な時代に、前を向いて歩み続けたトーベの生き方に思いを馳せると、小さな勇気が湧いてくるような気がしていた。
(内山さつき 著『トーベ・ヤンソンの夏の記憶を追いかけて』より)
No.2477『テレビが終わる日』
私は昔からあまりテレビを見ないほうでしたが、現在も1週間に3本程度しか見ません。ただ、ご飯を食べるときに孫たちがテレビを見ているので、食べながら見ることはありますが、あまり興味のない番組ばかりなので、ほとんど記憶にも残っていないようです。
だから、今すぐにテレビがなくなるといわれても、あまり気になることはなさそうです。しかし、インターネットがなくなるといわれれば、それは困ります。私自身の情報の入手先は、インターネットを通じて入手しているので、それはほんとうに困ってしまいます。
この本に書いてあるように、近ごろのテレビのリモコンには、YouTubeやNetflix、そしてAmazon Prime Videoなどにダイレクトにつながるボタンが備え付けられています。もちろん、テレビにインターネットを接続しなければ見られないのですが、家庭内にWi-Fiがあれば、それも簡単につながります。ほんとうに便利な時代です。わが家のリモコンを見てみると、さらにTYerやABEMAなど12個もありました。
私の場合は、テレビより自分のパソコンで見た方が映像もきれいだし、音声もよく、気に入ったものは何度でも見られるのでよく使います。
ただ、つい見てしまうと、ずっと見てしまうので、それは気を付けています。だから、もしテレビが終わる日が近づいても案外平気だと思ってます。
おそらく、インターネットを中心とした情報は、これからますます増えるとは思いますが、問題はあります。たとえば、自分の興味のあるものしか見ないことで、視野が狭まったり、一部の情報だけで片寄った見方をしたりするような気がします。今のテレビも新聞も、ある程度、網羅的に配信しているので、興味がなくても見てしまい、これは大切かもしれないというものもあります。おそらく、地球全体のこととか、海外の問題などはそうかもしれません。
また、No.2474『人類の終着点』を読んだときも感じたのですが、今のITを運用しているのは、たとえばマイクロソフトやグーグルやメタなど、一握りの巨大IT企業が最終的な決定権を持っています。日本の情報すらそうです。たとえば、今回のトランプ米政権が同政権に批判的な意見や不適切だと判断した発言に対する「取り締まり」を強めています。今まで自由の国アメリカと思っていたのに、このようなことが起こりえるということです。まったく怖い話しです。
だとすれば、ますますテレビを見ないという人が増えてきそうです。私は植物が好きですが、テレビで植物を扱うのは、非常に限られています。でも、動画共有サイトでは、いくらでも検索すれば出てきます。まったく見たことも聞いたこともない植物でさえも、世界中のサイトにはあります。だから、つい本当に興味のあるものしか見なくなるのかもしれません。
でも、テレビというのは、この本には、ある程度のムダや遊びも必要だと書いてあり、それもよくわかります。そういえば、著者はNHKに入局してアナウンサーとして15年ほど勤務した経験があり、「私自身の経験として、番組のネタ探しに行き詰まって、街の中をふらふら歩いていたところ、たまたま入った図書館で見つけた本がきつかけになり、企画に結びついた、などということはしばしばあることです。テレビの仕事は、何が幸いするかわからないところがあります。あまリガチガチに管理してしまうと、面白いアイデイアも出てきませんから、ある種の「無駄」というか、「あそび」のようなものが必要とされるというのはあります。」と書いてます。そしてその後で、「ただ、それが悪い方向に働くと、「これくらいならいいだろう」「これくらい誰にも分からない」という思考に陥り、不正や不祥事につながりやすくなります。もし、テレビ局員に不祥事が多いのだとしたら、そういうところに遠因があるのではないか、と私は思っています。」とあり、これなどは本音だと感じました。
下に抜き書きしたのは、第5章「テレビからネットへ、なぜ主役は交代したのか」に書いてありました。
たしかに、今の時代は、企業城下町ですら、その基幹産業の流れが変われば、なくなったり、他に移転することもあります。むしろ、大手の企業は小回りが利かなくて、大変だという話しも聞こえてきます。
だとしても、ほんとうにテレビ局がなくなれば、困ることもあり、これはテレビがほんとうになくなってしまう前にしっかりと考えなければならない大きな問題だと思います。
(2025.10.22)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| テレビが終わる日(新潮新書) | 今道琢也 | 新潮社 | 2025年6月20日 | 9784106110917 |
|---|
☆ Extract passages ☆
一般の企業ならば、売り上げが落ちれば工場を閉鎖。売却するなど、保有設備を縮小するのが普通ですが、テレビ局はそれができないのです。従って、テレビを見る人がいればいるほど経営効率が良くなりますが、逆に見る人が減っていくと、固定的なコスト負担がどんどん重くなっていくという構造にあります。
こうしてみると、テレビ局は、今までは法令によって守られて、寡占的に放送業を営むことができていたのですが、テレビビジネスが下火になってくると、むしろそのことが重荷になってきているようにも見えます。テレビがメディアとして勢いを失いつつあるのに、テレビというビジネスモデルから離れられないところに、テレビ局の抱える間題の厄介さがあります。
(今道琢也 著『テレビが終わる日』より)
No.2476『新版「がまん」するから老化する』
本の題名って、ほんとうに大事で、私自身があまり我慢することが好きではないので、「がまん」するから老化するという考え方には賛成です。ある意味、我慢ばかりして長生きしたとしても、なんのための人生かと考えてしまいます。
ところが、この本を読むと、我慢しないことが長生きにつながるというのですから、願ったり叶ったりです。
この本は、2011年2月に新書版として出されたものを、新版として文庫版にしたものと「あとがき」に書いてあり、著者の老化予防のひとつの結論をまとめたものだそうです。文庫版になり、活字も大きくなり、とても読みやすいと思いました。それと、具体例が載っていて、とてもわかりやすく、たとえば、日本食はあまり内蔵に負担をかけるものではなく、懐石風の料理ならお勧めだそうです。
これは、「たとえば日本の会席風の料理なら、魚介などタンパク質の食材を使った先付が出て、刺身、焼き物と続く。油を使った揚げ物が出されるとしたらその後だ。タンパク質から摂ることになるので、血糖値は緩やかに上昇する。最初からインスリンを大量分泌させたりしないので、揚げ物が出てくるころにはかなりの満腹感がある。締めで軽くご飯を食べて、最後にデザートとして果物が出るという、タイムリー・ニュートリションの理論に適合する賢い食べ方だったのだ。」とあり、私も茶懐石などで経験しているので、すぐに納得できました。
ここに出てくる「タイムリー・ニュートリションの理論」というのは、クロード・ショーシャ博士の理論のことで、「臓器の活動時間に合わせて最適な食事をすれば内臓の負担が少なく、細胞の炎症も少なくてすむ」という考え方です。
たしかに、すべての臓器が24時間つねに働いているわけではなく、それぞれの動きによって活動時間帯が違うというのは理解できます。
また、「廃用」という現象もすぐに理解できました。この「廃用」と呼ばれる現象は「歳を取れば取るほど起きやすくなる。脳の知的な活動についても同様だ。若者の場合、勉強をさぼっているとテス卜の成績こそ下がるものの、知能テストの結果がどんどん悪くなるということはありえない。だが高齢者が入院して、ずっと天丼を見ているような暮らしをしていると、急速に記憶力や、日時や自分がどこにいるのかという見当識が衰えて、認知症のような症状が現れることは珍しくない。筋肉も脳も、使わないことによる衰えが激しくなるのだ。」ということで、私も長く生きてきたことで、すぐにわかりました。
昔は、脳細胞は年を取るほどに減少するといわれましたが、細胞そのものは減ったとしても、知的な活動まで衰えるということはないというのが、今の主流の考え方です。つまりは、脳でも筋力でも、年を取ればそれなりに衰えますが、ある程度の状態を維持することもできるそうです。たしかに、オリンピックなどを見ていても、中年の星みたいな選手はいます。
ちょっと老化とは違いますが、心理療法についての行動主義について、今年の5月まで更生保護に関わってきたので、なるほどと思ったのですが、「たとえば心理療法において注目される行動主義とか行動療法は、それまでの精神分析が心の奥底に原因を突き止めて心を治していたのと違い、行動を変えれば心も変わってくるという考え方に基づいている。「うつで歩けない」と訴えている人に、原因から迫って治療し歩けるようにするより、「歩けるじゃないですか」と声をかけるなどして行動から入る。そのほうがよく治るし、早く治るのだ。あるいは非行少年に対して、カウンセリングで心を治していって非行をしないようにするよりは、信賞必罰の体系をきちんとつける。これも行動療法的な発想だ。」という指摘です。
なんでも許されると思っている少年に、はっきりと、これはダメだ、もしやったら次はもっと大変な施設に入れざるを得ないよというと、ギクッとします。やはり、釘を刺すということも大切だと感じました。
下に抜き書きしたのは、第5章の「がまんは老化の元」に書いてあったもので、まさにこの本の題名通りです。
この下りの前に、「ブドウ糖が足りなくなれば、即座に脳に悪影響がある。糖分と酸素は脳にとって最重要な物質なのだ。だから脳に酸素が足りなくなるとすぐにあくびが出てくるし、必要なものに対しては欲求が出るように人間の体はできている。味覚はその大切な機能である。」とあり、なるほど、身体が欲しているということは、それだけ必要だからかもしれないと思いました。
(2025.10.19)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 新版「がまん」するから老化する(PHP文庫) | 和田秀樹 | PHP研究所 | 2022年12月16日 | 9784569902715 |
|---|
☆ Extract passages ☆
人間が「美味しい」と感じるのは、甘いもの、脂肪分、うま味成分=アミノ酸である。自分の体に必要なものは美味しく感じるように、生物進化の過程でできあがっているのだ。甘いものはエネルギーにしやすい糖分だし、脂肪は効率的なエネルギーであるとともに細胞膜の生成や修復に欠かせない。食事で摂ったタンパク質はアミノ酸に分解されてから、私たちの細胞の材料になる。
美味しく感じるものを体が欲しているわけだから、元気がないときは脂肪がいつもより美味しく感じたりする。「肉が食べたいな」「ラーメンが食べたい」というのは体が求めているわけだ。
(和田秀樹 著『新版「がまん」するから老化する』より)
No.2475『人類の終着点』
副題が「戦争、A1、ヒューマニティの未来」で、朝日地球会議が企画し、エマニュエル・トッド、マルクス・ガブリエル、フランシス・フクヤマ、メレディス・ウィテカー、スティーブ・ロー、安宅和人、岩間陽子、手塚 眞、中島隆博の9名の方が著者として出ています。聞き手はの4名で、対談形式のところもあり、まさに今の時代の直近のことばかりです。
この朝日地球会議というのは、「朝日環境フォーラム」としてスタートしたそうですが、2016年からは現在の「朝日地球会議」あらため毎年秋に開催してきたそうです。しかし、コロナ禍のなかでは、リアル国際シンポジウムができなくなり、4年ぶりに開かれた今回のメインテーマは「対話でひらく コロナ後の世界」となったといいます。
そこでは、「第1部では、AI研究者で元グーグルの研究部門責任者のメレディス・ウィテカー氏、ストラテジストの安宅和人氏、ヴィジェアリストの手塚眞氏を加え、長野智子さんにコーディネーターをお願いしました。一部のプラットフォーマーがなかば独占的にAIを開発する現状についての懸念を示しつつ、日本の文化の価値再認識によって、この新たなテクノロジーと共存する可能性も語られました。第2部では、国際政治学者の岩間陽子氏、マルクス・ガブリエル氏とも親交の深い哲学者の中島隆博氏をお招きしました。このセツションでは、世界の知性のインタビューを引き取って、グローバル化の流れを70年代のドイツの「東方外交」やデタントと紐づけて説き、希薄化したコミュニティやアソシェーションヘの「参加と責任」の実現が民主主義再生のきっかけになると提示しています。また、多様な文化、社会に埋め込まれているスイツチを相互理解により見出すことの大切さに言及したことはマルクス・ガブリエル氏が強調する「道徳的実在論」による対話的アプローチともシンクロしています。」とあり、まさに世界的な研究者が寄り集って開催したことがわかります。
私は、マルクス・ガブリエル氏の「絶対的な道徳的事実」という考え方に共感しました。たしかに、非常に単純な例ですが、単純化されているからこそ、真実が伝わってくると思います。この「絶対的な道徳的事実」は、誰でも、どんな国であっても、さまざまな制約を乗り越えてひとつになれることだと思います。
そこで、これを下に抜き書きしましたので、ぜひ読んでもらえればと思います。
また、AIといえでも、人間の力がなければ開発できないことは当然ですが、まさかアフリカのケニアの人たちがからんでいるとは思いもしませんでした。それは、「たとえば、ChatGPTを開発したOpenAIは、ケニアのSamaという会社と下請け契約を結んでいました。その会社では、非常に低い賃金と引き換えに、労働者に不穏なコンテンツを繰り返し閲覧させ、ボタンをクリックしたり指示を与えたりして不適切な内容であることを機械に教え込む作業をさせていました。そうすることで、機械は出力すべきではない内容を統計的に認識するようになります。しかし、こうした作業が労働者にもたらす副次的な結果は、非常に有害です。不快なコンテンツに繰り返しさらされることで、働く人々は精神的に参ってしまったり、心身の健康を損なったりしてしまったと報じられています。」と書いてありました。
つまり、ロボットが情報を勝手に集めてくるわけではなく、「何を望んで何を望まないか、何がOKで、何がNGであるかを伝えるのは、知能を持った人間」しかできないのです。
やはり、多くの労働者たちが関わり合って、膨大なシステムができあがり、それらが巨大IT企業、マイクロソフトやグーグルやメタによって運用されるのです。その決定権を握るのは一握りの巨大IT企業だけです。まったく怖い話しです。
それと、現在のアメリカ大統領を報道で知る限り、これからの世界がとても心配です。フランシス・フクヤマ氏は、「優れた大統領やリーダーになるには、良い人格が必要なのです。その点、トランプは考えられる限り、最悪の人格を保有しています。リーダーとして、これ以上考えつかないほど最悪です。自己中心的で嘘つきで、公共心はありません。何事も個人の利益になるかどうかで判断して、公の利益は考えもしません。そんな人に資格はありません。」と言い切ります。
しかも、この発言は、前回のトランプ大統領のことですから、今の2期目はさらに世界中を混乱させています。毎日、ニュースにならない日もないようです。
このことを含めて、歴史は暗い過去へと逆戻りしているのかもしれませんが、なんとか明るい未来がやって来るように世界中の人々が手を取り合えることを願っています。そういう意味でも、下に抜き書きしたのを、ぜひ読んでみてください。
(2025.10.16)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 人類の終着点(朝日新書) | 朝日地球会議 企画 | 朝日新聞出版 | 2024年2月28日 | 9784022952547 |
|---|
☆ Extract passages ☆
非常に単純な例を使いましょう。子どもが浅瀬で溺れているとします。このとき、自分自身に問いかけてみてください。「その子どもを助けなければならないのか?」と。その際に、条件はありません。あなたは車椅子に乗っているわけでもなく、自分の子どもと他の子どものどちらかを、選ぶ必要もありません。問題は目の前に子どもがいるだけで、あなたがすべきことは、子どもを水から救い出すことだけです。
この状況では子どもは救うべきだ、とみな知っています。私が誰であろうと子どもが誰であろうと関係ありません。その子がどこの出身であろうと、どんな宗教、民族、性別だろうと関係がありません。また、私の民族、性別、宗教が何であるのかも関係ありません。それらのことはまったく関係なく、私はその子を救わなければならないのです。これこそ、私が「絶対的な道徳的事実」と呼ぶものです。
(朝日地球会議 企画『人類の終着点』より)
No.2474『文化が違えば、心も違う?』
この本の題名を見て、文化が違えば、たしかに心のありようも違ってくるのではないかと思い、読み始めました。
そういえば、だいぶ昔に和辻哲郎氏の『風土』を読んで、とても印象に残っているのですが、ここでいう風土というのは、その土地の気候、気象、地質、地形、景観だけでなく、今でいうところの人間を取り巻く環境などや自然などを含む空間すべてを含んでいたように思います。なかでも、砂漠で生まれた宗教とモンスーンで生まれた宗教の違いなどは、何度も読み返しました。
この本でも、終章の「文化心理学という知の冒険」のなかに、「文化心理学の視座から見れば、文化は単なる背景や外的な要因ではない。そうではなく、文化とは、人の思考や感情を形づくり、最終的には、人の心そのものの構成要素となる。北米と日本における研究に始まり、その後ラテンアメリカやサブサハラ・アフリカにまで広がった探究の旅を振り返ると、文化がどれほど私たちの知覚、感情、判断に影響を与えているかが明らかになる。また同時に、文化は人間の「つながり」を形成する重要な鍵でもある。と書いてあり、現在の文化的多様性のなかで起きているさまざまな分断が新たなつながりを築くきっかけになるかもしれないと思いました。
そもそも、この本の副題は「文化心理学の冒険」ですから、そのように読み解いてもあまり外れてはいないようです。
この本の中で、新型コロナウイルス感染症の海外での流行の早さに言及したところがあり、私もおそらくは日本人とは違い人との接触密度が違うからではないかと思っていました。それがデューク大学のサルバドールさんで「彼女は、私たちとともに、関係流動性の指標が存在する36カ国のコロナの毎日の感染数と死者のデータを入手・分析した。具体的には、それぞれの国でコロナの確定症例が見つかった直後の30日間に、どのような速度で死者数が増加するか、死者数の「成長曲線」を検討したのである。そして、予測通り、メキシコやアメリカなどの関係流動性の高い国は、日本やハンガリーなどの関係流動性の低い社会と比較して、ウイルスの拡散がかなり速いことを明らかにした。」ということで、その違いこそが国々による対応の違いになったのではないかと思います。
また、私はまったくお酒が飲めないのですが、欧米系の人たちと比べても、日本人はお酒が弱く、だから泥酔する人もいると聞いたことがあります。
この本には、「この地域に住む人の多くはアルコールに弱い。ちょっと飲むとすぐ赤くなり、飲み続けると二日酔いする結果になる。アルコールを摂取するとそれは分解されてアセトアルデヒドという物質となり、アセトアルデヒドはさらに分解されてエネルギーに変換される。この中間物質であるアセトアルデヒドの体内濃度が上がると、顔の紅潮や二日酔いが促される。したがって、飲酒をしようと思ったらアセトアルデヒドを分解するのが重要なのであるが、この分解の速度は遺伝的に制御されている。この関連の遺伝子の一つに、ADH1Bと呼ばれるものがある。この遺伝子には突然変異体が同定されているが、この突然変異体は、アセトアルデヒド分解の効率を低下させ、その結果、この変異体を持っているとアルコール摂取時に血流中にアセトアルデヒドが急速に蓄積される。つまり、この変具体の保持者は「お酒に弱い」ということになる。」と書いてあり、ちょっと長い引用でしたが、私自身がなぜ飲めないかという理由が知りたくて、書き移しました。
つまり、ADH1Bというのは、エタノールを分解する酵素のことで、それがないとアルコールを分解する能力がないというわけです。
そういえば、二十歳を過ぎてお酒が飲めるということで、仲間とビールを少し飲んだのですが、その後は倒れたそうで、病院に運ばれました。そのときのお医者さんが、お酒は飲まない方がいいとアドバイスしてくれました。そして30年後にそのお医者さんがいる医師会から講演を頼まれ、その後の懇親会でお会いしました。その後もなんどか通院したこともあり、私の顔を見るなり、お酌をしようと持って来たのをすぐ引っ込めて、あのときの話しをしました。それぐらい印象に残った患者だったようです。
下に抜き書きしたのは、第5章「多様性と普遍性を探る旅」にあったものです。
たしかに西欧的な独立しようとする人が多いところと、アジア的なものごとを丸く収めようとする地域的な違いはあります。でも、ある意味、地域に固有の帰結ではなく、相互関係についての文化の違いなので、そこから多様性と普遍性を導き出すことも意義のあることだと思いました。
(2025.10.12)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 文化が違えば、心も違う?(岩波新書) | 北山 忍 | 岩波書店 | 2025年8月20日 | 9784004320784 |
|---|
☆ Extract passages ☆
名誉と尊厳は、いずれも自己を肯定し、他者からの評価を含む価値観であるが、その成り立ちには大きな違いがある。名誉は社会中心的であり、他者からの評価や認識を条件とする。一方、尊厳は自己中心的であり、自己の内的価値を重視する。このような視点の変化は、近代西洋文化の形成において重要な役割を果たした。
(北山 忍 著『文化が違えば、心も違う?』より)
No.2473『それでも旅に出るカフェ』
この本の表紙を見て、勝手に旅先でいろいろなスイーツを食べ歩きを書いたのかと思いました。ところが、これは「小説推理」2022年1月号から2022年10月号にかけて連載されたものだそうで、小説でした。
それでも、行きつけのカフェ「カフェ・ルーズ」を中心に、様々な人生模様と、さまざまな世界のお菓子や食べものが出てきて、とてもおもしろかったです。ほとんどが初めて知るもので、その国やさの由来なども記されていて、興味を持ちました。
たとえば、最初のほうで出てくるバームクーヘンですが、もとはドイツのお菓子だとはみな知っていますが、ドイツでは地方のお菓子でむしろ知らない人が多いということで、びっくりしました。私は大丸東京店で売っている「ねんりん家」のストレートバーム「やわらか芽」が好きなんですが、日本には、「三大バームクーヘン」といわれるのが、このねんりん家とクラブハリエ、治一郎だそうです。だから、このバームクーヘンも日本の洋菓子として定着しているのに、ドイツではほとんど知られていないというのは意外でした。
この本には、そのようなことだけでなく、まったく見たことも聞いたこともない洋菓子がいろいろと載っていて、いつかは食べてみたいと思いました。
たとえば、「鳥のミルク」というケーキですが、これはロシアやウクライナ、チェコなどでも食べられているそうで、表面にチョコレートがかかっていて、なかは白いムースとスポンジが層になっているそうです。その上にミントの葉がのっていて、見た目はそれほどでもなさそうですが、名前の由来はスラブ地方の民話からきているそうです。つまりは、今のウクライナに対するロシアの侵攻は、まさに兄弟げんかみたいなものではないかと感じました。
この小説は、新型コロナウイルス感染症流行のさなかに書かれたもので、その影響もあちこちにあります。たとえば、「今日は何人の人が亡くなったと聞いても、知らない人ならばただの情報でしかない。それどころか、「高齢者だから、基礎疾患のある人だから仕方ない」などと言う人まで、いる。生活が制限されることよりも、まわりの人が無関心になっていく方がずっと恐ろしい。戦争な
どが起こっても、こうなるのだろうと、はっきり想像できるから。」と書いてあり、その当時は、いろんなことが新型コロナウイルスのことにされてしまうような雰囲気がありました。
下に抜き書きしたのは、この小説の題名につながる話しです。
私も旅が好きで、つい先日、9月29日から10月3日まで、大人の休日倶楽部パスを利用して津軽三十三観音札所詣りをして、そこから東京に出て、東京国立博物館で開催されている「運慶 祈りの空間―興福寺北円堂」を観てきました。この大人の休日倶楽部パスなら5日間JR東日本管内なら何度でも利用可能ですし、しかも6回まで指定席をとることもできます。
まさに旅好きにはもってこいの切符だと私は思っています。
下に抜き書きしたのは、それもありだと思いましたが、この小説の最後のところで、円が瑛子に「旅は、いろんなものを棚上げにできるから好きなんです」というくだりがあり、それはちょっと逃げているように感じました。つまりは、いったん棚上げにして、どこかに逃げ出すということになります。
私の旅は、旅先でのいろんな体験から、新しい物の見方や考え方ができるようになると思っています。つまりは、今までの自分にはなかったものを身につけるチャンスと捉えているようだと改めて思いました。
(2025.10.9)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| それでも旅に出るカフェ | 近藤史恵 | 双葉社 | 2023年4月22日 | 9784575246193 |
|---|
☆ Extract passages ☆
旅先で、どこかでキッチンを借り、その上地に伝わるレシビを試作してみたり、もしくはよその土地のお菓子を、別の土地で売ったりしているのかもしれない。
カフェ・ルーズのコンセプトは、「旅に出られるカフェ」だと、最初に訪れたときに聞いた。
お客さんが、遠い土地の飲み物ゃスィーツを楽しんで、旅に出た気分になれるカフェだということだが、カフェそのものが旅に出てしまうことも、できるかもしれない。
(近藤史恵 著『それでも旅に出るカフェ』より)
No.2472『ジジイの昭和絵日記』
著者は、1944年生まれで、私が20代のころに読んだことのある「本の雑誌」などで、表紙やなかのイラストなどもおぼろげながら覚えています。でも、この本では絵本専門の出版社として出てきますが、これはこぐま社のことで、ここに15年ほど勤務していたことは知りませんでした。
むしろ、椎名誠たちとは遊び仲間だとは思っていましたが、この本のなかでも触れていますが、千葉市立千葉高等学校で椎名誠と同級生で、「椎名の卓越したところは、言わば趣味の同人雑誌でありながら、すでに2号目から裏表紙に三松商事のネクタイの広告が入り、やがて丸井の全国店舗紹介の広告が入っていたことである。彼はデパート関係の業界誌の編集部に勤めていたから、おそらく無理やりお願いしたものだろう。と言うのも、いつもながらその行動力、相手を説得させる力は卓越したものがあった。高校時代から親分肌のところがあり、自分の遊び、仕事にがむしゃらに突き進み、周りの者を常に巻き込むのであった。」と書いています。
たしかに、椎名氏はその風貌もそうですが、文体も独特で、彼らとのつき合いからイラストレーターの道に入ったとばかり思っていました。また、彼が学生のころに学園紛争真っ盛りで、私もときも入学したのに1学期は学内がロックアウトされてしまい、9月になってやっと構内に入れたことを思い出します。
今年の4月、そのときの同期会がお茶の水の大学跡地に建てられた駿河台キャンパスの19階にあるレストランで開かれたのですが、久しぶりに訪ねたこともあり、なんとも複雑な気持ちでした。それでも、4年間、いろいろと苦楽を共にしてきた同期の人たちと話しながら、いろいろなことを思い出しました。おそらく、この本を読みながら、共感するのも、似たような体験をしてきたからではないかと思います。
そういえば、著者も中国の満蒙開拓団のことを知ったことで、なんどもこの地を訪ねたようですが、私も植物つながりで、中国の雲南省や四川省にはなんどか足を運びました。この本に中国での酒の話しが出てきますが、「洒といえば忘れてならないのが、1972年の日中共同声明のレセプションである。当時の総埋大臣。田中角栄と外務大臣。大平正芳が北京に渡り、日務院総理・周恩来、毛沢東も参列し、日中の国交を正常化した。問題は上海での訪中最後の歓迎の宴会の時に、日本側は歓喜興奮したのか洒を飲みすぎ酪酎してしまったことだ。周恩来はその姿を見て、外務担当者に「会食の時の酒は普段飲むときの三分の一の量を超えてはならない」と諭したそうだ。」と書いています。
実は私も四川省を訪ねた後に、北京で中国科学院の先生たちとの歓迎会があり、超高級店につれていかれたのですが、そのとき、私はお酒を飲めないと言ったのに、トップの人の乾杯だけはうけてほしいといわれ、やっとのことで飲んだことがあります。乾杯は、必ず杯を乾かさなければならないと初めて知りました。つまり、杯を逆さにして見せ合うのです。そのときに、中国の行政官僚は酒が強くないとなれないのではと思いました。
だから、そのときの印象がとても強かったのですが、私も歳を重ね、中国の植物研究者よりも年長になり、まわりの人たちも飲めないとわかったこともあり、それ以来、飲むこともなくなりました。でも、今思えば、どんなに酒を飲んだとしても、日本のような酔っ払いを見たことはありません。
下に抜き書きしたのは、「高原列車の旅」に出てくる小海線のことです。
じつは、私も2019年6月26日に小海線に乗り、小渕沢駅から甲斐小泉駅まで行き、念願だった平山郁夫シルクロード美術館にまわり、近くで1泊しました。そして翌日には小海線に乗り佐久駅まで行ったことがあります。
そのときに、野辺山駅がJR線のなかで一番高い位置にある駅ということで、標高1,346mと書いてありました。
でも、こんな山のなかを走る電車なのに、なぜ小海線というのかとか、それにしても海のつく駅名も多いのにもびっくりしました。すると、この本にその理由が書いてありました。
(2025.10.6)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| ジジイの昭和絵日記 | 沢野ひとし | 文藝春秋 | 2025年4月30日 | 9784163919737 |
|---|
☆ Extract passages ☆
小海線は海から遠く離れた山奥を走るのに、なぜか「海」のつく駅名が多い。
「佐久海ノロ」「海尻」「小海」「海瀬」などである。海瀬駅には皮肉にも「日本一海から遠い駅」の看板がある。
平安時代に八ヶ岳、天狗岳付近で山津波が起こり、大規模な岩崩れで千曲川がせき止められていくつかの湖を形成した。巨大な天然ダム湖は後に決壊して大洪水が起きることになるが、鎌倉時代まで残った湖もあり、あたりは小海と呼ばれるようになったという。
駅名にも海の名を残すところに、信州人のロマンと粋な心を感じる。
(沢野ひとし 著『ジジイの昭和絵日記』より)
No.2471『千利休101の謎』
9月29日から10月3日まで、大人の休日倶楽部パスを利用して津軽三十三観音札所をお詣りしてきました。そして、最後の日は上野の東京国立博物館で「運慶 祈りの空間 興福寺北円堂」を観て、旅を締めくくりました。
その間にこの本を読み終えました。いつもは、旅に出るときは旅籠のなかに抹茶碗や茶杓、茶筅などを持ち歩くのですが、今回は、久しぶりにそれらを持ち出さずに荷物をなるべく軽くしたいと思いました。それで荷物を少なくするために、なるべく削り、ついには旅籠もなしということにしました。
それでも、その地方の銘菓を食べたいという思いがあり、それでお茶に近づける方法として、この本を読むことにしたということです。これはだいぶ前に買って積んで置いたもので、そのなかから選んだのです。もともと、千利休のことは、あちこち読んでいたので、断片的にはわかるのですが、今回は長く新幹線に乗ることで、集中的に読み、それら断片がなんとなくつながったようです。
たとえば、利休は堺の出身ですが、なぜ堺で茶の湯が盛んになったのかというと、今まであまり意識はしていませんでした。それがこの本では、「まず、茶人の空海(島右京)が京都から堺へ移住したことと、京都で修行していた紹鴎が堺へ帰郷したことが、堺で茶の湯が流行する直接的な端緒となったものと思われます。なお、この茶人の空海は、真言宗を開いた僧侶の空海(弘法大師)とは別人です。茶人・能阿弥から東山流の茶の湯を伝授された茶人の空海は、堺で道陳を指導しました。これに対し、村田珠光の高弟・十四屋宗悟、宗陳に師事した紹鴎は、帰郷後に津田宗達、今井宗久、茜屋宗佐、油屋紹佐らをはじめとする堺の商人を指導します。やがて、紹鴎らの指導が身を結び、堺から宗及や利休などの、時代を代表する茶人が相次いで登場したのでした。」と書いてあり、やはり時代的な背景も押さえておかなければならないポイントだと思いました。
もちろん、堺は貿易都市として、当初は納屋衆、のちには会合衆が合意制によって市政を運営していたことは有名で、この納屋というのは今でいえば倉庫業とか、総合商社のようなものだったようです。だから、経済的にもゆとりがあり、お茶をたしなむことができました。
そういえば、利休没後、千家の茶は、子の道安と養子で娘婿の少庵へと受け継がれていくのですが、「子の道安、養子、娘婿の少庵の茶の湯の特徴は、それぞれ道安が剛と動、少庵が柔と静などといった言葉で表されることが多いようです。なお、京都の名刺・西芳寺(苔寺/京都市西京区)の湘南亭、麟閣と同様に少庵ゆかりの茶室と喧伝されてきました。さらに、水指、釜、棗、盆などの茶道具に、少庵好といわれる逸品の存在が知られています。」とあり、3代目の宗旦のときに表千家、裏千家、武者小路千家と別かれます。
私自身は、京都の醍醐寺にいたときに表千家とのつながりができ、自坊に戻ってからもお稽古を続けました。50年ほどして、私の師匠が亡くなり、それから近くのお茶の先生にも習いましたが、今はその方も亡くなられたのでお稽古もやめてしまいました。それでも、家ではほぼ毎日、お抹茶を点てて、そのときどきのお菓子といっしょにSNSに載せています。今回のような旅などでも、旅籠にお茶道具を入れて持っていくのですが、荷物が多くなるので、今回は持って行くのを諦めました。
昨年の春、福島県立博物館で会津若松ゆかりの茶道具などを見て、それから会津若松城のなかにある麟閣にまわり、お抹茶をいただきました。ついでに、赤べこの印刷された懐紙があったので、それを求めてきました。
今回の旅の最後に青森から東京へ出た日に、根津美術館で開かれている「焼き締め陶」の展示を見てきました。ここは、写真は一切ダメで、印象に残ったのはいろいろありますが、先ずは桃山期の「備前矢筈口耳付水指」で、銘は「黙雷」です。すごい存在感がありました。甕では、珠洲焼の焼き締めで、叩いたときの線がびっしりとつき、しっかり造られた印象です。
やはり、私もなるべくなら華麗な道具類より、素朴な焼き締め陶のようなものが好きだと改めて思いました。
下に抜き書きしたのは、第8章「利休と〈天下人&茶頭〉の謎」にありました。
ここには、禁中茶会を契機に、利休居士号を勅賜され、「天下の宗匠」という評価を得ることになったと書かれています。
もちろん、これを開催したのは太閤秀吉ではありますが、小座所の一室で公家や門跡らに茶を点てたそうですが、これは台子の茶という正式な茶道具を用いる作法でした。私も台子点前をしたことがありますが、正式であるが故に、難しいお点前だったという印象しかありません。
今回はお抹茶を点てることもない旅でしたが、帰路の前に少し時間があったので、トラヤ東京で、菓銘「栗粉餅」でお抹茶をいただきました。なかに求肥で包まれた御膳餡が入っていて、その秋らしい風情を味わうことができました。
(2025.10.3)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 千利休101の謎(PHP文庫) | 川口素生 | PHP研究所 | 2009年8月19日 | 9784569672991 |
|---|
☆ Extract passages ☆
禁中でこのように大規模な茶会が開催されたのは、これがほぼはじめてでした。こういった関係もあり、禁中茶会そのものと、これを開催した秀吉のことは、瞬く間に世間の耳目を集めました。同時に、利体居士号を勅賜され、茶を点てた利体の名声も、瞬く間に天下へ轟いた感があります。前後しますが、禁中茶会の終了後、利休はその様子を覚書に纏め、参禅していた臨済宗の禅僧・春屋宗国に送りました。党書の末尾には利休自身が、
「一世の面目、これに過ぎず候」
と記しています。これを機に利体は、「天下の宗匠」という評価を得るにいたります。
(川口素生 著『千利休101の謎』より)
No.2470『あなたがスマホを見ているとき スマホもあなたを見ている』
この本の題名が興味を引き、読むことにしました。
たしかに、今どきのスマホは、いろいろなデータを収集していますし、そこにたくさんの個人情報も入れている方も多く、むしろスマホがなければ動けなくなる人もいるそうです。
そういえば、数年前に電波障害からスマホが使えないということがあり、道もわからなければ電車も使えない、さらに現金の持ち合わせがないことから何もできないということが現実に起きたことがあります。私の場合は、今もなるべくなら現金支払いをしているので、たとえスマホを自宅に忘れてきたとしても、そんなにも不便さを感じることはありません。
そんなことを考えながら読んで見ると、そのようなことより、著者の身辺雑記のことが多く書いてありました。そこで「あとがき」をみると、読売新聞で書いてコラムが全部で238本あり、そのなかから選んだものが中心ということです。でも、3本はこの本のための書き下ろしで、この本の題名にもなっている「あなたがスマホを見ているとき スマホもあなたを見ている」もその1本です。
そのなかに、「人の行動や意識がすべて情報化されるネット時代では、メール、預金額、収入、株取引といった重要な個人情報から、昨日どの店で食事をし、コンビニで何を買ったか、朝から夜までの行動パターンまでネットは、あなたのことを何もかも知っているのだ。本人さえ忘れている行動も、スマホを通してネットは記録している。自分が見ているつもりでも、逆に見られているということにもなる。「君が深淵をのぞきこむとき、深淵もまた君を見ている」といったのは19世紀の哲学者、ニーチェだった。21世紀の「深淵」は長方形の液晶画面の裏側に隠れている。」と書いてあり、たしかにそうだと思いました。
だから、通販でも簡単に個人情報を載せたり、タダだからと思い、あまり使わないアプリを入れたりするのも、考えものです。いつの間にか、それらが勝手に使われたりしないとは限りません。便利な世の中も、時には注意しないとなにがあるかわからないものです。
いつも思うのは、何かひとつ買うと、それに類した商品を薦められたりするのは、おそらく情報としてどこかにプールしてあるからのようです。
これからは、なるべく商品を買うときには、実際のものを見て、納得してからとは思うのですが、どこから買っても同じなら、つい安いところから買ってしまいます。ときには、価格比較までしてしまいます。でも、商品の型番で買えるものなら、つい考えずに買ってしまう人が多いようです。
先日、ネットオークションを見ていたら、図柄のおもしろい菓子皿がありました。でも、これにどのようなお菓子を盛れば引き立つかを考えました。この本のなかで、著者がある料理屋で板前さんが常連客とかわした言葉について書いてありました。
それは、「最近の店は白い無地の器ばかり使うから、盛りつけが雑になっている。彼らは色や絵のある器は、使いこなせないんじゃないか」という話しです。
たしかに、最近のお店に行くと、白い皿や黒い皿など、図柄がないものが多いように思いました。
私は、使いやすさより季節感などがないほうがいつでも使えるから食器をたくさん揃えなくてもいいからではないかと思っていました。図柄があると、つい季節感や料理に引き立つものと考え、種類も数も増えてしまいます。
でも、私などは陶磁器が好きなこともあり、だからこそ楽しいのではないかと思うのですが、店主側にすれば置き場所や経費の節減にもなると考えているのかもしれません。
今年の7月に日本民藝館で「棟方志功展」を見てきましたが、ここには、柳宗悦が「用の美」として見出した生活の中で使われたものがたくさん収蔵されています。それらを見てみると、単なる機能美だけでなく、使われることで初めて輝きを放つものがありました。
下に抜き書きしたのは、「3日の情報断食に耐えられないなら、私もりっぱなデジタルバカ。」に書いてありました。
そういえば、私も昔は旅に出るときでさえもノートパソコンを持ち歩き、どこでも使っていました。ところが70歳をすぎたあたりから、1㎏に満たないノートパソコンでも重く感じ、持ち歩かないようにしました。その代わり、スマホをよけい使うようになり、それも、旅先では連絡用にしか使わないようにしています。また、デジカメも、以前は重いフルサイズの機種を使っていましたが、これ以上軽くできないようなコンパクトカメラを使っています。
それだって、スマホで間に合うのではと思うのですが、やはりカメラにはいろいろな機能が付いていて、それでなければ撮れないものがあります。
そう考えられば、私もりっぱなデジタルバカかもしれません。
(2025.9.30)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| あなたがスマホを見ているとき スマホもあなたを見ている | 藤原智美 | プレジデント社 | 2017年12月18日 | 9784833422581 |
|---|
☆ Extract passages ☆
現代人は夢中になれること、刺激的で興奮、あるいは感動することを追いかけるように暮らしている。だから若い世代は退屈な時間を知らないし、年配の世代も、かつて退屈な時間があったということを忘れている。
しかし退屈って、そんなに悪いことか?そんなことはない。外から情報や刺激がないと、案外、気分が楽になるし、ときに内省的になれる。ふだん忘れていたことを思いだし、自分の人間関係や自分自身について、あらためて考える時間にもなる。
(藤原智美 著『あなたがスマホを見ているとき スマホもあなたを見ている』より)
No.2469『増補 害虫の誕生』
この文庫版は、2009年にちくま新書として出版された『害虫の誕生――虫からみた日本史』で、その増補版という位置づけのようです。でも、基本的には新書版と同じだそうで、さらに「補章 害虫の誕生再考」は、新書版を出版して16年も経っているので、もう1度、自然と人間との関係について考えなおしたものだと著者は「文庫版あとがき」で書いています。
それにしても、害虫とか益虫だとかは人間の勝手な分け方で、虫たちにしてはまったくあずかり知らないことです。そして、この本を読むと、昔の人たちも、害虫という感覚はほとんどなかったようです。むしろ、今いうところの共生のような関係で、虫たちがいるのは自然だし、気にもしていなかったようです。この自然という言葉だって、明治時代も後半になって、西洋の「Nature」の訳語として使われるようになった言葉ですから、比較的新しい言葉です。
それでも、仏教では自然と書いて「じねん」と読み、「自ずから然らしむ」という意味でそれ以前から使っていました。これは、人間が作り出したものではない「あるがままの状態」を指していますから、虫たちだって、いるのが当たり前という感覚です。だとすれば、仏教的には、殺生を戒められてきたわけですから、害虫だからという理由で殺していいわけはありません。
私が初めてインドに行ったときに、食べものの上にたくさんのハエがいて、どうしても食べられなかったことがあります。すると、インドの友人が、フッと息をかけていなくなったスキに食べました。そんなのありですかと聞くと、もしあなたの先祖がこのハエだとしたら殺せますかと、逆に質問されてしまいました。それを聞いて、今もインドでは輪廻転生が生きていると感じました。
この本のエピローグで、「プロローグで述べたように、有害な虫をひとくくりにして総称する「害虫」という用語は、日本では近代に入ってから生まれた。そして〈害虫〉を人間の手で排除することが当たり前となったのも、明治期以降のことである。もちろん江戸時代以前にも害虫は存在したが、たんに「虫」と呼ばれ、一種の天災と考える人々が多かった。それが明治以降、農業害虫の排除がすすめられ、さらに大正期には衛生害虫が排除されるようになったのである。つまり日本では、〈害虫〉は近代に誕生した存在であると言えよう。」と書いていますが、虫送りのような伝統行事を思い出しても、たしかにそうだと思います。
そういえば、虫の語源は、「(貝原)益軒は1700年に著した語源辞書『日本釈名』で、「虫」の語源は「蒸し」であると述べ、虫が蒸し蒸しした状態から生じることを示唆している。国語学者ではない私には、この語源論が事実かどうかは判断できない。だが、虫が湿気によって発生するという観念が、江戸時代の日本では極めて一般的であったことがうかがえるだろう。このような「虫の自然発生説」は、決して奇妙な迷信などではない。西洋世界においても、虫の自然発生は古くから信じられていた。」とあり、今年のように蒸し暑い夜が続き、やっと涼しくなるころに秋の虫の音が聞こえてくると、たしかにそのような解釈はありうると思います。
ところが西洋では、17世紀になってイタリアのフランチェスコ・レディが、密閉されたフラスコと口を開けたフラスコを用意し、その中に肉片を入れて観察すると、口を開けたものだけからハエが発生することがわかり、自然に虫が出てくることはないと確信したそうです。どうも、日本人と西洋人のものの考え方が異なることもおもしろいと感じました。
しかし、そもそも害虫を殺す殺虫剤や除草剤などは、毒薬です。これらは、戦争を契機として開発されたという歴史もあり、「よく知られているのは、第二次大戦期のドィツにおける有機リン殺虫剤の開発である。1936年、化学企業I・G・ファルベンの化学者G・シュラーダーは、抜群の殺虫力を持つ有機リン化合物を発見した。ここから生まれたのが、パラチオンやマラテオンなど、戦後世界中で使われるようになる有機リン系の殺虫剤である。1938年、シュラーダーはもう一つの有機リン系の毒物を発見する。シュラーダーは、その物質に「サリン」と名づけた。」といいます。
サリンと聞けば、ほとんどの人があの忌まわしい地下鉄事件のことを思い出すでしょうが、どう考えてみても、殺虫剤や除草剤などは人間の身体にもよいはずはありません。
だからといって、これからの食糧問題を考えたとき、これらを使わないことで品質や収量に大きな影響があっても困ります。つまりは、なるべく人間に影響の少ないものを使うかどうかの問題でもあります。
下に抜き書きしたのは、プロローグに書いてあったものです。
今まで、コガネムシは黄金だから金持ちだと思っていましたが、そうではないと知り、びっくりしました。たしかに野口雨情は、北茨城市磯原出身で今でもの野口雨情の生家は、磯原の海を望むように建ち「観海亭」と呼ばれ親しまれているそうですが、ここで15歳で上京するまで過ごしていました。
だとすれば、小さいときから慣れ親しんだコガネムシをそのまま使ったと考えられます。やはり、子どものときの環境は、大人になってからも大きな影響を及ぼすと思いました。
(2025.9.27)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 増補 害虫の誕生(ちくま学芸文庫) | 瀬戸口明久 | 筑摩書房 | 2025年6月10日 | 9784480511782 |
|---|
☆ Extract passages ☆
群馬県高崎地方では、チャバネゴキブリのことを「コガネムシ」と呼んでいたという。「コガネムシは金持ちだ」という野口雨情の童謡で歌われているのは、この虫のことなのだ。ゴキブリが多いと金が貯まるという話は、愛知県や岡山県にも残っている。秋田県では、ゴキブリを駆除すること自体が厳しく戒められていたという。おそらく食料が多い豊かな家にゴキブリが居つくことから生まれた風習だろう。
このエピソードは、現在私たちが(害虫)と呼んで当たり前のように駆除している生き物が、かつては害虫ではなかった場合があることを示唆している。〈害虫〉の境界線は、時代によって常に揺れ動いているのである。
(瀬戸口明久 著『増補 害虫の誕生』より)
No.2468『生命と時間のあいだ』
著者の「生物と無生物のあいだ」を読み、それと同じような題名にひかれて読み始めました。
この本は、もともとはシチズン・カンパノラのサイトに掲載された「時の図書館」がもとになっているそうで、現在開催されている「EXPO2025」でプロデュースした「いのち動的平衡館」とのつながりもあるそうです。この本のなかで、著者が10歳の少年のとき、親にねだって出かけた「EXPO'70」のさまざまな思い出にも触れていますが、そう考えると、どこかでつながっているかのように思えます。
そういえば、レオナルド・ダ・ヴィンチの手稿はたくさん残っているそうですが、私が昔見たものにはヘリコプターのようなものがありました。あの当時に空を飛ぼうとしていたことに驚きましたが、著者は、おもしろい推理をしています。それは、「なぜ、彼はそれほどまでに空にあこがれていたのだろうか。ダ・ヴィンチは、フィレンツェ・メディチ家に仕える優秀な公証人セル・ピエロの私生児として生まれ、幼くして生母から引き離されて、近郊のヴィンチ村で世間の目からも隠されて育った。私生児は経済的にも社会的にも差別の対象だった。十分な学歴も得られなかった。田合の自然の中で育ったから、類稀なる自然観察者になったのではない。都会的なセンスと繊細さを併せ持つ少年が、田合の差別の中で息を潜めるように育ったがゆえに、内向的で孤独な自意識と冷めた観察眼を研ぎ澄ませたのだ。学歴がないことのコンプレックスが、彼の反抗心のバネを強化していく。……とすれば、飛翔への希求も自ずと理解できるのではないだろうか。イモムシはある日、急に固まって蛹となり、そこから優美な翅を持った輝ける蝶がまろび出ずるように、彼もまた変身し、変化し、一切の桎梏を振り切って、自由な空へ抜け出したかったのだ。」と書いています。
たしかに、このような流れのなかで育ったからということもありますが、また、数学から美術まで、いろいろなことがずば抜けてできたことで、いろいろな創造力が生まれてきたようにも思います。常人では理解すらできないことを、さらっとこなしていく多面性もあります。私が好きな言葉は、『超訳ダ・ヴィンチ・ノート』に載っている「私たちのあらゆる認識は、感受性で決まる。」です。考えてみれば、当たり前のことで、同じものごとを眺めても、人によって受け取り方が違います。だとすれば、先ずは感受性を育てることです。
同じものを見ても、何も感じない人もいれば、感動する人、さらに深く考える人もいます。まさに人それぞれですから、つまらないことでも、そのなかにはワクワクする工夫もあるはずです。おそらく、ダ・ヴィンチもコンプレックスを感じながらもいろいろなことに感動することを楽しんでいたのではないかと思います。
この本のなかで、時間を多面的な角度から考えていますが、時間軸を持つことの大切さを感じました。それは、「時間軸を持っていると、私たちヒトがいかにしてこの地球上にこれだけの文化と文明を築くまでになったのか、人類がどんな苦労をして、いかなる失敗を繰り返して進んできたのか、いや、そもそもヒトが出現する前にどれほど膨大な地球史的時間と生命史の物語が織りなされてきたのか。そのすべてのプロセスを、自分の内部の幹として立ち上げることができる。すると個々の知識は、その幹に連なる枝葉のようにおのずと配置され、その脈絡が見えるようになる。たとえ個々の固有名詞を忘れたとしても、すぐに幹と枝からたどって行くことができる。ネットの中に情報は溢れているけれど、情報をつなぐべき時間軸、つまり幹がすっかり見えにくくなってしまっている。時間軸はどこにあるのか。それはやはり本の中にこそある。」といいます。
そして、著者は、少年のころに時間軸の存在をはじめて明確に教えてくれたのが、バートンさんの『せいめいのれきし』だったと書いています。
私も、ひとつのことをまとめきれないときには、図を書いたり、箇条書きにしたり、それを上下にずらしたりします。おそらく、それも時間軸をつくろうとする無意識の作業かもしれません。たとえば、「系統樹」もそうですが、大雑把な進化の過程を知ることができます。これは、生物が共通祖先から分かれて進化した歴史を、樹木のように枝分かれした形で表した図ですから、この図を見れば、現代の生物の多様性がどのように形成されたかを理解するためには重要なツールのひとつです。
そう考えれば、時間軸を持つということは、いかに大切なことかがよくわかります。
下に抜き書きしたのは、第Ⅱ部の「生命とは何か』のなかに書いてありました。
私自身、あのアゲハチョウが卵から始まり、幼虫、蛹、そして成虫へと変化するとは知っていましたが、さなぎからあのきれいなアゲハチョウになることは不思議だと思いながらも、よくわかりませんでした。ここを読んだときには、びっくりするというよりは、生命の不思議を感じました。
まさに、破壊と創造です。昔、インドに行ったときに、知り合いのインド人に日本の大黒さまは豊穣の神で、どちらかというとものを生み出すという話しをしました。すると、彼は同じではないかといいます。そのとき、インドの大黒天は破壊の神ですが、ものごとは破壊しないと新しいものを生み出すことはできないと直感しました。つまり、破壊と創造はともに必要だということです。
この下の文章を読むと、やはり同じだということが理解できます。そういう意味では、自然というのはすごいシステムのような気がしました。
(2025.9.23)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 生命と時間のあいだ | 福岡伸一 | 新潮社 | 2025年7月30日 | 9784103322139 |
|---|
☆ Extract passages ☆
……もし何も介入を行わなければ、サナギの内部で劇的なプロセスが着実に進行する。ドロドロに溶けた幼虫の細胞から、アゲハチョウの美しい羽と胴体、細い脚と触角が再構成されてくるのだ。2週間ほどすると、サナギの背が二つに裂け、そこからアゲハチョウがこばれだしてくる。最初はくしゃくしゃに折り畳まれた紙のようだった翅脈に力がみなぎり、すっと伸びた見事な羽になる。蝶はしばしのあいだまるで呼吸を整えるようにサナギの殻につかまったまま羽をゆっくり開閉させた後、ふいに空中にひらひらと飛び立つ。私は胸を熱くしてそれを見送った。そして思った。なんて生命は繊細にできているのだろうか。どうして幼虫の身体はすべて溶けてしまう必要があるのだろうか。いかにしてそこから蝶ができてくるのか。破壊と創造。そして行き着く最後の間いはいつも同じだった。生命とは何か?
(福岡伸一 著『生命と時間のあいだ』より)
No.2467『Z世代のアメリカ』
トランプ氏が大統領になってから、今のアメリカを知りたいと思い、いろいろと読んでみましたが、この本はアメリカのZ世代に焦点を合わせているだけでなく、現在のアメリカの考え方にも触れています。これを読むと、なぜトランプ氏が大統領になれたのかもわかるような気がしてきました。
アメリカでは、1960年代中ごろから1980年代前半に生まれた世代を「X世代(ジェネレーションX)」と呼んだそうで、その次の1980年代前半から1990年代なかごろに生まれた世代を「Y世代(ミレニアル世代)」といい、その流れからその次の世代をアルファベット順で「Z世代(ジェネレーションZ)」というようになったそうです。つまり、Z世代というのは、1990年代後半から2010年代前半ころに生まれた世代を指す言葉で、小さいときからインターネットやスマートフォンが普及した環境のなかで育ったことから、デジタルに抵抗なく使いこなせる年代でもあります。
そのようなことから、情報の収集能力や社会問題への関心の高さ、さらには個人の価値観を重視する傾向も強いそうで、この本でも、「今のままでは自分たちはアメリカの歴史上、ほとんど初めて、権利の後退を体験する世代になってしまう」という危機感を感じ、民主党支持に駆り立てたのではないかといいます。
もともと、アメリカには「例外主義」というのがあり、これは「アメリカは物質的・道義的に比類なき存在で、世界の安全や世界の人々の福利に対して特別な使命を負うという考えである。『アメリカ外交辞典」によれば、対外政策における「アメリカ例外主義」とは、(1)アメリカは人類史において特別な責務を担っており、(2)他国に対してユニークであるだけでなく、優越していることへの信念として定義され、より具体的には、(a)堕落した「旧世界」ヨーロッパと対置される「新世界」アメリカという自負、(b)アメリカは歴史上のいかなる大国とも異なり、堕落や衰退の危険を免れ、革新
的な国家であり続けられるという自信、(c)アメリカはその行動によって人類史を進歩に導かねばならないとする使命感、として定義される。」といいます。
これを読むと、だから世界の警察のようなことをしたり、民主化のために軍隊を派遣したり、テロ対策だとして空爆をしたりしていたわけです。しかし、それが成功したとは、ほとんどの人が認めないと思います。むしろ、トランプ大統領が「アメリカ・ファースト」というのもある程度理解できます。
しかし、今回のロシアとウクライナの問題にしても、アメリカが動かないと今のところダメなようです。8月19日に、ホワイトハウスでトランプ大統領とゼレンスキー大統領の首脳会談が行われたのに続き、イギリスやフランス、ドイツなどの5か国、そしてEU=ヨーロッパ連合とNATO=北大西洋条約機構の首脳らも交えての会合が行われましたが、テレビで見る限り、トランプ大統領の起源を損なわないようにほめまくっていたようです。つまり、アメリカ抜きでは停戦も進まないと思っているからでしょう。
そういえば、今回のヨーロッパ各国の取り組みには、今までとは違うような気がします。この本には、ブルガリアのキリル・ベトコフ首相(当時)が語ったはなしとして、「ウクライナの(中略)人々は、私たちがこれまでに見てきた難民とは違います。彼らはヨーロッパ人です。知的で教養のある人々です。彼らは(中略)素性も過去もわからない、テロリストである可能性がある人たちとは違うのです」という話しが載っています。そして、その話しの続きでは、「ウクライナ侵攻への国際社会の対応は、私たちが語る「人道」が決して普遍的ではなく、レイシズムを内在させていることを明らかにした。ともに大規模な人道危機でも、西洋人に「そっくり」な人々が住むウクライナと、そのようにはみなされない国や地域では、寄せられる国際的な関心には明らかに差がある。」といいます。
これは、私も感じていました。この「レイシズム」とは、ヨーロッパに根強く残る考え方で、人種間にも優劣の差があり、優れた人種が劣った人種を支配するのは当然とする思想やイデオロギーのことで、それは当然ながら人種差別につながります。
おそらく、意識するとしないにかかわらず、心のどこかにこのような考え方があるように感じます。
下に抜き書きしたのは、第5章「人道の普遍化を求めて』のなかに書いてあったものです。
9.11というと、テロというイメージばかりが先行しますが、このような話しはアメリカではすでに知られていることで、「ワース 命の値段」という映画は日本でも2023年に公開されているそうですが、その嫌な役を無償で引き受けたというからすごいことです。おそらく日本の弁護士で、もし同じようなことがあれば引き受けたとしても無償ではあり得ないのではないかと思いました。
(2025.9.19)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| Z世代のアメリカ(NHK出版新書) | 三牧聖子 | NHK出版 | 2023年7月10日 | 9784140887004 |
|---|
☆ Extract passages ☆
9.11の後すぐに、犠牲者の遺族や現場で被害に遭った人を救済するため、公的資金で9.11被害者補償基金が設立された。事件後すぐに、ハイジャックされた飛行機の航空会社などを相手にした集団訴訟の動きが持ち上がったが、こうした訴訟が多発すればアメリカ経済への大打撃になりかねない それを危惧した政府が、訴訟を回避することを目的の一つとして立ち上げたのだ。補償金の受け取りと引き換えに訴訟権の放棄を求める形で、遺族や被害者合計5560人に対し、総額約70億ドル超(当時のレートで約1兆500億円)が配分された。この補償プログラムの特別管理人に任命され、犠牲者ひとりひとりの補償額を決定する中心的な役割を担ったのが、弁護士ケネス・ファインバーグだ。彼は33カ月間にわたって無報酬で取り組んでいる。人の命に「値段」をつける仕事に対して報酬をもらうのは適切ではないと考えたからだという。
(三牧聖子 著『Z世代のアメリカ』より)
No.2466『将棋指しの腹のうち』
もともと将棋にはあまり興味はなかったのですが、藤井聡太さんがテレビなどで見ていると、よく勝負めしが出てくるので、その食べものの方に興味を持ちました。
すると、そのものずばりのこの本を見つけ、すぐ読み始めました。
人というのは、自分の知らない世界のことを知りたくなるようで、仕事の内容もそうですが、どんな人がいて、どんな生活をしているのかも気になります。それが、その世界に長く住んでいる人なら、いろいろと知っているはずです。意外と薄い文庫本で、読みやすいこと請け合いです。
たとえば、加藤一二三さんですが、あのひょうきんな受け答えに親しみを感じます。ところが将棋界では往時は「神武以来の天才」と呼ばれ、A級在位36期、名人にもなった大棋士だそうです。しかも、引退後はタレントとしても活躍し、今現在もコマーシャルなどで見ることもあります。その現役のころ、明治の板チョコしか食べなかったそうで、著者が聞いたところ、「答えは明快すぎるものだった。「いや、それはですね、家の近所に明治製菓に勤めている人がいまして、やはり明治を食べないと悪いかな、と思って」「へ?それだけですか?」「はい、それだけです」私は腰が抜け、コンビニなどない時代、明治のチョコを求めて駆けずりまわった関係者のことを脳裏に浮かべたのだった。」そうで、その人柄がなんとなくわかります。
あるとき、担当者だった奨励会員が別なメーカーのものを用意したそうですが、絶対に食べなかったというから、たしかにユニークではあります。
このような話しを聞くと、それで将棋という勝負の世界を渡っていけるのかと心配になります。
でも将棋は戦いだそうで、「それも、高度な武器が発達した近代以前の戦争を反映したゲームなのだ。まず自分の陣形を作り合う。そして、戦いが始まって、相手の陣形の一角が破れたら、一気にそこからなだれ込んで敵の大将である玉に向かって一気に攻め込むのだ。小学校低学年からこのゲームをやり他には何もやっていない者が、闘争心が弱いわけがない。もちろん、盤を離れれば、争いごとを嫌う平和主義者が多く、それはむしろ一般の世界以上と言えるかもしれない。ゲームはゲーム、他は他。ゲームの理屈を他に持ち込まないから、我々はプロなのだ。」と書いています。
たしかに、それはそうだと思います。それでなければ勝てるわけはないので、それだけに集中して何時間もやり続けるわけですから、やはり好きでないとできません。
先日、藤井さんが小学生から一番好きなものはと聞かれ、結局は将棋ですかね、と答えていたことを思い出しました。そういえば、もし棋士になっていなかったら電車の運転士になりたかったそうですが、息抜きでチェスを解くこともあるそうで、それはあくまでも息抜きですから将棋が一番なんでしょうね。
著者は「あとがき」で、「将棋指しは変わらない。将棋のルールが変わらないかぎり、変わらない。生きるエネルギーのそのほとんどを将棋を勝つことに向け、おいしいものを食べ、そして酒を飲む。そしてどんな時代も若い人が先輩を打ち負かしてゆく。」と書いていて、なるほどと思いました。
勝負の世界だけでなく、どんなに無敵を誇る人でも、かならず負けるときがきます。だとしたら、その負けてからの人生というのは、それまでの戦いの日々とは違う生き方を考えなければならないと思います。そういう意味では、棋士のその後みたいなものも読んでみたいと思いました。
下に抜き書きしたのは、第7局『ふじもと』に書いてありました。
そういえば、私も、日光に夕方に行き、一晩中話し込み、明け方近くに運転して帰ってくると、疲れているのになかなか寝付けませんでした。いろいろな植物関係者と話しをして、世の中にはそんなに珍しい植物があるのかと知り、いつかは現地で見てみたいと思うと、考えただけでもワクワクし、眠れなくなります。そして、朝食を食べ、さあ、これからというときに睡魔が襲ってきます。
それでも若い時ですから、忙しさが去ってからバタンと眠りにつき、30分も寝るとすっきりと目覚めるというようなことが何度もありました。
(2025.9.15)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 将棋指しの腹のうち(文春文庫) | 先崎 学 | 文藝春秋 | 2023年3月10日 | 9784167920142 |
|---|
☆ Extract passages ☆
これはフアンの方には意外なことのようだが、棋士なら誰でも対局の前より対局の後のほうが眠れない。棋士同士答え合わせをして、逆のことを言った者はひとりとしていない。特に、深夜までかかった将棋ならなおさらである。集中しすぎて、脳が覚醒しきってしまい元に戻らないのだ。
(先崎 学 著『将棋指しの腹のうち』より)
No.2465『「選べない」はなぜ起こる?』
この本を見たとき、とっさに、だいぶ前に、あるデパートの地下で派遣の食品販売員をしていた方の話しを思い出しました。それは、あまりにたくさんの商品を並べるより、品数を絞って、これはというものだけを並べるというものです。
たしかに、今はいろいろなものがありすぎ、選ぶ楽しみというよりは、なかなか選べないということもあります。二択三択なら、そんなに難しい話しではありません。しかし、本を読んでみると、それもありますが、今は情報そのものも多すぎて、しかも企業の切磋琢磨からそれらの商品も、たいした差がなくなりつつあることもその理由だそうです。しかも、書いてある内容も字が細すぎて読みにくく、ついいつものを選び勝ちです。たしかに、この本の題名のように「選べない」ということも多々あります。
この本には、情報が多すぎる時代にはこんな行動をとる、とあり、「①新店舗を見つける。②地図アプリやグルメサイトでレビューをチェックする。③Instagramで料理の写真を見る。④「いつか行こう」と先送りする。⑤結局、いっもの店に行く。」というパターンです。
私なら、せっかく新しいお店を見つけたのだから、先ずは行ってみようと思います。飲食店なら、先ずは行ってみないことには、その雰囲気やおいしいかや自分の口に合わないかはわからないはずです。もし、それほどでもないなら、次に行かなければいいだけの話しです。そもそも、みんなの口に合うような料理なんて、無難なだけですし、インスタ映えするだけなのかもしれません。
もし、自分に合うものだったら、それでSNSの評価が低かったら、まさに穴場です。むしろ、そういうところを見つけ出すのが楽しみです。
人には、多数派の選択や行動に従うことで安心感を得る心理、「同調性バイアス」と、もう一つは他者と区別される自分らしさを表現したい欲求の「独自性欲求」があります。これを同時に満足させることはできないので、どちらかに絞る必要があります。ところが、今の時代は「みんなの最適解」がSNSなどで先に見えてしまっています。「だから自分の納得解を選んだつもりでも「最適解だから選んだ(自分の本当の意思は違う)のでは?」という意識が生じてしまう。かといって、すべての選択で最適解を外すのも不自然だ。それでは「ただの天邪鬼」になってしまう。」ということになります。
だとしたら、意識的に「最適解」を遮断したり、SNSなどを見ないということも必要です。つまり、自分で選択するということにすればいいわけで、以前はみんなそうしていたはずです。いわは、選択基準を自分に取り戻すということです。
そして、あまり幅を広げず、自分好みのものだけに焦点を絞ればいいと私は思います。
下に抜き書きしたのは、第2章『選べない時代の「選ばれ方」』のなかに書いてあったものです。
たしかに、多くの人に選んでもらいたいからといっても、そのニーズにすべて応えるようなものはありません。だとすれば、「すべての人に好かれようとしない」という姿勢も大切になってきます。いくらお客さんの声を大切にするとはいえ、ときには自分たちのもの作りの姿勢を全面に押し出すことも共感してもらえるきっかけになります。
十人十色といいますから、いろいろなものがあってしかるべきで、だからといって、品数があればそれでいいという問題でもありません。最後にAIを使った選択の話しが載っていましたが、「AIが何を根拠に「あなたにオススメ」とするか、そのロジックはいくつかある。代表的なのは「これを買っている人は、これも買っています」というデータや「あなたに近い人は、これも高く評価しています」という過去の他者データを根拠にしたロジックだ。つまりAIは他者データと過去の自分のデータを掛け合わせて、オススメをしてくる。実際にその選択で満足した人が多いのだから、提示された選択肢は「間違ってはいない」だろう。だがその一方で「驚き」や「大当たり」に出会うチャンスは失われていく。自分向けの元ネタが「過去の自分」なのだから、そこにセレンディビティを感じられないのはある意味当たり前だ。」とかいてあり、なるほどと思いました。
このAIのオオスメを使うことは選べないときにはそれなりにいいのですが、いつもは絶対に選ばないようなものを選んでみることも、AIを混乱させるのでおもしろいのではないかと私は思っています。
(2025.9.12)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 「選べない」はなぜ起こる? | 小島雄一郎 | サンマーク出版 | 2025年6月15日 | 9784763142313 |
|---|
☆ Extract passages ☆
「これが私たちの信念であり、それを共有できる人だけに選んでほしい」というスタンスが、逆説的に強い支持を生む。明確な意思があれば、生活者は「この考え方に共感できるか否か」という単純な基準で選択できるようになる。これこそ情報過多の時代における強力な「差別化」だ。
(小島雄一郎 著『「選べない」はなぜ起こる?』より)
No.2464『私、山小屋はじめます』
知り合いが、今年の7月に北アルプス黒部の秘境雲ノ平を歩いたと聞き、私はほとんど山小屋には泊まらず、テント泊だったことを思い出しました。それでも、まったく山小屋に泊まったことがないわけでもなく、最後に泊まったのは飯豊山の切合小屋で、食事も準備してもらいました。
そこで、今もやっているのかと気になり、ネットで調べてみると、今年も一泊二食付きで9,000円だそうです。
そんなこんなで、この本を図書館で見つけ、いろいろな自分の山登りを思い出しながら、読むことにしました。
著者は、2020年4月に川根本町で山小屋の管理人を募集していることを知り、それに応募して「県営 光小屋」の管理人になったそうです。この「光」というのは、私は山野草栽培をしていて、「光岳キリンソウ」を栽培したことがあり、「てかりだけ」と読むことができましたが、そのま「ひかり」と読む人の方が多いそうです。
もちろん、まったく山小屋の仕事をしたことがないわけではなく、「鳳凰小屋」や「金峰山小屋」などでアルバイトをしたことがあるそうですが、ここの「光小屋」は標高2,520mのところにあり、南アルプス最南端の山小屋だそうです。登山口までは最寄りの高速道路のインターからおりて2時間弱で、そこから歩いて1時間半でやっと登山口。そこから登り初めて山小屋まで8時間かかるというから遠いというか、おそらく日本百名山にでも選ばれてなければここまでやって来る人はあまりいないのではないかと想像できます。
しかも、せっかくここまで上ってきてくれたからということで、「夏の間の1ヵ月は、朝ご飯の時間を4時に前倒しすることにした。「さっき寝たばっかじゃないっけ?」と思いながら、まだ真っ暗な3時に起きる。根裏にあるスタッフ部屋からノソノソと下りていき、開いているのか閉じているのか自分でもわからない瞼を無理やり開けて、コンロのつまみをひねる。それができたら安心。ご飯さえ炊ければ大丈夫だ。朝ご飯は、白ご飯に梅干しをのっけて、お味噌汁、煮魚ともちふの卵とじという、至ってシンプルな献立にしている。寝坊が一番恐ろしいからな。早発ちの人には、夜のうちにおにぎり弁当を渡す。これは夕飯の後にせっせと握る。」を毎朝繰り返しているわけです。
そして、登山者を見送り、朝食を食べ、少し休んでからトイレや宿泊棟、食堂などの掃除をして、そうこうしているうちに、日帰りの登山者が記念品を買ったり、トイレを使ったり、まさにシーズン中は休みはとれないそうです。
もちろん、小屋を開ける時や閉めるときなどは、利用者こそいないのですが、しっかり段取りをしないと後々困ることになります。たとえば、小屋開けはお祭り騒ぎみたいで、「小屋開けとは、9ヵ月ほど閉めていた空き家にお客さんをお招きするようなもの、とお考えください。まず鍵を開けて、閉め切った雨戸を開放するところからスタート。そこから1階部分と食堂の荷物を片付け、ヘリで上がってくる荷を置くスペースを確保する。そして大事なライフラインの整備。水のポンプアップ、放電対策で外していた発電機のバッテリーを付け、それぞれが正常に機能するか祈るように確認する(毎年、どこかしら不具合が見つかっている……)。それから、やっばり掃除が一番大変な作業だ。閉め切っていた室内はカビだらけ、ほこりだらけ。食器棚のうつわ類も丁寧に洗う。小屋の中には、撤収した太陽熱温水器、スターリンクの設備、太陽光パネル、単管や床板を保管しているので、それら大物をまず外に出さなければスペースがない。20項目以上ある″やることリスト"を進めながら、ヘリ荷受けの準備も整える。なんせ、ヘリは予定どおりには飛ばないことが前提で、2024年シーズンは1週間も遅れてしまった。遅れれば遅れるほど営業開始までの時間が少なくなって焦るのだが、どうなるかはお天道さま次第。天候を見ながらできる作業を進めるしかない。毎年、ドキドキである。」と書いてあり、ちょっと足りないものをコンビニで買ってくるというわけにはいきません。
こうして今も続いていますが、この間、新型コロナウイルス感染症が流行したり、登山道が崩落して通れなくなったりとさまざまなことがありました。ときには、素泊まり営業にするしかなかったそうですが、それが逆に良い方向に進み、「自分で食料を背負い、小屋に頼らず自炊をする自己完結型の登山者が増えた結果、彼らは到着も早く、日没後に到着する方は1年目よりも格段に減ったのだ。また、食事を提供しない分、今まで仕込みにあてていた時間を小屋周辺の環境整備に使うことができた。」そうで、そういえば、私の知り合いもこのような素泊まりだったと聞きました。
私も観音詣りのときなどにホテルを利用するときには、ほとんど素泊まりです。その方が時間にしばられないし、自分のペースでなんでもやれるので便利です。そう考えれば、山も町も同じかもしれません。
下に抜き書きしたのは、山小屋を任されて1年目の話しに出てきました。
たしかに、夏場がかき入れ時なので、ほとんど休みはないと思っていましたが、やはりそうでした。それでもスタッフはそれでは集まらないので、休みをなるべくつくるようにしているそうです。
ただ、自分の休みは、自営業と同じで、なかなかとれないというのが実情で、やはり山が好きでないと勤まらないようです。
(2025.9.9)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 私、山小屋はじめます | 小宮山 花 | 山と渓谷社 | 2025年6月5日 | 9784635330855 |
|---|
☆ Extract passages ☆
シーズン中、管理人の私には基本的に休日はなくて、お客さんがいない悪天候の日が休日になる。薄暗い小屋に雨音と風音。寝たり起きたりしながら、お菓子をぼりぼり食べたり。小屋開けから駆
け抜けた日々を振り返ったり。ジメ~とした小屋の空気のなか、軽やかななにかが欲しい時、私はポップコーンを作りたくなる。よく量を読み間違えてフライパンから爆発させるのだけど、それもまた休みっぽくていい。
半端な時間のお休みには、少し小屋から離れたところまで散歩に出たり、お気に入りの場所で日なたぼっこをするのが好きだ。毎日を過ごす小屋の居心地が悪いわけではないけれど、小屋から離れると手に入る、一人だけの時間。気持ちの整理がついたり、新しい発見があったりする。山小屋の仕事って、意外と小屋内で過ごす時間が長いので、日に当たりたくなります。日なたぼっこ、結構大事。気持ちが前向きになるよね。
(小宮山 花 著『私、山小屋はじめます』より)
No.2463『雑草散策』
副題は「四季折々、植物の個性と生き抜く力」で、植物好きにとっては魅力のあるものです。
そして、田中 修さんの本は、どちらも中公新書ですが、『植物はすごい 生き残りをかけたしくみと工夫』や『植物のいのち-からだを守り、子孫につなぐ驚きのしくみ』、『雑草のはなし』などを読んだことがあります。これ以外にも読んでいるので、少しダブっているところもありました。
たとえば、スミレの繁殖法ですが、いろいろな本に載っています。この本には、その巧みな方法として、「1つ目は、タネの表面に「エライオソーム」という、アリの好きな物質をつけていることです。……アリに運んでもらえば、飛び散る範囲を超えて、生育する場所を広げることができるのです。2つ目は、花のうしろに袋状の「距」という部分をもつことです。……距の蜜を吸えるのは、 ストローのような長い「口吻」とよばれる器官をもつ昆虫に限られます。……その構造によって、花粉を運ぶ昆虫を選ぶことができれば、受粉の効率が高まることが期待されます。3つ目は、唇弁とよばれる、くちびる状の花びらに縞模様があることです。これは、ハチやチョウを蜜のある距へ誘うための「蜜標(ネクター・ガイド)」とよばれます。……4つ目は、夏から秋に、「閉鎖花」とよばれるツボミをつくることです。このツボミは花咲くことがなく、ツボミの中で自分の花粉を自分のメシベにつけて、タネをつくります。」とあり、その戦略を詳しく書いています。
だからこそ、春先になると、あちこちにスミレが咲くのです。そういえば、スミレの同定は難しいのですが、それは交雑しやすいからです。おそらく、それだけ「閉鎖花」を利用せずに、他のスミレの花粉を使おうとしているからです。
小町山自然遊歩道にも、たくさんのスミレが自生していますが、ここに30数年前に記念樹で庭に植えたけれど、大きくなりすぎたので植えて欲しいと頼まれたのが、「ヒマラヤスギ」でした。その後、1988年5月にインドのマナリーに言ったときに、この辺りがヒマラヤスギの自生地だというところを通りました。ところが、そのときにスギというよりはマツに近いと思いましたが、この本に「ヒマラヤスギは、スギという言葉がついていますが、スギ科に属する植物ではなく、マツ科の植物で、マツの仲間なのです。そのため、大きなりっぱな松ぼっくりをつくるのです。」とあり、たしかに雪の残る時期に小町山自然遊歩道に行くと、ヒマラヤスギの松ぼっくりが落ちています。
この本には、ヒマラヤスギの英語名は、「ヒマラヤン・シーダー」なので、日本では、この「シーダー」がスギなので、そのまま「ヒマラヤスギ」と命名されたのではないかといいます。このシーダーというのは、ラテン語で「ケドラス」といい、針葉樹を意味するとあり、なるほどと思いました。
また、ときどき小町山自然遊歩道でも「ヘクソカズラ」の花を見ますが、このような名前をつけられていやだろうなと思います。でも、この本にも書いてありましたが、このような名前だからこそ、人の印象に残り、次の世代まで残されていったことを思うと、これはこれでそれなりの理由があるということです。学名も、「パエデリア・スカンデンス(Paederia scandens)」で、「パエデリア」はラテン語で「悪臭」を意味し、「スカンデンス」は「よじ登る性質の」を意味するそうです。
下に抜き書きしたのは、第5章「秋の野で、季節を演出する植物たち」のなかに書いてありました。
ススキは、スクスク伸びるからススキという和名がうまれたといいますが、秋の七草では「尾花」と詠まれています。とはいえ、不用意に触れると、ナイフで切ったようにケガをします。
おそらく、葉が鋭いからだろうと思っていたのですが、それだけではありませんでした。
こうしてみると、植物というのは、調べれば調べるほど、いろいろと不思議なことをなんでもないことのように生活しています。だから、この「プラント・オパール」を調べれば、日本のいつの時代からイネを育てていたのかもわかるわけで、大切なことだと思います。
(2025.9.6)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 雑草散策(中公新書) | 田中 修 | 中央公論新社 | 2025年6月25日 | 9784121028624 |
|---|
☆ Extract passages ☆
ススキは、土の中に含まれる水に溶けた「ケイ酸」という物質を吸収し、葉っばにため込んでいます。これが、葉っばを硬く強くしているのです。この物質は葉っぱの表面にもありますが、縁にも多くあります。そのため、ススキの葉っばの縁を触ると、手を切ってしまうことがあるのです。
この植物は、ケイ酸を材料に、生きた証として、「プラント・オパール」とよばれる、小さなガラス質の物質を残します。「植物の宝石」ともいわれます。……
たとえば、「日本で、イネが縄文時代から栽培されていた」といわれるのは、縄文時代の地層からイネのプラント・オパールが見出されるためなのです。
(田中 修 著『雑草散策』より)
No.2462『「おいしい」は国境を越える』
海外からの旅行者のインタビューで、日本で食べたいと思って来日する方が多く、ということは自分たちが暮らしいてるところにも日本食を提供しているところが増えていると思いました。つまり、本場の日本食を食べてみたいという気持ちではないかと思います。
そこで、この本を見つけ、読むことにしました。今はネット社会で、どこにいても情報が瞬時に手に入るので、日本食を調べてもいろいろと検索できます。この本では、「情報を食べる」と表現していますが、「現代の食文化は、単なる栄養摂取を超え、健康、幸福、文化的豊かさといった象徴的な価値の消費へと変化している。言い換えれば、私たちは食べ物を選ぶ際、その物理的(ハード)な側面だけでなく、そこに込められた「物語」や「イメージ」(ソフト)も食べている。つまり、私たちは「情報を食べている」とも言えるのである。」とあり、たしかに、身近な例でも、こんなに奥まった交通の不便なところの一軒家に、話題になると人が集まってきます。
そこには、遠いとか不便だとか、あるいは高いとかというようなことを乗り越えた物語りがあるようです。
そういえば、コロナ禍前は、よく中国とか東南アジアに行きましたが、向こうの食文化は屋台や簡単な建物のなかで食べることが多かったのです。この本の中でも、アジアにおける食文化の特徴について、「暑い気候であるために、昼間より夜にかけて人の活動が活発になるため、それに対応した食べ方が生まれてきた。屋台で食べる食文化はアジアの特徴の1つである。日本では一部地域を除き、今では屋台はお祭うの日にしか出店されないが、アジアの国々ではどこへ行っても人の集まるところには屋台がある。日本では家で調理して家族で食べることが多いが、アジアでは家で調理するよりも気軽に安く食べられることから屋台で食事することが多い。もちろん、家で好きなものを調理して家で食べることも普通に行われているが、アジアの食文化には屋台で食べることが生活の一部に
深く入り込んでいる。また、アジアの食文化の特徴として、香辛料が多いことが挙げられる。」と書いてあり、なるほどと思いました。
思い出すと、中国雲南省の麗江で、街頭で食べた米粉でできた揚げパンみたいなものもおいしかったし、南インドで食べた「ドーサ」は、絶品でした。これは米と豆を発酵させた生地で作るクレープのようなもので、店によって少しずつ違いました。だから、その日の気分によってあちこちで食べました。
よくインド料理は香辛料が多く使われるといいますが、北インドのほうはそうかも知れませんが、南インドは意外とあっさりした味付けでした。もちろん、インド国内でもいろいろな食文化がありますし、世界中ではさらに多くの食の違いはあります。以前からファーストフード店の多くがアメリカ発祥が多いと思っていましたが、この本に「アメリカのファストフードに代表される食ビジネスがなぜグローバル展開できるかというと、それは食そのものの魅力というよりもマネジメントの方法である。食文化、宗教、言語、習慣等が違う多民族社会で仕事を行うには、個々の職務を明確にする必要がある。各々の職務の体系が仕事の仕組みであり、それをどう目標の達成に向けて導くかがマネジメントカである。この仕組みをつくってきたのがアメリカの経営の特徴であり、それは今でも進化し続けている。アメリカの経営は、世界どこでも通じる普遍的経営(ユニバーサリスティック)であるのに対し、日本の経営は島国でほぼ同じ民族からなる日本社会で育まれてきた特殊的経営(パテキュラリスティック)と言われてきた。」と書いてあり、これで納得しました。
日本生まれのハンバーガーといえば「モス」ですが、アメリカなどのファストフードと競争するには、それなりの工夫が必要です。この「モス」というのは、「"MOS"は、「山(Mountain)のように気高く堂々と」、「海(Ocean)のように深く広い心で」「太陽(Sun)のように燃え尽きることのない情熱を持って」という創業者の思いが込められた名前である。」といいます。
創業者は、櫻田慧氏で、もともとは証券マンだったそうで、証券業界の不況で脱サラし、起業したそうです。やはり、食には物語があると思いました。
下に抜き書きしたのは、第10章「食ビジネスのさらなる挑戦に向けて」のなかの、最後のもとめに書いてあったものです。
なんでもそうですが、最初に挑戦した人たちは、大きなリスクと大変な℃食をされたことは間違いありません。さらに、この下に抜き書きしたような「国際事業の企業家精神」を持った人たちでなければ、そもそもやってみようとは思わないかもしれません。
そう考えれば、単に食ビジネスだけのことではなく、何ごとに対しても通じることだと思います。これは、日本の代表的な国際企業である先進的ものづくり製造業の21人のリーダーにインタビュー調査をしたことからわかったことだそうです。
(2025.9.3)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 「おいしい」は国境を越える | 高橋浩夫・マリア・ヨドヴァ | 同文館出版 | 2025年6月30日 | 9784495391003 |
|---|
☆ Extract passages ☆
〈国際事業の企業家精神の特徴〉
①強い好奇心 未知なる新市場への人一倍の野心と好奇心を持っていること。
②開拓者精神 市場を開拓し自社商品を何としてでも売り込もうとする強い開拓者精神に支えられていること。
③確固とした経営ビジョン 支流から本流へと国際事業の将来構想を描く壮大な願望とビジョンがあること。
④ロマンチスト 原体験を起点にした海外、異国へのロマン、夢を持ち続けていること。
⑤インターナショナル・ヒューマニスト 自然体で外国人と接することができる偏見のない人間愛があること。
⑥専門的交渉能力 国際経験の蓄積による専門家としての強い自信と交渉能力を持っていること。
⑦人一倍の勉強家 語学のハンデを負いながら、常にそれを学習しようという向学心があること。
⑧平常心の業務遂行能力 総合すると自然体で国際事業に取り組める素質のある選ばれた人であること。
(高橋浩夫・マリア・ヨドヴァ 著『「おいしい」は国境を越える』より)
No.2461『忙しい人のための美術館の歩き方』
今もそうですが、旅に出ると、その土地にある美術館や博物館などを観ることにしています。ところが、以前は1日に2~3ヶ所ぐらいは観て回れたのですが、最近は午前か午後に1ヶ所ぐらいで、それ以上観ると疲れが残ります。
今も、9月27日から29日まで三陸にいるのですが、この本を見つけ、あわよくば手軽に観て回ることができないかと思い、旅先で読むことにしました。
でも、読みながら、せっかくいいものを観たとしても、時間に制約されてはつまらないと考え、今まで通り時間をかけて観ることにしました。それでもこの本は、参考になることがたくさんあり、最後まで読み切りました。
たとえば、タイパの関連では、「美術館に並ぶ作品一点一点には、作者が創作に費やした膨大な時間が詰まっている、ということはすでに語りました。何層も油絵具が塗り重ねられた油彩画、緻密な装飾が全身に隈無く施された仏像など、実際に対面して間近で観察すればするほど、私たちはその作品を生み出すためにかけられた時間の途方も無さに感嘆します。人は圧倒的な質量の物体を前にした時にはその壮大さに感動を覚えますが、それと同じように膨大な時間を内包した物体を前にすると、無意識のうちにその時間を追体験してやはり感動するのです。」と書いてあり、観ているだけで圧倒される作品もあります。
それと同じように、国宝展などを観たときに感じたのですが、飛鳥時代や平安時代などから伝えられてきた古美術の長い長い時代に思いを馳せると、今、この時代に観ることのできる不思議さです。もし、どこかで火災や盗難にあったり、戦火で焼失されることもあり得ないことではないと思います。No.2457『マボロシの茶道具図鑑』にも書きましたが、たとえば名茶器なども信長とともに本能寺で焼け焦げてしまいました。
だから、今、美術館や博物館で観ることができるというのも、不思議な縁です。そう考えれば、忙しいからといってパッと観ることはできなくなります。
では、なぜ美術館に行くかというと、この本には、「ヨーロッパでは知的な刺激を求めて美術館に行く人が多いのに対し、日本は癒やしを求めて美術館に行く人が多数派であるという話もあります。静諦な空間で泰西名画ゃ国宝をじっくりと眺めて満たされた気持ちで帰る、というのが人多数の人にとっての楽しみ方なのです。」とありましたが、私的には、知的な刺激を求めたり、美術品を眺めて癒やされるという両面があります。
10年ほど前にイギリスの大英博物館に行ったときには、その膨大なコレクションに圧倒されましたし、テート・モダンでは気楽に写真を撮りながら鑑賞したこともあります。そのときの体験はすごく刺激的だったこともあり、次に訪問したときには自然史博物館なども見学しました。
だから、著者が展覧会に行くのも旅行みたいだというのもよくわかります。旅行に出かけるときも、いろいろな体験が待っているわけで、テレビなどで風景を見るのとはまったく違います。著者は、「どの展覧会を見ようかなと思案して、スケジュールをやりくりして時間をつくり、電車を乗り継いで、ちょっと寄り道をしながら美術館まで歩いて、趣のある美術館の外観をながめて、荷物が重いからロッカーに預けて、受付でチケットを買って、そしてようやく会場に足を踏み入れる。一通り鑑賞をして展示室を出た後は、ミュージアムショップでグッズを物色する。帰り道は手頃なカフェを探してぶらぶら歩く。そこでコーヒーを飲みながら一息つき、図録をパラパラ眺めて余韻に浸ったり、または一緒に来た人と感想を言い合ったり。そして電車を乗り継いで我が家に帰る。美術作品を鑑賞することと、こうした行動は切り離せないものであり、それらが全部組み合わさって一つの鑑賞体験となるからこそ、心に刻まれるのです。」と書いていて、だからこそ、何十年前に観た美術館が風景のなかで蘇るのです。
そういえば、自然史博物館のミュージアムショップで元素記号の書かれたマグカップを見つけたのですが、荷物になるし壊れると困ると思い諦めたのですが、今でも買ってくればよかったと思い出します。そう、いろいろなことが組み合わされて鑑賞という行為につながっているようです。
下に抜き書きしたのは、第2章「美術鑑賞の変遷」のなかにありました。
たしかに、展覧会の誕生がアーティストの誕生になったというのは、まったく考えてもいませんでした。ここを読んだだけでも、この本に出合ってよかったと思いました。
今も昔も同じでしょうが、アーティストといえども材料を揃えたり食べたりと、ある程度の収入は必要です。だからこそ、昔は注文主と基本的には一対一の関係、というよりは、注文主の意向に添ったものをつくるしかないわけです。ところが展覧会が始まると、出品料は必要でしょうが、多くの人たちの目に触れることになり、売れることにもなります。これは大変な出来事で、まさにアーティストの誕生です。
(2025.8.31)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 忙しい人のための美術館の歩き方(ちくま新書) | ちいさな美術館の学芸員 | 筑摩書房 | 2025年7月10日 | 9784480076977 |
|---|
☆ Extract passages ☆
しかし展覧会が始まって以降は、極端な話ですが公募展に作品を出品すれば、その時点で誰でもアーティストと名乗ることができるようになりました。そして工房で集団制作をするのではなく、個人の名前を前面に出してオリジナリティを重視する意識が芽生えていきました。また、作品にタイトルを付ける、という今では至極当たり前のことも、展覧会でたくさんの作品が横並びで陳列される中でそれぞれを区別する必要があるために始まったことです。
そして何より注目すべきは、アーティストの創作の動機として、自己表現という意味合いが強くなった点です。特定の注文主のためではなく、不特定多数の人に向けて作品を発表するようになったことで、受取手不在の状態での創作となり、誰かのためではなく自分との対話を通して、アーティストは内面性を表現することがメインテーマとなっていきました。
(ちいさな美術館の学芸員 著『忙しい人のための美術館の歩き方』より)
No.2460『中村哲という希望』
副題が「日本国憲法を実行した男」とあり、中村哲さんも日本国憲法にはこだわりがあったといいます。
たとえば、『医者 井戸を掘る アフガン旱魃との戦い』のなかで、『「憲法はご先祖さまの血と汗によってできた一つの記念塔」であり、「平和憲法は世界の範たる理想」である。それは日本国民を鼓舞する道義的力の源泉でなくてはならない。それが憲法というものであり、国家の礎である。祖先と先輩たちが、血と汗を流し、幾多の試行錯誤を経て獲得した成果を、「古くさい非現実的な精神主義」と嘲笑し、日本の塊を売り渡してはならない。戦争以上の努力を傾けて平和を守れ』と言っているそうです。よく、今の憲法は連合国側から押しつけられたものだから自分たちでつくろうという主張がありますが、いまの流れからつくれば、第2章第9条の「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」という項目は、おそらく改変されると思います。
たしかに、この条文は理想かも知れませんが、このような理想を掲げるということも大切なことだと思います。被爆国の日本だからこそ、主張すべきことです。
この本の著者の高世仁氏は山形県生まれだそうで、早稲田大学法学部を卒業後、日本電波ニュース社に勤務を経てテレビ制作会社「ジン・ネット」を設立しさまざまな番組を製作してきたそうで、現在はフリーです。この『本のたび』のNo.2399『ウクライナはなぜ戦い続けるのか』で取り上げた本も、高世さんの著書で、出版社も旬報社です。
また、著者の佐高信氏も酒田市生まれだそうで、同じ県内ということもあり、親近感が湧きます。
佐高氏の「はじめに リメンバー中村哲」に書いてあるそうですが、中村さんがお医者さんらしいネクタイを締めて清潔感のある人という印象もありますが、その清潔感の裏を返すと何をやっているかわからない人もいる、だから私は「裏表つくるとあとが大変ですから。だいたいホンネで通すことにしているんです。一つ隠すと二つも三つもウンをつかなくちゃいけないですからね」と言ったそうですが、本当にそうだと思います。
また、高世さんの話しで、「例えば学校を建てる、クリニックを建てる、用水路を造ったりも実際あるんですけど、ただプレゼントするだけだから維持できない。屋根から水が漏ったりしても誰も構わなくですぐに廃屋になっちやう。でも、中村さんのプロジェクトは現地のアフガン人が自分たちの手で造ったんです。ぽんともらったものじゃなくて、自分たちで造ったという意識がものすごく強いから、それで維持できてるという、もう本当にまれな例なんですよね。さらに、新しい用水路が中村さんが亡くなってからできてます。私も現場にも行ってきましたけど、ものすごく急峻な斜面を切り開く難しい工事をやっていました。中村さんが長年育ててきた弟子たちが、彼の遺志を継いでやるんだと決意し、地元の人たちもぜひやりたいと協力している。」とあり、これこそが本来の国際援助だと思いました。
じつは、これに近いことで思い出すのは、ある県の日本とネパールの友好協会で小さな水力発電装置を贈りたいからとネパールの友人に打診があったそうです。その内容をみると、日本の発電装置だったので、もし壊れたらネパールでは直せないと答えたそうです。むしろ、ネパール製の水力発電装置なら部品も手に入るし、直す技術者もいると話すと、でも日本製のほうが性能はいいし壊れないと大半の人は考えていたので、日本人の技術者が現地に行って設置したそうです。しかし、危惧した通り、数年で壊れ、そのまま使えなくなってしまったそうです。
友人は、その贈る側のメンバーに日本のメーカーに近い方がいたからではないかと言ってましたが、たしかにそれはありそうです。つまり、相手のことを考えているようで、じつは自分のことを考えているから、そのような結果になったのではないかと思います。
それを思い出すと、いかに中村さんのやり方が相手を思い、それから先の長いスパンで考えていたということがよくわかります。これは政府機関でも同じで、つい自分たちの思い込みだったり、自国の利益を考えて押しつけてしまいがちです。それでは、本当の意味での援助にはなりません。
だから、政府関係者だけでなく、若い人たちにも中村哲さんの生き方を学んでほしいと思いました。
下に抜き書きしたのは、第3章『「義」に生きる』に書いてあったもので、高世さんの話しです。
なんでも徹底的に調べて、そして実行するというのは大切なことですが、皆ができるわけではありません。それでも、短期間で集中してやり遂げるのはすごいことです。やはりそれだけのことを準備しているからこそできる自信につながるのかもしれません。この本を読んで、学ぶべきことはたんさんありますが、少しだけでも、真似でもいいから、実行したいと思いました。
(2025.8.28)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 中村哲という希望 | 佐高 信×高世 仁 | 旬報社 | 2024年1月25日 | 9784845118458 |
|---|
☆ Extract passages ☆
中学高校のころ、強迫神経症で人前でしゃべれなかったそうです。特に同年代の女子の前では緊張して何もできなくなったとか。それでたぶん心の問題に興味があって精神科医になったと思いますが、そのままではパキスタンのペシャワールでらい病(ハンセン病)の患者を診ることができない。
赴任前、中村さんは福岡徳洲会病院に行って、総合医の研修、要するに内科も外科もできるように研修して、国立療養所邑久光明園でらい病の勉強をします。……
それから、英国、ロンドンに行って英語を勉強して、その後、リバプールの熱帯医学校で熱帯病の勉強して、らい病については後で韓国に行ってもう一回勉強します。
ベシャワールに赴任すると、まずパキスタンの公用語ウルドゥー語の語学学校に入り、さらに現地に多いパシュトゥン人のパシュトゥー語、それにアフガニスタンの公用語の一つ、ダリ語(ペルシャ語)を学びます。現地の三ヵ国語をやるんです。ものすごい努力をして活動のための準備をしているんです。
簡単に、ちょっと山が好きでペシャワールに行ったんだなんて言うんだけど、赴任にあたっての準備を知ると、とんでもない努力をしてるのに驚きます。本当に。
(佐高 信×高世 仁 著『中村哲という希望』より)
No.2459『戦争と法』
1945年8月15日の日本の終戦から数えると、今年は戦後80年です。まさに節目の年であり、終戦記念日のあたりには、テレビなどで戦争のことについての報道がたくさんありました。
しかも、ロシアのウクライナ侵攻やパレスチナのガザ地区の攻撃などをテレビで見ていると、以前より戦争に対する危機意識が高まってきているように感じます。だから、あの忌まわしい戦争の体験などを風化させたくないという気持ちもよくわかります。そのようなときに、この本を見つけ、読むことにしました。
でも、あまりにも重い内容なので、お盆頃から読み始めたのですが、とうとう10日ほど経ってしまいました。
著者は、現在日本弁護士連合会災害復興支援委員会委員長の要職にあり、日本だけでなく、諸外国の戦争時の法律も詳しく解説しています。それを読むと、戦争時というのは、どこの国も同じように国民よりも国家を護ろうとするようです。そういえば、この本の中でも、国家緊急権というのは「国家緊急権はもともと個人の人権を守るための制度ではなく国家を守るための制度であり、国家を守るために人権を大幅に制限し、または、犠牲にする制度でした。日本においては国家緊急権は二・二六事件で濫用され、軍が暴走の果てに戦争に突入するに至り、国民の命と暮らしは大きく侵害されました。ナチス・ドイツでも、国家緊急権はヒトラーの独裁を確立させ、第二次世界大戦やユダヤ人大量殺害を引き起こし国民の命と暮らしを大きく侵害しました。アメリカでも国家緊急権の濫用によって、在米日系移民の社会的地位、財産、名誉を奪い、暮らしを大きく侵害するものでした。」と書いてあります。
つまり、簡単に言ってしまえば、警察は国民一人一人を護りますが、軍隊は国家を護るということで、個人よりは国家を優先するということになります。この本には、警察の護るべきものは「国民の生命。身体・財産という人権ならびに公共の安全および秩序の維持としています。これに対して軍隊の目的は、通常、国家の防衛や国内の治安維持とされています。守るべきものは国家や秩序の維持であり、国民の人権の保護は予定していません。」とあります。
しかも、国家を護るとはいいながら、最終的には自分や家族を護ってきたようで、満州の新京にあった新京西広場小学校の女性教師が、同窓会誌に書いているそうです。そのことを、この本には、「昭和20年8月初旬の頃でした。「起立」「礼」が終わった途端に私は「アレッ」と思わず声を出しました。欠席者が非常に多いのです。3分の1の子の机が空席になっています。思わず廊下に出て見ました。両隣の教室や、もっと向うの教室からも担任の先生が次々に出てこられました。みんな異様なお顔をしておられます。追い詰められた不吉な予感が胸をよぎります。(中略)先生の1人が「欠席しているのは軍関係の児童ばかりです」といわれました。ぎわめく児童たちに声をかけておいて、私たちは職員室に小走りで行きました。校長さんも教頭さんも緊張でお顔が引きつって見えました。「大変なことが起こりそうですね」(中略)軍関係の家族が一番先に新京を離れ、次の日は満鉄社員の家族が逃げ出し、事の重大さに気付いた一般の人々が命がけで新京駅に駆けつけた時には1つの車両もなければ駅員の日本人の姿もなかったと、後で知りました」と書かれていました。
おそらく、戦争というのは、一番困難な状況に陥るのは一般人です。たった一枚の紙切れで戦争の第一線に立たされ、自分たちの立ち位置もわからず、命令ひとつで動かされる駒みたいなものです。しかも、不都合な事実は教えられず、気づいたときには放り出されているわけで、これらを聞いただけでも戦争は絶対にしてはならないと思います。
今年は戦後80年ですから、ぜひ、このような本を読んで考えていただきたいと思います。
下に抜き書きしたのは、第3章「核がもたらすもの」にあったものです。
今年も広島や長崎に投下された原爆の悲惨さをテレビなどで何度も見ましたが、正視できないほど残酷なことでした。でも、映像ではなく、現実の数値としてとのようなことが起きたのかと考えていたら、この抜き書きのところに書いてありました。
これは長崎での原爆のときの記録で、おそらく、現代の原爆はこれ以上の破壊力を持っているのではないかと想像できます。しかも、被爆してすぐに出るものだけではなく、だいぶ経ってからでも「晩発効果」というのがあるといいますから、原爆というものがいかに悲惨で長く続くものかを考えてほしいと思いました。
(2025.8.25)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 戦争と法(岩波新書) | 永井幸寿 | 岩波書店 | 2025年6月20日 | 9784004320692 |
|---|
☆ Extract passages ☆
高い放射線を全身に受けたとき、爆心地から1キロメートル以内で遮蔽物のない場合、10~50グレイの被曝となり、胃腸管症候群を生じ、2週間以内に全員死亡します。1~10グレイの被曝では、骨髄症候群が生じ、造血系や免疫系の障害による感染が高くなります。爆心地から1.3キロメートルでは、3グレイの被曝で、平均して60日以内に50%の人が死亡します(半数死線量)。また、爆心地から3ないし5キロメートル以内の被爆者にはさまざまな急性放射能症の症状が現れました。先ず、悪心、嘔吐、倦怠などの前駆的な症状が発症し、その後近距離被爆者では早期に下痢、発熱が発症し、被曝線量が少なかった人は、若千の潜伏期間をおいて出血傾向、出血、口腔咽頭炎、さらに脱毛、発熱が発症しました。放射線の被曝後まもなく起こるこれらの影響は、「早期効果」といいます。これを乗り越えても、多年の間を置いて発生する影響が「晩発効果」です。
(永井幸寿 著『戦争と法』より)
No.2458『植物の形には意味がある』
植物とのつき合いが長いので、その形には意味があるといわれれば、ある程度は理解できます。たとえば、日陰の植物の葉は比較的大きいし、梅雨時に咲く花は下向きが多いようです。
よく言われる植物を上から見ると、それらの葉がお互いになるべく重ならないようにしています。しかし、それは結果的にそのようになっただけで、最初から意図的にそうなったのではなさそうです。それを見て、植物たちはお互いに助け合って生きているといわれれば、生存競争をして必死に生きている姿がぼやけてしまいます。
また、これらの葉の厚みについては、ツユクサの実験を載せています、「ツユクサの表皮の部分をはいで、光合成をする細胞を外気にむき出しにしてしまいます。そうすると、当然ながら蒸散は
大きく増えるのですが、光合成の速度はそれほど変わりません。」と書いてあります。
つまり、葉の厚みもそれなりの理由はありますが、だからといって、葉の大きさも厚みもある程度のバランスが必要だということのようです。
そう考えれば、ムダに大きくなるのも極端に小さくなるのも、それなりの理由がありそうで、植物を観察するときの指標になりそうです。そういえば、私はシャクナゲが好きなんですが、今年の夏のように極端に雨が少なくなると、葉が巻いてしまいます。おそらく、そうすればなるべく葉からの蒸散が少なくできるからだと思います。そこで、8月5日まで極端に雨が降らなかったので写真を撮ると、葉は丸まり場所によっては葉先が茶色くなっていました。そして、5日の朝から午後にかけて雨が降ったので、同じ場所のシャクナゲの写真を撮ったのですが、それでもほとんどの葉は丸まっていました。
これだけ乾燥するとちょっとの雨ではほとんど変わらないようです。しかし、5日の夜から翌6日の朝にかけて雨が降り続くと、6日の朝にシャクナゲの葉を撮ると、今度は元気に葉が開いていました。やはり、植物たちは、移動出来ないので、その環境の下で、出来るだけの対策をしてジッとしているのかもしれません。
しかし、ウイルスに対しては、ただジッとしているだけでは絶滅してしまいます。「病原体に対する防御には終わりがない点です。多様性があるために、一部の個体がある病原体に対して生き残ったとしても、そのうちその病原体は変異して、その残った個体に感染するようになる可能性があります。そのような事態を避けるためには、残った個体のなかでまた多様性を確保しておく必要があります。生物同士の競争があるときには、常に多様性を維持し続けなければならないわけです。そして多様性を維持するためには、同じ個体の花粉と胚珠が出合うのではなく、別の個体から花粉を胚珠に届けることによって、遺伝的な多様性を生み出す必要があるわけです。」とあり、そこに自家受粉ではなく、他からの花粉が必要となる理由です。
そう考えて行くと、いろいろな植物を見ていると、ムダなところはまったくありません。みな、それなりの意味があるからこそ、いろいろな植物があるのです。
たとえば、ツクシは毎年見ていますが、ツクシの胞子を顕微鏡で見ることはありませんでした。ところが、その胞子に「ゆっくり息を吹きかけてください。そうすると、あたかもびっくりしたように、胞子の4本の足が本体に絡まって小さくなります。しばらくすると、ゆらゆらとまた元に戻りますから、何度でも繰り返してその動きを観察することができます。ツクシの胞子の4本の足は弾糸と呼ばれていて、湿度の変化に応じて形を変えます。乾燥した状態では弾糸を伸ばし、空気抵抗を大きくして、風などによって遠くまで飛ばされます。一方で、湿度が高いときには、弾糸を縮めて風に飛ばされにくくなります。」と書いてあり、ツクシたちが晴れて乾燥するときをねらって胞子を拡散するのです。
まさか、あのたくさん芽生えるツクシたちも、晴れや雨などを感知して、4本の足を丸めたり伸ばしたりしているとは思いもしませんでした。やはり、植物について、まだまだ知らないことがたくさんあると思いました。
下に抜き書きしたのは、第10章「生物と環境のかかわり」に書いてありました。
私もアカマツは尾根筋にあったり、乾いたところにあるので、そのような植物かと思っていましたが、じつは万能植物だといいます。ということは、どんなところでも生きていけるわけで、だからこそ、他の植物たちが嫌うような乾燥したところにでも生きていけるということのようです。
つまり、多様性のある植物ほど、生き強いということで、人間も多様性を身につけたほうがいいように思います。
改めて、植物っておもしろいと思いました。
(2025.8.22)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 植物の形には意味がある(角川文庫) | 園池公毅 | KADOKAWA | 2022年12月25日 | 9784044007270 |
|---|
☆ Extract passages ☆
アカマツはどちらかといえば万能タイプで、さまざまな環境に侵入することができます。ところが、実際にアカマツが生えている場所は、土地が痩せているなど、他の植物から見るとあまり食指が動かない場所が多いのです。ただし、これはアカマツが痩せた上壌に特化した専門家であるということではありません。実際には、アカマツを単独で植えれば、痩せた土地よりも肥えた土地でよりよく生育します。しかし、肥えた土地では、そこに特化した専門家との競争に負けるので、痩せた土地でも肥えた土地でも生育できる万能タイプのアカマツが、実際には痩せた土地に見られるようになるのです。
(園池公毅 著『植物の形には意味がある』より)
No.2457『マボロシの茶道具図鑑』
だいぶ前ですが、『嘘八百 京町ロワイヤル』という映画が山形県内では上映されないということで、仙台まで観に行ったことがあります。これは、古物商の則夫役を中井貴一、そして陶芸家の佐輔役を佐々木蔵之介で、古田織部の幻の茶碗の話しでした。しかも鑑定士などに竜雷太なども出て、まさにコメディタッチのドタバタでした。
そのマボロシの茶碗が、もしかして、この本に出てくる「ひづみ茶碗」かもしれないと思いました。これは、この本に「織部の業績として大々的に語られるのが陶磁器の改革、とくに歪んだ造形を見せる陶磁器の開発です。自由奔放な絵付けの「黒織部」は人気が高いのですが、実は名物として記録される伝来の確かな作品はありません。その中で、織部が使った茶碗として記録されるのかが、「ひづみ茶碗」です。」とあり、まさに絵付けのない「織部黒」のような茶碗でした。
この「ひづみ茶碗」は、古田織部が大坂夏の陣で徳川家に対する謀反の疑いから切腹し、それらの道具は徳川家の預かりになり、その後行方不明になったと書いてあります。この織部の茶道具のなかには、有名な「勢高肩衝」や「芽張柳蒔絵中棗」、「野溝釜」、そして利休遺愛の茶杓に「泪」と名づけ、位牌代わりにしていたというエピソードのある茶杓などもあります。この「泪」は、現在、徳川美術館所蔵となっていて、私も本などで見たことがあり、そのエピソードとともに記憶に残っています。
でも、これは例外で、そのほとんどが明暦大火で失われたり、方々に散らばってしまい、その確認ができないそうです。
この本を読むと、マボロシになってしまったのは、戦火や政変、そして自然災害や人災など、さらには所有を知られたくないという事情もあるようです。たとえば、小堀遠州家伝来の筆頭に位置する清拙正澄筆「平心」の軸は、徳川家光から遠州に下賜され、まさに家宝でした。それが「明治10年代のこと、茶道界の不振の中で、小堀家はこの家宝を手放してしまいます。これを大手したのが品
川御殿の跡地に本邸を構えていた益田孝(鈍翁)で、明治45年(1922)3月9日にはこの「平心」墨跡を掛け、遠州御成の再現茶会を催しています。しかし益田家も第二次世界大戦後に道具を手放し、現在は所在不明となっています。」とあり、まさに茶道具は、主が変わることで箔が付くこともありますが、行方不明にもなりうるわけです。
そこで思い出したのは、2024年9月30日に観た「眼福 大名家旧蔵、清嘉堂茶道具の粋」という特別展です。このなかに、「茶入 松本茄子(紹鴎茄子)」や「茶入 付藻茄子」もあり、その他に大名物や中興名物などの茶入もあり、いかに大切にされてきたかがその付属物をみればわかります。「付藻茄子」は本能寺の変で焼失されたと山上宗二は書いていますが、現在は清嘉堂文庫美術館に納まっています。また「松本茄子(紹?茄子)」は本能寺の変では難を逃れますが、大阪城落城に巻き込まれ、その後藤重親子によって修復され、これも清嘉堂文庫美術館に収蔵されています。
この展覧会は、大名家旧蔵ですから、その動きをみると、歴史やその当時の力関係が見えてきて、おもしろいと思いました。
また、清拙正澄筆「平心」の軸は行方不明ですが、これはもともとは覚源禅師に与えた字号で、この後に偈頌が付いていますが、その切り離された偈頌の部分が、幕末には高松藩松平家の所蔵となり、現在は香川県立ミュージアムで見ることができるそうです。
著者は、マボロシであったものが再出現が待たれるという表現を使っていますが、誰かが知らずにか、あるいは知っていながら一人で楽しんでいるのか、それはわかりませんが、またこの世に現れることもあるということです。だからこそ、『嘘八百 京町ロワイヤル』という映画では贋作でしたが、本物だって出る可能性はあります。
先日も、テレビ東京の「開運!なんでも鑑定団」で、タダ同然で手に入れたものが、とんでもない評価額になったのも、そうかもしれません。だから、この番組はおもしろいのです。ただ、高額で手に入れたものが圧倒的に低かったりすると、他人事だからかもしれませんが、つい笑ってしまいます。
下に抜き書きしたのは、第1章「失われた名物たち 本能寺の変―織田家の受難」に書いてあったものです。
じつは、この白い釉薬には思い出があり、1998年にサントリー美術館で「樂茶碗の400年 伝統と想像」を観たとき、その展示品のなかに2代目常慶の「白釉井戸形樂茶碗」がありました。それまでは、楽茶碗というと、黒楽か赤楽などしか知りませんでしたが、このような白釉があり、しかも井戸形なのでびっくりしたのです。そこには、15代吉左衛門の「れき釉楽茶碗 銘 雪千片」も展示されていて、樂茶碗にもいろいろあることを知りました。
その後、機会があって15代吉左衛門さんの講演を聞く機会があり、そのサントリー美術館で感じたことを質問したこともありました。
おそらく、ものはなくなっても、名を残した茶道具は、これ意外にもあるかもしれないと思いながら読みました。
(2025.8.19)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| マボロシの茶道具図鑑 | 依田 徹 | 淡交社 | 2019年10月13日 | 9784473043306 |
|---|
☆ Extract passages ☆
現在する「白天目」は徳川美術館のものが有名ですが、これは愛知県の瀬戸で作られた「和物」でした。『唐物凡数』に記載された本願寺のものは「唐物」だったはずで、実際に中国からも白天目が発掘されています。信長は人手した翌年、宿敵であった越前(福井県)の朝倉氏を滅ぼしました。天正元年(1573)11月23日、信長は京都妙覚寺に堺衆を呼び寄せ、朝倉氏からの戦利品とともに、「白天目」を披露しています。…… その袋から取り出された白天目を実見した宗及は「比」、つまり大きさについて「言葉に言いあらわせない」と絶賛し、そして形、土、釉薬のすべてが素晴らしいと述べています。この他、「白天目」については記録があまりありません。本能寺の変で焼け、多くの謎を残す名物となったのです。
(依田 徹 著『マボロシの茶道具図鑑』より)
No.2456『お布施のからくり』
清水俊史氏の『ブッダという男』(ちくま新書)を読んだことがあり、この『本のたび』No.2280にも載せています。その最初の書き出しが、「この本の題名の「ブッダという男」って、たしかにブッダは男かもしれないが、ちょっと失礼な言い方ではないかと思いました。私は仏陀とかお釈迦さまとかいいますが、何かほかの意図でもあるのかと考えました。副題は「初期仏典を読みとく」ですから、尊師と呼ばれる前の話しかもしれないと思い、読むことにしました。著者のプロフィールをみると、「2013年、佛教大学大学院博士課程修了。博士(文学)。日本学術振興会特別研究員PD、佛教大学総合研究所特別研究員などをつとめる。著書に、『阿毘達磨仏教における業論の研究――説一切有部と上座部を中心に』『上座部仏教における聖典論の研究』(ともに大蔵出版)がある。」とあり、生年月日はないので詳しくはわからないのですが、若い研究者のようです。」と書いてあります。
そのときも思ったのですが、たしかに正論といえばそうかもしれません。お釈迦さまは、解脱するために家族を捨て、修行を始めたのですから、今の僧侶が家族を持つことは仏教の教えに反するのはそうかもしれません。しかし、日本には家元制度のようなものがあり、血統を重んじる風潮があります。むしろ、そのことによって寺院を維持したり、教えを広めることだってできます。すべて、もともとのお釈迦さまや宗祖の教えにもどらなければならないとは思いません。キリスト教やイスラム教だって、原理主義で押し通すことは難しい時代です。
でも、この旧盆のときだからこそ、正論を考えてみることは大切なことだと思います。ということで、この本も読むことにしました。たしかに、棚経で来てくれた僧侶にお布施を差し上げた方も多いと思います。この本の副題は、『「お気持ち」とはいくらなのか』で、戸惑った方もいると思います。もちろん、定価はないのですから、いくらでもよさそうですが、その曖昧さが「お気持ち」という表現になったのではないかと思います。
なぜ、お布施があるのか、それはどのような歴史をたどってきたのか、いろいろと考えてみることは大切なことです。この本には、「お布施の起源は古代インドのバラモン教にあり、そこでの祭祀が、生天(天界への再生)を目的として行われていたことが背景にある。バラモン教では、祭祀が宗教的実践の中心に位置づけられており、その対価としてお布施が不可欠なものとされていた。これに対し、仏教はバラモン教の祭祀の効果を否定し、善業によって生天が叶うという新たな倫理観を提示した。この善業の代表が、出家修行者に対するお布施である。お布施は単なるサービスの対価ではなく、純粋な気持ちとして行われるべき善業であり、その本質は、出家者と在家者の相互依存による関係性にある。」と書いてあり、2012年12月に一人でインド仏跡の旅をしたときのことを思い出しました。
たしか12月11日の夜に、ベナレスのガンガー河畔で、ヒンドゥー教のプージャというお祭りを見ていて、このような盛大な儀式をするのにはだいぶ資金が必要だろうなと思いました。だとすれば、それなりのお布施も必要で、私なりに少しばかり寄進をしてきました。
それよりだいぶ前の2007年3月にネパールに行き、友人の家にホームスティしながらボダナートのストゥーパやその娘さんがボランティアしている孤児院を訪ねたり、テントを持ってシヴァプリ山に登り、シャクナゲを見たりしていました。その案内は、これも友人のアンバブさんで、彼と雪の降りしきるテントのなかで、インドの仏跡を訪ねようということになりました。彼はシェルパで仏教徒なので、話しがまとまるのも早かったのです。
そこで、先ずはカトマンドゥのインド大使館に行き、インドへの入国ビザをもらいましたが、ネパールの人たちはビザなしで入国できるのです。2007年3月20日にネパールのトリブヴァン空港から国内線でバイラワ空港まで行き、そこからインドに入国しました。そして、車をすぐに手配し、チュンダ屋敷跡やお釈迦さまが火葬されたラマバルや涅槃堂などをお詣りしながら祇園精舎に向かいました。ところが、暗くなって道に迷い、しかたなくお寺が一番安全だからという理由で、近くのスリランカ・ラマヤ寺院に泊めてもらいました。
翌日、昨夜は遅く着いてしまい、住職に挨拶できなかったので、早朝に般若心経を唱えお勤めをすると、お寺の方が日本語で聞いてくれ、これから祇園精舎に行きたいというと、そのお寺の前に出て、これが祇園精舎だから、朝食後に案内してくれると言いました。これも不思議なことでしたが、実はその朝食後に本を読んでいるとスリランカの人たちが私のところにやって来て、イスに座っている私の膝に頭をすりつけるのです。おそらく、アンバブさんが話したのではないかと思うのですが、上座部の仏教徒の人たちの信仰心の篤さを感じました。それと同時に、私のような者に、膝を折ってすり寄せることに恥ずかしさも感じました。
このときの印象がとても強く、その後もブッタガヤでも霊鷲山でもスリランカの人たちに会うと、すごく懐かしく思い出しました。またその縁もあって、2011年にスリランカに行ったときには、念願だったアヌラーダプラのボダイジュを見ることができました。何れも不思議な縁で導かれたような気分でした。
でも、著者がいうように、「在家主義の強い宗派ほど僧侶と在家者の垣根を低いものとして見ており、逆に出家主義の強い宗派ほどその垣根を高いものとして見ている。ただしこれはそれぞれの宗祖たちが残した教理にもとづいていて、実際には、妻帯世襲が当然となった現代日本仏教においては、釈尊より続く正統性はすでに断絶している。原理原則に照らし合わせれば、日本仏教のすべての僧侶が、「袈裟を身にまとった在家者」にすぎない。」というのは、原理主義にとっては正しいと思うかもしれないが、現代の僧侶がみなそのようなものではなく、苦しみもがきながら考えている僧侶もいると私は思っています。
下に抜き書きしたのは、終章「現代におけるお布施の意義と再定義」に書いてありました。
私は学問的にどうのこうのというよりは、最終的には施主側の判断しかないと思います。いくら仏典を批判しても、それを信じるかどうかは個々人の問題です。
(2025.8.16)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| お布施のからくり(幻冬舎新書) | 清水俊史 | 幻冬舎 | 2025年5月30日 | 9784344987715 |
|---|
☆ Extract passages ☆
何をもって立派な僧侶とするかは、結局、施主側の判断で決まるだろう。
(清水俊史 著『お布施のからくり』より)
No.2455『文房具を深める 100のことば』
元々、文房具が好きというより、本を読んだり、何かを書いたりと、必然的に使わなければならなかったのです。ところが、たとえば万年筆を使えば、なるべく書きやすいものとか、持ちやすいものと考えると、いろいろな万年筆を使ってみないとわからないわけです。
ということで、いつの間にか、万年筆が手もとにありました。でも、今使っているのは、パイロットの「Justus95」です。ペン先はFMで、特徴はペン先の弾力調整ができることです。つまり、自分のその日その日に使う弾力に合わせられるということです。おそらく、この万年筆は、販売されたときに購入したもので、柄はネットブラックで、自分の名前が彫られています。
それまでは日本製や外国製の万年筆も手に入れましたが、今は片ケースのなかにしまわれたままです。
また、そのインクは、いろいろな製品を使ってはみましたが、セーラー万年筆から「極黒」が出てからそれだけを使っています。これは顔料なのに目詰まりしにくく、水に強く、にじみが少なく、裏抜けもあまりありません。しかも、染料インクとほとんど変わらない書き心地で、最近はこれ一択です。ただ以前の極黒にはリザーバーが付いていたのですが、今のボトルには付いてなく、別売りになっているのが、ちょっと不満です。
だから、文房具マニアというよりは、使いやすいものに出合うまでは買いますが、出合えば、それだけを使います。
ただ、万年筆はいいのですが、ボールペンやシャープペンシルなどは、これは使い易いと思っても、年数が経つと品切れになり、替芯も手に入らなくなり、使えなくなります。ただ、この本を読むと、これらの製品は日々進化しているそうで、ある意味、仕方のないことのようです。
そういえば、この本を読んで初めて知ったのですが、「鉛筆の芯は黒鉛と年度を焼き固めてつくります。黒鉛が多けれは、柔らかく濃く、粘土が多けれは硬く薄くなります。……硬度ラインナップの多い、世界的な鉛筆ブランドで並べてみますと、まず三菱鉛筆ハイユニでは、柔らかいものから、10B~2B、B、HB、F、H、2H~10Hとなります。そう、FはHBとHの間です。いきなり現れて焦りますが、FIRM(強くてかたい)の頭文字でして、ちなみにHはHARD、BはBLACKの略ですね。」と書いてあり、その種類の多さにびっくりしました。
そういえば、その三菱鉛筆の工場は川西町にあるのですが、老朽化したので今年の1月から飯豊町に移ったということです。それで、7月28日付けの地方紙によると、川西町と飯豊町のふるさと納税の返礼品を一部共通化するための連携協定を結んだそうです。つまり、川西町で製造されたボールペンと、飯豊町で生産された鉛筆をセットにするということで、ふるさと納税ポータルサイトで早ければ9月にも取り扱いを始めるということでした。
川西町には、「かわにし森のマルシェ」という施設があるのですが、そこの売店でも三菱鉛筆の製品を売っていて、世界的なメーカーでも、地域と密着しているというのはいいことです。
また、この本を読んでなるほどと思ったのは、後漢の皇帝が日本の「倭奴国」の王に贈ったとされる金印についてです。まだ紙も発明されていないのに何に使うのかと気にはなっていたのですが、もしかして、単なるシンボルなのかとも思っていました。ところが、「実は、金印は今でいうシーリングスタンプだったのです。古代の中国では、文書を竹などの木簡に書いていました。その中で、重要なものに関しては、改ざんされないように粘土に印を捺して、封をしました。……中国以外にも、封泥は古代メソポタミヤ文明や古代エジプト時代から使われており、文書が未開封であることや差出人が本物である証明をしていました。」と書いてあり、これで納得しました。
下に抜き書きしたのは、69話「ペンは剣よりも強し」という名言についてです。
おそらく、ほとんどの人は、福沢諭吉とのつながりで覚えていますが、その由来もなにもわかりません。ところが、この本には、しっかりと書いてあり、今まで真逆の意味に取っていたのですが、つい、えっと思いました。
そこで、この下に引用することにしました。ぜひ、多くの人たちに知って欲しいと思います。
(2025.8.13)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 文房具を深める 100のことば | 高木芳紀 | 翔泳社 | 2025年5月26日 | 9784798186955 |
|---|
☆ Extract passages ☆
この言葉、原点は英国で1839年に発表されたエドワード・ブルワー=リットン卿作の戯曲『リシュリュー』から、主人公であるリシュリューのセリフの一部です。問題は、ノシュリューとは誰なのか?ということです。なんと、主人公リシュリューは時の権力者、つまりペンによって批判される側の人間だったのです。
そしてそのセリフがこちら。自分の暗殺を企てている、軍力司令官かいることを聞き、
「まことに偉大な統治のもとでは、ペンは剣よりも強し」
そう、自分のような権力者にとっては、ペンひとつで部下の粛清ができるぞ、という内容で、見事に反対の意味なのです。
(高木芳紀 著『文房具を深める 100のことば』より)
No.2454『下り坂をそろそろと下る』
題名の『下り坂をそろそろと下る』ということは、どういうことなのかと思い、目次を見ると、各地の話しが載っていて、おもしろそうだと思いました。
それで読んで見ると、「序章」に「下り坂を下っていくことには、寂しさがつきまとう。いまだ成長型の社会を望んでいる人は、この寂しさと向き合うことを避けようとしている人々である。一方で、「成長は終わった、成熟型の社会、持続可能な社会を創ろう」という方たちもまた、この「寂しさ」をないものとして素通りしているように私には思える。それでは、問題は何も解決しない。」と書いてあり、なるほどと思いながら、つい、最後まで読みました。著者は、いろいろなところでいろいろなことをしていますが、それについて書いてあるので、まさに実体験そのものです。
というのも、私はその「寂しさ」を感じるために、一人旅をするときがあります。一人だと、すべて自分で決めなければならないということもありますが、お茶を飲んだり、食事をしたりするときに、ふと寂しさを感じます。あるいは、その寂しさが人に伝わることを心配して、つまりそう思われたくなくて、おいしそうなお店に入れないこともあります。
ネットなどで調べて、おいしそうだけれども、実際にその店の前まで行ってみると、ちょっと入りにくい雰囲気を感じることもあります。
でも、最近は無理に入らなくてもいいと思うようになってきました。コンビニでおにぎりと飲みものを買って、いい風景のところを探し出して、食べるのも楽しいです。寂しいと思う気持ちがあると、むしろ別な楽しさもわかってくるように思います。
ただ、よくネットを使っている立場から考えると、「インターネットは、世界共通のメディアであり、私たちは、世界中と情報を共有しているという錯覚がある。しかし、このメディアは、国ごと、言語ごとに、そうとうに偏った情報しか流さないという特質を持っている。特に日本語や韓国語のような英語圏以外では、その傾向はますます強くなる。……人間は、自分が読みたいと思っている情報、欲しいと思う情報の方に近づいていく。さらに昨今は、自分が広めたいと思っている情報に機械的にアクセスを集中させてランキングを上げるといった手法もあると聞く。こうして私たちは、 一見、公正に見えるインターネット社会で、なかば無意識の情報操作の大海原に漂っている。」とあり、特に今回の参議院選挙でもそれは感じました。
最近は、あまり新聞を読まなくなったと聞きますが、本来は新聞なども各社で個性がありますが、それでも自分では絶対に読まないようなことが書いてあったりします。だから私は新聞もよむようにしています。また、英語の勉強に、たまに外国の放送を聞くことがありますが、日本で流されているものと、まったく違う報道のされ方があったりします。むしろ、この視点の違いがおもしろいと感じ、それがその国のアイデンティティではないか思います。
下に抜き書きしたのは、第3章「学びの広場を創る――讃岐・善通寺」に書いてあったもので、四国学院大学との関わりからの話しです。
この引用前に、「四国の片田舎というハンデは、逆に長所でもあった。18歳の子どもを東京に送り出す、まして演劇をやらせるというのは、どの親にとっても心配事が多いだろう。30年以上演劇をやっている私から見ても、「それは心配だろうなぁ」と思う。四国学院大学ならば、美しいキャンパス、治安のいい環境(何しろ周りは自衛隊とお寺しかない)で、演劇と勉強に集中できる。試算では、東京の私立大学に行かせるのに比べると、学費と生活費や帰省費用の総計は、半額程度で済むことも分かった。いまでは、経済的な理由で、この大学の演劇コースを志望する学生も多い。」と書いてます。
ただ、この場合も、片田舎でも本物に多く触れさせることができればという前提が必要です。
そうすれば、18歳の子どもでも、今の情報化の社会に住んでいれば、それなりのことがわかるはずです。もしかすると、ちょっと甘いかなぁ?
(2025.8.10)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 下り坂をそろそろと下る(講談社現代新書) | 平田オリザ | 講談社 | 2016年4月20日 | 9784062883634 |
|---|
☆ Extract passages ☆
この身体的文化資本を育てていくには、本物に多く触れさせる以外に方法はないと考えられている。それはそうだろう。子どもに美味しいものと不味いものを交互に食べさせて、「どうだ、こっちが美味しいだろう」と教える躾はない。美味しいものを食べさせ続けることによって、不味いもの、身体に害となるものが口に入ってきたときに、瞬時に吐き出せる能力が育つのだ。
骨董品の目利きを育てる際も、同じことが言えるようだ。理屈ではなく、いいもの、本物を見続けることによって、偽物を直感的に見分ける能力が育つ。
(平田オリザ 著『下り坂をそろそろと下る』より)
No.2453『メダカの花嫁学校』
連れ合いが読んでおもしろかったというので、私も読んで見ました。
いつもは、まったく読む本は違うのですが、著者の本は、なんとなく急所を突いているところがあり、つい、にんまりとして読みました。おそらく、本音で書いてるような感じです。
たとえば、「人は他人と同じであることに不満を持ちながら、他人と違うことをするのを恐れる。 他人が安定した居場所を見つけているのに、自分の居場所が見つからないと、焦り、嫉妬し、悲観する。しかし、みんなそれぞれに生き方が同じはずはないし、ペースも違う。私は同年代の友達と比べるとペースが遅いのだろう。でも、どんなペースであろうと、楽しんでさえいればいいではないか。そう思えるようになったのは、つい最近のことである。」と書いてますが、たしかにそうだと思います。
でも、これはある意味、女性でないとわからないこともあり、自分の居場所は自分でつくるしかないと私は思っています。
だって、自分でつくるからこそ自分に合うものができるのだし、そこには焦りも嫉妬も、まして悲壮感など感じようもありません。
そういて読んで見ると、連れ合いがおもしろかったというのも、理解できます。まさに自分と似たような感覚だし、肯定したくなることが多々ありそうです。
たとえば、「私の場合、旅の目的は何よりも日常からの逃避にある。できるだけ時間の束縛がなく、行かなければならない場所もなく、買わねばならない物もない。空気と景色と人間が変わって、ささやかな感動があれば、それがいちばんだと思っている。そんな旅は、決して一方的に人から与えられたものであってはいけない。自分で地図を見て、時刻表を繰って、人に尋ね、迷いながら、失敗しながら進んでいくことが大事である。自分で開拓する旅だからこそ、自分のペースに合わせられる。」と書いてあるところもあり、半分は納得できても、半分は違うような気がします。
もともと、私は団体ツアーのような旅はしないし、ほとんどが一人旅です。たまには連れ合いとも旅をしますが、なるべくなら喜んでもらえるようなホテルとか食事などを考え、一人ではここには絶対来ないだろうなと思ったりします。
基本的には、今まで日帰りだったときには1泊し、2泊していたなら、3泊にするというような時間的なゆとりを最優先に考えます。そして、自分の家でなら、こんなことは出来ないだろうなということをするようにしています。
たとえば、朝食を果物だけにするとか、その場所でしか買えない和菓子をさがして、その近くで湧き出している水を汲んできて、お抹茶を点てて飲みます。ほとんどの旅で、たとえ海外だとしても、毎日お抹茶を点てて飲んでいます。この場合は、水だけは現地の水というわけにはいかないので、ミネラルウォーターを使います。だから、そのときの写真を撮っていますから、ときには風景の写真などより、それをみるといろいろな思い出が広がります。
下に抜き書きしたのは、第Ⅰ章の「いり卵ゴハン」に書いてありました。
私もそうですが、たとえ外食するときでも一人で食べるときは、コンビニで買ったもので間に合わせたり、とくに観音詣りのときなどは車のなかでおにぎりやサンドイッチを食べてしまいます。せっかくここまで来たのだから、と思わないわけではないのですが、いざ食べる段になると、簡単で時間のかからないことを考えてしまいます。それがいつのまにか習い性になってしまいました。
それと、たかが食べることでも、一人で食べると、どんなおいしそうなものでも、あまり感じません。でも、何人かで食べると、おいしいね、と言われただけで本当にそう思います。だから、孫たちにも、おいしいおいしいと言いながら食べると、もっとおいしくなるんだよといいます。これは間違いなさそうです。
(2025.8.6)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| メダカの花嫁学校(文春文庫) | 阿川佐和子 | 文藝春秋 | 2000年10月10日 | 9784167435080 |
|---|
☆ Extract passages ☆
料理の腕というものは、その料理を食べさせる相手があってこそ磨かれるもののようだ。「うまい」「まずい」と反応されて初めて次回への意欲にも、反省にもつながる。自分が食欲のないときでさえ、飢えた家族のためには台所に立たざるを得ない。必然、レパートリーはふえ、上手な手順を身につけることになるのだろう。
(阿川佐和子 著『メダカの花嫁学校』より)
No.2452『新プロジェクトX 挑戦者5』
私もなんどか観たことのある「NHKのプロジェクトX」が新しくなり、その制作班が書いています。目次には、「クルーズ船集団感染」など、多くの人たちが関心を寄せた5つの未曾有の危機に立ち向かった人たちの物語が書いてありました。
これも、手に取っただけで、すぐ借りてきて読みました。挑戦者5というのは、クルーズ船集団感染、パンデミック東京の危機、能登輪島炊き出し、タイ大洪水復旧劇、トルコ海底トンネルの5つに挑戦した人たちのことです。
たとえば、クルーズ船集団感染もそうですが、まさに未知の新型コロナウイルスが入ってきて、どのようにしていいかもわからないなかで、なんとかして食い止めて、さらに感染者の命を救うという使命を全うするには、考えられないような苦労があったようです。初期のころの映像を思い出しても、あの防護服の物々しさを思い出すだけでも緊迫感が伝わってきました。当然、医療に当たる人たちはそれなりの知識があるから、もっともっと困難な作業だったと思います。
「パンデミック東京の危機」のなかに書いてありましたが、「……植木(救急医の植木穣氏)は言う。「医療従事者は、強い責任感と使命感を持って、毅然としてコロナに立ち向かっていました。ただ、家族が喉の痛みを訴えたり、自分の熱が少し上がったりして、コロナが自分事になると、突然ものすごく不安に襲われるんです。普段とても冷静に仕事をしている人が、半分泣きながら『どうしたらいいんですか』と電話してきたこともありました」。新型コロナウイルス感染症は、重症化すれば命に関わる。重症患者を積極的に受け入れていた医科歯科の医療従事者たちは、日々その事実を目の当たりにしていた。実態を知っているからこそ、張り詰めていた糸が切れるように、不安や苛立ちに襲われる瞬間があった。」そうです。
つまり、一般の人たちはもちろんですが、その治療に当たっておられた方はその実態を日々みているからこその怖さもよくわかります。しかも、毎日、テレビ等でその姿を目にしていると、おどろおどろしたとらえどころのない恐怖心があります。そのときは、体外式腹型人工肺「エクモ」のこともよく話題に出ていましたが、この本を読んで、その使い方の難しさを知りました。それは「人工肺という名の通り、肺の機能を代行する装置で、静脈の血液を遠心ポンプで体外に出し、酸素を与えて体に送り返す。病気そのものを治すものではないが、肺の機能を助けることで肺を休ませ、患者が回復する時間を稼ぐことができる。のちに医療従事者以外にも広く知られることになる、新型コロナウイルス感染症の"最後の砦"だった。だが、エクモによる治療とて万能ではない。海外の報告では、エクモを使った場合の救命率は6割と言われていた。また、血液が通る太いカニューレ(管)を首と脚の静脈に入れるため、患者への負担が大きく、合併症の危険が高くなるリスクもあった。管理には細心の注意と多くの人手が必要で、「エクモでなければ助からない」という患者だけに行うべき治療法だった。」と書いてありました。もちろん、一般の人たちは知り得ないことですが、この"最後の砦"が一人歩きしたようなものだったのかもしれません。
そういえば、「能登輪島炊き出し」もそうで、「地震発生から1か月が経過する頃には、避難所から自宅に戻る人も出るようになっていた。とはいえ、依然として炊き出しの需要は大きい。炊き出しメンバーは、2月に3万5680食、3月に3万8754食を提供した。4月に入ると炊き出しの需要はようやく落ちつき、1日700食程度になった。結局、炊き出しは6月末まで半年間続く。この間、トータルで提供した食事の数は、およそ10万食におよぶ。」と知り、やはり人間は食べなくては生きてもいけないと思いました。
ところが、やっと精神的に落ち着いてきた矢先、9月21日に輪島市を含む奥能登地域に豪雨が発生し、河川氾濫や土砂災害に見舞われたのでした。たった1年の間に2度も災害に襲われ、仮設住宅も床上浸水し、輪島市で11日、能登全体で16人も亡くなられたそうです。それなのに、先月に自民党参議院議員の鶴保庸介予算委員長(この発言で責任をとり辞任)が、「運のいいことに能登で地震があった」と発言しました。さらに、「たま、なんだっけ」とも語ったそうで、その上、責任の取り方について「みなさんの気持ちがおさまることであれば、どういう形であってもやぶさかではない」といいながらも、議員辞職や離党については「現状ではそこまで考えていない」と述べました。
おそらく、今回の参議院議員選挙で自民党が大敗した一因にもなったのではないかと思います。そして、この本でも読んで、いろいろな方たちが力を合わせて災害から立ち直ろうとしているその姿を考えてほしいと思います。
下に抜き書きしたのは、第Ⅳ章「緊急派遣5千人 日本メーカーの総力戦」にあったものです。
これはタイ大洪水復旧劇の最後に書かれていたもので、その大洪水から立ち直ってからのことですが、この物語りの中心人物の元沖電気工業の山田隆貴の誕生日でのエピソードです。
タイの人たちに「お父さん」と親しまれていたからこそ、タイの他の企業に再就職した山田さんを囲んでパーティーをしてくれたのです。私は、この大洪水が気になったのは、ここに日本のカメラメーカーがあり、カメラ本体やレンズなどもなかなか手に入らなかったので覚えていました。
でも、あの大洪水のなかで、日本人やタイの人たちが力を合わせて、なんとか乗り越えてきたことを知り、すごいことだと思います。これこそが、本当の意味での国際交流ではないかとさえ思います。
(2025.8.4)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 新プロジェクトX 挑戦者5(NHK出版新書) | NHK「新プロジェクトX」制作班 | NHK出版 | 2025年5月10日 | 9784140887431 |
|---|
☆ Extract passages ☆
この日のパーティーは大いに盛り上がり、別れを惜しむように夜遅くまで続いた。未曽有の大洪水との闘いは、図らずも、山田たちの絆をより一層深いものにしたようだ。社会の分断が進み、人と人とのつながりが希薄になりつつある昨今、立場や国境を越えて互いを″家族"とまで呼び、笑顔で語り合う姿はとりわけ眩しく見える。それはきっと、私たちが忘れかけている大切な何かが、彼らの間に確かに存在しているからではないだろうか。
(NHK「新プロジェクトX」制作班 著『新プロジェクトX 挑戦者5』より)
No.2451『受け手のいない祈り』
この本は、たまたま図書館の新聞の書評欄で取り上げられたコーナーにあり、題名の『受け手のいない祈り』に惹かれて借りてきました。
読み始めて、これは小説だったと気づきました。それでも、医師として勤務しながら小説を書いていると知り、だから病院の内情を詳しく書けるのだと思いました。その生々しさやリアリティ、そして、どこまでが現実で、どこからが幻想というか創作なのかの境もわからないままに読みました。
たとえば、「ペンライトを胸ポケットにしまい、聴診器を胸に当てる、冷えた胸だった。中からは何も聞こえてこない。ドォン、ドオンと和太鼓のように響く心臓の音も、小腸のキルキルと蠕動する音も聞こえてこない。せめて、パチパチパチパチと夏の打ちLげ花火のように、傷んだ肺胞が潰れて弾ける音が聞きたかった。耳を澄ましても、物音一つしない。深夜の台所でさえ、時に食器がズレる音がするというのに。どんな病気さえ入りこむ隙のない、完全な静寂が体の中にある。病めるのは生きている間だけという当たり前のことが奇妙に思われてくる。胸に当てている聴診器が冷えてきた。指先にしんなりとした冷気が染みこんできて、胸から聴診器を外した。」とあり、このあとに「午前五時五十分 死亡確認いたしました。ご冥福お祈り申し上げます」という言葉かついてきます。
そういえば、電気メスという言葉は知っていましたが、具体的にはまったくわかりませんでした。それが、「ピーッという作動音の後に、メスの先端でバチバチと火花が散る。小場の脂肪がジジジと焼けこげ、真っ白な蒸気が立ち騰がってくる。蒸気を顔面で受けると、ホルモンの焼けた匂いがした。」と書かれていて、まさに電気で直に切り取るようなメスだと知りました。それでも、まさか人間の身体を電気メスで切るという行為は、想像できますが、理解はできません。
この小説を読み、医師の大変さとテレビなどで知る医療行為の実態との乖離を感じました。まさに、事実は小説より奇なり、のようです。
この本は、著者が芥川賞受賞後の初の単行本だそうで、主人公が働く病院は「誰の命も見捨てない」を院是に患者を受け入れ続けていることで、医師は長時間の連続勤務による極度の疲労で、まさに死と狂気が常に隣り合わせの日々を綴っているのではないかと感じました。もっと簡単にいえば、患者の命を救うために、医師の命が軽んじられているということでもあります。
下に抜き書きしたのは、この小説の後ろの部分に書いてあった手術中の描写です。
小説を抜書きするのはいつもためらうのですが、今回も選ぶのが難しく、うしろの方でなんとか選びました。それでも、小説というのは言葉よりも流れやストーリーだと思う気持ちには変わりありません。たまたま、気になったという程度です。
ですから、もし興味を持ったなら、ぜひ読んでいただきたいと思います。流れとしては、医師という仕事をしていなければ描けない部分も多く、医師の仕事の大変さも理解できます。
でも、どこからとは詳しくは書いてなかったけど、差し入れの高級弁当が冷蔵庫に入っていて、それをチンして食べるシーンがあります。しかし、手術で大量の出血などを見てすぐに食べることなど、一般の人には考えられない状況です。たしかに、それでも腹は減りますが、だんだんと慣れてくるのか、ある程度そのようなことに耐性があるのかはわかりません。
やはり、外科医になるには、学力だけではなくそれなりの適応力が必要だと思いました。
(2025.7.31)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 受け手のいない祈り | 朝比奈秋 | 新潮社 | 2025年3月25日 | 9784103557326 |
|---|
☆ Extract passages ☆
高熱で頭がぼやけると、眠気が懐かしく降りてくる。ひさしぶりの眠気は涙液のように、固まった眼球をほぐしていく。すぐに目がぼやけてきて、じんわりとする。
仮眠だけでやり繰りする生活だった。最後にしっかりと眠ったのはいつだろうか。数週間前か、それとも一か月以も前かもしれない。最後にはっきりと眠気を感じたのはもっと前だ。
眠気は大量の湿気を含んだモンスーンのように全身を包んで、干からびて過敏になっていた神経を湿らせていく。神経はしんなりと弛んでいき、体全体が甘ったるく脱力していった。強烈な眠気に、目を開いていても眠りに落ち、私が欠落していく。呼吸も深くに落ちて、人工呼吸器でも取りつけられたように、シューコーシューコーと自動的に呼吸が繰り返される。
私は手術をしている夢を見ているのだろうか、それとも眠っている私を何かが動かしているのだろうか。何らかの実感を頼りに探ろうとしても、確かなのは全身に浴れるこの甘やかな眠気だけで、その他は眠りに理没して捉えようがない。
(朝比奈秋 著『受け手のいない祈り』より)
No.2450『基礎からわかる クリティカル・シンキング』
この本を読もうと思ったのは、情報量は格段に豊富になったのに、実際は正確でなかったり、信憑性に欠けたり、さらにはヘイクな情報も溢れていて、それを見極めることが難しくなってきたと感じたからです。特に、トランプ大統領が就任してから、その発言が大きな問題を引き起こし、世界中を混乱させています。しかも、日本語でいうと、発言そのものも二転三転するから、どれを信じていいのかさえもわからなくなります。
たしかに、「今は古代エジプトの「アレクサンドリア大図書館」に匹敵する情報量が、ICTのおかげで手のひらサイズほどのスマートフォンに収めることができてしまう時代なのです。しかし悪ぃことには、たとえ大量の情報を簡単に入手できても、正確さと信憑性を自分で判断することができなければ、ニセの情報を無条件に信用してしまうだけでなく、情報の送り手が「事実」と偽って広めた情報をもとに、誤った結論を導き出しかねません。そういったニセ情報は、推論の欠陥を悪用して世論操作をする人々から発せられることが多々あるのです。」とあり、2016年の大統領選挙も多くのアメリカ人が理性よりも感情に基づいて意思決定を行ったのではないかと疑問を投げかけています。
じつは私もそう思っていて、序文のなかに、元アメリカ大統領バラク・オバマが2009年にクリティカル・シンキングの大切さに触れていたとあり、それもこの本を読むきっかけになりました。この先に引用した情報に関するものも、この序文のなかにあったものです。
やはり、人と直接対話するときやインターネットでも同じですが、好意的な理解や共感性はとても大切です。今回の参議院選挙の演説を聞いていても悪意に満ちた発言もあります。この本にも、『「好意の原則」の欠如が市民の対話にもたらす結果を見たければ、ニュースサイトやソーシャルメディアのコメント欄をのぞくだけで十分です。そこは、文法の間違いや誤字脱字の指摘、あるいは相手の反論を茶化すなどのいさかいが日常茶飯事の世界です。しかし、それらとは逆に相手の主張を好意的に置き換えて理解することは、単に論理の展開がしやすくなるといった次元を超えた恩恵をもたらしてくれます。』とあります。
まさに今は、相手の話に耳を傾けるよりも、先ずは自分の主張を言い合うような時代になりつつあります。
さらに、この本には日本の原発事故についても書いてあり、「そこで問題視されるのは、前提の理解と活用が、希望的観測と最も理想的なシナリオに基づく緻密さに欠けるものだったのではないかということです。前提の理解と活用は、いずれも日本国内の原子力発電拡大を望む筋の意向を汲んだ規制が当局によって歪曲されていた可能性があります。前提を的確に理解せず、間違って活用したことは、原発は安全であるという「安全神話」を誕生させ、政策決定者自身にもバイアスを与え、結果的に間違った推論と間違った証拠を導いたのではないでしようか。」とあり、たしかに日本ではあの事故が起きるまでは、絶対にそのようなことはありえないという安全神話があったように思います。
そういえば、初代原子力委員長に就任した正力松太郎国務相の働きかけで、湯川博士も5人の原子力委員の1人に名を連ねました。正力委員長は、就任当初からアメリカから技術を輸入して5年間で原発を実現したいと考えていたそうですが、湯川博士は「輸入技術への過度の依存は自主性を妨げる」と強い懸念を示しました。そして、結局は就任からわずか1年余りで辞任をされました。
今回の事故も、アメリカ任せだったことも大きな事故につながったのではないかと伝えられています。だとすれば、ここで大きな反省をして、新たな進み方を考えるべきではないかと思います。
また、この本を読んで身につまされたことは、アンカリング効果についてです。私も先に言われるとそれに引きづられやすく、なんでだろうといつも思っていました。
すると、カーネマン著「ファスト&スロー」(2011年、邦訳は2012年に早川書房から)に書いてあるそうで、それからの抜粋によると、「ある未知の数値を見積もる前に何らかの特定の数値を示されると、この(アンカリング)効果が起きる。……「ガンディーは亡くなったとき114歳以上だったか」と質問されたら、「ガンディーは亡くなったとき35歳以上だったか」と問かれたときよりも、あなたははるかに高い年齢を答えることになるだろう。家を購入するときも、最初の提示価格に影響される。同じ住宅でも、提示価格が低いときより高いときのほうが、立派な家に見えてしまう。相手の言い値には惑わされないぞと心に決めていても無駄だ。……何らかの推定や見積もりをするときに、可能な選択肢として提示された数字は、すべてアンカリング効果をもつことになる。」といいます。
つまり、バイアス、1種の思考の偏りを生み出すので、これをアンカリング効果と呼ぶそうです。つまり、自分では理性的に判断したつもりでも、始めに入ってきた情報だけで理解し、意思決定をしてしまうのです。そういえば、これはもともと1,000円だけど、500円にするからと言われると、たいした根拠がないのに500円も安いと考えていまいます。
世の中には、このようなことがたくさんありそうです。
下に抜き書きしたのは、第4章「クリティカル・シンキング志向の世界を目指して」に書いてありました。
デューイは、アメリカ合衆国の哲学者のジョン・デューイのことで、著者も彼の『思考の方法』を薦めています。彼は1859~1952年ですから、だいぶ前の方ですが、今でも「なすことによって学ぶ(Learning by Doing)」を実践したことで、自分自らが体験することによって、その行為を反省的に思考することが「学んでいる」ことだといいます。
おそらく、これは今でも通用する学びではないかと重い、ここにも取り上げました。
(2025.7.28)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 基礎からわかる クリティカル・シンキング(ニュートン新書) | ジョナサン・ヘイバー 著、若山 昇 監訳 | ニュートンプレス | 2022年7月15日 | 9784315525762 |
|---|
☆ Extract passages ☆
デューイによれば、生徒の学習意欲に火をつけるのは、疑間を解消したいとする欲求です。しかし教師がすべての答えを用意したら、生徒の心にはそうした欲求は生まれてきません。したがって、教員養成や学校に配布される教材の開発といった教育学的戦略は、次の点を重視すべきでしょう。まず(1)正誤問題式ワークシートやテストを廃止して、生徒のモチベーションを喚起し、疑間を植えつけるように構成された問題へと切り替える(少なくとも補助教材にはすること)。そして(2)知的生産性を高める形で、生徒主体で疑間を解消できるような思考法へと導くこと。これを繰り返すことで思考の習慣が生まれ、それは学年が上がっても生徒の心に消えることなく刻まれるはずです。さらにはこのような思考の習慣が教科や学校といった枠を超えて、日常生活にも「学習の転移」が起きるようになれば何も言うことはありません。
(ジョナサン・ヘイバー 著『基礎からわかる クリティカル・シンキング』より)
No.2449『ヒトとヒグマ』
先日、星野道夫さんの写真集を見て、その数日後に図書館に行くと、この本がありました。そういえば、星野さんは、1996年8月8日にロシア・カムチャツカ半島クリル湖畔でヒグマによる事故で急逝されました。
その前にガイドたちは星野さんに小屋で寝るよう説得したそうですが、「この時期はサケが川を上って食べ物が豊富だから、ヒグマは襲ってこない」としてテントに寝たそうです。それで襲われました。
私は、先月から今月初めにかけて津軽三十三観音札所をお詣りしましたが、あちこちに「クマ注意!」の立て札があり、第25番札所の松倉観音堂は3㎞ほどもあり、途中スマホも通じないところがあり、地元の人にお願いし、いっしょに上ってもらいました。それほど、クマがあちこちに出て、ニュースでも取り上げられます。しかも、今のクマは昔のクマと違い、あまり人間を怖がらないそうで、雑食とはいいながらも、北海道のヒグマはエゾシカなども食べているそうです。
この本でも、「ヒグマは草食性に傾いた雑食性である。また、現在の北海道では、人間活動の影響を受け、主に草本を食す草食獣エゾシカが急増しており、生息域での餌資源について、ヒグマとの競合が起きている。エゾシカの個体数が増加すると、ヒグマは植物を十分食べられなくなるという問題が生じている。一方、エゾシカの増加にともない自動車や列車との交通事故の件数も増加し、社会問題化している。そのため、交通事故により死亡し道路脇に放置された死体(ロードキル個体ともいう)やけがを負って野外で死亡した個体も増えている。さらに、 ハンターによるシカの死体やその一部が野外に放置されることもある。冬季の積雪や低温に耐えられなくて死亡したシカ幼獣の死体も春先に野外で目撃される。このような状況のなか、ヒグマはシカ肉を食す機会が増え、肉食化している。そのため、肉食化したヒグマは、放牧されている家畜やヒトまでをも襲うようになっているのではないかと考えられている。」といいます。
だから、今のヒグマは怖いのです。それなのに、ツキノワグマやヒグマが檻にかかると、それに批判的な人たちの電話などによる批判が急増するので、行政側もどうしていいかわからないような状況です。それで、人里離れたところに、放してしまいます。一般的に、クマの移動範囲は非常に広いそうで、オスは約70㎞、メスは約40㎞ほどだそうで、あまりなわばり意識はなく、エサのあるところを移動しているそうです。
だとすれば、放したところから舞い戻ることもあり、だから判断が難しいといわれるのです。しかし、ヒトに大きな被害が出れば、クマを大切にとばかりは言えません。
この本のなかに、「成獣になると獰猛で危険な動物である一方、幼獣はぬいぐるみのようにかわいらしい。このようなヒグマに対する感情の二面性というか感覚のギャップが、さらにヒグマがヒトの心の奥底に眠る無意識を刺激し、特別な動物と意識されるようになったといえるだろう。」と書いています。
つまり、クマのいるところで生活している人たちはクマは獰猛で危険な動物ですし、クマを動物園やテレビなどでしか見たことのない人たちにとっては、それが子グマであればあるほど、おそらくぬいぐるみ感覚でしか考えていないと思います。その、いわば感情の二面性があるから、問題を複雑化しているようです。
しかし、ヒグマの近くで長く暮らしてきたアイヌのヒトたちは、「ヒグマがカムイ(神)の世界から、動物の姿を借りてこの世に現れたものであると考えられてきた。特に、ヒグマは山の神「キムンカムイ」として高い地位にあり、それを捕獲して食すに際して、そのカムイに礼を述べ、ヒグマの再来を願いながら、丁重に山々(天上界)に送り返すクマ送り儀礼が行われてきたのである。ヒグマが自然の神の世界からやってきた神の化身であるという考え方は、ユーラシア北部の先住民の間でも広く共通するものである。ヒグマは自然と結びついた崇高なもので、畏怖の念をもって認識されている。よって、ヒグマを送る儀礼では、ヒトから見れば、ヒグマは人間界(地上界)で生きた後、死して元来のカムイ界(天上界)に戻るのである。」と考えるのだそうです。
そうすれば、ヒグマは狩猟し食べたとしても、再び復活して、ヒグマとして戻ってくれば、矛盾や葛藤を和らげることができます。
下に抜き書きしたのは、第4章「狩猟からクマ送り儀礼へ」にありました。
最近のクマは、秋に十分な食料を確保できなかったりすると、冬眠ができないこともあるそうですが、そういう意味では今のクマはたいへんです。頭数が増えたということもありますが、気候変動などの影響で、山の果実なども激減することもあります。それでも、生きていかなければならず、人間と出くわす機会も増えてきているようです。
ある意味、どちらにとっても不幸なことで、この本に「P170」と書いてあり、そういえば昨年はクマの捕獲に関して、苦情などの電話がたくさんあったとことなどを思い出しました。
これだけクマ被害が出ると、ほとんどニュースでも取り上げなくなりましたが、おそらく、野生のクマを見たことがない人たちにとっては、ぬいぐるみのイメージがあるのではないかと思います。
(2025.7.24)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| ヒトとヒグマ(岩波新書) | 増田隆一 | 岩波書店 | 2025年3月19日 | 9784004320593 |
|---|
☆ Extract passages ☆
……母グマは冬眠中に出産する。そして、通常、生まれた仔グマとともに二度の冬眠をする。つまり、仔グマの養育に二年という長い年月を費やす。このような冬眠および仔グマの出産と養育は、ヒグマの母性の象徴として、古代の人々に感じとられたものと思われる。
一方、ヒグマが生息する亜寒帯の森林では、春の到来とともに枯木から新緑の葉が一斉に芽生え、本々の緑が夏にかけて一面に繁茂していく。そして、秋には紅葉とともに広葉樹は落葉し、冬が訪れると積雪のため林床は深い雪に覆われる。
(増田隆一 著『ヒトとヒグマ』より)
No.2448『自由人は楽しい』
この本はだいぶ前に購入し、なかなか読む機会がなかったのですが、先月から今月初めにかけて津軽三十三観音札所をお詣りしたときに持っていきました。その旅の途中で読んだのですが、先に写真を整理しなければならず、この「本のたび」はその後になってしまいました。
旅に持ち出すのは、基本的に文庫本で、しかも電車内で読むことも考え、ほどほどの活字の大きさも必要です。でも、あまり大きな活字本だと、何冊も持って行かなければならず、それも困ります。たまたま、この本がそれらに合致していたということです。
しかも、題名の『自由人は楽しい』も、ここに取り上げられたヒトたちも、ほとんど旅好きです。たとえば、ゲーテの旅の仕方は、「旅人がまず欲しがる地図といつた情報をわざと遮断します。地図・案内書・案内人、そういうものを受け入れない。そうすると目が非常に生き生きしてくる。自分がどこにいるのか、どの方向に向かっているのかということを目が確かめ、耳がいろいろな音を聞きつけ、自分の足が道を探り出していく。要するに、目や耳や体、肉体の感覚が非常に鋭敏になる。情報が先に入ると、それだけを見てしまう。地図だけを見て、教えられたところにしか行かない。ゲーテは情報をまず遮断したうえで、自分の感覚だけで町を歩いた。ゲーテの歩き方、旅の仕方は、旅に必要な本質というものをよくとらえている。」と書いてあり、今回は観音詣りですから、いわば目的のある旅です。だから、ゲーテのようにまっさらの体験をするというわけにはいかないので、ある程度、札所のまわり方を決めて行動します。
しかし、もし、普通の旅なら、どちらかというと私もゲーテのような歩き方がいいと思ってます。だからほとんど案内書も買わないし、地図も買わない。ある意味、出たとこ勝負のようなところがあります。
また、モーツァルトのように、「モーツァルトの生涯にわたる旅にはどのような意味があったのだろう。遠くから自分の育つたところ、住んでいるところを絶えず振り返つてみるということ、そこに才能を開花させるための非常に大きな意味があった。モーツァルト自身が手紙の中で、「すべて自分は旅を通して学んだ。旅をしない人は石のような人間になる」と、そういう言い方をしています。」とありますが、たしかに旅をすることによって「ヨーロッパがどのように変わりつつあるのかを肌で感じ」たからこそ、宮廷のお抱え楽師から抜けだし、いろいろな体験をしながら、今も残るような作曲もできたのではないかと思います。
ちなみに、この本では、モーツァルトやゲーテのほかに、ロートシルト、グリム兄弟、シュリーマン、トーマス・マン、ヘルマン・ヘッセ、ケストナーの8人を取り上げています。彼ら個性のある人たちの生き方を読むと、「人生は楽しむためにある」という思いを強く感じます。
下に抜き書きしたのは、ハインリッヒ・シュリーマンが日本に来て、感じたことのひとつです。
彼は、トロイヤの遺跡を発掘したことで有名になりましたが、もともとは考古学者ではありません。登記や金融、商品取引などをする承認だったそうですが、40歳を過ぎてから遺跡の発掘に取り組みました。それも、ホメロスの『イリアス』や『オデュッセイ』を丸暗記するほど読み、ほとんどの人はこれらは文学作品だと思っていたのに、彼はそのなかにある記述をすっかり信じ切っていました。
だからこそ、発掘に踏み切ったわけです。まさに、信じるものは救われます。
それが不思議なことに、「彼はトロヤやミケネ、ほかにも二ヵ所ほど大々的に発掘しました。これらの発掘で、シュリーマンは明らかに間違ったところを掘っていた。当人は予測した場所を掘ったはずなのですが、実際には予測とまったく違ったものを掘りあてている。このことははっきりと自伝には書かれていませんが、つまり予測は間違っていたわけです。それにもかかわらず、彼は意図したよりもはるかに豊かな発見をした。シュリーマンという人の運命というか、生き様の中でいちばん不思議で謎めいたところでしょう。当人は明らかに間違えたのに、むしろその間違いがより大きな収穫をもたらした。」といいます。ある意味、既存の考古学的知識がないからこその出合いだったのかもしれません。
(2025.7.20)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 自由人は楽しい(NHKライブラリー) | 池内 紀 | 日本放送出版協会 | 2005年1月15日 | 9784140841914 |
|---|
☆ Extract passages ☆
シュリーマンが感心した日本人の風習に、懐紙の使い方があります。彼は「吸取紙」と書いていますが、日本人はハンカチではなく懐紙を袖に入れており、鼻をかむたびに懐紙を一枚使ってはそれを捨てる。なぜそれに感動したのかというと、ヨーロッパ人はハンカチをポケットに入れて、何日問も同じハンカチで鼻をかんでいたからです。それに、町中いたるところに公衆浴場があり、老いも若きも豊かな人も貧しい人も風呂に行く。だから世界で最も清潔な国民であろうと書いています。鼻紙とお風呂に感動するところなどは、いかにも商売で鍛えてきた人、学者ではなく、実業の世界に生きてきた人の見方だと思います。
(池内 紀 著『自由人は楽しい』より)
No.2447『くだもの栄養学』
この本は、もともと1981年4月に毎日新聞社より刊行されたもので、くだものを栄養学から考えるというあたり、ちょっと古さを感じます。でも、買ったのは10年ほど前で、もともと果物が好きなので、いつか読もうとしたのですが、今になってしまいました。
ある意味、今ではありふれた果物も、この本が出た当時はとても珍しかったり、今ではほとんど出回らなくなった果物もあったりして、とても楽しく読むことができました。たとえば、バナナひとつでも、昭和37年の夏にコレラが上陸したということで大騒ぎになり、この影響でバナナが焼却されたり海に投棄されたのだそうです。
今では、このバナナもスーパーなどの店頭では4~5本で200円程度で売られたり、高地栽培の高級品でも400円程度と、比較的安定した果物になっています。私の子どものときには、1本100円ほどもして、その当時のキャラメルが1箱10円でしたから、そうとう高い果物でした。だから、病気でもしないとなかなか食べられなかったのです。
初めの書き出しのところに、「果物こそは神意仏心に添うた食物であるし、これなら天の啓示の食物だから人間の食物として可なるもの」というガンジーの話しが紹介されていて、果物好きとしては、納得です。
そういえば、インドといえばマンゴー、バナナ、グァバ、リンゴ、ブドウなどの生産が盛んですが、そのなかでもマンゴーの生産量は世界トップで、世界の生産量の約4割を占めているそうです。またバナナの栽培も盛んで、その種類も多く、調理用バナナなども市場にたくさん出ていました。
たしかにインドでリンゴも栽培していますが、ダントツは中国で4,757万トン、2位のトルコの10倍ほどです。インドは第5位で、258万トンです。日本は世界ランキングには出てきませんが、世界的に日本のリンゴは大きくきれいでおいしいというのはおおかたの意見です。
リンゴといえば、昨年の12月2日、「リゾートしらかみ」に乗り、深浦駅で頼んでおいた「中まで赤いりんごのフォカッチャジャムサンドパン」を食べました。この本に、この中まで赤いりんごの話しが載っていて、「青森県の津軽は五所川原在で、土地では「津軽の二宮尊徳」と敬称されていた前田翁が長い年月、精魂を打ち込んで品種改良を行った努力と汗の文字通の結果として、昭和30年に芯までも紅いリンゴが入工で出来上がったのである。」と書いてあり、今では、「紅の夢」、「ムーンルージュ」、「御所川原」、「栄紅」、「なかの真紅」などの品種があるそうです。
ちなみに、私の食べたフォカッチャジャムサンドパンは、「御所川原」という品種でした。ジャムになっていたので、はっきりと芯まで赤いかどうかまではわかりませんでしたが、誰も頼んだ人はいなく、たった1個を駅のプラットホームまで届けていただいたのが申し訳なかったです。
そういえば、今回の津軽三十三観音札所詣りのおり、7月2日の第25番松倉観音堂は最大の難所で、クマ出没情報もあり、地区の方に同行していただきました。すると、そのお礼かたがた寄せてもらうと、その帰りにリンゴをいただきました。その晩、それを食べましたがサクサクで、どのように保管していたのかと思いました。
下に抜き書きしたのは、「果物から葉へ、水分の恩返し」に書いてあったものです。
果物農家に朝早く収穫するのは、市場に出荷するためだと聞いたことがありますが、このレモンの実験を知り、理にかなったことだと思いました。
これから桃が市場に出てきますが、これなどはサクランボと同じように保存しておくことは難しく、収穫したらなるべく早く食べたほうがいい果物です。だからこそ、この旬の時に食べたいと思うのですが、それも大切なことだとこの本を読みながら思いました。
この桃などは、本を読みながら食べるというと、果汁で本が汚れてしまうこともあります。ゆっくり果物を味わって、それからのんびりと本を読む、それがいいな、と思います。
(2025.7.16)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| くだもの栄養学(新潮文庫) | 川島四郎 | 新潮社 | 1990年1月25日 | 9784101090139 |
|---|
☆ Extract passages ☆
レモンの木で行われた実験によると、朝の6時から果実が萎み始め、午後の4時に一番小さくなる。それから夜になると、果実は再びだんだんと膨らみ始め、夜明けの6時前までこの状況が続く。そして果実と葉の間に毎日々々同じことが繰り返される。
地面が乾いて水分が少ないほど、果実の膨らみ方と萎び方の幅が大きくなる。
こうして見ると果物というものは、前日の夕方から夜にかけて膨らんで充実した、その朝にとって食べるのが一番うまく、夕方にとって食べたのでは、葉の方へ成分や水分を送って萎びたのを食べるわけで比較的まずい道理である。昔から果物は朝とって食べるとうまいというのは道理にかなっているわけである。
(川島四郎 著『くだもの栄養学』より)
No.2446『なみまの わるい食べもの』
この「わるい食べもの」シリーズは、2冊は読みましたが、その流れから、ついついまた手にとってしまいました。だからといって、気に入らないわけでもなく、どこかで惹かれるものがあるからです。
このシリーズは4作目だそうで、時期としては2023年から2024年の2年ほどで、この間は直木賞を受賞したり、2度目の結婚をしたりといろいろと重なったようです。とくに、それは直木賞受賞後からのことで、「なんだか大波に翻弄されているみたいな年でした」と書いていて、そこからこの本のタイトルにある「なみま」が生まれたようです。
ここまで、なぜ「なみま」だか、よくわからなかったのですが、これで了解しました。
私も著者と同じように、食べもの好きだし、とくに甘い和菓子系はお抹茶とともに、ほぼ毎日食べ飲んでいます。それをSNSで流したりするので、むしろ出さないと落ち着かないときもあります。ただ違うのは、著者のように好き嫌いがはっきりしてなくて、何でも食べて見ようというタイプです。
先ずは食べてみないことには、美味いか不味いか、自分の口に合うか合わないかもわからないと思ってます。もし、口に合わなければ、それから先は食べなくなりますが、それでも十数年も経てば、好みも変わることがあるので、また試すときもあります。
だから、基本的にはわるい食べものというのはないと思ってます。
ただ、あまり好きなものだけを食べていると、新しい食べものとの出合いがなくなると思い、その出合いだけはなくさないようにしてます。
この本の最後のところで、ウィーンに行く話しが載っていますが、最初はいろいろと心配して情報も集めていました。ところがいざ、行ってみると、「懸念していたパンと生クリーム問題も無事にクリア。冷たい飲みものに氷が入っていないのも、オレンジジュースが甘すぎないのも万歳したいくらい胃腸に合ったし、ワインを炭酸水で割ったグシュプリッツァー、葡萄の収穫期しか飲めない発酵途中のワインのシュトルムをごくごくと飲んだ。日本にいるときより水分が体に入ってきやすかったせいで、出国前に患っていた膀洸炎も完全に治った。」とあり、まさに案ずるより易しです。
私も似たような経験があり、イギリスに行くとき、あそこは食事が不味いとさんざん聞かされましたが、それほどでもなく、嫌いなタラを使ったフィッシュ・アンド・チップスでさえも、食べられました。またウサギやシカなどのジビエ料理もおいしく、なかでもスコットランドで食べたパンも絶品で、毎朝通ったぐらいです。
だから、あんまりいろいろと情報を集めてから行くより、何も知らないで行く方がよいときだってあります。
著者も、京都に住んでいたこともあり、どうしても行くとなじみのところばかりになってしまうそうです。この本には、「湿った京都の夜道を、馴染みのバー「月読」へと歩いている途中で気づいた。朝から目的地にしか向かっていない。短い滞在日で行ける店は限られている。だから、予定を組み、予約をして、ひとつひとつこなすようにして好きな店をまわっていた。新しい店も、歩いたことのない道も目に入っていない。興味深いものを見つけたとしても、私には割く時間もなければ、次にいつ来られるかもわからないから。」といいます。そして、「住んでいたときはこういう時間の使い方はしなかった。予約も目的もない空白の時間があり、その中で碁盤の目の街をふらふらと歩き、四季折々が見せてくれる違う顔を楽しんだ。それが日常だった。いまは同じ京都にいても、音の記憶をなぞっているだけだった。それでも、なぞれるだけいいのだ。なくなってしまう店もあるし、街並みだって変わっていく。」と続けています。
やはり知っているところをまわれば、安心感もあれば、失敗もあまりありません。でも、それだけでは、せっかく行く意味も半減します。わからないからおもしろい、ということもあります。
だから、毎年、まったく知らない土地をほっつき歩くようにしています。いつまで、こんなことができるかわかりませんが、歩けなくなるまで続けようと思ってます。
下に抜き書きしたのは、「石見銀山編」のなかに出てくるものです。
小説家というのは、どこから書こうとするアイディアが生まれるのか、ちょっと興味があり、ここを読んだときには、なるほどと思いました。それと同時に、そんなにとんでもないことからでも書くきっかけがあり、それがその人の持つ個性ではないかと思いました。
この編が最初にあるのも、意外と著者も印象に残ったからではないかと考えたりしました。
(2025.7.13)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| なみまの わるい食べもの | 千早 茜 | ホーム社 | 2025年5月30日 | 9784834254006 |
|---|
☆ Extract passages ☆
早起きして宿を出て、ひと気のない道を歩いた。昔ながらの面影を残す人森の町を抜け、『しろがねの葉』の主人公のウメが住んでいた仙ノ山へ向かう。濡れた地面に陽がさして水蒸気がゆらめく。草葉は朝露で光り、烏の声だけが響いている。男性の親指ほどもあるナメクジを眺め、葉の裏のカタツムリをつつき、昨日買ったドライフルーツやナッツがみっしり入ったパンを噛みちぎりながら進んだ。自分だけの自由な時間は手足や感覚を伸び伸びとさせた。ああ、こういう寄り道の果てで物語は生まれるんだった、と思いだした。
(千早 茜 著『なみまの わるい食べもの』より)
No.2445『鳥類学者の半分は、鳥類学ではできてない』
著者の『鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。』を読みおもしろかったので、この本にも、つい手が伸びました。学者らしからぬ書き方に、親近感を覚えます。
さて、学者というのはどのようにして研究をするのかと思いながら読んでいると、「研究には大きく分けて2つのタイプがある。1つは仮説検証型だ。まず過去の知見から論理的な仮説を立て、それを証明するのに適した方法で調査や分析を進めるという様式である。その一方で、データ駆動型の研究というのがある。こちらは特に仮説がないままに発見が先行するもので、こんなの見つけちゃったから報告しま―す、というタイプのものだ。」と書いてあり、なるほどと思いました。
私は植物が好きなので、こんな珍しい植物を見つけちゃいました、という発想が多いようです。それを図鑑などを調べて、どのような名前なのか、分類的にはどこに属するのかなどを見つけ出します。
だからといって、新種などというのは滅多にというか、ほとんど絶対に見つかりません。牧野富太郎の時代ならいざ知らず、アマゾン河流域や中国奥地へでもいかないと難しいようです。しかも、今はDNA鑑定が主流ですから、素人の入るスキはまったくありません。だから、植物分類学をやろうとする学者もいなくなっているようです。
そういえば、あるテレビに出ているコメンテーターの方が、1日に100編ぐらいの論文に目を通すと話していましたが、この本にも、「論文を書くためには、過去に書かれた論文をたくさん読む必要がある。似たような例がないかどうか、この分野でどのくらいのことがわかっているかを調べることで、自分のデータが持つ意味を明らかにするためだ。」と書いてあり、学者には論文がとても大切だとよくわかります。
そういえば、誰かとよく似た論文を書けば、もしかして盗作だと思われてしまいますし、すでに同じような内容の論文があれば、二番煎じになってしまいます。でも、この検証って時間もすごくかかりそうで、大変な仕事だと思います。
ところが、この本の著者は、意外と物忘れをしたり、うっかりミスをしたりと、楽しい研究をしています。たとえば、たまたまJALのマイルがたまったので、今まで行ったことがない宮崎に行こうとしたら、「確かに私が申し込んだのは「どこかにマイル」という特典航空券だった。これにエントリーすると4つの候補地がランダムに表示され、申し込み後に行く先が決まるというミステリーツァー的チケットだった。そのシステムを全く理解していなかった。」ということで、1週間前に宮崎ではなく奄美大島に行くことに決まったそうです。
そこでバタバタと宮崎のホテルをキャンセルをしたりしながらも、「とはいえ、奄美大島が嫌なわけではない。むしろ神の采配に感謝している。」と言うんですから、幸せ者です。
いわば、出たとこ勝負ですから、何が起きるかわからない、それも人生の大きな楽しみではあります。
下に抜き書きしたのは、第2章「鳥類学者は偶然を愛し、偶然に愛される」に書いてあったものです。
じつは、パンダも双子を産む確率が50%近くもあり、しかし2頭とも育てることが難しく、結果として1頭しか生まれないといわれていたそうです。この鳥の話しを読み、何となくそれと似ていると思いました。
また、カルガモの話しもおもしろく、そういえば、鳥は生まれて最初に見たものを親だと思い、その後ろをついていくということが多いそうです。それを「刷り込み」とか「インプリンティング」というそうですが、だとすれば親は誰でもいいということになります。
でも、人間の場合は生まれたばかりの赤ちゃんは一人では生活できないので、親がかかり切りに世話をすることになります。だからこそ、絆が生まれるのかもしれません。
(2025.7.10)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 鳥類学者の半分は、鳥類学ではできてない | 川上和人 | 新潮社 | 2025年5月15日 | 9784103509134 |
|---|
☆ Extract passages ☆
たとえば、山岳の王者たるイヌワシや熱帯の島で繁殖するカツオドリは2つの卵を産む。すると2羽のヒナが生まれるわけだが、彼らは巣の中で兄弟殺しをし、巣立つのは1羽のみだ。親鳥がそれを止めることはない。カインとアベルが神話になったのは、それが特別なことだからだ。イヌワシやカツオドリの世界では当たり前のことすぎて、だれも気にしない。
カルガモではヒナ混ぜという現象がある。池でヒナを連れた家族がすれ違う時に、ヒナたちが別の家族に混じってついて行ってしまうのだ。その結果、一方の家族はいつの間にか大家族になり、一方は小家族になる。お母さんはヒナが増えても減っても気にしないし、ヒナも実のお母さんに執着しない。あんなに仲良さそうに見えたのに親子の絆を感じさせない。
(川上和人 著『鳥類学者の半分は、鳥類学ではできてない』より)
No.2444『和菓子の京都 増補版』
この本の初版は1990年ですから、平成2年で35年ほど前です。なんとなく読んだような記憶もあるのですが、増補版ということで、もう一回読み直すのもいいかもしれないと考えました。
この本を読んで知ったのか、あるいは他の本か誰かから聞いたのかはわかりませんが、粽に使う笹のことはおぼろげに覚えています。この本では、「この北山の笹というのは非常に香りがあって、何百枚かのうち一枚ぐらいは、すばらしい方香を放つような葉が、いまだにまじっているんです。これが北山から滋賀県境へかけて生えていて、秋深くなって、霜がおりてくるようになると葉が硬くなって、まったくだめになります。反対に、上用までに採りますと、新葉の青臭さが残っていたり、軟らかすぎたりしてやはりだめなんです。」と書いています。
ということは、この笹の葉の採集は「土用の後の、もうほんの一時期のわずかなチャンスしかない」ということになります。だからといって、この限られた日数のなかで「大量に刈り込む」というのは、さすがに大変だし、非効率のような気がします。さらに、自然保護の観点からみても、ちょっと強引すぎると思いましたが、だからこそ、伝統が守られるといえば、そうかもしれません。
本当に難しい、ギリギリのところで京都の和菓子が作られているとも思います。
そういえば、川端道喜といえば、葩餅も有名で、今ではどこのお菓子屋さんでもお正月の菓子として作っています。でも一番は道喜のもので、一般にはなかなか出回らないので、だからこそ食べて見たいと思うわけです。この葩餅は、今ではゴボウが挟み込まれていますが、昔は鮎だったそうで、それが不思議でもありました。
すると、この本に、「さてこの鮎が、ごぼうに変わるのはいつごろからか、というのは定かでないのですが、当時地震とか天災にたいする恐怖感が根づよくあって、上中に深く、家の基になるというごぼうを愛でる、あるいは、その灰汁でもって厄除けにするという意味合いでごぼうというものをめでたい具に使っていました。そういうことが重なって、この鮎がごぼうにいつしか、変わってしまったということだと思うんです。そして、御所では、葩何枚重ね、 つまり五十重ねとか、百重ねといったことで、菱餅を何枚にも重ね、ごぼう、味噌とみな別々の桶に入れて禁中へ運び込む。そして、公家百官をはじめ雑色(ぞうしき)といった警護に当たる役人にいたるまで、これが配られる。そして、配るときには、葩をまず出して、その上に菱餅をのせて、ごぼうをのせて、味噌をつけて渡されました。その場で食べるにしても持って帰るにしても、自由に折りたたんで食べていたようです。」とあり、鮎からゴボウになったことだけではなく、あの独特の葩餅の形までが理解できました。
たしかに、和菓子にも長い歴史がありますから、なぜこのような材料が使われたのかとか、この形はどこから生み出されたのかとか、いろいろ考えさせられることがあります。だからこそ、このような本を読むことによって、わかることもあります。
そういえば、よく職人気質ということを伝え聞きますが、同じ職人から聞くと、なるほどと理解できます。
この本でも、著者が餡を炊くときの様子を書いています。それは、「私も餡を炊くとき、「こんちくしょう」といって炊くんです。これが大村しげ(1918―99年)さんの筆にかかると、いとしい餡を愛でるようにして、慈しみ炊き上げるという表現になるんでしょうが、実際には、親の敵にでも出会ったような顔をして炊き上げているんです。案外、職人というもんはそういうもんじゃないですか。もし、職人の誇りというようなものを強いていうなら、手間隙かけて苦労してやっても、それをいかにもプロだから朝飯前のお茶の子サイサイで作ったんだよと、涼しい顔をしてるようなところが京都の職人根性かもしれないですね。」といい、たしかにありそうだと思いました。
今では、その手間暇のかかる餡炊きも、機械がやってくれる時代ですが、炊きあげるときの気象条件とかタイミングとかは、個人の力量にかかっているような気がします。そうでないと、どこのお菓子屋さんの餡も同じでは、選ぶ楽しみもなくなります。
私も和菓子が大好きで、毎日お抹茶を点てながら、食べています。すると、長年伝えられてきた老舗の味というのは、たしかにあります。だからこそ、いろいろな和菓子を食べてみたいと思うのです。それを記憶にとどめておくために、写真を撮り、Facebookにも掲載しています。
下に抜き書きしたのは、第3章「宮中の歳時記、茶の湯の四季」に書いてありました。
たしかに薄味であれば、好みによって少しは味を変えられますが、濃い味にしてしまうと、それから差し引くことはできません。これはたしかに合理的です。
たとえば、味噌汁のようなものであれば、湯を足して薄くすることはできますが、料理として出されれば、それから引き算はできません。
(2025.7.7)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 和菓子の京都 増補版(岩波新書) | 川端道喜 | 岩波書店 | 増補版第1刷2025年5月20日 | 9784004320661 |
|---|
☆ Extract passages ☆
……味というものは必ず個人個人の個体差があるため、自分にあった味つけをするといぅのが、日本料理、とりわけ京の料理なり菓子なりの基本だということなんです。たとえば敷砂糖という一つの方法があります。これは、砂糖の少なかった時代の名残でもありますが、砂糖を薄く器に敷いてその上に味のつけてない餅なり餡なりをのせて、自分の好きな味にしていくやり方です。だから、つくり、刺身という魚の切身を、自分でたで酢で食べようと、あるいはわさび醤油で食べようと、味を自分の好みに合わすということがあくまでも基本であるのと同じです。京料理が薄味であるということは、そんなとこに原点があるんじゃないかというふうに思われるんです。
(川端道喜 著『和菓子の京都 増補版』より)
No.2443『あしたはアルプスを歩こう』
6月30日に出発し、今、津軽三十三観音札所をまわっています。旅に出るときは文庫本を持ってきますが、その1冊がこの『あしたはアルプスを歩こう』です。
これは、もともとは『あしたはドロミテを歩こう イタリア・アルプス・トレッキング』として岩波書店から単行本として出たのですが、その文庫版です。薄くて旅先で読むにはちょうどいいと思い、持ってきたのですが、あまりにも簡単に読み終えてしまいました。
だからといって、印象にのこらないかというと、そうではなく、旅先だからこそなるほどと思うところもありました。
たとえば、「イタリア人ってなんかすごい。このとき私は密かに思った。あの雪山では本格的なエスプレッソだったし、この渓谷ではワインである。エスプレッソもワインも、道具もボトルもかさばるし重い。それでも持ってくる根性がすごい。インスタントですまそうとか、ワインは我慢しようとか、近道的な発想がないのだ。おいしいものを味わうためには、ひとときの安らぎを得るには、まるで労を惜しまない。」という話しです。私もどこへ旅するときでも、今、津軽三十三観音札所をまわっていても、リックにお抹茶を点てる道具が入っています。つまり、お湯さえ沸かせれば、いつでもお抹茶を点てられます。そして、なるべくなら、その土地のお菓子を手に入れられれば最高です。
そう思っていたら、次のページに、「私たちも茶道具を持って山を登るべきなのだ」と書いています。それを何でも便利にしたいとか楽をしようとか、近道をしてしまうことがもったいないことだといいます。そう、たしかに便利でないことや楽でないことが、後から思い出すことが多いようです。近道を歩いてしまうと、ほんとうに大切なことを抜かしてしまうこともあります。
そんなことを、ひなびた龍飛旅館に夕方着き、お抹茶を飲みながら思いました。
著者の登山のガイドをしてくれたマリオさんは、仏教僧侶でもあるそうですが、なぜ仏教なのかと聞くと「キリスト教は信じなければならないものが多すぎるとマリオさんは言う。神とマリア、イエスとその奇跡、真実と天国。信じることを必要とする宗教は、人を子どもにするような気がした。マリオさんは静かに語る。なんにも考えなくてもいい、子どもにしてしまうんじゃないかと。自分が感じた違和感というのは、つまりそういうことなんだ。」そうです。
たしかに、そういわれれば、キリスト教というのは信じることが救われるようです。ところが仏教は、とくに欧米人にとっては、哲学だと考える人がいます。いかに生きるか、どのように生きていくかを考える、それが仏教の教えだといいます。
そしてマリオさんは、「あそこに山がある。頂上に登れば、向こう側の景色が見える。登らないで、見えない景色を推測することを私はしたくない。自分の足で登れば、頂上から向こう側の景色が見える。自分の日で見ないと信じられない。逆に、自分の目で見てしまったら、もう信じるしかないんです。それは山も、神も私にとって同じなのです」といいます。
そしてさらに、「山に登っていると、頭のなかが空っぽになる。禅も同じ。禅を組んでいると、自分自身が空っぽになる。それで、自分以外の何か大きなものと一体になるという実感がある。山と禅はよく似てるんです。」と付け加えます。
そういえば、観音詣りをしていても、お詣りするとすぐから、次の観音さまへの道順を考えたり、それ以外のことは考えないから、いわば観音さまだけを考えているようなものです。それも巡礼のいいところかもしれません。
下に抜き書きしたのは、この本の解説を書いた三浦しをんさんの文章に出てきます。
私も元山岳部としては、なぜ山に上るのかと考えたことがありますが、そこに山があるからというのではありません。登るときには辛いのですが、登りきった後の達成感というか爽快感は、とても素晴らしい快感です。だから、また登りたくなります。
この三十三観音札所の旅も似たようなものです。この津軽のあちこちをまわって歩くと、昔の人たちがお詣りしながら歩いた気持ちと共鳴しあいます。つながっているような感じがします。もう2度とは来ないかもしれないと思いながら、一ヵ所一ヵ所をまわります。そこには、なぜ、という疑問も何もありません。
つまりは、全部まわりきったときの達成感みたいなものがあるからだと思います。
(2025.7.3)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| あしたはアルプスを歩こう(講談社文庫) | 角田光代 | 講談社 | 2007年7月13日 | 9784062757829 |
|---|
☆ Extract passages ☆
問いかけても詮ないことと知りながら、問わずにはいられない問いというものがある。たとえば、「なぜ山に登るのか」「なぜ走るのか」「なぜ文章で表現するのか」といったようなことだ。
登ってくれと山に頼まれたわけではない。電車や車に乗れば、走るよりもずっと早く目的地にたどりつける。毎日毎日机に向かって描写した光景も、実際の光景を見てもらえば、文章を読むよりも正確に一日で伝わる。しかしそれでも、山に登り、走る練習をし、書きつづけずにはいられねひとがいる。
これらの行為、間いかけても詮ない問いを、答えを得られぬまま実践しつづけることとは、つまり、「生きるとはなんなのか」を問うのに等しいのではないか、と私は思っている。
(角田光代 著『あしたはアルプスを歩こう』より)
No.2442『木に「伝記」あり』
私の小学校の母校の樹は、イチョウで、文集の名前も「イチョウ」でした。もちろん、記念撮影もこの樹の下で撮るので、いつも小学校の思い出とともにこの樹があります。
だからなのか、イチョウと聞くと、つい興味を示しますが、イチョウに関する本も何冊か読みました。なかでもおもしろかったのは、『イチョウの自然誌と文化史』長田敏行著、『イチョウ奇跡の2億年史 生き残った最古の樹木の物語』ピーター・クレイン著、矢野 真千子訳です。
もちろん、小石川植物園の世界で初めて精子を発見したイチョウも見に行きましたし、中国四川省のイチョウや都江堰で大きなイチョウの盆栽を見てびっくりしたこともあります。
そういえば、イチョウの精子を見るのは大変だそうで、この本には「イチョウは雌雄異株で、雌のイチョウには「胚珠(若いギンナン)」があり、春、雄のイチョウが飛ばした「花粉」をこの胚珠で受け止める。しかし「受粉」したといっても、この段階ではまだ花粉のなかに精子は存在しない。「花粉」は約3ヵ月半、胚珠のなかで過ごし、胚珠自体の生長にともなって8月中頃に2個の精子となる。問もなく花粉管が破れて「繊毛」のついた精子が飛び出し、泳いで胚珠につくられた卵細胞に到着し受精が行われる。受精した卵は細胞分裂を続けて次の世代の子(胚)となる。精子の観察、確認が非常にむずかしいのは、この精子がつくられた後、飛び出して泳ぐ期間が極めて短いからだという。1本のイチョウではギンナンのなかで精子はほぼ一斉につくられ泳ぎ出す。1年でせいぜい3日くらいしか観察できないらしい。」と書いてあります。
ということは、たった数日しかないとすれば、ある意味、最初の発見は偶然だったのかもしれませんが、つねに気を付けて見ていたからこそ、発見できたともいえます。荻巣樹徳氏に氷河期の生き残りのイチョウを訪ねて中国に行った話しを聞き、私も見に行きたいと思いましたが、コロナウイルス感染症の拡大などで、その機会もなくなりました。
私は、毎年、喜多方市の会津新宮熊野神社(通称長床)の大イチョウを見に行きますが、拝殿の「長床」は、国指定重要文化財に選定され、44本の太い柱が印象的な建物です。その前に、樹齢800年以上といわれるご神木の大イチョウがあり、特に、秋の落葉のときには、黄色い絨毯のようになります。
また、今年の4月に下野三十三観音札所のお詣りをしたとき、足利市の鑁阿寺にまわりましたが、ここの境内で最も大きな樹がイチョウで、樹齢550年前後と推定されています。それぐらいでは、ランキングにすら載らないのですが、見るからに堂々としていました。やはり、イチョウには、ドラマがあります。
たとえば、あの鶴岡八幡宮のシンボルであったイチョウが、2010年3月10日の未明に突然倒れました。私はニュースで見ましたが、ほんとうにびっくりしました。原因は、2月以降の雨で地盤が緩んでいたこと、さらに前日の9日の夕方からの強風が原因とされましたが、あの土壌の薄い石段脇の斜面に立っていたことも影響したのではないかといいます。いずれにしても、「幹回り6.8m、高さ約30m、樹齢1,000年」といわれる大イチョウが突然倒れたことは間違いの無い事実です。
この本には、「全国どこの巨樹イチョウも風害、雪害、火災、落雷等なんらかの被害は被っている。他の樹種の巨樹に比べ満身創疾といってもいいほどだ。巨樹といわれるようなもので、まっとうな体を保っているイチョウなどめったにあるものではない。手入れの行き届きすぎた感さえある都会の街路樹のイチョウとは生き抜くうえでの年季の人り方が違う。」とあり、たしかに風格があるとさえ思います。
そこで、不幸にも倒れたり、枝折れしたりしたイチョウを、なんらかの形で新たな命を吹き込みたいということで、そのような枝などからイチョウの念珠をつくって売っていたという実例も紹介しています。これなどは、ご神木であれば、なおさら大切にしてもらえると思います。
下に抜き書きしたのは、第5章「14、15世紀のイチョウ」に書いてあったものです。
たしかに、巨木や巨樹は、誰の目にも強い印象として残りますが、実際にそれがどのような大きさで、どのような故事来歴を持っているのかなど、詳しく調べる人は少ないと思います。でも、そのような文字化されたものがなければ、後々の人はその全体像をつかむことはできません。
そういう意味では、この本はとても興味深いものです。著者も、「それにしても、今のところ近代以降で全国的に見てもこれほど詳細なデータと、それに近い頃の写真が備わっている例を私は知らない。似たものとして第2章で紹介した岩手県久慈長泉寺のイチョウの大正元(1912)年の調査がある。「久慈町小林区役人来視して本尺を明細に書記す」「42尺6寸」。ただこれとて菩提寺のような徹底した調査だったかどうか、今残る数字だけではとてもそこまで詳しいものだったとは思えない。」として、この菩提寺の詳細な調査は、構成の人たちにとってとても大切なことだとしています。
そうそう、今日から大人の休日倶楽部パスを利用して、津軽三十三観音霊場へ旅立ちます。何ヶ所お詣りできるかわかりませんが、青森県西津軽郡深浦町近くには、イチョウのランキング1位の「北金ケ沢のイチョウ」や「折曽のイチョウ」などもあり、今回はおそらく無理かもしれませんが、いずれ立ち寄りたいと思っています。
(2025.6.30)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 木に「伝記」あり | 瀬田勝哉 | 朝日新聞出版 | 2025年4月25日 | 9784022631398 |
|---|
☆ Extract passages ☆
立本のイチョウの確実な文字史料は、永徳元(1381)年、足利義満の造作中の花御所のために、摂関家近衛家のイチョウが召し上げられ移し替えられた記録だ。イチョウが人の目を引くには少なくと
も30年から50年程度は経っているだろうから、14世紀半ばには確実に摂関家の庭に植えられていたといえる。最高級貴族摂関家であることが特に重要だ。南北朝時代中頃には間違いなく日本の権力中
枢部にイチョウの立木はあったことになる。
(瀬田勝哉 著『木に「伝記」あり』より)
No.2441『花とハーブに囲まれたイギリスの物語』
表紙絵が花とイラストで描かれ、他の本とは違ったやさしさが感じられ、読もうと思いました。
だいぶ前から、たとえばルイス・キャロルの『不思議の国アリス』とかピーターラビットのはなしとかで、動物たちが話しをするのをどのようにして考えたのかと思っていました。すると、この本に、「『不思議の国のアリス』が出版される少し前に、イギリスではチャールズ・ダーウィンの『種の起源』が発表され、生物の進化や生存競争について注目され始めました。それに伴い、昆虫や草花を擬人化するという傾向も強まりました。アリやハチの世界を人間社会にたとえるのもその一例です。キャロルはダーウィンの学説に興味を持っていたといいます。実際、作品の中で擬人化された花々には少なからずダーウィンの影響が感じられるでしょう。鏡の国では花々が喋るだけでなく、オニユリが他の花を制圧し、権力をもっている点にも注目したいものです。」と書いてあり、そういえば2014年に初めてイギリスに行ったときにまわったロンドンの自然史博物館の2階へ上る踊り場のところに大理石に彫られたダーウィン像があったことを思い出しました。
やはり、今でも科学者の代表的な存在なので、相当な影響があったことは間違いなさそうです。そういえば、2014年7月に王立園芸協会が主催する「ハンプトン・コートパレス・フラワーショー」に行きましたが、まさに園芸大国だと痛感しました。植物を見せるだけでなく、園芸用品などもたくさん展示されていて、びっくりしたのは日本の盆栽のコーナーもありました。
そして、そのなかに子ども用の小さな園芸用具もあり、それがちゃちなおもちゃではなく、しっかりと実用に耐える造りになっていました。
また、アン・フィリパ・ピアスの『トムは真夜中の庭で』のなかに、「マッターホルン」、「見はらし」、「セント・ポール寺院の階段」、「油断大敵」といったあだ名のついたイチイの木が出てきます。この本には、「イギリス人にとってイチイは身近な木であると同時に、大事な木だとされています。それはイチイが、しばしば神秘化、神聖化されることからもうかがえるでしょう。イギリスには樹齢5000年を超えるイチイもあると言われています。」と書いてあります。
このイチイの大木のあるケンブリッジ郊外のフライさんのお宅に伺ったことがあり、その入口のところに植えてありました。しかも、そのお宅がイギリス伝統の民家で、かや葺き屋根の家です。フライさんによると、その居間にある天井の木は、この家が建てられたときのものだそうで、それだけ大事に使われてきたということです。その後で、食事につれて行ってもらったのですが、その途中に不動産屋さんがあり、その窓にいくつも物件が掲示されていたのですが、新しい豪華な家より、古民家のほうが数十倍も高いのにはびっくりしました。
戻ってから聞くと、このかや葺きの屋根も決まった職人がいて、2年後に修繕してもらうとのことでした。つまり、このような古民家を守り伝えていくにも、大変なようです。
話しは変わりますが、2017年9月にエジンバラ植物園に行く機会があり、そのときに聞いたのは、イングランドはバラ、スコットランドはアザミ、アイルランドは三つ葉のクローバー、そしてウェールズはラッパ水仙ということでした。でも、スコットランドがなぜアザミなのかはわかりませんでしたが、この本にその答えが書いてありました。
A・A・ミルの「プー横丁にたった家」のなかに、「物語ではトラーと呼ばれるトラがプーたちに食事を勧められ、アザミを口にする場面があります。しかし、イーヨー(ロバ)の好きなアザミをトラーは好まず。そのトグが嫌だと言います。ところで、スコットランドではアザミがその地域を象徴する花です。それはアザミが勝利のエピソードと結びついているためです。13世紀までスコットランドではヴァイキングの侵入に苦しんでいました。ところがある日、アザミのトゲを裸足で踏んでしまった敵の兵士が、その痛みから大声を上げてしまい、その結果、敵の侵入に気づいたスコット
ランド軍が勝利したというのです。それ以来、スコットランドではアザミがとても大事な植物になりました。アザミは食用としては、エキスやハーブティーにも使われ、体内浄化作用があると言われています。」とあり、なるほどと思いました。
この本には、そのほかにプラントハンターのこととかエディブルフラワーことなども書いてあり、画を見るだけでも楽しい本でした。
このような本を、孫にも読んで聞かせたいとは思いますが、すでに高校生にもなった孫では、おそらく鼻で笑ってしまいます。やはり、ものごとには、適切なときというものがあり、それをのがすとダメになるようです。
下に抜き書きしたのは、第2話「秘密の花園」に書いてあったものです。
たしかにイギリスはガーデニング大国で、私は2度ほどしか行ったことはないのですが、ほとんどが庭園を巡る旅だったので、イギリス人のガーデニングに対する思いみたいなものを感じました。それって、いつ頃から芽生えるのか気になっていましたが、この文章を見て、なるほどと思いました。
どんな国であっても、子どもの時の教育というのは大切です。むしろ、そのときから生き方さえも違ってくるのではないかとさえ思います。
(2025.6.28)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 花とハーブに囲まれたイギリスの物語 | 寺嶋さなえ | 彩流社 | 2025年3月20日 | 9784779130410 |
|---|
☆ Extract passages ☆
イギリスでは19世紀の中頃から子どもたちにガーデニングが推奨されました。戸外での活動が健康に良いばかりでなく、「労働は善」という考え方が子どもたちにとって大切だと思われたからです。子どもたちの小さな手でも摘めるキイチゴ、イチゴ、スグリ、野生のリンゴなどはジャムやゼリーとなり、クロイチゴゃニワトコの実からはパイや自家製ワインが作られました。またこの時代には印刷技術の発達により、色もきれいな子ども向けのガーデニングの本がたくさん出版されました。
(寺嶋さなえ 著『花とハーブに囲まれたイギリスの物語』より)
No.2440『ままならなぬ顔、もどかしい身体』
おもしろい題名の本だと思って手に取ると、副題が「痛みと向き合う13話」とあり、私もだいぶ腰痛などの痛みを経験してきたので、興味を持ちました。
すると、この本の元になったのは、東京大学出版会のPR誌『UP』に連載したのをまとめたもののようで、そのきっかけは著者自身のがんの闘病体験だったそうです。だから、出版社が東京大学出版会というのも納得です。
その第1話に、「がんは、長期の治療ゃ観察を要する病気です。手術や治療も大変ですが、病とのつき合い方を学ぶことが必要です。特に現役世代にとって、周囲との折り合いをどうつけるかは大きいことなのです。私の場合、手術と治療スケジュールは、仕事に支障が出ないように組みました。体力を使う仕事は抗がん剤治療日の直前に入れて、仕事を終えてそのまま治療に入りました。たとえば研究費の成果発表、遠方出張や一般向けの講演会など、ストレスのかかる大きな仕事をやった翌日に病院で静かにする。それは人生の休息のようなものでした。仕事を終えた達成感とハイな気分のまま、ベッドに横たわるのです。その後、病院から一歩出たら「普通の人」を演じていました。」とあり、やはり研究者としてのがんとの向き合い方で、とても参考になります。一般の患者は、どうしても怖さから眼を避けるようにしてしまいますが、それをしっかりと見据えて、研究も平行しておこなうその姿勢に驚きました。
著者は、視覚を中心とした知覚・認知の発達研究者です。だから、がんとの向き合い方も納得できることがたくさんあります。それとおもしろかったのは、喜怒哀楽などの表情を伝える働きについての話しです。第3話の「顔研究者の顔に麻痺が起きる」では、自分自身が帯状疱疹ウイルスにかかり、顔面神経麻痺になったそうです。まさにその専門家ですから、その経緯がとてもわかりやすく、具体的です。
そもそも表情というのは大切で、「顔面筋が麻痺した顔からは、表情がいかに大切かを知ることができます。表情は喜怒哀楽の感情を伝えるという欠かせない働きをしますが、表情の役割はこれにとどまりません。表情は生き生きとしたその人の印象を伝えます。おっとりと表情を作る人、ころころと表情が変わる人、そのふるまいから人柄に触れることができます。つまり、表情はその人の印象や魅力を決める力があるのです。逆に言うと、全く反応しない表情は、それだけで悪い印象となる恐れがあります。もう一つの役割は、自身のメンタルに関するものです。表情を作る筋肉の動きによって、表情を動かしている当人に感情を伝えるのです。こうして考えると、表情が消えた顔とは、灯された火が消えたようなものとも言えましょう。」と書いてあり、他人に対してばかりでなく、自分自身に対しても表情が伝えられないということは、大変なことだということがわかります。
よく、表情が少ない人には、どのように接して良いかさえもわからないときがあります。今、うれしいのか、あるいは悲しいのかもわからなければ、どのように接していいのかわかりません。これは大きな問題です。
そういえば、新型コロナウイルスの急速な感染拡大のとき、外出時にはマスクをするようにと政府からも広報があり、あまり役にも立たないマスクが配られたりしました。ところが、とくに欧米各国では、マスクをしない人が多かったと聞き、なぜだろうと思っていました。この本には、「欧米のマスクヘの忌避感には、根深い歴史があります。欧米では公共の場で顔を隠すことを禁じる「覆面禁止法(Anti-Mask Law)」があります。テロ防止のために1845年のニューヨークで施行されたのがアメリカ各州に広がり、21世紀になってヨーロッパの各国にも広がっています。そのため欧米諸国では、病院の外に出られない重病人ならば医療用のマスクの着用を許される、という雰囲気なのです。」と書いてありました。
さらに、「文化による顔の読み方の違いが関係しています。……欧米人は相手の口もとを見るのに対し、東アジア人は目もとに注目することがわかりました。」といいます。つまり、日本人などは口元をマスクで隠していたとしても、眼の表情で読み取れますが、欧米人は口持が隠されてしまうと、喜怒哀楽の表情がわからないことになります。つまり、相手がなにを考えているのか不安になりますから、嫌がるわけです。
これは実験でも、東アジア人は、生後7ヶ月というきわめて早い段階で眼の表情で相手をわかろうとすることから、不思議といえば不思議なことです。そういえば、今でもマスクをしているのは東アジア人ばかりのようです。
下に抜き書きしたのは、第13話「顔と身体を持つことによるもどかしさ、生きること」に書いてありました。
この後のところで、日本人と海外の人の美容整形の実態調査によると、海外では顔に関するものが4割で、体形に関するものが過半数を占めるのにたいして、日本人の場合は顔に関するものが9割を占めているのだそうです。たしかに、テレビのコマーシャルを見ていても、二重まぶたにするとか、鼻を高くするとか、そういうのが多いようです。
私は、時代が変わって、好みが変わってしまったらどうするのかと思ってしまいますが、それでも顔が変われば印象も変わるといいますから、それなりの需要はあるようです。
(2025.6.25)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| ままならなぬ顔、もどかしい身体 | 山口真美 | 東京大学出版会 | 2025年4月24日 | 9784130133197 |
|---|
☆ Extract passages ☆
この地球上に存在する人にとって、顔と身体を持つことは生きている証とも言えます。身体があることで、人は地球上を移動して配偶者と出会い、自身の子孫を残すことができます。多様な遺伝子の子孫を残すためには、遠くにいる配偶者を獲得する頑丈な身体が必要です。そして身体の一部である顔は、視覚・聴覚・嗅覚といった感覚受容器、栄養分を取りこむ口を備え、生きる上で欠かせない器官の集合体とも言えます。顔も身体も、存在理由をそれぞれ持つのです。
(山口真美 著『ままならなぬ顔、もどかしい身体』より)
No.2439『歩きながら考える』
著者の漫画はほとんど読んだことはないのですが、随筆はおもしろく、ときどき読みます。
表紙のところに肩書きとして、漫画家、文筆家、画家とあり、その表紙絵も歩きながら本を読んでいる姿でした。私も昔は歩きながらでも本を読むことがあったのですが、今は電車やバスのなかで読む程度です。
そういえば、画家になりたい著者をあきらめさせたいために、母は『フランダースの犬』を渡された、とこの本に書いてあります。たしかに貧しい少年ネロが、最後に大聖堂のルーベンスの祭壇画の前で愛犬パトラッシュと極寒のなか絶命してしまいます。母は、画家になるというのは大変なのよと伝えようとしてこの児童書を読ませたようですが、著者は、「しかし、物語を読み終えた私には、ネロをかわいそうだと思うことができませんでした。そこへ至るまでの彼の煮え切らない態度に何か納得のいかないものを覚えていたので、「ネロは勇気がなかったから、こんな目に遭ったんだ」と受け止めたのです。誰かが自分の絵を認めてくれるのを待っている姿には、謙虚さよりも「騎り」すら感じました。誰かの助けを当てになどせず、いざというときには知恵を狡猾に駆使すればいいだけのことだったのではないか、運河に停まっている船にでもこっそり乗り込んで、もっと暖かい地域に行っていれば、大まで道連れにして死ぬようなことはなかったのでは、と考えたものです。」と書いてあり、なるほど、著者らしいと思いました。
たしかに、今まで信じていたものを疑うということは、とても不安だしエネルギーも使います。だからといって、今まで信じて疑わなかったことだけにすがりついていたとしても、ときには命取りになることもあります。だから、メディアやSNSで流れてくる情報や人の話しだけだと、ときには大切なものを見失うこともあります。だとすれば、普段から自分で考え、自分で判断することをしなければならないと思います。まさに、思考することの訓練です。
この本は、2022年に書かれていますから、ある程度は新型コロナウイルス感染症に対する初期の恐怖感も薄れてきてはいますが、だからこそ、わかってきたこともあります。それは、「今回のパンデミックを通して、画期的なまでに認識させられたことは、「人間は生物的に地球から優遇されている特別な生き物ではない」ということです。例えば、ウイルスや細菌のパンデミックは、人間だけに起きるものではありません。ネズミやゴキブリにもパンデミックがあり、ネズミに関しては意味不明の大量死が発生して、その総数が激減するときがあるのだそうです。つまり、パンデミックは生物であれば起こり得るもので、今回は人間にそれがやって来たというわけです。」と書いてあり、たしかにそうだと思いました。
おそらく、新型コロナウイルス感染症のまん延で、生き方そのものを変えざるをえなかった人もいたでしょうが、5年も経つと、それ依然にもどってきたようにも感じます。
あれほど、不要不急の外出を自粛させられたり、どこへ行っても手洗いや消毒、さらにはマスクをしなければならない生活だったのに、また感染者が少し増えたといってもマスクをしない人もいます。とくに海外からインバウンドで来日される外国人はほとんどマスクをしないようです。やはり、そんなにいつまでも対応しているのは気苦労ですし、あるいは忘れたいのかもしれません。
私は男性なので意識もしなかったのですが、「イタリアに限らず、世界の多くの男性が妻に求めるのは、自分のダメなところを認め、どんなときも無条件に寄り添い、慰め、許してくれるかどうか、という点なのではないでしょうか。どこかで羽目を外すことがあっても最後には許してくれる。妻に求められるこうした精神的忍耐は母性的な寛大さとほぼ同質だと思われます。」とあり、なんか不意を突かれたような気分になりました。
でも、それはあるかもしれない、というのが本音です。
下に抜き書きしたのは、第5章「心を強くするために」に書いてあったものです。
私の場合の旅も、どちらかというと物見遊山というよりは、いろいろな人たちと出会い、多様なものと出会う機会でもあります。また、その地方の食べものだって楽しみですし、そこで作られた和菓子を食べることも楽しみのひとつです。だから、必ずお抹茶を点てる道具を持っていきます。
今月2日に、ここで茶筅供養をしましたが、茶道具で絶対にないとお茶を点てられないのは、茶筅です。それ以外はなんとか代用できますし、もちろん抹茶がなければ話しになりません。それだけさえあれば、どこでもお抹茶を楽しむことができます。茶筅の「筅」という字は、竹冠に先と書きますが、先にさんずいをつけると洗うという字になるように、これはもともと鍋などの焦げ付きを洗い落とす「筅(ささら)」に由来しています。ところが、奈良の生駒にある高山などでは、茶筅と鍋を洗うささらといっしょにされては困るということで、竹冠に完全の「全」という字を書いて、これは完全な作品であるという意味を込めて茶筌と書いています。
(2025.6.22)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 歩きながら考える(中公新書ラクレ) | ヤマザキマリ | 中央公論新社 | 2022年9月10日 | 9784121507730 |
|---|
☆ Extract passages ☆
私にとって、旅とは価値観の違いを学ぶ教育の場でした。幼い頃から読書を通じて世界中の倫理観や価値観の違いが気になっていたこともありますが、若いうちに国外に出たことによって、それぞれの国にはそれぞれの国独自の社会環境を守るためにでき上がった、様々なルールがあるということも明確に見えてきたのだと思います。
価値観の違いをこの目でリアルに学べたことは、人間として生きていく上で私の大きな糧になっていることは間違いありません。そういった自覚が、傍目には"芯の強さ"として見えているのかもしれません。
(ヤマザキマリ 著『歩きながら考える』より)
No.2438『徳川四百年の内緒話』
著者の徳川宗英氏は、田安徳川家第11代当主で、石川島重工業に入社後、1995年に石川島タンク建設副社長で退職されたそうです。1929(昭和4)年生まれですから、戦前戦後の厳しいときもあったでしょうが、会社勤めの経験もあり、庶民的な感覚を持っていたように思います。
それでも、徳川家に伝わる内緒話ですから、いろいろな意味で興味はあり、読むことにしました。版もだいぶ重ねているところをみると、同じような興味を持った方もいるようです。
よく時代劇などを見ると、お庭番という役が出てきますが、この多くが将軍直属の密偵であったそうです。そういえば、「水戸黄門」というテレビドラマに「風車の弥七」というのが出てきますが、忍者という設定だそうですが、呉服屋になったりいろいろと変装するので、次はどのような姿で現れるのか、それも楽しみのひとつです。この本では、「八代将軍吉宗は、江戸の人間はあまり信用できなかったらしく、将軍になったとき、205人の紀州の家臣をつれて江戸にやってきた。そのうちの十七家には、将軍直属の密偵であるお庭番の役を命じたのである。吉宗は、紀州にいるときも密偵をつかっていた。太っ腹なようで、けつこう細かいのが吉宗という人である。この密偵たちは《町廻横日》という名で、まさに城下の者が自分の命令を守っているか、横目でじろりと見張らせるという役目だった。江戸城の中奥の御休息の間というところのそばには、お駕籠台があった。遠出のさいは、ここで将軍が駕籠に乗るのだ。お庭番はここに呼び出され、直接、吉宗から命令をうけるようになった。このとき、彼らはホウキを片手に持って参上した。まさにお庭番のような恰好である。命令をうけると、彼らはまず、大伝馬町にあった呉服屋の「大丸」にむかい、その奥で着替えをした。そこには、虚無僧、猿回しなど、さまざまな職業の衣装が準備してあった。お庭番は変装を終えると、屋敷にはもどらず、そのまま任地へ赴いた。」とあり、まさに事実は小説より奇なりです。
また、将軍だからこそ狙われることもあり、だから隠密などを使うようになったのかもしれないが、この本によれば、不審な死をとげた将軍が4人もいるといいます。15代続いた将軍たちの四分の一も暗殺されたかもしれないと考えれば、おそらく気の休まるときがなかったのではないかと思います。
だから、第15代将軍慶喜は、「美賀子という正室のほかにお信とお幸というふたりの側室がいて、寝るときには正室といっしょではなく、側室の2人といつもYの字になって寝ていた。川の字で寝るとはよくいうが、Yの字は聞いたことがない。これは、暗殺者から身を守る手段だったらしい。夜中に暗殺者が忍びこんできたとき、真っ暗だとどれが誰の頭かわからない。しかも、Yの字だと、部屋の四方のどこから入ってきても、誰かにぶつかるから、気がつく可能性も高くなるのだそうだ。」と書いてあり、おちおちゆっくり寝てもいられないようです。さらに寝るときは真綿入りの羽二重蒲団二枚の上に寝たいたそうですが、その下には厚さ一尺にもなる藁蒲団を敷き、これは床下から刀を突きたてられても大丈夫なようにするためだったということです。
あの堅固なお城のなかにいてさえもそうですから、お忍びで城外に出るなどというのは、やはりドラマの世界だけの話しかもしれません。
下に抜き書きしたのは、第1章「やっぱり家康はエラかった」に書いてありました。
この話しは、別な本でも読んだことはあり、それは浜松城に逃げ帰ってすぐに絵師を呼び、自分の惨めな姿を描かせたということですが、この画像は徳川美術館に現在も所蔵されていて、ときどき展示もされているそうです。
しかも、徳川家康につながる著者が書いたとなれば、さらに信憑性は強まります。それでも、著者は、「この逸話も真実なのかどうかはわからないが、たしかに家康の生きかたにぴったり一致する話である。家康はこの敗戦をいくどとなく噛みしめ、うかつな戦さをせぬよう自らをいましめたことはまちがいない。」と結んでいます。
(2025.6.19)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 徳川四百年の内緒話(文春文庫) | 徳川宗英 | 文藝春秋 | 2004年8月10日 | 9784167679224 |
|---|
☆ Extract passages ☆
家康は馬のうえで、脱糞していた。天下をとった後でもこんなことをいわれたのだから、これはやはり事実だったのだろう。
家康は、敗走の途中も、よほどあわてていたらしい。
空腹のあまり、途中で茶店に入って、小豆餅を食べた。そこは小豆餅という地名になっている。しかも、小豆餅を食べたはいいが、あわてていて、代金を忘れて走り去ろうとした。すると、茶店のばあさんが怒って家康を追いかけ、代金を払わせた。そこは銭取という地名になって、いまも残っている。
(徳川宗英 著『徳川四百年の内緒話』より)
No.2437『それでも昭和なニッポン』
たしかに、私たちの年代は、昭和と聞くと、なんとなく懐かしく感じたり、そんなにも悪いイメージはないのですが、この本を読むと、旧弊のようにも感じられます。また、それ以上に、まだこんなようなことが平気で行われているのかとさえ思います。そういう意味でも、自分自身を振り返ってみるいい機会でした。
たとえば、GDPでアメリカに次いで世界第2位だったときがありましたが、今では中国やドイツに抜かれ、まもなくインドにも抜かれようとしています。でも、自分たちの生活は、それほとせ不自由は感じないし、世界とそれほど比較しなくてもいいではないかとさえ思います。でも、今回の米騒動をみていると、まだまだ昭和を引きづっているようです。農家の方に伺うと、人件費や農機具代、さらには農薬や肥料など、すべてが大幅に上がっています。それなのに、今までは低く抑えられていたのに、ちょっとばかり高くなったからといって、高過ぎるとマスコミなどでは毎日取り上げられます。じゃあ、いくらぐらいなら適正価格なのかといわれれば、だれも答えてくれません。
考えてみれば、それも昭和的な感じがします。この本の副題が「100年の呪縛が衰退を加速する」ですから、とても大切なことだと思います。
たまたま今年は2025年で、昭和に換算すると昭和100年になります。この本には、「こうした占い日本的システムの大半が賞味期限切れとなっているにも拘らず、既得権が優先されるなど、そのまま残され、本質的には、あまり変わっていない。それが原因で、日本は、先進諸国から取り残され、国のあちこちにガタが来ている。2025年は、「昭和100年」に当たる。同時に、明治維新から昭和20年の敗戦までの期間とほぼ同じ「戦後80年」の年でもある。日本という国は今、昭和のシステムという「呪縛」から抜け切れず、戦後の成功体験を支えた体制にも「金属疲労」が来ている。私たちの社会は、二重の意味で大きな転換点を迎えているのではないか。」と書いてありました。
これが「はじめに」に書いてあるところをみると、そのような危惧からこの本が書かれたような気がします。しかも、元日本経済新聞社の記者でもあり、つねに政治や経済などの第一線で取材していたので、その昭和という時代の良い面と悪い面の両方を知っていると思います。
具体的には、ぜひこの本を読んでもらえばと思いますが、実は、日本だけでなくアメリカもおなじようなサイクルで変化が起きているそうです。
アメリカの未来学者で政治学者のジョージ・フリードマン氏は、アメリカの歴史について、80年周期の制度的サイクルと50年周期の社会経済的サイクルの組み合わせで進んでいるという説を唱えているそうです。この本によると、「《アメリカ合衆国は戦闘のなかから生まれ、その制度は戦争によって築き上げられてきた。アメリカはおよそ80年ごとに、政治制度の仕組みを変える。憲法の大きな枠組みは保たれるものの、連邦と州の制度の相互関係は変わり、それぞれの機能自体も変わる。これまで、そのような変化が3度起きた》《独立戦争とその余波のなかから誕生した第1の(制度的)サイクルは、憲法が制定された1787年から1865年の南北戦争の終結と憲法修正まで続き、連邦政府が作られたが、政府と州との関係は不安定なままだった。第2の制度的サイクルは、州にたいする連邦政府の権限を確立したのち、1945年の第二次世界大戦終結まで続いた。同年に始まった第3の制度的サイクルは、州のみならず経済・社会全体にたいする連邦政府の権限を劇的に拡大していった。このパターンが同じように続けば、次の(第4の)制度的サイクルは2025年ごろから始まる》と書いています。
つまり、どこの国でも変革が起きなければ、政治も経済も社会も立ちゆかなくなるということのようです。アメリカの80年周期というのがあったとすれば、日本は2025年が昭和100年に当たるので、すでに20年も過ぎてしまったということになります。それで、いまだに旧態依然と変わらないとするならば、やはりどこかがおかしいということになります。
しかも、第4の制度的サイクルが始まるのは、2025年ごろからというのも意味深です。今、ほぼ毎日、アメリカのトランプ大統領の話題がニュースにならないときはありません。まさに、今までのアメリカをぶっ壊すかのような勢いです。それが将来のアメリカにとって益になることなら我慢もできるでしょうが、なぜかそうでもなさそうです。それでも、ロシアや中国などと違って民主的な選挙制度があるので、このまま進むということもないでしょうが、壊すだけ壊して後は知らないということでは困ります。
やはり、変革というのは、将来のためにという大きなビジョンが必要です。
下に抜き書きしたのは、第7章「職人魂+AIが道を拓く」の最後に書いてあったものです。
たしかに、今は円安だけではなく、食べものもおいしく、一番は安全だということがインバウンドにつながっているようです。私もコロナ禍前までは、人並みに海外に出かけていましたが、日本に帰ってくるとホッとしました。また、食べるものがおいしいと実感しました。コーヒーだって、日本で飲むと不味いのがありません。パンだって、クロワッサンもフランスパンも、日本のほうがおいしいです。
それより何より、たとえ知らずに間違って入ったとしても、とがめられることはあっても、身の危険を感じるようなことはありません。つまり、それだけ安全な国だということです。
ただ、これだって、この本にも書いてありましたが、「日本では、財布を落としても、ほとんど警察や駅などに届けられて、無事に返ってくることが多い――ネット上には、「戻ってくるなんで思わなかった。こんなことは我が国では考えられない」といった外国人観光客らの感激、称賛の声があふれている。」とはいうものの、これからは違ってくるかもしれません。
だとすれば、毎日のようにネット詐欺や無差別殺人などがニュースになる時代ですから、そろそろ過度な安全神話から抜け出さなければならないようです。
(2025.6.16)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| それでも昭和なニッポン(日経プレミアシリーズ) | 大橋牧人 | 日本経済新聞出版 | 2024年9月9日 | 9784296120697 |
|---|
☆ Extract passages ☆
地球儀を回してみると、北半球のインドから東、大平洋までの地域で、政治的な自由が欧米なみにある国は、日本くらいだ。日本を訪れている中国人観光客の表情が生き生きしている理由は、美味しいものが安く食べられ、電気釜やサプリメントが買えることだけではない。
日本では、何をしゃべっても自由で、たとえ政府の批判をしたとしても、官憲に咎められることもない。この事実は、実は竜要なメリットだ。実際に日本へ来てみれば、安定した社会や穏やかな国民性なども自然に伝わるだろう。
こうしたアドバンテージは、今や数少ない日本の手持ちカードだ。これは、大事にしていかなければならない。その効力が消えないうちに、昭和型や高度成長期流の時代遅れになっている法制度や経営スタイル、習慣をどれだけ早く終わらせられるかに、この国の将来が懸かっている気がしてならない。
(大橋牧人 著『それでも昭和なニッポン』より)
No.2436『集団はなぜ残酷にまた慈悲深くなるのか』
ちょっとドキッとしながら立ち読みすると、副題が「理不尽な服従と自発的人助けの心理学」で、ちょっとは興味を持ちました。
でも、集団はなぜ残酷になるのかというので思い出したのは、やはり第2次世界大戦でアウシュヴィッツ強制収容所に収監されたフランクルの『夜と霧』です。まさに、同じ人間なのに、あれほどに残酷になれると思うと、人間不信にでもなりそうです。ただ、その中でさえも、仲間を助けたり、親衛隊の中にも収容者に私費で町の薬局から高価な薬を購入して渡すこともあったと知り、人間とは不思議な存在だと思いました。その両極端になぜブレるのだろうか、それを知りたいと思い、読み続けました。
それにしても、人というのは、いろいろな環境や状況次第で、善にも悪にもなりうるというのは、思い出すのはこの本の「あとがき」にも載せてありましたが、菊池寛の『恩讐の彼方に』を読んだときも感じました。それが集団となれば、なおさら強まることは考えられます。
では、なぜ、人は集団を作ろうとするのか、その集団に属しようとするのか、をこの本では次のように指摘しています。「第1の理由は集団がメンバーの力や知恵を結合し、それが個人の生存にとって役に立つからである。個々の人間は非力であり、集団に所属することによって環境に適応している。大きな建造物の建設や国家などの巨大組織の運営は個人の力の及ばないところである。第2は愛情や親密さを求める欲求を満たしてくれることである。特に家族や友人との情緒的関係、サポート関係は大事である。これが欠けると生きていくうえでのウェルビーイングが損なわれる。……第3は自分や世界を理解するための枠組みを与えてくれることである。自分の能力や学力、体力は、集団の中の自分と似たような他者と比較してわかるものである。……第4は、アイデンティティ確立に貢献することである。人は個人としてのアイデンティティと社会的アイデンティティの両方を持っている。」と書いてあり、やはり、人は1人では生きられないのです。
このことは、下に抜き書きしたこととも関連がありますが、人は集団のなかにこそ安心ややすらぎがあるともいえます。
でも、この本の題名でもある『集団はなぜ残酷にまた慈悲深くなるのか』ということを考えると、その具体的な例として、9.11同時多発テロのときの世界貿易センタービルからの避難や、ガルーダ・インドネシア航空機福岡空港離陸失敗事故などを取り上げています。
9.11同時多発テロの避難のときには、お互いに協力し助け合ったことが報告されているとして、「以上の研究から、人間は危機のときに協力し、互いに助け合う傾向があることがわかった。別の研究も、貿易センター内では圧倒的多数の人々が、パニックになったり、利己的な行動をとったりしなかったことを明らかにしている。危機の渦中にいると知りながらも、人々は冷静で協力的な行動をとったということである。人々は、密集した階段の吹き抜けを整然と下り、消防士を上がらせるため通路を空け、気を失いそうになっている人や怪我人を助けることも行った。理性を失いそうになった人も、集団の冷静な行動で落ち着きを取り戻したとの報告もある。中には、ビルの中に残ってドアを開けたり、交通整理をしたりする人もいたらしい。」と書いてあり、まさに人は博愛的な行動をしていたことがわかります。
たしかに、集団でなぜこんなにも残酷なことができるのか、目を覆いたくなるようなこともたくさん報告されていますが、それでも、このような慈悲深いことがあったということを知ると、ホッとします。
だからこそ、いくら緊急事態が起きたとしても、人間としての理性だけは失いたくないと痛切に思いました。
下に抜き書きしたのは、第7章「航空機事故発生時の機内で人々はどのように行動したのか」の最後に書いてあったものです。
その機内での詳細な人々の行動や音声なども掲載されていて、その切羽詰まった人たちの緊張感も伝わってきます。しかし、乗客のほとんどが団体旅行客であったこともあり、会社や知人同士のつながりもあり、利己的な行動が抑制されたり、リーダーシップも発揮しやすかったりしたのではないかといいます。
しかし、この本では、もし面識がない人たちの緊急事態においてもそれなりの行動をするということを、実験で明らかにしています。
それでも、下に抜き書きしたように、そのときに身近な人たちがいるということの大切さを感じてもらうためにも、少し長いのですが引用させてもらいました。
(2025.6.13)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 集団はなぜ残酷にまた慈悲深くなるのか(中公新書) | 釘原直樹 | 中央公論新社 | 2025年4月25日 | 9784121028518 |
|---|
☆ Extract passages ☆
アメリカで行われた第2次世界大戦中の士気調査によれば、多くの兵七が他の部隊に配属されることをいやがった。というのは自分の部隊が安全だと感じていたからである。また海に投げ出されているといぅ極限状況でも戦友と一緒であれば冷静であった。それから兵士と将校の絆は戦闘直前や戦闘中に強くなり、互いに強い愛着感情を持つようになるということであった。また戦場では兵上は戦友と離れるより、死ぬ可能性が高いとわかっていても、戦友と運命をともにする傾向があった。
また天寿を全うした人の中に、死の間際に、亡くなった親が訪ねてきたと言う人が何人もおり、そういう人は皆安らかな死を迎えたという報告もある。これを「お迎え」と呼び、介護関係者の7割が経験しているということである。
結局、生死の境においても、親しい人と一緒だったり、親しい環境に置かれていたりすれば恐怖は感じるが理性を失うことはなく、パニックにはほとんどならないといえる。
(釘原直樹 著『集団はなぜ残酷にまた慈悲深くなるのか』より)
No.2435『「不」自由でなにがわるい』
本の題名だけをみると、ちょっと突っ張っているような感じですが、副題は「障がいあっても みんな同じ」で、なるほどと思います。
もちろん、同じとはいっても、それなりの違いはあると思いますが、なるべくなら同じに持って行くのが大切です。そのような気持ちで読み始めました。
この本は、医療福祉ライターの今村美都さんと、友人の山下智子さん、この本のなかではいつも呼んでいる「ともっちさん」と名前で登場しますが、彼女は生まれたときから脳性まひという障がいがあります。しかも、24時間365日、介助者を必要とする重度の障がい者です。そのともっちさんに本を書いてほしいと言われたのが、きっかけで生まれたものです。
著者自身も生まれたときからいっしょに暮らしている脳性まひの伯母さんがいますが、常にいっしょだったこともあり、ちょっと変わっているなぁとは感じていたそうですが、障がい者だとは思ってなかったそうです。だから、「障がい者と言われればなるほどと納得しますが、障がい者である前に伯母は伯母です。そんなふうに思えるのは、きっと赤ちゃんの頃から当たり前にそばにいる存在だったからでしょう。だから、子どもの頃から一緒にいたほうがいいというともっちさんの考えは、とてもよく理解できます。偏見という色眼鏡をかける前に、その人自身を知ることができれば、差別をなくすきっかけになる。大人になるにしたがって、わたしたちはいろいろな色眼鏡を知らず知らずのうちにかけていることがあります。重なりすぎた色眼鏡で、大切なことが見えなくなっていることも。ともっちさんは、相手から色眼鏡をサッと取り外して、にやり。色眼鏡をかけない世界を一緒に見ようとします。なんなら、どうせかけるのならと、世界のカラフルさをありのままに楽しめる、世界がもっと愉快に見えてくるような眼鏡を一緒に創り出そうとすらするのです。」と書いてます。
たしかに、今の教育も、障がい者と健常者とをなるべく分けないようにしようとしているように見えます。もちろん、はっきりと分けて欲しいという意見もあるでしょうが、それだってケースバイムースです。
いっしょに生活したり勉強したりすれば、相手に対する優しさも違ってきます。それもたいへん大事なことです。
そういう意味でも、ご自身が脳性まひの小児科医である熊谷晋一郎先生の言葉に、「自立とは、選択肢がたくさんあること、依存先がたくさんあること」だと言っているそうです。
つまり、近くにいる大人だけが依存先というより、もっと広く多くの人たちとつながっていることが自立するには大切だということです。だから、ともっちさんが自立できたのも、たくさんのつながりがあったからで、それが彼女の強みでもあります。
下に抜き書きしたのは、第4章「自立生活を始めてから 重度の障害があっても一人暮らしはできる」のなかに書いてあったものです。
これは健常者でも同じで、何かを実現しようとすれば、先ず行動することが必要です。いつまでも考えていたとしても、実現できません。そういう意味では、とても参考になると思います。
また、健常者でもなかなかできないようなことにも、諦めないで食らいついていく姿勢は、読んでいてもすごいと思います。24時間365日、介助者を必要とする重度の障がい者だからこそ、自分で介護事業所を立ち上げるというのは、その発想もすごいし、それを実現させるのですからもっともっとすごいことです。
もう、なんでもできないことはない、と考えているのではないかとさえ思いました。
(2025.6.10)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 「不」自由でなにがわるい | 今村美都 | 新日本出版社 | 2025年2月20日 | 9784406068703 |
|---|
☆ Extract passages ☆
なにか叶えたいことがあるとき、まずはやってみる。エラーが続くときは、違うアプローチをしてみる。それでもエラーが続くなら、ゴールに近づくためのアクションはなにか分析してみる。今度は、それをやってみる。ともっちさんは、トライ&エラーのサイクルが速いのです。そしてあきらめない。だから、最後には最適解を探し当てます。
かかりつけの病院のある板橋区で5年間生活したのち、2軒日で念願のヴェルディの練習場とスタジアムに通いやすい場所へと引っ越しが叶いました。
(今村美都 著『「不」自由でなにがわるい』より)
No.2434『信頼と不信の哲学入門』
最近のメディアをみると、信頼していいのか、信頼できないのか、その判断が難しくなっているような気がします。前回のNo.2433『持続可能なメディア』を読んでいても、そう感じます。
まさに、現在は何を信じていいのか、信じられないのかが混沌と入り交じっているようです。だからこそ、この『信頼と不信の哲学入門』という本が出てくるのかもしれません。
しかし、信頼とか不信というのは、とても大切で大事なものだとは思いますが、なかなかつかみ所のないものでもあります。監訳者は、解説のところで、「信頼は現代社会の基盤であるが、他方で不信もまた現代社会の問題点を改善するために必要となる。にもかかわらず、信頼や不信は空気のようなもの、いわば透明な存在であり、それゆえに、思考の対象となることは難しかった。しかし、そういった空気のような、当たり前のように思われていることを問うのが哲学である。本書は信頼と不信を哲学的観点から考察するもので、登場する具体例も多様である。つまり、本書はたいへん読みやすく、しかも哲学的議論の精度は一定水準を維持しているという信頼・不信の哲学に関する優れた入門書である。」と書いています。先に種明かしをしたみたいで恐縮ですが、たしかにその通りだと思います。
読んでいても、なかなか理解しにくいところもあり、何度も読み返したりと、時間はかかりました。それでも、わからないところが読み進めることで、後から理解できたところもあります。
これこそ、読書の良さであり、楽しみでもあります。テレビなどは、理解できてもできなくても、勝手に進んでしまいます。なんども振り返ることはしません。最後は、時間が多少かかったとしても、ゆっくりと精読することも大切だと思いました。
たとえば、信頼することのメリットや不信のデメリットなどは、「人々から信頼されると人生はなめらかに進む。適切な信用(credit)の格付けがなされていれば懲罰的な利息を支払うことなくお金を借りることができ、公正な取引に関する評判は中小企業の振興に貢献し、それらしい立ち振る舞いは法廷で自己弁護しなければならない場合に大いに役立つ。他方、不信を抱かれるとこのようなメリットは受けられず、不信そのものに起因する問題ももたらされる。有罪判決を受けた犯罪者は就職に苦労し、不信を抱かれたごろつきの妻は他の人々と友人関係を維持することができず、会話すらままならない。警察に不信を抱かれた地域や人種の若者は、路上で何度も乱暴な「職務質問」を受けることになる。」と書いてあり、このような具体的な内容なら、たやすく理解できます。
しかし、それが個人ではなく地域とか仕事とか、さらには国家とか多くの人たちが集まってくると問題も複雑化します。また、最近のインターネットなどの問題はさらに難しくなっています。
たとえば、ウィキペディアなども、本当に信頼できる内容なのかと考えるときもあります。自分がある程度知っている内容なら、それなりの判断ができますが、まったく知らないことだったら、判断すらできません。だからといって、そのまま信じることもできないから、やはり本を読むか、知っている人に直接聞くしかありません。
だとしたら、「信頼されることは、追求する意味のあるあらゆる種類の前提条件であり、他の人があなたの言うことを信頼しなかったり、あなたがコミットメントをやり遂げることを信頼しなかったりする状況では、多くのやりがいを得ることは難しい。信頼性のおかげで、あなたは他の人から信頼されるに値するようになり、それを効果的に示すことができれば、信頼は後からついてくる。」ということになります。
この「信頼は後からついてくる」というのは、たしかにそうです。最初から信頼されることなど、ほとんどありません。
ということは、「信頼は、信頼される側が信頼に値することを直接示すことができない状況において最も価値があり、最も危険なものとなりうる。わたしが自分の誠実さをあなたに直接証明できるのは、わたしの証言を裏付ける独立した情報源をあなたがもつ場合だけだ。」というのも納得できます。
下に抜き書きしたのは、第3章「信頼と協力の進化」に書いてありました。
これを読むと、地球温暖化や紛争の解決なども、このようなしっぺ返し戦略が必要ではないかと思えてきます。大国だけがごり押しをしてもいいとなると、この世界はますます混沌として先が見えなくなりそうです。
そういう意味でも、お互いに信頼しあい協力する関係が構築されなければならないと思います。そのためにも、しっぺ返しなどを考えなくてもいい社会が理想です。
ときには、なかなか難しい問題ではありますが、このような哲学入門書も読んでもらいたいと思いました。
(2025.6.7)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 信頼と不信の哲学(岩波新書) | キャサリン・ホーリー 著、稲岡大志・杉本俊介 監訳 | 岩波書店 | 2024年12月20日 | 9784004320449 |
|---|
☆ Extract passages ☆
現代社会では、わたしたちが集団で行うプロジェクトの多くは、決して出会うことのない人同士を結びつける――たとえば、気候変動と闘うこと、水産資源を守ること、安全な路上環境を維持することなどのプロジエクトがそうだ。警察や法制度、政府を通じて実現されている国家の装置は、しっぺ返し戦略によって適切な条件を生み出すために欠かすことができない。なぜなら、個人としてのわたしたちが、こうした大きな事業に協力しない者を同定したりペナルティを与えたりできることは、めったにないからだ(そしてこれは実務上の問題だけではない。法制度の外にある略式の私人裁判を避けることにはとても十分な理由がある)。実際、これらのプロジェクトで取り組まれている問題の多くは、国境を越え、大規模な困難を生み出す。わたしたちの不正検出モジュールができることはここまでである。
(キャサリン・ホーリー 著『信頼と不信の哲学入門』より)
No.2433『持続可能なメディア』
今年に入ってから、いろいろとメディアに関する問題が噴出していて、これは相当な期間をかけて解きほぐしていかないと難しいかな、と思っていたら、案の定まだまだその方向性が見えてきません。そんなとき、この本を見つけました。読んで見ると、まさに今のインターネット時代の問題を含め、避けては通れないことだと痛感しました。
そういえば、劇的に変わったのはコロナ禍からで、不要不急の外出はしないとか人との接触はなるべく避けるということで、学校も会社もネットを使えるものはそれですませるようになりました。この本でも、イギリスのエコノミスト誌の話しが載っていましたが、「英エコノミスト誌は、コロナ禍の2021年も定期購読の契約者数を103万人から112万人に増やしている。面白かったのは、コロナ禍によって変わつた働き方の良い点、悪い点を学生が聞いた時だった。かつてひとつの部屋にギュウギュウ詰めになって、それこそ床に座るものもいた月曜日の会議は、今はZoomになった。木曜日から金曜日の朝にかけて、ひとつの部屋でゲラを回し読みして最終チェックをしていたのも、デジタル上で家からやるようになった。金曜日の未明に、タクシーで家に帰る必要もない。これは良い点、しかし、失われたものもあるとダニエルは言う。「オフィスにいた時代は、予期せぬ出会いによって新鮮なアイデアがスパークのように閃くことがあった。そうした予期せぬ出会いというのがなくなった」と英エコノミスト誌のエグゼクティブ・デイレクターのダニエル・フランクリンは話したそうです。
これはどんなところでもあり、どちらも一長一短かもしれませんが、コロナ禍という非常事態においてだからこそ推進されたような気がします。
以前から、リモートでできることはそうすればいいとは言いながら、できなかったのです。しかしコロナ禍でやってみたら、これもありかな、と思う人もたくさんいたと思います。ただ、人と直接に会わないとできないこともありますから、是々非々ということです。
ただ、SNSなどのニュースは、確実なものばかりではなく、いかにもヘイクと思われるものも混じっています。また、どこのニュースサイトを開いても、似たようなものしか出てきません。
タダで、いつでも見れるからいいというものではなく、正確なことを知りたいという場合には、確実な署名記事が一番です。しかし、これはタダでは無理です。
この本には、有料課金の話しが載っていて、「英エコノミスト誌を発行しているエコノミスト・グループの2017年のアニュアルレポートにはこんな文言がある。〈グーグルとフェイスブックが世界のデジタル広告の6割をとっている。アメリカ市場に関してみれば、ここ数年は新規のデジタル広告費の99パーセントはこの2社にいく〉だから、英エコノミストは、グーグルやフェイスブック、ヤフーなどのプラットフォーマーに記事は出さず、1カ月からの定期購読しか提供していない。」そうです。
やはり、そうでもしないと、それなりの記事を集めて、編集して、発行するとなれば、当然コストはかかります。しかし、その記事がグーグルやフェイスブックでも読めるならば、誰もお金を出してまで読もうとはしません。そこが悩ましいところです。
しかも、最近では生成AIなどが勝手に情報などを収集してしまうことも大きな問題です。また、グーグルの検索を使うと、一番上に「AI による概要」が出てくるので、その下の検索まで使わない場合も増えてきています。それもまた、問題ではないかと思います。
どちらにしても、現在、アメリカなどでグーグルやフェイスブックが巨大になりすぎたということで独占禁止法訴訟を起こす準備をしていると報じられています。これから、どのように進んでいくか、まだまだわかりません。
下に抜き書きしたのは、第2章「繁栄する国内の雑誌メディアを探す」にあったものです。
最近もフジテレビの役員が「おもしろければいい」から脱却しなければならないと言いましたが、たしかにそうです。私は、そもそもテレビをあまり見ないのですが、若い時にテレビを見てどれぐらい覚えているかという実験をしたのです。ところが数週間経つと、ほとんど覚えていないのです。連ドラだって、1~2回見ないでしまうと、見たいという気さえ起こらないのです。
ところが、本だと何週間経っても覚えてるし、カードを作ったものはほとんど忘れないのです。それで、テレビより本をということになり、今も続いています。
だって、同じ時間を使うなら、有意義に使いたいと思うのが人情です。
(2025.6.3)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 持続可能なメディア(朝日新書) | 下山 進 | 朝日新聞出版 | 2025年3月30日 | 9784022953063 |
|---|
☆ Extract passages ☆
当時は、ネットフリックスもアマゾンTVもなかった。人々が娯楽を得ようとすれば、日本の新聞社の系列であるテレビ局の番組からしか得ようがなかったのだ。新聞社と系列のテレビ局、そしてそれにスターを手配している芸能事務所、これらが握ってしまえば、数えきれないほどの未成年への性的虐待も「なかった」ことにしてしまえたということだ。
それが人々の情報をえる手段が地上波からネットにかわっていったことによって、この鉄のトライアングルが崩れた。たとえば、BTSのようにグローバルに活躍しようと思えば、ハーベイ・ワインスタインよりひどい性的虐待者が経営をする事務所からでは難しい。
企業もそのような事務所のスターが登場する番組にお金を払うことはできない。これがこの20年の間に進んだ構造変化だ。
(下山 進 著『持続可能なメディア』より)
No.2432『さよならは 小さな声で』
これは「松浦弥太郎エッセイ集」の1冊で、ところどころに写真が載っていて、とても読みやすく工夫されています。
その写真も、なんとなくこのエッセイに合わせたような雰囲気のあるもので、書いてある内容を補足するようです。私も写真は好きなので、読んでは見て、また見ては読むの繰り返しでした。
そういえば、旅先でなるべく同じ店に行くと書いてあり、カフェやデリカテッセンで朝食をとるそうで、『なぜ同じ店に行き続けるのかというと、1週間の滞在で毎日そこに通っていれば、余程のことがない限り、知り合いができるからだ。少なくとも店で働く人とは言葉を交すようになる。「あなた、どこから来たの?」と、2日目あたりから自然と向こうから話しかけてくる。毎朝「おはよう。今日は元気?」と、自分からも声をかけ続けていれば、顔はすぐに覚えてもらえる。入り口ですれ違った人や、隣に座った人、とにかく目が合ったら笑顔であいさつをする。そんなふうにひとつの店に通っていれば、知りたい街のあれこれは苦労なく知ることができる。インターネットなどより、余程簡単に面白いことが知れる。どんな旅にも、勇気を出してどんなことでも人に声をかけることで開く魔法の扉があり、そんな心持ちで過ごせば、ただの旅が一冊の本のような物語になっていく。』と書いています。
たしかに、何度か通ううちに親しみが増し、挨拶するようにもなります。私もイギリスのエジンバラに行ったときに、ホテルの近くにとてもおいしいパン屋さんがあり、窓際にテーブルもありました。パンにいろいろなものをはさんでもくれるので、そこでコーヒーを頼み、朝食にしました。しかも焼きたてのパンだと、それだけでもおいしいのです。
そこでここに3日間通いましたが、お店の人も挨拶をしてくれるようになり、どこへ行くのかなどと話しにもなりました。このような経験をしたので、日本でもホテルに泊まったときには朝早くから開くパン屋さんを探し、出来たてのクロワッサンやはちみつバターパンなどを買ってきて、部屋でコーヒーを淹れてのんばりと朝食をとるのが通例になっています。もちろん、それだけでは味気ないので、前日にフルーツなどを買い、それも食べますが、出来たてのパンはちょっとばかり遠くても外さないようにしています。
この本に出てくる人たちは、女性が多いのですが、知人の画家の女性の話に、「たとえば、顔は化粧で隠せるけれど、手や指の老いは隠しようがないわ。そんな自分を認めてあげるってこと」はとても大切なことだと言い、著者は、「なるほど。老いというものは、どうしたって止めることはできないし、隠すこともできない。それならば、まずは老いていく自分を受け入れるということだ」と解釈します。
その画家の女性は、さらに、「避けられないことってたくさんあるでしょ。でも、人間って不思議なもので、避けられないことについては耐えられるようになっているものよ。だから逃げる必要はないの。逃げれば逃げるほどに追いかけてくるってこともほんとうよ」と話します。
たしかに、この世の中には、「いくら避けようとしても、決して避けられないことがあるのよ」ということは間違いのないことだし、たとえば老いを化粧で隠したり、サプリメントに頼ったりすると、逆に老いが目立つ場合もあります。
だから、老いを隠そうとするよりは、気持ちだけでも若くいたいと考えることのほうが私は大切だと思います。要は気持ち次第です。
下に抜き書きしたのは、第1章「すてきなあのひと」のなかの「あいさつ上手」に書いてあったものです。
とくに海外などでは、言葉の問題もあり、なかなか挨拶もできないときもありますが、私はどこへ行く時でも、その国の挨拶の仕方と「ありがとう」ぐらいは覚えています。
また、日本でも挨拶のタイミングとか、ときどき戸惑うこともありますが、ここに書いてあるように、「あいさつは自分を守るよろい」でもありますから、常に心がけることは大切だと思っています。
(2025.5.31)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| さよならは 小さな声で | 松浦弥太郎 | 清流出版 | 2013年6月27日 | 9784860294038 |
|---|
☆ Extract passages ☆
人と人とのつながりの目的は、自分たちの安全のためである。自分が決して害を与える存在でないことを知ってもらうために自己紹介し、同時に相手のことも知る。常にあいさつを交わし、互いに知り合うことで安心を得るのである。「あいさつは自分を守るよろい」という教えがあるが、まさにその通りである。
安心したければ、あいさつをする。他人に自分を受け入れてもらいたければ、まずはあいさつをする。あいさつは他人への思いやりでもある。思いやりを伝えるためには心から言葉をかけること。思いやりとは感謝から生まれ、感謝とは尊敬によって生まれる。なにより大切なのはいつどんな時でも他人を尊敬する気持ちを失わないことである。
(松浦弥太郎 著『さよならは 小さな声で』より)
No.2431『雨だれの標本』
著者は、2004年、「紅雲町のお草」でオール讀物推理小説新人賞を受賞したそうで、この紅雲町にある珈琲屋をシリーズ化していて、この『雨だれの標本』も「紅雲町珈琲屋こよみ」のシリーズです。
私は、この本の装丁がきれいで、そろそろアジサイが咲く時期なので、その図柄にも惹かれました。
小説というのは、なかなか評論が難しく、さらに抜書きなどしてしまうと、「ネタばらし」になってしまうこともあり、この『本のたび』でもほとんど扱わないことにしています。
でも、珈琲は好きだし、お草さんはコーヒー豆だけでなく、和食器のお店もしているとわかり、ついつい読んでしまいました。そういえば、4月に下野三十三観音札所詣りに行ったときに鑁阿寺だけでなく、その「ばんな寺正面通り」を歩きました。そこには、和菓子屋さんや小間物屋さん、古い道具を扱うお店などもあり、楽しく見てまわりました。
そのなかに、「蘭と月」という香と古道具を扱うお店があり、棚に並べられた古い朱塗りの皿や碗がたくさんありました。自分で組み合わせて選べるということで、菓子器にできそうな皿を1つだけ買ってきましたが、そういう小物が好きなので、そこに親近感をいだいたようです。
小説の中に出てくるお店は、「小蔵屋」というのですが、登場人物が風変わりな人たちが多く、高名な映画監督の新作の撮影候補地になったことから話しが進められていきます。だから、具体的にとのような商品があるのかさえわかりませんが、和食器が多いようです。
今の時代に即して考えてみると、「かつて日本は不況の中で、戦争の特需景気に沸き、軍部を支持、その末に先の大戦で国を焦土にし、必ず誰かの家族や友人だったはずの多くの命を犠牲にした。国民である以上、知らぬ存ぜぬは通らない。年数ミリの地盤沈下のような変化に、気づかないで、あるいは気づかないふりをし続けて沈黙を守るなら、望んだも同じだ。草は今でも苦くそう思う。」と書いています。
たしかに、今もロシアはウクライナに侵攻し、さらに世界のどこかで紛争が起きています。テレビなどで大きなビルや一般の家などが次々と爆破される映像を見ていると、なぜこんな醜い争いを続けるのか判断に苦しみます。
下に抜き書きしたのは、その映画監督に多大な影響を与えた古い映像作品をつくった無名な男をさがしてほしいとお願いされますが、やっとさがしたのにその男は監督に会う気持ちはないといい、下のような言葉を伝えてほしいといいます。
たしかに、考えてみれば、影響をあたえたかもしれないけれど、それを受け取った人こそが育んだ物語でもあります。たとえば、名言だとしても、それを読んだり聞いたりした人がそれをどのように感じるかの問題です。
この『本のたび』だって、私自身がこのように感じたということだけで、他の人が読めば、まったく違うように感じるかもしれないわけです。もちろん、正解などありませんし、だからこそ本のおもしろさがあると私は思っています。
ですから、この本も、ぜひ読んでみて、いろいろ感じることが大切だと思います。
(2025.5.29)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 雨だれの標本 | 吉永南央 | 文藝春秋 | 2023年10月10日 | 9784163917597 |
|---|
☆ Extract passages ☆
あなたを変えたのは、私でも、私の作品でもない。あなた自身が育んだ物語だ。
(吉永南央 著『雨だれの標本』より)
No.2430『清掃はおもてなし』
この本の著者のことを、2015年に放映されたNHK『プロフェッショナル 仕事の流儀』を、偶然に見ていて、清掃管理業務も大変だがやり甲斐のある仕事だと思いました。
それが記憶のなかに残っていて、たまたま図書館にあったのを借りてきて読みました。
副題は「9年連続世界一の羽田空港の清掃を支える 職人の働き方と考え方」で、さらに「モノを思う心」で丁寧な仕事をし、「人を想う日浩」でお客様から言葉が返ってくる、とも書いてあります。たしかに清掃はとても大切なことですし、おもてなしにつながります。ただ「人を思う心」って何かと思いながら読んでいると、「終章 思う心」のなかに書いてありました。
それは、「「思う心」を具体的に表すと、次の3つになるでしょうか。①自分にやさしくする ②観察をする ③敬意を払う
自分にやさしくすることで、「心」に余裕がうまれます。「心」に余裕がうまれたら、相手(人・物・自分など)を観察します。相手をよく観察することで「思う」ことができる。そして、思ったことを実現するにはどうすればいいかと考える。方法や手順が見つかったら行動に移しますが、その時に必要なのは敬意を払うこと。相手を大切に思い、さらに考えながら行動します。この一連の流れが「思う心」です。」といいます。
言葉そのものは簡単ですが、これを実行することはなかなか大変です。でも、著者は自分が清掃という仕事をしっかりと身につけ、考えたからこそ生まれた言葉だと思います。
おそらく、新しいことを始めるには、よく物怖じしないこととか、失敗を恐れずに堂々と挑戦するとかいいますが、著者が中国残留孤児二世だということもいい意味で影響しているのではないかと思います。著者自身が、「私は子どもの頃から、人に迷惑をかけないように、自分で生活していけるように、と親に育てられてきました。自分の力で生きていくため、手に職をつけること、働いて稼げるようになることが必要だと学びました。中国にいる時、仕事上で男女で差を感じた経験もありませんでした。」と語っています。
日本の国技である相撲の世界でも、外国から来て、死にものぐるいで稽古に励み、番付を駆け上る力士が話題になります。とくに、日本人に欠けているハングリー精神が発揮されているように思います。そういう意味からも、清掃という仕事に真正面から取り組んできた姿に共感するところがたくさんあります。
下に抜き書きしたのは、第6章「表舞台へ」に書いてありました。
これは、NHK『プロフェッショナル 仕事の流儀』の放送後の大きな反響があったからこその言葉です。たしかに、清掃は大切な仕事ではありますが、なかなか評価されにくい面があります。たとえ家庭内の清掃でも、なんとなく当たり前のような雰囲気があります。
それが、世界が認める仕事となれば、誰もが認めざるを得ない仕事になります。そのように仕事を通じて意識を変えていった著者のすごいところです。それと同時に、清掃という仕事にスポットライトを当てたテレビ局のスタッフも見識があります。
誰もが大切なこととは思いながら、それをはっきりとした形で評価する姿勢こそ、大切だと感じました。
日本では、「父母」という言葉がありますが、英語では「mother & father」というそうですが、清掃を女性の仕事だとする意識ではなく、女性だからこそ細やかな気配りができるということではないかとこの本を読みながら思いました。
(2025.5.27)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 清掃はおもてなし | 新津春子 | 日本能率協会マネジメントセンター | 2025年3月10日 | 9784800593115 |
|---|
☆ Extract passages ☆
清掃は社会的に評価されにくい仕事かもしれませんが、私はこの仕事が好きですし、この仕事をすることでお給料をもらって生活しています。
今清掃の仕事に携わっている方も恥ずかしがったりしないで、「私は清掃員です」と、この仕事に自信を持って取り組んでもらいたいなと思っています。
(新津春子 著『清掃はおもてなし』より)
No.2429『朝日連峰の狩人』
だいぶ前に大井沢の旧大日寺跡にある湯殿山神社のお祭りで、話し手の志田忠儀さんに会ったことがあります。というのも、このお祭りは夜に開催され、火渡りをするので、当日は泊まりでした。それで、お祭りが終わって後片付けをすると、地区の人たちも集まって、懇親会をするのが習わしでした。
そのとき、いろいろな話しを伺うのが楽しみで、翌日には西村山郡大江町沢口の西林寺さんに案内され、県道27号線、通称大江西川線の狭い峠を越えたこともありました。特に、旧大日寺の話しは興味深く、古老たちの話しに耳を傾けました。
そういえば、この県道27号線から少し離れたところに古寺地区があり、ここの「七軒西小学校古寺分校」で教師をしていた渡辺一美先生が三沢東部小学校に転勤になり、この古寺分校は昭和49年に閉校になり、ここは冬になると雪で閉ざされることもあったといいます。その教師は、ほとんどを僻地の分校で教えてこられたので、話しもおもしろく、よく聞いたものです。この本のなかにも、志田さんが原生林を守らなければならないということを相談に行ったという記録して残っています。
この本も、ところどころに方言が使われていて、そのときのことを思い出しました。
もともと、この本は、1991(平成3)年に発行された文庫本を、30年ほど経って、再版されたもので、それだけ自然や野生動植物に関して関心が向いてきたということでもあります。
この本を読もうとした直接のきっかけは、最近、町中に出没するクマ問題です。もともとは山奥に棲息していたクマが、なぜ町中に出没するようになったのか、あるいはクマと出会い頭の事故も増えていることなども疑問です。自然の動植物を大切に保護しなければならないのもわかりますが、普通に町中で生活している人たちがクマに襲われるとしたら、それは考えなければならないと思います。
先ずは、クマそのものの生態を知ることも必要だと思い、読み進めると、子グマにも呼び名があるそうで、「クマは1年越しに2頭ずつ子を生むって言ったの。たまには年子がいて親子5頭一緒に歩いてたとか。連れて歩かなくなるのをこっちではウゴバナレ、小国ではヤライダシって言うけど、ヤライってのは2年目の子っていう意味だろう。本当は1年半連れて歩くのだが、年子を持ちたために子を離すのだなあ。それをウゴバナレと言うのだが、離された子は、一人でエサ充分とれないので冬の中まで歩き回っていたり、炭焼き小屋に来たりする。1年目の子はここではワカメ、2年日の子はウゴ、3年目は独立するので名前はないがクマはクマとこのへんでも呼ぶ。」と語っています。このような話しを聞くと、昔の狩人は、クマのことをいろいろと知っていたようです。
また、「クマは尾根を歩くけど、次の地形によって目的地に向かって歩く。最短距離ってわけではないが。この時は沢の対岸に上流向かって歩いていたんだけど、大きなクマだと対岸からこちらに来る時も、沢渡らないで、なるだけ平に歩いて沢の奥まで行ってトラバースして来る。だからそのまま尾根を越さないで、ぐるっと回ってやってくると判断して、待っていたら案の定来たのでうまく撃った。」とあり、クマの習性などもわかっていたから、仕事にもなっていたようです。
ただ、現在は狩人で生計を立てることは難しく、最近のクマ狩りは、駆除の依頼を受けることが多いようです。それでも、皮はほとんど売れないし、昔は貴重品だった熊胆も今ではそれほどでもないといいます。だから、この本の話しは、その当時の話しとしてはおもしろいのですが、今では参考程度にしかならないようです。
ただ、志田さんが語る「大きく天気がくずれるのは予報でわかるから、荒れそうだったら登らないことだね。それに捜す方から言うと、遭難ってわかってからは、あまり動かれるとちっと困るね。」というのは、私もそうだと思います。以前、私が山岳部に所属していたときに、遭難騒ぎあったのですが、その捜索のときもそれは実感しました。
後から、遭難した人たちに聞くと、だんだんと暗くなってくると怖くなって、じっとしていられなくなるということでしたが、これが体力を消耗する原因となります。
下に抜き書きしたのは、第3章「ワナと動物」に書いてあったものです。
私も子どもの時に小町山にウツギをとるワナをかけたことがありますが、針金をいろりであぶって、輪にしただけの簡単なもので、それでもたまにかかることがありました。それを自作の小屋で飼うのが楽しみでした。
やはり、狩人というのは狩りをすることが仕事ですから、今のような娯楽性の強い鉄砲ぶちとは違うようです。そうして、時代が変わってきたということをこの本を読みながら思いました。
(2025.5.24)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 朝日連峰の狩人(ヤマケイ文庫) | 志田忠儀 話・西澤信雄 構成 | 山と渓谷社 | 2022年11月5日 | 9784635049528 |
|---|
☆ Extract passages ☆
おれは1日にウサギ13ぐらいは何回か撃ったことあるけど、それ以上はないな。だいたい弾は15しか持ってないからだけどね。だから、13ぐらい捕って、2発ぐらいはずすともう弾ないってことでね。若い人だと、ダンダン、ダンダン撃ってね。……
今の人だったら、そうだね、10発にひとつか2つぐらいだろうね。クレーなんか撃たせると上手なんだけどね。実猟にかけてだと、だめだね。慣れてないというより、やっばり娯楽で。見えるだけで撃つ。補れる距離じゃなくても撃ってしまうということだね。
(志田忠儀 話・西澤信雄 構成『朝日連峰の狩人』より)
No.2428『目的への抵抗』
副題が「シリーズ哲学講話」で、基本構成は、東京大学教養学部主催「東大TV――高校生と大学生のための金曜特別講座」において、著者が2020年10月2日に行った講義と、2022年8月1日にオンライン開催した『「学期末特別講話」と題する特別授業(「不要不急と民主主義」。対面開催)』です。
どちらも、時期から考えても、コロナ危機が主題になっていて、今読んでも、たしかにあの時はこのような状態だったと思い出しました。でも、少し時間が経っているので、あのときの強烈なインパクトがやや薄れ、ほんとうにあれでよかったのかどうか疑問に思うところもあります。
そういう意味では、改めて、あの世界的な混乱を引き起こしたコロナ問題を考えてみることも必要だと思いました。
また、この本のなかに、カール・マルクスの「資本論」が出てきますが、私が学生のころに読書会でこの本を読んだことを思い出しました。この本では、「当時19世紀のイギリスの資本家にピール氏という人がいて、他の資本家同様、労働者をこき使つていた。そのピール氏が当時まだイギリスの植民地だったオーストラリアのスワン・リヴァーに、労働者や召使いを連れて移住します。オーストラリアはまだ土地もたくさん余っていて資源も豊富にある。生産力も資本も倍増できると目論んだのでしょう。しかし『資本論』には、オーストラリアに引っ越した翌日、ピール氏には、労働者はおろか自分の身の回りの世話をする召使いすらいなくなったとります。「ピール君は、そのほかに労働階級の男女と子供3000人を同伴したほど周到だった。目的地に着いた時、「ピール氏には、彼のために寝床を用意したり、河から水を汲んだりする一人の召使もいなかった」。何もかも用意しながら、イギリスの生産関係をスワン・リヴァーに輸出することだけは忘れていた不幸なピール君!」(カール・マルクス一『資本論』向坂逸郎訳、岩波文庫、1969年、第3分冊、420ページ)。いかにもマルクスらしい意地悪な書き方で思わず笑ってしまいますけれども、いったい何が起こったのかお分かりいただけるでしょうか。オーストラリアヘ行ったら、こんな資本家に従っている必要はなくなったというわけです。いくらでも土地は余っているし、そこで好きなことを自分でやればいい。資本家に従わなくてもよい客観的な条件が現地には揃っていたわけです。マルクスはィギリスにいた時点で「ピール君」の支配を可能にしていたものを、「イギリスの生産関係」と呼んでいます。この生産関係は先に述べた支配の複雑さに対応するものです。」とあります。
たしかに、よく考えてみれば、いろいろな縛りがなくなれば、自由に生きられます。その縛りが何なのかを考えることも哲学です。
だから、最後のところで、著者は、「目的のために手段や犠牲を正当化するという論理から離れることができる限りで、人間は自由である。人間の自由は、必要を超え出たり、目的からはみ出たりすることを求める。その意味で、人間の自由は広い意味での贅沢と不可分だと言ってもよいかもしれません。」と書いていて、さらに「そこに人間が人間らしく生きる喜びと楽しみがあるのだと思います。」と結論づけています。
振り返って、コロナのときを考えてみると、私は「不要不急」の外出をしないようにということに、違和感を感じました。最初のうちは、もし自分がコロナに罹り、他人にうつしたら大変だとは思いましたが、こういう時だからこそ、観音さまにお詣りしてあるこうと考えました。実際に各地の三十三観音札所は、多くが山や人里の離れたところにあります。しかも、誰もお詣りしないので、蜘蛛の巣が張っているところもあり、まさに巡礼そのものも危機に瀕していました。
そこで、細心の注意はしましたが、お堂ではほとんど誰とも会わず、朱印も書き置きがほとんどでした。人との接触がなければ、「不要不急」もありません。だから、この本に書いてあることに、すぐに納得できました。
下に抜き書きしたのは、第1部「哲学の役割――コロナ危機と民主主義」に書いてあったもの。
たしかに、哲学って何、と私も思いますが、なかなか一口で説明するのは難しいと思ってました。ところが、「自分で問いを立てる」といわれれば、なるほどと思います。さらに、この後で出てきますが、プラトンの「ソクラテスの弁明』のなかに、「ここに一匹の馬があるとして、これは素姓のよい、大きな馬なのだが、大きいために、かえって普通よりにぶいところがあって、目をさましているのには、なにか虻のようなものが必要だという、そういう場合に当たるのです。」と書いてあるそうで、これも哲学として必要なことだと思いました。
(2025.5.21)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 目的への抵抗(新潮新書) | 國分功一郎 | 新潮社 | 2023年4月20日 | 9784106109911 |
|---|
☆ Extract passages ☆
世の中には或る問題、論点についてのパターン化された答えが溢れかえっています。それらはだいたいが、賛成ならこう、反対ならこうという形を取っています。賛成と反対でパターンが決まっているわけですから、もうそれ以上話が進みません。どちらかがどちらかを何らかの仕方で圧倒して否定するしかその問題への解決はなくなる。今だと「テンプレ」なんて言葉もありますが、ある事柄について意見を形成しようとすると、まず賛成か反対かを決めなければいけなくて、そして賛成にも反対にもテンプレが用意されているから、そのテンプレのどちらかに身を置くことになってしまう。
でもそこで問題になっていることについてよく調べて考えてみると、テンプレが見落としている論点が見えてくることがあります。そしてその論点に注目することによって、テンプレ上の対立が無効化されることがよくあります。あるいは、テンプレに留まっていたならば考えることのできなかった問題が見えてくる。そういう風にしてテンプレに留まることなく考えを進めていけるようになることこそ、哲学を勉強することの意味の一つだと僕は思っているんです。なぜならば、哲学というのは基本的に問いを立てて、その問いに概念をもって答える営みだからです。
(國分功一郎 著『目的への抵抗』より)
No.2427『イスラエルについて知っておきたい30のこと』
この本を読んで、意外とイスラエルのことについて知らなかったというのが本音です。また、知っていたことが間違っていたこともわかり、とても読み応えがあります。
それと、2023年10月7日のハマスを中心としたガザ地区の武装組織が越境してイスラエル領内に侵入し人質を拘束しガザに移送しました。すると、即座にイスラエルは報復攻撃をし、それが今も続いています。もちろん、どんな理由があるとしても、先に踏み込んで殺戮したことは大きな問題です。しかし、この本のなかで、「客観的な事実は、イスラエルの諜報機関もエジプト軍も情報を把握して報告していたこと、イスラエルはコラボレーターを使っていること、多数の偵察ドローンなどを24時間飛ばしていること、スパイウェアを使ってほとんどの通信を傍受していることです。」と書いてあり、戦争になってしまえば、どちらも都合のよい情報しか流さなくなります。
そこで、今知っておきたいこととして、この本を読むことにしました。
もともと、アラブ世界は、3つの宗教が共存していたそうです。私は、イスラム教もキリスト教もユダヤ教も、みな一神教です。たしかに、そのなかにおいても神は1つですから、不思議でもなんでもないのですが、過去には宗教戦争が起こり、争ってきた歴史もあります。だから、相容れない部分があるのではないかと考えていました。
この本に、「三つの宗教では、神はもちろん、啓典や預言者の多くも共通しています。ユダヤ教で「ヘブライ語聖書」「トーラー」「モーセ五書」と呼ばれるものは、キリスト教が「旧約聖書」と呼ぶもののコアの部分です。それは、ユダヤ教徒にとってもキリスト教徒にとってもムスリムにとっても、大事な啓典です。イスラームでは、啓典を共有する民として、ユダヤ教徒、キリスト教徒のことを「啓典の民」と呼びます。また、アブラハムやモーセ、イエスはムスリムから見ても預言者であり祖先です。アラビア語では、アブラハムはイブラーヒーム、モーセはムーサー、イエスはイーサーとなり、同じ預言者です。ただ、キリスト教では、イエスは預言者の一人ではなく、救世主(キリスト)という解釈です。」と書いてあり、類似点もあります。
でも、昔から骨肉の争いという言葉があり、身近だからこそ争えば激しくなるということかもしれません。
昔から、領土問題はなかなか難しく、国境の線引きひとつでも争いが起こります。しかも、現代の最新兵器を使っての戦争になれば、その被害はとんでもない規模になります。だから、1938年にマハトマ・ガンジーは、このイスラエルの入植に関して、「入植は侵略と同じだ」ということを指摘しましたし、シオニズム運動そのものも批判したそうです。
ガンジーは「非暴力」を全面に押しだしていましたから、入植することによってパレスチナに暴力を持ち込んでいると考えたのです。そして、残念ながら、今もそれが続いています。
これは、とても大切なことですし、これからの大事な問題でもあるので、多くの人たちにイスラエルのことを知るためにも、読んで欲しいと思います。現在は、いろいろな本も出ていますから、ぜひ関心を持っていただきたいと思っています。
下に抜き書きしたのは、第Ⅰ部「イスラエルはどのようにしてつくられてのか」の「3 シオニズムの物語とは」に書いてあったものです。
おそらく、多くの人たちは、なぜ新たにパレスチナの地にイスラエルという国を作ったのかわからない部分もあると思います。このシオニズムという考えが強引にも建国にいたったようですが、そのことからもう一度、イスラエルという国を知るきっかけになるのではないかと思いました。
この本は、どちらかというとパレスチナ側に立っている本なので、次はイスラエル側の本も読んだみたいと思いました。
(2025.5.18)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| イスラエルについて知っておきたい30のこと | 早尾貴紀 | 平凡社 | 2025年2月10日 | 9784582839746 |
|---|
☆ Extract passages ☆
シオニストたちがユダヤ教徒のコミュニティに対して、パレスチナヘの移住者を募る際に使ったのが「約束の地」「離散と帰還」という言葉です。
「約束の地」とは、 ヘブライ語聖書に記されている、神がイスラエルの民に与えると約束した地を指します。「離散と帰還」とは、紀元70年に古代ユダヤの王国にあった第二神殿がローマ帝国により破壊され、国を失ったユダヤ人が離散し、離散したユダヤ人がその地に戻って国を復活させることを意味します。つまり、離散したユダヤ民族が神に約束された土地に帰って国をつくるということです。
しかし、シオニストの「古代に離散したユダヤ民族が「約束の地」に帰還するのだ」という主張は歴史的事実とは違うことが、これまでの研究で明らかになっています。古代王国のユダヤの民と、近代のシオニズム運動を担ったヨーロッパのユダヤ人は、大きく異なるのです。
(早尾貴紀 著『イスラエルについて知っておきたい30のこと』より)
No.2426『キリン解剖記』
この本の題名を見たとき、キリンを解剖するかのように詳しくみると、というような本だと思いました。
ところが、題名のように、キリンを実際に解剖してみてこそわかるということだそうで、びっくりしました。しかも、小さいときからキリンが大好きだったそうで、初めてキリンを解剖するときも、ワクワクしていたというから驚きです。さらに、おそらく世界で一番キリンを解剖していると自認しているからすごいものです。
この本は、「物心つく前からキリンが大好きだった私が、18歳でキリンの研究者になることを決意し、恩師と出会い、解剖を学び、たくさんのキリンを解剖して「キリンの8番目の"首の骨″」を発見し、キリンの研究で博士号を取得するまでの、約9年間の物語だ。」そうです。
まさにこれまでの一途な思いを、1冊にまとめたような本です。題名ではわからなかったのですが、読んで見ると、その情熱が伝わってくるようで、楽しく読めました。
私たちは、キリンというとためらいもなくアフリカの大平原で背の高い木の葉を食べている姿を思い浮かべますが、じつは4つのグループに分けられるそうで、しかもそれがわかったのは2016年だそうです。「実は、科学者たちも、長い間そう考えてきた。ところが2016年、ドイツやアフリカの国際研究チームによって、キリン1種説に一石が投じられた。たくさんのキリンからDNAを採取し、遺伝子の特徴を調べてみたところ、遺伝的特徴の異なる4つの集団に分けられることが明らかになったのだ。研究者たちは、その4つのグループを、「アミメキリン」「マサイキリン」「ミナミキリン」「キタキリン」と名付けた。日本の動物園で飼育されているのは、多角形の斑紋から構成されるきれいな網目模様をもつ「アミメキリン」と、ギザギザした不規則な形の斑紋をもっ「マサイキリン」の2種のみである。「ミナミキリン」と「キタキリン」は飼育していない。」ということです。
ということは、私が動物園で見たことのあるキリンは、「アミメキリン」のようです。
そういえば、植物の世界でも、このDNAを検査することができるようになって、分類も劇的に違ってきました。以前は牧野富太郎の伝統的なやり方でしたが、現在の主流は、DNAを使ったAPG分類になっています。でも、そうなれば、花びらとか葉の付き方とかでは分類できず、研究室でDNAを採取して分類するということで、素人には手も足も出なくなりました。それがいいかどうかはわかりませんが、そのような話しでもなさそうです。
また、キリンというと、あの長い首を思い出しますが、あの高い頭まで血液を運ぶのは大変ではないかと思います。この本では、キリンの血圧は最高で300㎜Hgもあると書いてありましたが、それ以上に血液の送料も体のわりには少ないそうで、心拍数もさほど高くはないそうです。それでも、メスを獲得するための戦いでは、あの長い首を使うわけですから、あの強靱な首はどうなっているのだろうと思ってました。すると、その秘密は「項靭帯」にあるそうです。「その名の通り、「項」にある靭帯だ。項靭帯は弾性をもった組織を大量に含み、ゴムのような特性をもつ。引っ張って伸ばすと元に戻ろうとする力を生む。エネルギーを使って能動的に力を発揮する筋肉とは違い、靭帯は受動的に収縮する力を生む。キリンは、非常に分厚い立派な項靭帯をもっている。この項靭帯という名の強力なゴムのおかげで、キリンには常に「首を引っ張りあげる力」がかかっていることになる。キリンは、この引っ張りあげる力を利用して、筋肉をあまり使わずに重力に対抗して頭と首を持ち上げているのだ。」と書いてあり、なるほどと思いました。
このようなことを知るためにも、キリンを解剖しなければならないということです。そして、解剖したからこそ、キリンのことがわかったといえるのかもしれません。
下に抜き書きしたのは、第8章「キリンから広がる世界」の「コラム」に書いてあった母との関係です。
ちょっと変わったキリン研究者ですから、両親はどのような人かな、と思いましたが、父は不通のサラリーマンで、母は専業主婦だそうです。
しかし、著者がいうように母は「ちょっと変わった人」だそうで、今では調香師としてカルチャースクールで香作りを教えているそうです。好きということは、いかに大事なことかを教えてくれています。まさに、この母にしてこの娘あり、です。
私も、「自らの喜びとして主体的に知識を得る」ような学問をしてみたいと思っています。
(2025.5.15)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| きりん解剖記 | 郡司芽久 | ナツメ社 | 2019年8月1日 | 9784816366796 |
|---|
☆ Extract passages ☆
当時の母は、50歳くらいだった。「記憶力が落ちてるから、すぐ忘れちゃう」などと困り顔で言いながら、毎日楽しそうに本や資料を読み込んでいる母の姿は、お香と出会う以前よりもはるかに輝き、人生を楽しんでいるように見えた。
知識は生活を豊かにし、目にとまるものに価値を与え、新たな気づきを生み、日常生活を輝かせてくれる。私は、母の姿を通じて、知識を身につけることの楽しさと素晴らしさを学んできたような気がする。そして、誰かに強いられて知識を詰め込む「勉強」と、自らの喜びとして主体的に知識を得る「学問」の違いに気がついたのだと思う。
(郡司芽久 著『きりん解剖記』より)
No.2425『これで暮らす』
この本は、じつは家内が図書館から借りてきたのだが、おもしろかったというので、私も読んだのです。
たしかに、日常の細々としたことが書いてあり、あまり興味のないものもありましたが、読み切りました。ということは、それなりにおもしろかったです。
もともと、この本に出てくるものは、「小説 野性時代」の2018年11月号から2020年6月号まで連載されたもので、最後の「21 |花瓶|花を飾る」だけは、書き下ろしだそうです。この月刊誌「小説 野性時代」は、KADOKAWAが発行・編集するエンターテインメント小説誌で、いろいろなジャンルのものが入っています。私も何度か立ち読みをしたことがあります。
この『これで暮らす』のなかに、「昔はインクを注入するのが、ちょっと面倒くさかったが、最近はコンバーターで注入するのも楽しくてたまらない。インク瓶を見ては、こんなに減ったとうれしくなる。他にも明るいブルー系の「紺碧」、ゲラ(校正刷り)への記人用の赤い「紅葉」も待機しているが、まだ出番はない。鉛筆で文字を書いて、間違えたら消しゴムで消す。万年筆に好きな色のインクを入れて書く。そういったちょっと面倒なことが、とても楽しくなってきた。若い人に比べて残りの時間は明らかに少ないのに、時間がかかることが楽しくなってきたなんて、不思議なものだと自分でも首を傾げているのである。」と書いていますが、私も万年筆をよく使うので、そうそうと頷いてしまいました。
私も、昔は、インクの交換が嫌だったので、カートリッジインクを使っていましたが、それだと気に入ったインクが別なメーカーだったりすると、使えません。たとえば、今使っている万年筆は、パイロットの「ジャスタス95 FJ-3MR-NB-FM」ですが、これはペン先の弾力調整ができるので重宝しています。これにたどり着くまでは、ペリカンやシェーファー、パーカーなども使いましたが、やはり日本の文字は日本製の万年筆がいいと思い、セーラーやプラチナなども使いました。
その選ぶ過程で、インクはセーラー万年筆の「極黒」の顔料インクとの相性がよく、あの黒々とした色が気に入りました。
それでしかたなく、セーラー万年筆も使いましたが、それでも今はパイロットのジャスタスに落ち着いています。そうなれば、ボトルインクを使うしかなく、今では著者と同じように、ボトルの減り具合を楽しむようになりました。この「極黒」も以前はいかにもインク瓶というような形で、しかもリザーバーも付いていたので、とても使いやすかったのです。ところが新しい今風のガラス瓶になってからは、同じ50mlですがリザーバーは別売りになってしまいました。
この本のなかでも、どうでもいいような細いことがけっこう出てきますが、私も同じです。そのこだわりが楽しさに結びつき、また新しい展開につながっていきます。
下に抜き書きしたのは、「9 |豆皿、大皿|ふだん使いの食器」に書いてあったものです。
私も和食器は好きで、茶道をやっていたこともあり、茶懐石に出てくるような食器にも関心があります。たしかに、和食器には西洋の食器にはないバラエティがあり、とくに向こう付けなどの奇抜な器などにはびっくりさせられることもあります。
また、自分で作った器に、お菓子を盛ったり、料理に使ったりすると、ますます楽しくなります。
それでも、アイルランドの知り合いが、結婚のときに祖母からプレゼントされた珈琲カップが気に入り、帰国するたびに少しずつそれと同じデザインの食器を買いそろえているという話しを聞いて、それもいいなあ、と思いました。しかも、値が張るものの場合には、古道具屋さんでも探すことができるといいますから、同じサイズやデザインというのもそれなりの楽しみがあると思います。
(2025.5.13)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| これで暮らす | 群 ようこ | 角川書店 | 2021年2月19日 | 9784041108529 |
|---|
☆ Extract passages ☆
ずいぶん前に陶芸を教えている大学の教授にお話をうかがったとき、日本の陶芸家は外国の陶芸家から、とてもうらやましがられるとおっしゃっていた。外国の食卓はプレートやカップなどの大きさがほぼ決まっている。それに比べて、和食の食器を作る日本の陶芸家に対して、「さまざまな形の食器を作ることができていいね」といわれたのだとか。皿などは寸でほぼ決まっているが、花や動物、魚を象ったものなど、変形のものも多い。小鉢や向こう付けなどは、器自体がリアルな紅葉や空豆の形になっていたりする。形は何でもありの自由さなのだ。外国の食器もその国らしさが表れていて、持っていると楽しい。洗う手間が面倒なのはわかるけれど、そういった生活の楽しさをすべて手放すのは残念だと思う。
(群 ようこ 著『これで暮らす』より)
No.2424『戦場からの証言 ウクライナ』
副題は「わたしのことも思い出して」で、これはタラス・シェフチェンコの「遺言」という詩の一節からとられたものです。とてもいい詩ですが、これを抜書きするのは控えて、ぜひこの本を読んでもらいたいと思います。
前回のNo.2423『新聞記者がネット記事をバズらせるために考えたこと』でも考えたことですが、とくに戦争などの場合は、当事国だけの情報では、正当な判断はできません。しかも、国際ジャーナリストで歴史学者のマックス・ヘイスティングズの「本書によせて」のなかで、「わたしは50年以上前、戦場記者Lして、また戦争歴史家としてのキャリアを歩みはじめた時、愚かにも、自分の役目は戦闘を記録することだけだと思っていた。だが今は、ジョージ・バトラーが自身の人生の多くをかけて、言葉と絵でなにを伝えようとしているのか理解している。つまり、兵士たちの話は彼が伝えたいことの一部にすぎず、大半を占めるのは戦争に翻弄される人々の話なのだ。どんな紛争においても、銃をもって戦う兵士たちより、はるかに多くの民間人、とくに女性や子どもたちが、ハリケーンのような暴力でなぎたおされていく。われわれのように平和で安全な暮らしを送っている者は、恐怖の中で生きることを強いられた人々の思いを理解しなければならない。ウクライナの人々は、剥奪と犠牲と破壊のさなかに祖国にとどまり、大義をかかげることで、すでにその勇気を示している。」と書いていますが、だからこそ、私たちも副題のように忘れず思い出すことが大切だと感じました。
この本を読んでびっくりしたのは、キーウに住むアルテールさん40歳が、クラゲの水族館を開設していることでした。そのきっかけは、日本でクラゲ水族館を見たことがきっかけで、ロシア侵攻前からキーウの「フレシチャーティク通り」で開いていたのです。
それが侵攻後は道路の封鎖などで施設に行くこともできず、領土防衛隊に入隊後は、水族館の電源も自らの判断で落としてしまい、クラゲを全滅させてしまったそうです。しかし、2022年3月下旬からキーウに戻り再開し、現在は一からやり直し、戦争を少しでも忘れられる場所として多くの人々が訪れているそうです。
日本のクラゲ水族館の名称は書いてなかったのですが、おそらく山形県の「鶴岡市立加茂水族館」ではないかと思いました。そういえば、あのゆったりした動きを見れば、一時でも戦争の悲惨さを忘れられるかもしれません。
また、マリウポリのナータという女性の話も衝撃的で、たしかテレビなどでも2022年2月にロシアがウクライナ東部のマリウポリへ侵攻し破壊した様子が放映され、さらに『マリウポリの20日間』という映画にもなったほどです。そこの話しですから、まさに悲惨そのものです。「ある日、地下室の入口から外をのぞくと、自宅があるアパートが遠くに見えました。燃えていました。ああ、これで帰る場所がなくなった、と思いましたね。泣きたいとは思いませんでした。感情を表に出すことにエネルギーを使いたくなかったんです。その時のただひとつの願いは生きのびることでした! 残っていた力は全部そのために使いました。物なんで、もうどうでもよくなりました!一番恐ろしかったのは飛行機の爆音です。飛行機が1機飛んでくれば、ミサイルが3、4発落ちてくるとわかっていました。みんな、自分のいるアパートにあたらないことを祈り、はずれるたびに胸をなでおろします。でも同時に、「はずれた」ということは、どこかのだれかの家に命中しているだけだとわかっていました。そしてそこにも、わたしたちと同じような人たちがいるのです。」122
また、クープャンシクでアンドリィが話した、「ここでは、1日を測る唯一の単位は、その日の終わりに生きていることであり、あれこれ考えるより早く眠りに落ち、すべてからのがれることなのだ。」という言葉もすごく印象に残っています。
もうひとつ、印象に残っているのは、前線に近づく途中で見かけたロシア語のメッセージです。それを翻訳してもらうと、「地獄へようこそ」という意味で、これが侵攻してきたロシア軍へのウクライナの人々からのメッセージそうです。たしかに、ほとんどの人たちには不気味に感じるメッセージですが、はたしてロシア軍に通じるかどうかは不明です。
下に抜き書きしたのは、イジュームというところで、医師のユーリイに話を聞いたときのものです。
彼の病院の正面は、2022年3月8日のロシア軍のミサイル攻撃で破壊されましたが、インタビューのときにもその病院の診察室で多くの患者の診察をし、それが終わってから話しを聞いたそうです。しかも、ほとんどこの病院で寝起きし、避難もしなかったそうです。
彼は、「この病院は守護天使に守られている」と行っているそうですが、それ以上に人の命ほど大切なものはないという気持ちから診療に明け暮れているようです。
(2025.5.10)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 戦場からの証言 ウクライナ | ジョージ・バトラー 著、原田 勝 訳 | 小学館 | 2025年2月3日 | 9784092906822 |
|---|
☆ Extract passages ☆
ある時、近所に住む人たちがやってきて、こう言ったんだ。「おい、きみの家にミサイルが命中したぞ」ってね。むろん、心配だったよ。すぐにでも帰って、ほんとうかどうか確かめたかった。でも病院の仕事が忙しくて、なかなか帰れなかった。やっと帰ってみると、家の一部がめちゃめちゃにこわれていた。わたしはいきなり大声で笑いだした。近所の人たちが、「どうかしてるぞ。なぜ笑ってる?」と言うので、わたしはこう答えた。「忙しくてしばらく家に帰れなかっのは運がよかった、と思ってるからさ。帰っていたら、たぶん、今こうして、あなたたちとしゃべってないだろう」と。
つまり、昼夜を問わず働いていたから命拾いしたんだ。今、こうしてここにいて、きみと話せることがうれしいよ!
(ジョージ・バトラー 著、原田 勝 訳『戦場からの証言 ウクライナ』より)
No.2423『新聞記者がネット記事をバズらせるために考えたこと』
この本を読むまで、新聞もネットの記事も同じようなものだと思っていましたが、読み始めはなんとなくわかり、最後の方ではなるほどと思うようになりました。
たとえば、新聞記事は「逆三角形スタイル」というそうですが、「特に、私が勤める共同通信社では書き方が徹底されている。重要なポイントをできるだけ記事の前に置き、配信を受けた新聞社が記事を途中で切って紙面に掲載しても、意味が通じるようにしている。これは「逆三角形スタイル」と呼ばれ、読者へ効率的に情報を届けるには、最も優れた技法とされてきた。記者を10年もやっていれば、たちどころに逆三角形の記事を書くことができる。」と書いています。
それまで新聞記事を文体などまで考えていなかったのですが、たしかに、どの新聞を読んでも、似たような文章です。これも、長い間の経験から導き出されたもののようです。
でも、その新聞の発行部数も年々減少し、日本新聞協会によると、2023年10月時点の新開発行部数は2859万486部、2003年10月時点では5287万4959部だったといいますが、20年間でほぼ半減したということになります。そういえば、2024年9月30日に、毎日新聞社と産経新聞社は、輸送コストの増大などで富山県内への新聞の配送を休止したというニュースが流れました。
これでは、新聞紙という紙を使った記事は、このまま進めばもしかするとすべて休止になるかもしれません。
では、その紙の記事をデジタル化しただけで読んでもらえるのかというと、そんなに単純なものでもないようです。やはり、求めているものが違います。
だから、デジタル記事には、それなりの書き方があり、この本では、
●記事を説明文にせず、物語(ストーリー)にする
●出だしは、できれば場面の描写から入る
●リードの末尾には、本文に読み進んでもらうための「匂わせ」を入れる
●主人公を一人立てて、場面ごとに主人公の気持ち・感情を書き込む
●できれば時制をさかのぼらず、時系列で書く
●一文を短くし、テンポを良くする。主語の前に長い修飾を付けない
●カギカッコの前にはできるだけその発言者を置き、後ろに述語を置かないようにする
●接続詞や指示語をくどいくらい付け、段落や文同士の関係性を明確にする
●データや識者の言葉など「説明文」になりがちな要素はストーリーの後ろに回す
●新聞慣用の省略形は使わない
●表記に迷ったら、グーグルトレンドで比較する
と書いてありました。
もちろん、これだけではわかりにくいところもありますので、なるべくなら、これからバズるような文章を書いてみたい人はぜひ読んでみてください。
下に抜き書きしたのは、第4章「説明分からストーリーへ――読者が変われば伝え方も変わる」に書いてありました。
これを読むと、やはり新聞には新聞としての役割というか、メリットがありますし、デジタルに親しんでいる人にはそれなりの伝え方があると私も思います。
ただ心配なのは、感情に訴えるあまりに、理性的に考えることができなくなり、流されやすくなるような気がします。とくに政治的にも経済的にも困難なときには、その傾向が強まります。それと、コピペで作られたような記事ばかりになれば、その発信元もわからず、無責任になるような気もします。
そういう意味では、一次情報が中心の新聞と、それを元にしたデジタル情報が両立することこそが大切ではないかと思います。この本のなかに、「こたつ記事」という話しが載っていましたが、それのみでは、何を信頼すればいいのかさえ、わからなくなりそうです。
(2025.5.7)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 新聞記者がネット記事をバズらせるために考えたこと(集英社新書) | 斉籐友彦 | 集英社 | 2025年2月22日 | 9784087213508 |
|---|
☆ Extract passages ☆
新聞のメリットは、最新の情報をコンパクトに簡単に得られること。見出しやリードにニュースの重要な要素が要約されて詰まつているため、特に時間がない読者は、各面の見出しとリードさえ読んでおけば最低限のニユースをまとめて把握できる。さらに時間がない時は、見出しを頭に入れるだけでも、どんなニュースがあるのかぐらいは押さえられる。雑多な情報を能動的に得ようとする読者にとっては、現在でも最適なツールだと思う。
一方で、デジタルの読者は、より受動的だと感じる。たとえば、スキマ時間に何気なくスマホを触っていて、画面に表示された記事に不意に出会うイメージだ。そこで気が向いて読み始めた人にとって、大切なのは読み心地の良さであって、かたい説明文ではない。ストレスを感じずにストーリーを読み終わった時、ある社会課題の存在を、具体例を伴って理解できていればいい。
(斉籐友彦 著『新聞記者がネット記事をバズらせるために考えたこと』より)
No.2422『60代 大人旅の愉しみと工夫』
私も70代後半になると、今までのような旅はできなくなり、いろいろと考えていたときに、この本を図書館で見つけました。副題は「体力と費用を温存しつつ楽しむ人生後半の旅のかたち」とあり、なんで題名が「愉しみ」なのに、「楽しみ」と変わってしまったのかと思いました。
個人的には、「愉しみ」のほうが、自分のほうから積極的に楽しもうとする気持ちが感じられて、いいのではないかと思っています。
まあ、それほど字面にこだわることもないのですが、最近は、少し時間をかけて旅の計画を立てるようになってきました。だから、今まで1泊だったのを2泊にするとか、2泊で帰ってきていたのを3泊に伸ばすとかしています。
そういえば、この本にも書いてあったのですが、旅にでるときにはフォークや箸、ナイロン袋なども持って行きます。たしかに、おいしそうなケーキを見つけても、男一人だとお店の中では食べにくいし、そういうときにはホテルに持ち帰ってコーヒーを淹れて食べます。また、果物などを見つけるとすぐ買うので、そのようなときもフォークやナイフがあると便利です。
もちろん、最近はコンビニでもナイロン袋は有料ですし、それより自分で持っていったほうがきれいにゴミをまとめることもできます。
それと、私も「年齢的にもうっかりが多くなったので、気持ちよく旅を終えるためにも忘れ物には気をつけ」るようにしています。つい先月も、冷蔵庫のなかに抹茶を入れたまま忘れてしまい、フロントから部屋に戻りました。それでも、まだ部屋のカードを返す前だったからよかったけど、私も注意しなければと思いました。
著者は、東京都美術館で「マティス展」を見たそうですが、私はイギリスに2014年7月に行ったときに、テート・モダン(Tate Modern)を見に行くことになり、たまたまそこで「マティス展」をしていたのです。海外でなかなかそのような機会はないと思い、ゆっくりと見て、そこのレストランでランチをしたことを思い出しました。
この本には、「観賞してまずハートを掴まれたのが「夢」という作品。うつぶせの女性の下に描かれた布の青色が印象的で。マティスと聞いて私が真っ先に思い浮かべたのはデッサン画だったのですが、さらさらと細い線で描かれた作品がやはり好きなのだなと思いました。最後の展示フロアでは晩年作である切り紙絵を観て、デッサンや油彩画とはまた違う素敵さに驚きました。体力の低下で筆を持っことが難しくなってしまったマティスが模索してたどりついた技法だったのだとか。人生、いくつになっても諦めない姿勢って大事ですね。マティス展に行って本当によかった。知らなかった世界を知るっていいなと改めて感じました。」とあり、私も記念にマティスの絵ハガキを買ってきましたが、孫たちには本のしおりをお土産にしました。
私もマティスというと、やはり青色が印象的で、今でもときどき思い出すことがありますし、テレビなどで取り上げられると、つい見てしまいます。
下に抜き書きしたのは、「お決まりの旅の友~旅ノート」に書いてあったものです。
私もここに書かれているようなノートではありませんが、持ち運びしやすいように野帳のようなものに、これから行くところのいろいろな情報などを書きとめています。そこには、行くか行かないかもわからないようなお店だったり、陶磁器の窯場だったり、ときには図書館のような情報も書き込んでいます。
そして、必ず調べるのは、その土地の老舗の和菓子屋さんで、旅先でお抹茶を点て飲むのが好きだからです。だから、必ず持って行くのは抹茶と茶筅で、最近は小さめな旅茶碗も持っていきます。電車の旅のときはなるべく荷物が少ないほうが楽なのですが、これだけはないと旅の愉しみも半減するような気さえします。
(2025.5.4)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 60代 大人旅の愉しみと工夫 | 小暮涼子 | 主婦と生活社 | 2025年3月10日 | 9784391164336 |
|---|
☆ Extract passages ☆
最初にノートを使ったのは、10年前の9月に行った初めての京都ひとり旅です。当時はスマホの地図機能も今ほど充実しておらず、またうまく使いこなせなかったので、手描きの地図に行きたい場所や訪れたいお店の営業時間や定休日などを書いていました。……
そうして、出発が近づくころには、それなりの量の情報や大まかな地理がわかってきて、より旅が楽しいものになっていくのです。近くの温泉に行くようなのんびりした旅のときは別ですが、まだ見ぬ土地へ思いをはせてアンテナを張り、自分の好奇心を満たす場所を旅ノートに書き込む時間はなかなか楽しいもので、ここから旅は始まっているように私は思っています。
(小暮涼子 著『60代 大人旅の愉しみと工夫』より)
No.2421『おいしそうな文学。』
最近は、題名のところに「。」などが使われるようになってきましたが、どうもなじめないのは性格なのか年のせいなのかはわかりません。それでも、気にはなりますが、もしかしてそれを意図しているのかもしれません。
初出は、「群像」2024年10月号で、この本のなかの「100年前の台所」だけが粥川すずさんの描き下ろしだそうです。でも、文字ばかりの本のなかに、この漫画が入っているのかわかりません。
なんとも不思議なことの多い本ですが、たった125ページなので、一気に読んでしまいました。
なかでも興味を引いたのは、斉籐倫さんの「おいしいにはりついて」です。たしかに食には情報というかストーリーというか、そんなものがおいしさにつながります。このなかに、『「群像」で「野良の暦」を連載されていた、鎌田裕樹さんのお野菜が通販で買えるようになった。いただいて目から鱗がおちた(野菜だから、ポリフェノールを含んだ外皮かもしれない)。農家としてのじぶんをたちあげる日々の記録を読み、さらにその結実を味わえるなんて、こんなに輻輳的な歓びがあるだろうか。こう書くと、いかにも情報やストーリーに左右されてるようだけど、たんにすごくおいしいのだ。ただ、ひとは面倒なもので、その「たんにおいしい」にたどりつくための鍵がいる。それは、情報でもストーリーでもありえるだろう。「空腹は最大の調理人」だって、いわばひとつの物語なのだから。』といいます。
このなかで、「輻輳的な歓び」とありますが、意味がわからなかったので調べると、「輻輳」というのは、「一般的に何かが1カ所に集中して混雑している状態のことをいい、通信分野では、電話回線やインターネット回線、ネットワーク機器などの一部にトラフィック(送受信される信号やデータ)が過剰に集中して、通信が遅延したり、つながらなかったりする状態のこと」と書いてありました。
つまり、さまざまなものが1ヵ所に集中して混雑した状態のようで、まさに今の情報ネット化の時代だからこその言葉のようです。
また、原武史さんの「戦場で頬張る塩の味」で思い出したのですが、あるところでいろいろな塩を集めている方がいて、そのなかでもカリマンタンの塩が私には一番おいしく感じられました。この本のなかで、塩を1つまみずつ頬張るシーンがありましたが、その1つまみでけでも、カリマンタンの塩には甘みすら感じられました。それから十数年後にその塩を買ったというカリマンタンにつれて行ってもらったのですが、やはりおいしい塩でした。
それ以来、どこへ行っても塩を探し、ネパールでは黒っぽい岩塩も見つけたり、中国の雲南省では、昔ながらのやり方で塩を採取するところもあり、そこでも買ってきました。それぞれに塩の味があり、お土産として持ち帰っても安くていいのですが、ちょっと重いのが難です。
下に抜き書きしたのは、土井善晴さんの「おいしさの気配」に書いてありました。
著者の土井さんは、テレビなどで活躍していた料理研究家・土井勝さんが父で、その縁からなのか、料理研究家やフードプロデューサーでもあります。そういえば、東京大学先端科学技術研究センター客員研究員でもあるそうで、いろいろなところで活躍しています。
日本の食卓の基本は、和食の基本でもある「一汁一菜」でよいという提案は、毎日何種類ものおかずを作らなければならないというお母さんたちのプレッシャーをだいぶ和らげたのではないかと思います。この一汁一菜は、米沢藩の上杉鷹山公の食事でも有名ですが、あの時代に72歳まで生きたのですから年表を見ても、元気だったようです。
そして、食事というのは、たしかに栄養を取るということも大事ではありますが、それとみんなで食べるということも大切なことだと感じました。
この文章を読み、そのときの驚きが蘇ってきました。
(2025.5.2)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| おいしそうな文学。 | 群像編集部 編 | 講談社 | 2025年2月25日 | 9784065384428 |
|---|
☆ Extract passages ☆
そもそも味覚、嗅覚は言語中枢とつながらず、おいしさは言語化できません。ゆえに、食事をともにした者だけがそのおいしさを知り得るもの。低級感覚とされた不完全な味覚と嗅覚の恩恵に、人間らしさがあるのです。おいしさに代わって心に留まるものとは、人の思いの交わりの大切な物語です。
(群像編集部 編『おいしそうな文学。』より)
No.2420『修験道大系』
久しぶりに修験道関連の本を読みましたが、副題は「歴史・思想・儀礼」で、いずれも大切なものです。とはいえ、いずれも難しく、理解するにはそうとうな時間がかかりました。
それでも、いい機会なので、読み通しましたが、わからないところもありました。なかには、現代にそのまま使えるのかというと、疑問のところもありました。
特に興味を引いたのは、自分が修行した醍醐寺や花供入峰をした大峰山、葛城山など、さらには地元の出羽三山のことなどです。知っているようで知らなかったこともあり、羽黒山の「三関三渡」などもなるほどと思いました。それは、「羽黒山の『羽黒占実集覧記』では、羽黒三所権現の下の谷にある羽黒権現の根源の地とされる本地の阿久谷を現世の観音、月山は過去世の阿弥陀、湯殿山は未来世の大日如来であるとし、この各々の権現の下で三世を超越して真如実相・即身即仏の妙果を得ることを三関三渡としている。またより具体的に秋の峰の一の宿を胎内で過去世、二の宿を胎外で現世、三の宿を未来世とし、この二の宿から三の宿は入る時を有為の岸から無為の彼岸に渡る故、大渡りと呼んでいる。そしてこの三つの宿を順に参拝することによって三世を超越して永遠の生命が得られるとして、これを三関三渡としている。」とあり、これは現在も同じような考え方をしているように思います。
だから、私たちも、逆に湯殿山から月山に上り、そこから羽黒山に下り、柴灯護摩を修したことがあります。いまでは、このルートを自分の脚で歩くことは大変になりましたが、やはり修行は若いうちにこそすべきだとつくづく思います。
また、羽黒山は江戸時代になり天台宗になり、湯殿山の真言宗との軋轢もありましたが、この本に室町期のことが書いてあり、「室町初期の羽黒一山では一山を統率する院主の下に一か月を一旬(約10日)ずつ担当して法務にあたる上・中・下の三旬長吏、検断や先達を司る政所を中核とする一山組織が認められた。14世紀中頃成立した『神道集』の「出羽国羽黒権現事」の項には、羽黒権現は観音、軍荼利、妙見の三神で、推古天皇の代に能除大師によって顕されたとしている。室町時代末には羽黒山では開山を能除(法名弘海)、初代執行を弘俊とする歴代をあげた系図が作られている。ちなみに現在の羽黒山の五重塔は棟札によると永和3年(南朝天授3、1377)に完成している。そして室町中期の羽黒山は山上の羽黒権現と寂光寺、奥院の荒沢寺、祓川の五重塔を守る清水寺の光明院と山麓の手向の黄金堂を預かる中禅寺を中心として栄えていた。なお手向では羽黒権現の市、山上の観音堂前では馬市があり、商人、手工業者、芸能人が集まっていた。そしてすでにこの頃から羽黒一山では各地の末派修験に知識や先達などの補任を行なっていた。戦国期(1467~1568)に入ると大宝寺(鶴岡)に居した武藤政氏が文明2年(1470)に羽黒山別当となり、天正15年(1587)の同氏の減亡まで三旬長吏を支配した。」と書いてあり、その当時の手向の賑わいを彷彿とされます。
このような本は、どうしても抜書きが多くなりますが、やはり、出典元がはっきりと書いてあるものは、貴重です。たとえ、言い伝えであっても、ここにこのように書かれているということが大事なことなのです。たとえば、法螺などについても、「法螺はバン(梵字)字型をしているが、これは金剛界大日如来の智恵の本体である真実そのものを示している。なお法螺を吹く時に唱える法螺の文「三味法螺声、 一乗妙法説、経耳減煩悩、当人阿字間」は精神を統一して吹く法螺の音声は真実の教えを説いているゆえ、この経の音声を耳にすれば煩悩を減して必らず物事の本源である阿字の教えのすべてを感得することが出来るということを意味している。」とあり、この法螺の文は知っていても、法螺がバン字の形とはいわれればそのようにも思いますが、あまり気にもしていませんでした。
とくに修験道というのは、もともと仏教などと違い、自然発生的な宗教です。役行者を始祖に仮託したもので、おそらく、古来の山岳信仰や神道など、さらには仏教などの影響もあり、思想や儀礼が整えられてきたようです。
そういえば、中国の青城山に行ったときに、道教というものに触れてきましたが、その影響もあります。まさに複雑だからこそ、奥が深く、興味がかき立てられるのかもしれません。
下に抜き書きしたのは、第3章「修験道の崇拝対象」に書いてあったものです。
だいぶ前のことになりますが、世田谷美術館で2004年11月20日から翌年の1月23日まで、「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界遺産に登録されたのを記念して「祈りの道 吉野・熊野・荒野の名宝」特別展が開催されましたが、ここに金峯山寺の重要文化財「蔵王権現立像」が展示されました。その大きさにも圧倒されましたが、その異様な姿にも驚きました。
この文章を読み、そのときの驚きが蘇ってきました。
(2025.4.30)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 修験道大系 | 宮家 準 | 春秋社 | 2025年1月20日 | 9784393292075 |
|---|
☆ Extract passages ☆
『金峰山秘密伝』の「金剛蔵王尊像習事」の条によると、その尊像は一面三目二臂の青黒のな怒相で、頂上に三鈷冠を戴き、左手に剣印を結んで腰に案じ、右手に三鈷杵を持って頂上にあげ、左足は磐石、右足は空中を踏みしめたもので、それぞれについて次のような説明がなされている。まずその身体の色が青黒であるのは降魔の相をあらわす。次にその面上の三つの目は、左眼は弥勒の大悲の眼、右眼は観音の大悲の眼、中央の一眼は釈迦の大定不二の眼で、総じてこの三仏の徳を秘蔵して三界を照らして三菩提を開くことを示し、頂の三鈷杵は弥勒、観音、釈迦を表象する。左手の剣印は三世の怨敵を降伏すること、これを腰に案ずるのは、腰が地輪ゆえ、地魔を降伏し国土を鎮めることをさす。一方右手の三鈷杵は法界の魔群を降伏することを意味し、これを空中にかざすのは三妄の雲を払い、天魔を調伏することを示す。次に左足で磐石を踏むのは、四海の重障を鎮めること、有足で空中を踏むのは曜宿の障りを踏みつけることを示している。
(宮家 準 著『修験道大系』より)
No.2419『この世界を科学で眺めたら』
副題は「真理に近づくための必須エッセイ25」で、科学もエッセイで読むとわかりやすいのではないかと思い、読み始めました。
それにしても、科学は意外と身の回りにある問題にも答えられないと書いてあり、びっくりしました。たとえば、「比較的正確な解答が求められるのは、学生実験のように条件を厳しく制約するケースに限られる。」といいます。だから、よく「建物の耐震基準は、震度6以下なら耐えられる」などと表現されるときがありますが、これだって「水平加速度がある値以下ならば重要な構造体が破損しない」という意味だそうです。でも、実際の地震は縦揺れと横揺れが激しく合わせたような揺れが多く、それに付いてはどのぐらい耐えられるかまではわからないそうです。つまり、ほとんどの場合は、机の上の想定でしか考えられないということです。
たしかに、地震が起こるときの予報も、あまりあてにはならないようですが、さりとて何も予報がないというのも心配です。
わからないといえば、カラスは黒いと思っている人が多いと思いますが、マダガスカルに行ったときに白と黒の羽毛を持つカラスを見て驚きましたが、このカラスは「ムナジロガラス」というそうで、たくさんいました。日本でも2023年8月に白いカラスが新潟県内で捕獲されましたが、これの遺伝子解析からメラニン色素が作れず色が白い「アルビノ」ではなく、白変個体とみられるそうです。
海外の調査結果などを参考に推計すると、全身白色の出現確率は2万~3万羽に1羽程度ということですから、たしかに珍しいだけでなく、白いカラスがいることは間違いないそうです。
この本には、「カラスは、道具を使ったり遊んでいるとしか思えない行動をしたりと、きわめて知的な動物である。中でもカレドニアガラスは、道具を″作った″ことで知られる。垂直に立てた円筒形の筒にフックの付いた餌入り容器を入れ、そばに針金を置いたところ、足と嘴を使って針金を曲げ、フックに引っかけて容器を釣り上げたという。道具を使う動物なら結構いるが、道具を作る動物は、ヒト、チンパンジー、ボノボ以外ではカラスくらいだろう。もっとも個体差があるようで、オス・メス2羽のカレドニアガラスを観察したオックスフォード大学チームの論文によると、メスはうまく餌を釣り上げたのにオスの方はどうしてもできず、メスが得た餌を横取りしていったとか(情けない!)。」と書いています。
私も、子どもの時にケガをして飛べなくなったカラスを駐在所に持っていくと、元気になるまで飼っていいといわれ、何週間か飼育したことがあります。毎日、学校帰りにエサを集め、食べさせました。すると、近くまで私が行くと、鳴き声で答えてくれるようになりました。そして、飛べるようになってから、扉を開けっ放しにして学校に行くと、近くの木に止まって、鳴いていました。数日は帰るころになると、その木に止まっていましたが、だんだんと見えなくなりました。
それでも、通学途中の道でその鳴き声を聞くことがあり、まだ近くにいたんだと懐かしく思うこともありました。
よく、カラスにいたずらすると、後ろから飛んで来て、頭を突っつかれるとかいいますが、それはあり得ます。また、遊んでいる姿を見たこともあります。
そういえば、量子コンピューターのことを知りたくて、何冊が本を読んでみましたが、わからないことばかりでした。この本には、「本来備わっているはずの多くの性質を無視したせいで、量子力学における電子は、かなり常識外れの振る舞いをする。例えば、電子には小さな磁石としての性質があり、その向きはアップとダウンの2つしかないとされる。しかし、本来3次元のどの方向にもなり得るはずなのに、磁石の向きがなぜ2つに限られるのか? 実は、磁石の性質は電子の場が4つの成分を持つことに起因するのだが、場の変化が非相対論的な量子力学では扱えないため、安定な2つの共鳴状態を使って表記を簡略化したにすぎない。無限の変化を実現できる場の存在を黙殺して「状態は2つだけ」と頭ごなしに仮定したせいで、量子力学における電子スピンの説明は、ひどくわかりにくくなってしまった。」とあり、それでは、その中間の部分がわからないではないかと思いました。
それでも、途中で何が起きているのかわからなくても、トランジスタの設計などに応用できるというから不思議です。それで、量子コンピューターを作ろうとしているのですから、ますます不可思議な世界です。
下に抜き書きしたのは、第2章「生活と科学」に書いてありました。
そういえば、将棋の藤井聡太棋聖の対戦で、AIが93%の確率で負けるとの予想が出たとき、それを何度かひっくり返して勝利をおさめたときがありました。つまり、パソコンより強いということは、おそらく、この回り道思考のおかげかな、と思いました。この本には、「人間は、脳の部位という性質の異なる複数のハードウェアを、さらに別のハードウェアがコントロールするという重層構造によって、結論の妥当性を担保している。」とあり、脳の回路というのは、まったく複雑怪奇なようです。
(2025.4.25)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| この世界を科学で眺めたら | 吉田伸夫 | 技術評論社 | 2025年3月4日 | 9784297146924 |
|---|
☆ Extract passages ☆
脳が機能的に分化したさまざまな部位から構成されるため、人間の思考は、各部位からの情報が複雑に組み合わされることで形成される。これが、AI(人工知能)とは異なる人間の強みである。AIは、中枢神経のネットワークを模倣している場合でも、入力から出力に至る処理手順はカスケード的である。一方、人間は、これから何かをしようとするとき、別々の情報に基づくシミュレーションを何度も繰り返し、その内容を比較照合しながら、最終的に何をするかを(主に無意識的な過程を通じて)選び取る。ふつうのAIは、こうした複合的な処理は行わない。SFの世界では、国家を管理する中央コンピュータが少しずつ性質の異なる複数のマシンから構成され、その合議で最終決定を行うという設定がしばしば用いられるが、人間の脳は、こうした合議を自然に行う仕組みが、進化を通じて備わっている。
(吉田伸夫 著『この世界を科学で眺めたら』より)
No.2418『小さな悪魔の背中の窪み』
前回、『アタマはスローな方がいい !?』を読み、そういえば買っておいた文庫本のなかに、同じ著者の本があったはずと思い、探したのがこの本です。積んであるところから類推すると5~6年前に買ったもののようです。
たしか、血液型に関心があるというよりは、最初に書いてあったカッコウの托卵のことを知りたくて買っておいたようで、「カッコウのメスは宿主となる鳥の巣のありかをあらかじめ入念に調べておく。どこにどの営巣段階の巣があるかを頭に叩き込んでおく。というのもカッコウは、宿主が卵を産みつつある、まさにその時期を狙って自身の卵を産み込まなくてはならないからである(カッコウ
の宿主となる鳥は、たとえば一日おきに一卵ずつというような産み方をする。抱卵はすべて産み終えてから始める)。……オスとの交尾を終え、いよいよ準備万端整ったメスは、狙いをつけた巣の近くで辛抱強く待機する。何時間でも待っている。宿主が巣を離れるとその隙に、さっと飛び立ち、巣の縁に止まってまず卵を1~2個くわえて取り除く。卵をくわえたまま向きを変え、巣に総排泄腔を突き出し(その末端の部分は″産卵管″も兼ねている)、今度は自分の卵を一つ産む。巣に到着してから産み終えるまでの所要時間たるや、たった10秒足らず!」と書いてあるのを読み、それも自然のなりゆきで、カッコウが悪いわけでもないということも理解できます。
ところが、まだ目もよく見えない孵化したばかりのカッコウのヒナが、「頭をぐいと腹側に曲げ、左右の翼と両脚とを目一杯押し広げて踏んばっている。背中に載せているのは何と宿主の卵……。そうして巣の内側の壁をエイコラ、 エイコラとよじ登っているのである。卵を支える都合上、当然バックしながらの登攀である。カップの形をした巣の縁に翼が届くと、ヒナは力を込めてぐいとそれを掴む。卵を巣の外へ放り出すべく体を震わせ、最後の力をふり絞ってエイッと体を突き上げる。」といいます。
おそらくこれを見ていたら、自然の摂理などと考えるより、なんと残酷なことをするものだと誰しも思います。
この本の最初のところにこの様子が詳しく書いてあり、理解はできますが、なんとも自然というのは恐ろしいことをするものだというのが率直な印象です。
今の若い人たちは、身長がだいぶ伸び、特に足がするっと伸びています。著者は、それは体内から腸管寄生虫、つまり回虫やギョウ虫が駆除されたからだといいます。たしかに、それらの寄生虫は、臓器にいるわけで、その分が開くとすればその余分なものは手足が伸びるようになるというのは、たしかにありうる話しです。著者は、「ここ40年ほどの日本人の身長の伸び、特に足の長さの伸びは、大部分が回虫、ギョウ虫などの腸管寄生虫の消滅に関わっていると私は見ている。食生活の変化なども、もちろん無視するわけにはいかないだろうが。」といいます。
ところが、世の中はすべてが良い方に動くわけではなく、戦後の花粉症やアトピー性皮膚炎などの急増は、この腸管寄生虫が消滅したからではないかという説もあります。
それは、「いずれにしても人間は、今や回虫、ギョウ虫込みでこそ正しい人間なのである。免疫グロブリン(抗体として機能するタンパク質)の一種であるIgEは、そもそも寄生虫を駆除するためのものとして作り出されてきたのだという説がある。現代人がゼンソクや鼻炎、皮膚炎などのアレルギー性疾患に悩まされがちなのはIgEのせいであるとも言われる。つまり本来の日標である腸管寄生虫に行き当たらないIgEが、やむなく粘膜や皮膚に作用を及ぼしてしまうということらしいのだ。回虫やギョウ虫さえおなかに持っていれば、ゼンソクにも、花粉症にも、皮膚炎にも悩まされずに済むかもしれないのに。」と書いています。
なんとなく、あちらを立てればこちらが立たずのようですが、それだけ自然界というのは微妙なバランスの上に成り立っているということなのかもしれません。
下に抜き書きしたのは、第4章「他者の中に自己を見つける」のところにある「長生きするのはどういう人か」に書いてあったものです。
長生きするといえば、よくいわれるのが身体的・精神的な負担の少ない医療職や教育職、研究職などなどですが、ここで取り上げられている生物学者や画家も長生きの方が多いようです。ただ、これだって個人差はありますが、昆虫を追いかけたり、描き始めると夢中になりまわりを考えないという性格も長生きにつながるかもしれないと思いました。
そういえば、一昨年に放送されたNHKの『らんまん』のモデルになった植物学者牧野富太郎も、好きな植物のために一途に突き進んでいくような性格ですが、むしろそれが好評だったようです。
だとすれば、小児的などと嫌われる性格でも、長生きできるかもしれないと思うと、うれしくなります。
(2025.4.22)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 小さな悪魔の背中の窪み(新潮文庫) | 竹内久美子 | 新潮社 | 1999年2月1日 | 9784101238135 |
|---|
☆ Extract passages ☆
画家と生物学者の共通項は何だろう。それは、子どもに特徴的な性質を大人になってもまだ持ち続けているということではないだろうか。人にはお絵描きに夢中になったり、壁や床にまで落書きをして親を困らせる時期がある。トンボやバッタを追いかけ、転んだり泥だらけになったとしても一向に気にしない時期もある。ところがたいていの人はその楽しみをいつしか忘れ、面倒臭いとか服が汚れるから嫌だなどと感じ始めるのである。画家や生物学者というのは、いつまでもその楽しみを忘れない人々、大多数の人間に比べ非常にゆっくりとした展開で大人になっていく人々と言えるのではないだろうか。彼らの長生きの秘密はそのあたりにあるような気がするのである。
(竹内久美子 著『小さな悪魔の背中の窪み』より)
No.2417『アタマはスローな方がいい !?』
この本は、「週刊文春」の人気コラムを集めたものだそうですが、いろいろな質問にズバッと答えているところがおもしろかったです。オスたちの切実なる競争とか、メスたちの止まらない煩悩とか、ちょっと答えにくいものでも、ほとんど包み隠さず直球で返答するあたりは、読んでいてすっきりします。
この「遺伝子が解く!」という副題も、遺伝子には興味がありながらも、それですべてが決まってしまうと思い、知ってしまうのも怖いものがあります。たとえば、「言ってはいけない 残酷過ぎる真実」(橘玲著)もそうですが、否定したくてもできない現実を目の前に突きつけられたら、やはりへこんでしまいます。
でも、意を決して読み始めるとおもしろく、つい、最後まで読みました。なかでもおもしろかったのは、「一発で覚えるというのは一見、いいことのように思えるが、そうではない。たまたまそうだったという現象を覚えてしまうという危険があるのだ。一方で記憶を促進し、他方で記憶を抑制する。そうして様々なケースに当たりつつ、じっくり覚えるようにプログラムされているのだ――。呑み込みが悪いことが重要だった!」と書いてあり、それこそ題名の『アタマはスローな方がいい !?』と同じだと思いました。
なんでも早いほうがいいわけではなく、だからといって遅いのもいいわけではなく、なにごとも程度問題です。本を読むことでも、早く読み終わったり、何度も読み返しながら時間のかかることもあり、速読か精読かというよりも、本の内容にもよります。基本的には、わかるということが大切だと思っているので、時間云々の問題ではありません、
でも、このように考えさせるということでは、『アタマはスローな方がいい !?』のかもしれません。
また、「鳥の場合はまず、オスとメスとで体の大きさがほとんど違いません。さらには、メスによるオス選びというステップに力点が置かれるため、オスに美しさや求愛の歌、踊りなどの魅力が驚くほど進化していることになるのです。しかしそもそも、なぜメスがオスを選ぶのであり、その逆ではないのか?メスには産むことのできる子の数に限りがあるが、オスにはそれがない。条件さえ整
えば、無限といっていいくらいに子を残すことができる(逆にゼロということもある)。メスとしては同じ産むなら質のいい子を、ということでオスの質を慎重に見極める。オスはダメ元でどんどんメスに求愛する……。これが、メスがオスを選ぶという構図となって現れる次第。」とあり、今のあまりにも不倫に対する強烈な批判もほどほどにと思ってしまいます。
ただ、悪いことは悪いのですから、弁解の余地はないのですが、人生のすべてを否定するような報道はいかがなものかと思います。
下に抜き書きしたのは、第3章「家族、この深淵なるシステム」に書いてあったものです。
よく、似たもの夫婦という言葉がありますが、あまり似ていてもいいことばかりではなさそうです。だからといって、違いすぎては衝突することも多いのではないかと危惧します。だから、下に抜き書きしたのは、よく考えてみるとなるほどと思いました。特に今年の冬のように大雪ですと、その経験のない地域から来ると、なかには戸惑ってしまう方もいるようです。ところが同じ雪国育ちですと、いくら降っても春になればとけてしまうと考え、そんなに深刻には考えないでしょう。
そういえば、植物などもそのようで、「ヒエンソウは牧場などに一面に生えている草で、生えている場所の近さが遺伝的な近さとだいたい対応しています。ある研究者は一つの花に、それから様々な距離にある花の花粉をつけるという実験をしました。すると、 1メートルから10メートルくらいの花粉で最もよく実がついた。近すぎても、遠すぎてもいけない。ほどほどに似ていてちょっと違う、というのがよい結果に至るのです。」と書いてありました。
(2025.4.19)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| アタマはスローな方がいい !?(文春文庫) | 竹内久美子 | 文藝春秋 | 2008年1月10日 | 9784167270124 |
|---|
☆ Extract passages ☆
近すぎるのがいけないというのは周知の通り、近親婚による弊害があるから。
つまり、誰でも劣性の何らかの有害な形質についての遺伝子を数個は持っている(といっても染色体の片方に)。それと同じものを相手も、血縁が近いゆえに持っている可性が高い(もちろん染色体の片方に)。するとできた子はしばしばその有害な形質の遺伝子を二つ揃えてしまい、害が現れてしまうこともあるからなのです。
すると、遠すぎてもよくないとはどういうことか。
実は、生物たるものは家系ごとに何らかの戦略(繁殖戦略なり、生きていくための戦略なり)を持っている(戦略は一つだけではないだろうが、これを仮にA戦略とする)。遠い相手では戦略は全然違うだろう(B戦略とする)。
つまり、遠い相手とつがうとAもBも得意とする者も現れるが、AもBも不得意などっちっかずの者が現れることの方が多い。
その点、適度に近い相手とつがえば手堅い、というわけなのです。
(竹内久美子 著『アタマはスローな方がいい !?』より)
No.2416『三谷幸喜のありふれた生活 11 新たなる希望』
著者の三谷幸喜さんのことはほとんど知らなかったのですが、TBSテレビの「情報7daysニュースキャスター」で、司会の安住紳一郎アナとのちょっとかみ合わないこともあるコメントを聞き、それから意識的にみるようになりました。時間帯が土曜のよる10時からというのも、見る機会が増えた理由です。
少しずつなれてくると、わざとかみ合わないようなコメントをすることもわかってきて、この本を読んでから、それもわかるような気がしてきました。
それにしても、この本を書いている間の仕事データを見ただけでも、舞台や映画、テレビドラマなど、まさに八面六臂の活躍です。しかも、それぞれに話題作ばかりで、その源泉がここにあるような気がしました。
たとえば、舞台「ベッジ・バートン」で狂言師の野村萬斎さんがロンドン留学時代の夏目漱石の役で出ていて、それもプロデューサーの北村明子さんが「背広を着た野村萬斎が見たい」の一言で決まったそうです。この本には、「相手が台詞を言っている時、萬斎さんは微塵も動かず、まるで仏像のように佇んでいる。もう少しリアクションをして貰えますかとお願いすると、「狂言の世界では相手が喋っている時は、大抵の場合じっとしているのです」と表情を変えずに彼は言った。同じ演劇でも、狂言と僕のやっている芝居とでは、これほどまでに差があるのだ。萬斎さんにとって今回の稽古場は、五百年前から現代にタイムスリップして来たお公家さんに匹敵するくらい、カルチャーショックだったに違いない。顔合わせの時、「今回はニュー萬斎を作り上げましょう」と彼と約束した。だから、僕としてもとことん粘った。苦労した甲斐あって、舞台上の萬斎さんは実に新鮮でチャーミング。萬斎さん以外の誰も演じることの出来ない、若き文豪の姿がそこにある。」と書いています。
それでも、萬斎さん自身もロンドンに留学していた経験があり、そのときの体験談も少しは物語りに反映されているそうです。
やはり、狂言の世界と現代の演劇の世界では、相当な違いはあると思いますが、それを乗り越えてしまうのですから、監督も役者もすごいと思います。むしろ、その違いがおもしろさをもたらしているのかもしれません。
そういえば、著者がチェーホフの「桜の園」を演出したときの話しですが、そのチラシの表には白い衣装の役者さんの写真を使い、裏にはチェーホフに扮した著者が舌を出してふざけている写真を載せたそうです。そのときに、特殊メークの江川悦子さんにお願いし、衣装も実際に当時のロシア人が着ていたものを見つけてもらい、こりに凝ってカメラの前に立ったといいます。そのときの思いですが、「本人になりきることで、ほんの少しだけ彼に近づけたような気がする。おかげで戯曲の読み込みも深まった(と勝手に思っている)。僕よりもチェーホフに造詣の深い方は、日本中に沢山い
らっしゃると思うけど、ここまでチェーホフ自身に変装した研究家は、そういないはず。「変装」は、作品に対する僕なりのアプローチなのである。」と語っています。
おそらく、チェーホフの研究家がチェーホフ自身に変装しようとは考えもしないでしょうが、それを実行するのが三谷幸喜さんなのです。
下に抜き書きしたのは、「降り出した幸運の雨」のなかにあったものです。
このときのロケは長野の山の中で、準備の途中で雨が降りだして、なかなか止む気配がなかったそうです。そこで、チーフ助監督の片島さんが撮影の中止を決定し、機材の撤収をはじめたときに、台本の第1稿のト書きに「雨が降っている」と書いたことを思い出し、人工的に雨を降らせるのは相当なお金がかかるということで諦めカットしたそうです。
たまたま雨があったことで、それを思い出し、まさに幸運の雨になったという下りです。
役者もそうですが、何ごとにも運不運はあるもので、著者には運を引き寄せるものがあるのではないかと思いました。
(2025.4.16)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 三谷幸喜のありふれた生活 11 新たなる希望 | 三谷幸喜 | 朝日新聞出版 | 2013年8月30日 | 9784022511072 |
|---|
☆ Extract passages ☆
慌てて片島さんを呼び戻す。「撮影しましょう!」。彼は目を丸くしていた。「当初の予定ではこのシーンは雨だったんです。これこそ、僕が撮りたかったシーンなんです!」
早速、待機中の深津さんに状況を説明 「雨に濡れるのは嫌だわ」と言われたらどうしようと思ったが、「やりましょう。やるべきです!」と、逆に力強い言葉を頂く。
急きょ撮影開始。それは、やんで欲しいと願っていた雨が、「やまないで欲しい雨」に変わった瞬間でもある。こうして、葉っぱのついた枝(美術スタッフが見つけてくれた)を手に、雨の中をとぼとぼ歩くエミの姿は、永遠にフィルムに焼きつけられた。
びしょ濡れの深津さんを見ながら、自分が思い描いていた映像を、(それもかなり安上がりに)撮影することが出来た幸運に、僕は感謝した。
この映画が、何かに守られていると最初に感じたのは、その時だ。
(三谷幸喜 著『三谷幸喜のありふれた生活 11 新たなる希望』より)
No.2415『新版 知的創造のヒント』
外山滋比古が亡くなられたのは、2020年7月でしたが、私が講談社現代新書の『知的創造のヒント』を読んだのは、だいぶ前です。
その後、ちくま学術文庫として文庫化され、今回はその新版だそうです。そこで、たまたま図書館にあったのを借りてきたのですが、記憶もおぼろげで、しかも活字が大きくなり、とても読みやすくなっていました。
そして、「特別講義」が加わり、そのなかに「おしゃべり会をひらく」という項目があり、「人生において「ものを考える」ことの楽しさ、面白さを実感するには、そういう志を同じくする仲間と楽しく、お互いを尊敬し合いながら意見をぶっかり合わせて、そこで今まで意識しなかった形で頭を刺戟した方がいい。本を読んだり、学校で講義を聞いたりすることはもちろん価値がありますが、もっと体全身で考えることを実感するのが何よりも大事なのです。」とあり、そういえば学生のころは、喫茶店や自分たちの部屋で語り明かしたことを思い出しました。おそらく、今の学生たちはそんなことはしないようで、すぐスマホで調べ、それで終わりにしそうてす。
この本にあるように、ものを考えることの楽しさは、それだけでは感じられないと思います。そのとき、語り合った同期の集まりが4月10日に中大駿河台キャンパスの19階にある「グッドビューダイニング」でありましたが、その会でも、若い日々に語り合った同期たちと楽しく語り合いました。
この本のなかに、何度か出てくる欧陽修の「三上」というのがあり、私もそのきっかけが何度もありました。この「三上」というのは、「精神を自由にするには、肉体の一部を拘束して、いくらか不自由にする方がいいらしい。中国の宋時代の詩人、欧陽修が三上、馬上・枕上・厠上を妙案の浮ぶ場所としてすぐれていると考えたのも、それぞれ、完全に自由にならない立場にあるからだといえそうである。馬上にしても、枕上にしても、トイレの中にしても、ほかにすることとてないが、そうかといって、別にほかのことをするわけにもいかない。そういう状況でものを考えるのも、″ながら族"の一種である。」といいます。
私も馬に乗ったのは一度しかないので、それはわかりませんが、寝ながらとかトイレに入ったときとか、意外とおもしろい考えが浮かびます。ただ、すぐに忘れてしまうので、トイレにもメモ帳や筆記具などを用意してメモるようにしています。
また、どちらも人に邪魔されないところなので、それがいいのかもしれないとも思います。
私は一人旅が好きですが、人に煩わされないことも知的創造には大切なことだと思っています
下に抜き書きしたのは、第1章「忘却のさまざま」のなかの「カタルシス」に書いてありました。
ここでいうカタルシスというのは、文芸作品、特に悲劇などを鑑賞して、そこに繰り広げられる世界への感情移入が行われることで、日常生活の中で抑圧されていた感情が解放されて快感がもたらされることだそうです。つまり簡単にいうと、浄化です。
この本には、歩くことだけでなく、お風呂に入ることもカタルシス効果が高いと書いていますが、たしかにのんびりと入浴していると開放感があります。頭でいろいろと考えているのがつまらないことのように思うことだってあります。
下に抜き書きしたなかに、タブラサラという言葉がありますが、これはラテン語の「tabula rasa」で、「何も刻まれていない石板」とか「白紙」を意味する言葉だそうです。つまり、よく頭を真っ白にして考えるということのようです。そういれば、いろいろなことから開放されて、自由に考えられるということです。
私も若いときに小町山自然遊歩道を造り、他を歩けなくなったときに自分の好きな自然の植物たちを眺めながら歩きたいと思いました。それがコロナ禍で不要不急の外出ができなくなったときにはとても重宝しましたが、ここを歩くだけでも足腰の痛みすら忘れられるような気がします。
(2025.4.13)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 新版 知的創造のヒント(ちくま文庫) | 外山滋比古 | 筑摩書房 | 2025年2月10日 | 9784480440020 |
|---|
☆ Extract passages ☆
自由な考えが生まれるには、じゃまがあってはいけない。まず、不要なものを頭の中から排除してかかる。散歩はそのためにもっとも適しているようだ。ぼんやりしているのも、ものを考えるにはなかなかよい状態ということになる。勤勉な人にものを考えないタィプが多いのは偶然ではない。働きながら考えるのは困難である。歩くのは仕事ではない。だから、心をタブララサにする働きがある。時間を気にしながら目的地へ急ぐのでは、歩いても思考の準備にはならない。
ものを考えるには、適当に怠ける必要がある。そのための時間がなくてはならない。
(外山滋比古 著『新版 知的創造のヒント』より)
No.2414『裏道を行け』
副題が「ディストピア世界をHACKする」で、ディストピアとは何かを調べてみると、ディストピア(dystopia)とは、理想的な社会の対義語で、不幸や抑圧が支配する未来社会を描いた概念だそうです。つまり、ユートピアの反対の反理想郷や暗黒世界ということです。
また、ハックするということは、この本でハッカーの説明をしていますが、「1990年代のハッカーであるポール・グレアムは、並はずれて優れたプログラマーと、コンピュータに不正侵入する者が、ともに「ハッカー」と呼ばれるのは間違ってはいないという。ハッカーとは、「コンピュータに、良いことであれ悪いことであれ、自分のやりたいことをやらせることができる者」のことなのだ。何かをとても醜い方法でやったら、 ハックと呼ばれる。しかし、何かを素晴らしく巧みな方法でやってのけてシステムをやっつけたなら、それもハックと呼ばれる。なぜなら、この2つには共通点があるから。それは、両方とも「ルールを破っている」ということだ。ハッカーとは、常識やルールを無視して「ふつうの奴らの上を行く」者たちのことなのだ。」といいます。
たしかに、初期のハッカーは、自分のコンピューターに対する知識の発露だったり、人を驚かすことだったりしていましたが、最近のハッカーはお金もうけの手段になっているような気がします。だいぶ昔に読んだ本のなかに、とんでもない大金持ちはお金に執着することがなくなると書いてありましたが、この本のPART5「世界をHACKせよ――どうしたら「残酷な現実」を生き抜けるか?」にもその例がいくつか載っています。
ただ、今の個人主義的な生き方が続けば、「社会のリベラル化が進み、誰もが「自分らしく」生きるようになれば、教会や町内会のような中間共同体は解体し、一人ひとりがばらばらになっていく。これによってわたしたちは法外な自由を手にしたが、それは同時に、自分の人生のすべてに責任を負うことでもある。リベラルな社会では、人種や身分、性別や性的指向などにともなう差別はなくなるはずだから、最終的には、あらゆることが「わたしの選択」の結果、すなわち自己責任になるだろう。誰もが自由に生きられる社会では、至るところで「わたし」と「あなた」の利害が衝突する。」と書いてあり、まさに現代が直面している課題でもあります。
たしかに自由になればいいこともたくさんありますが、それぞれに勝手に振る舞えば、困ったこともありうるわけです。そこに、自由の限界がありそうです。
民主主義だってそうです。みんなの意見を尊重するとはいうものの、みんなの意見を聞いてばかりいては、ものごとは進みません。世の中はきんきんの課題もあります。だから、どこかで打ち切らなければ進むことはできません。
この本の購買スイッチのところで、おもしろい話しが載っていました。1970年にデンマークで生まれたマーティン・リンストロームという人が、大規模な実証実験で「購買スイッチ」を探そうとしたそうです。そのひとつが、「コカ・コーラとペプシコーラを商品名を教えずに試飲させると、ペプシの方が美味しいとの答えが多数になるが、商品名をあらかじめ伝えると結果は逆になる。このときの脳をスキャンすると、(美味しさの刺激を感知する)腹側被殻だけでなく、内側前頭前皮質への血流の増加がみられた。この領域は、高度な思考や認識を司る部位だ。リンストロームは、これがブランドのちからだという。コーラの歴史、ロゴ、色、デザイン、匂い、子どもの頃の思い出、長年のテレビ広告や印刷広告などがサブリミナルで被験者の感情を揺さぶり、「ペブシの方が美味しい」という理性を打ち破ったのだ。」と書いています。
でも、私の場合は、学生のころからコカ・コーラを飲んでいるので、ブランドのちからというよりは、懐かしさではないかと思っています。コーラは、やはり、この味でなければということです。
もちろん、いろいろな考え方もあるでしょうから、この購買スイッチだって、たくさんあるのではないかと思います。
そういえば、最近はとくにオンラインカジノなどの問題も出ています。もちろん、日本では禁止されていますが、簡単に海外にアクセスできるので、つい手を出してしまう人もいるかもしれません。しかし、これも依存症になる確率が高く、テレビで伝えられているようなことが起きてしまいます。どうしても、若いときには好奇心もありますから、ネット時代には要注意です。
下に抜き書きしたのは、PART5「世界をHACKせよ――どうしたら「残酷な現実」を生き抜けるか?」に書いてあり、印象に残りました。
やはり、自分でコントロールできないことを、いくら考えてもらちはあきません。だとすれば、考えないことも大切で、そこから「無」の教えが起こるのかもしれません。
(2025.4.10)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 裏道を行け(講談社現代新書) | 橘 玲 | 講談社 | 2021年12月20日 | 9784065265703 |
|---|
☆ Extract passages ☆
エピクテトスは帝政ローマ時代のギリシアで奴隷として生まれ、その後、解放されて哲学を講ずるようになった。
エビクテトスの教えが現代的なのは、政治に参加して社会を変えるのではなく(当時のローマでは、哲学者が「改革」を論ずることは許されなかった)、個人の内面の幸福や、より善く生きることを説いたからだ。
エピクテトスは、自分がコントロールできるものを「権内」、自分でコントロールできないものを「権外」と峻別し、権内のものごとだけに集中すべきだとする。……
エピクテトスにとっての「自制」はたんに我慢することではなく、逆境においても権外のものごとを無視することで安寧を獲得する技術なのだ。
ストア哲学では、富や健康、病気や貧困なども権外で、善悪とは無関係とされる。富(自分でコントロールできないもの)に執着していては幸福を手に入れることはできないとして、こころ(内面)のゆたかさを説く思想はブッダの教えと重なっている。
(橘 玲 著『裏道を行け』より)
No.2413『忘れ得ぬ人 忘れ得ぬ言葉』
この本は、月刊誌「致知」に連載された「忘れ得ぬ人 忘れ得ぬ言葉」で、2018年1月号から2024年2月号までのなかから、46人分を抜粋し、加筆修正を加えたものだそうです。
私もときどき「致知」を読むのですが、そんなに熱心な読者でもないので、この連載もあちこちしか読んでいなかったのですが、こうして1冊になると、読み応えはあります。つい、時間を忘れて、読んでしまいました。
たとえば、犬養道子さんとの話しで、犬だか猫だか忘れてしまったそうですが、ドイツの住んでいたときに、たまたまそのペットが死んでしまったので、かわいがっていたこともあり自宅の庭の樹の下にそっと埋めたそうです。しかし、ドイツでは犬を庭に埋めることは違法だそうで、翌日に警察がきたそうです。たまたま新型コロナウイルス感染症が大流行し、世の中がギスギスして相互監視のような雰囲気になってきたので思い出したようです。「ドイツの市民は、法を守ることに厳格である。自動車を運転していても、ちょっと交通規則に違反する車があると、周囲の車が一斉にクラクションを鳴らして注意したりする。車を洗わずにいると、近所の人から注意されることもあったそうだ。そんなこんなで、いささか気が重くなってフランスに引っ越した。フランスもある意味では厳格なところのある国だが、お互いの私生活には干渉しない自由さがあって、気持ちがうんと楽になったのだそうだ。」と書いています。
たしかに、法律を守るということは大切ですが、なんでも行き過ぎると社会全体が窮屈になってしまいます。この本の星野哲郎さんとの話しにも出てきますが、歌も芝居も「ダレ場」が必要だというのはうなづけます。
また、石岡瑛子さんの話しもおもしろく、NHKの新日曜美術館で3月9日に放送された「時代のアートの伴走者として小池一子 89歳の颯爽」とも相似たような印象を持ちました。この本のなかで石岡さんは、「十人のスタッフを選ぶとき、もっとも優秀なメンバーの中に一人か二人、どうということのない平凡な人物を加える。ときには変人と思われる人物を選んだりもする。「優秀な人ばかりで作りあげた仕事は、百点はとれても百二十点はとれない。均質な才能を組み合わせて創りだす仕事には限界があるような気がする。ちょっと異質なものが混ざっていたほうが、思いがけない飛躍があるんじゃないのかな。だからわたしは、大きなプロジェクトのスタッフには、何人かちょっと変った人を加えることにしてるんだ」」と話していて、なるほどと思いました。
とくにデザインやアートの世界は、杓子定規ではなんともならないものがあります。むしろ、型破りぐらいでないと、新しいものは生まれません。だから、つねに新しいアーティストがもてはやされるのです。
だからといって、新しさばかりでは息が詰まります。むしろ、ある意味、見慣れたものやありふれたものも大切です。その道一筋に生きてこられた人たちもすごいと思います。そういえば、洋画家の野見山暁治さんと著者が福岡の九州文化協会の催しのときに会って、「なにか日頃、健康のためにおやりになっていることが、おありなんですか」と聞いたときの返事が、すこぶるシンプルでした。
それは「絵描きさんにしても、詩人、小説家にしても、持続して描く、または書くことが何よりも大事だということを、あらためて教えられたのである。アーチストも、年をとると創造力がおとろえてくるのは自然の理だ。しかし、それでもなお日夜、仕事を持続することが必要なのである。持続すること。若い頃のみずみずしい才気は失われても、それにかわる何かがそこにはあるのではないか。」ということで、102歳まで生きられた画伯のシンプルさに、納得しました。
下に抜き書きしたのは、林達夫さんとの対談で聞いた「その土地に根ざしたものより、移植されて育った植物のほうが強い」に書いてあった言葉です。
この話しは、1960年代の終わり頃のころで、林さんとある出版社の人気のない編集室でのことだったそうです。
私も若いときから植物を育てるのが趣味でしたから、この意味するところはよくわかります。実際にも、たとえ海外からもたらされた植物でも、まったく違う日本の環境のなかでたくましく育っているところを見ると、なるほどと思います。
(2025.4.7)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 忘れ得ぬ人 忘れ得ぬ言葉(新潮選書) | 五木寛之 | 新潮社 | 2025年1月25日 | 9784106039201 |
|---|
☆ Extract passages ☆
「人は、その土地に根ざしたもののほうが強いと思っているが、そうではない。移植されて育った植物のほうが強い場合が多いんだ。人間もそうだね。ロシアの国民詩人の第一人者プーシキンの曾祖父のルーツはエチオピアだ。英文学のコンラッドはポーランドからきた。デラシネ(故郷から離れた人)が文化を創るんだよ」
(五木寛之 著『忘れ得ぬ人 忘れ得ぬ言葉』より)
No.2412『私の同行二人』
副題が「人生の四国遍路」で、そういえば、私も2017年2月28日から3月15日まで、四国八十八ヵ所を遍路したことを思い出しながら読みました。
私の場合は夫婦二人での巡礼なので、自宅から車で四国まで行き、それでまわったのですが、著者は歩き遍路ですから、本格的です。しかも、今回で2回目ということで、1回目のことなども思い出しながら書いています。
おそらく、歩き遍路で一気にお詣りしたほうが印象には残ると思いますが、それをするには、まだは歩き通すだけの体力が必要です。また、約2ヶ月間ぐらいの期間が必要なので、それも工面できないと難しいと思います。それと、やはり、どのような遍路をするかによって違ってはきますが、先立つものも必要です。少なくても、これだけのものがなければ、現在のお遍路はできません。だとすれば、お遍路できることも幸せなことだと改めて思いました。
それにしても、著者が聞いた山の宿の女将さんの「お遍路さんはベテランも若い人もみなさん前身湿布だらけですよ」という話しには、なるほどと思いました。私も、旅行に出かけるときには必ず湿布をもっていきますが、歩くというのは、やはり大変なことです。
この本は、1~12までは新潮社Webマガジン「考える人」に連載されたもので、13~23までは、新たに書き下ろされたそうです。
よく、四国八十八ヵ所では、「同行二人」といい、いろいろなところにも書かれています。これは、「遍路は来るものを拒まず、弘法大師は誰にでも寄り添う。そして囁き続ける。ある時は風となり、雨となり、花となり、木の実となり、月となり、星となり、ある時は道行く人の口を借りて、呼びかけ続ける。それらの"サイン"を受け取れるかどうかは、こちら側にかかっている。私たちが気づかなくても、大師が諦めることはない。それが同行二人なのだ。」と著者も書いていて、私も金剛杖に書かれたその文字をときどき眺めながら歩きました。
そうすると、ナビだけではわからなった道筋がおぼろげながら見えてきて、そちらの方に進むと案内書にも書いてある道に出ることもありました。
遍路をすると、札所も大事なことは当たり前ですが、そこにいたる道筋も楽しく、石仏や花を見つけたり、優しい春風を感じることもありました。そういえば、山頭火の「山へ空へ摩訶般若波羅密多心経」という句が載っていて、私も観音巡礼でも持ち歩いています。
著者は、「札所と札所の間の"辺地"こそが"遍路″だ。遍満する仏の意思を感受するには、辺地の自然のなかを歩き回らなければならない。そう、鳥の声にも、花にも、星の瞬きにも、小さな蜘蛛にも、仏の意思や宇宙の真理が顕れているのに。多くの人がその"サイン"を見逃している。スーザンはそこがよくわかっているのだ。」と書いてます。
スーザンというのは、遍路で出会った方で、彼女は、「日本人の多くが未来のことを心配し過ぎている気がするの。今日の昼食のこと、先々の宿の予約のこと、老後のことと、心配ばかりしている。もっと″いま"を生きないと。この鳥の声! こんなに素晴らしいのに、なぜみんな急いで歩くの?」と話したことからの言葉です。
そういえば、私がネパールのカトマンドゥに泊まっていたときに、ほとんどの日本人は朝早くから出かけて、夕方遅くに帰ってきます。ところが、とくにヨーロッパの人たちは、朝はゆっくり出かけて、お昼過ぎにはホテルに戻り、芝草の上でのんびりと寝転がったりしていました。1日中、イスに座り、本を読んだり、昼寝をする人もいました。それを見ていて、私も旅先でのんびりすることを意識するようになりました。
それと、どうしても旅行に行くときの荷物が多くなりすぎる傾向があります。この本のなかに、ある野宿のお遍路さんが、「荷物の量は不安の量。あなたが不安と戦って不安を捨てることができたとき、荷物は減る……」と出会った人に聞き、なるほどと思ったそうですが、これはたしかにそうかもしれないと私も思いました。
下に抜き書きしたのは、7「カイロスと呼べる自分だけの時間」に書いてありました。
この洞窟というのは、住居として使った御厨人窟と行場として使った神明窟で、もともとは海岸端にあったのですが、今ではその間に道路ができてしまいました。私が訪ねたときには、落石が多いことから、立ち入り禁止でしたが、この本によると、落石防護用の鉄製の屋根が新設されたことから、入れるようになったそうです。
この御厨人窟の奥には、大国主をまつる五所神社が鎮座していて、空海はここで修行し悟りを開いたとされています。たしかに、ここからは真っ青な海と空が見えるので、名の由来もここではないかと思います。
また、ここに出てくる蟹というのは、神明窟の祠の前にいた赤い蟹で、一匹だけぷくぷくと泡を吐きながら海の方を向いてじっとしていたそうです。
(2025.4.5)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 私の同行二人(新潮新書) | 黛 まどか | 新潮社 | 2025年1月20日 | 9784106110733 |
|---|
☆ Extract passages ☆
太平洋に突出した室戸岬の風雨にさらされた洞窟は岩を剥落させながら、ひたすら空と海に対峙する。この地で空海は斗藪(修行の一種)しつつ、造化に従い、海や山の恵みを得て自給自足で暮らしていたはずだ。隔絶されたこの地では生きることが即ち″行″ではなかったか。「一枚に逍遥し、半粒に自ら得たり」(「三教指帰』巻の下・仮名乞児論)。生きることのすべてが自然の活動と共にあり、空海の感覚器官(六根)は研ぎ澄まされた。
「五大にみな響あり、十界に言語を具す」(『声字実相義』)。自然の一部と化した空海。彼とその他を隔てるものはなく、融合していた。洞窟をおとなう蟹のつぶやきは仏のつぶやきそのものだった。彼は蟹に"仏性"を見たに違いない。蟹のつぶやきも、波音も、星の煌めきも、仏の言葉であり、あらゆるものが真理を伝えようとしていた。この隔絶された小さな洞窟には仏の声が犇いていただろう。
(黛 まどか 著『私の同行二人』より)
No.2411『妄想気分』
たまたま、この本を見て、作者が以前書いた「博士の愛した数式」という映画を観たことを思いだし、懐かしくなり、この本を読むことにしました。
この本に書いてあるプロフィールを読んで初めてわかったのですが、この「博士の愛した数式」は読売文学賞と第1回本屋大賞を受賞したそうで、私に撮っても思い出深いものでした。しかし、著者は、これを書いた後の心境を、「慣れない分野を題材にして書いたからか、疲れが出て唇が腫れた。唇の奥に潜んでいるウィルスが、時折むくむくと盛り上がって、唇をとんでもない形に変えてしまうのだ。最初に、口のまわりが妙に緊張してくる。そのうち、薄い皮の下でうごめくウィルスたちの動きが、伝わってくるようになる。彼らも焦っているのが分かる。「おい、こんなくたびれた小母さんに巣食っていて大文夫か?」などとささやき合っている。「どうぞ心配しないで下さい」と言ってなだめるが、もう手遅れだ。押し合いへし合いしながら、唇の皮を持ち上げ、時には亀裂を生じさせ、半透明の体液を染な出させる。」と書いてあり、いくら好きで作家になったとしても、創作をするというのは大変なことだと感じました。
それと同時に、慣れない分野を題材にして書けたり、疲れをさまざまなイマジネーションで表現したり、やはり作家になれる人はすごいとも思いました。
今でこそ、新型コロナウイルス感染症にさんざん痛めつけられたことで、ウィルスという存在も身近に感じられますが、この本が出たのは2011年ですから、おそらくインフルエンザやノロウイルスなどが念頭にあったと思いますが、なんともウイルスのうごめきまで伝わってくるかのようです。
そういえば、「フンコロガシの心の中へ」では、「ファーブルの視線の先でフンコロガシは、か弱い後ろ足を使い、皆から見捨てられたフンを集めて回る。誰に命令されたわけでもないだろうに、一心に、修行するように、大きなフンを転がしてゆく。」と書いていて、私も昔、フンコロガシの映像を見たときのことを思い出しました。まさに掃除人の風格さえ感じたものでした。
この本を読みながら、そういえば最近は私も……、というところもあり、共感を持ちました。十人十色とはいうものの、人は似たところも多いのではないかと思います。
たとえば、「頭にははっきり姿が浮かんでいるのに、名前だけがどうしても口から出てこない、という経験をすることが、最近少しずつ増えてきた。その場にいる誰かがうまくこちらの気持を察知し、代わりに名前を言ってくれるとすっきりするが、結局思い出せないまま、いつしか誰の名前を何のために思い出そうとしていたかさえ、忘れてしまう。」と書いてあり、私の場合は、その人の名前を思い出すまで、何となく落ち着かなくなってしまいます。
植物名なら、今でもすらすらと出てくるのに、なぜ人の名前が出てこないのか不思議ですが、いくら考えても出てこないのですから仕方ありません。むしろ、必死になって考えると、ますます出てこないような気がします。
そして、まったく関係ないことをしていると、フッと出るから、また不思議です。
下に抜き書きしたのは、第5章「自著へのつぶやき 書かれたもの 書かれなかったもの」のなかの「おとぎ話の忘れ物」に書いてありました。
長く生きてくると、いろいろなトラブルに巻き込まれる経験もしますが、このようにトラブルのおかげで小説が出来上がることを知り、まさに必要なトラブルだったと思いました。やはり、このように考えれば、トラブルも明るく前向きにとらえられるような気がします。
(2025.4.2)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 妄想気分 | 小川洋子 | 集英社 | 2011年1月31日 | 9784087813715 |
|---|
☆ Extract passages ☆
樋上公実子さんの絵が既に出来上がっていて、それに小説を書く約束になっていた。編集者が原画を持って来てくれたのだが、何とホテルのトイレに忘れてしまった。無事、絵は戻ってきてほっとした。このトラブルのおかげで、タイトルと物語の全体像が決まった。あれは、物語の神様のいたずらだったのだろうか? 編集者は胆を冷やし、寿命を縮めたようで気の毒だったけれど、この本のためにはどうしても必要なトラブルであったのだ。たぶん。
(小川洋子 著『妄想気分』より)
No.2410『私のまんまで生きてきた』
たまにテレビなどで著者を見ることがありますが、あの大きな声にはちょっと驚きます。しかも大きいだけでなく、騒々しいような音質で、長く聞いていると疲れてきそうです。
本人も、この本の「はじめに」のところで、「声がでかい人に、悪い人いないと思いませんか? 陰湿な人は、声が大きいなんてことないでしょ。やっぱり声が大きくて元気がある人のほうが、しゃべってて気持ちがいい。よく注意されたけど、声が大きいって私はいいことだと思うなあ。」と言ってしまうのですから、やはり、そのまんまのようです。
それでも、料理もそうですが、子育てもそのまんまでも、理にかなっていることが多く、だからこそ、テレビなどでも重宝されるのかもしれません。たとえば、子育てにしても、子育ては親育てと同じで、「私は息子のおかげでずいぶん勉強をした。人間的にもうんと成長したような気がする。あんなにわがままだった私から、わがままがとれて、今まで持ち合わせていなかった思いやりや、やさしさが生まれてきた。息子に対する思いやりがきっかけになって、誰に対してもその人の気持ちをわかろうと努めるようになった。結局、子育てというものは、親育てなのだと思う。」と書いていて、声が大きいだけではないと思いました。
このちょっと先に、忙しくてなかなか子どもの野球の試合の応援に行けなかったそうで、そのことをチームメイトのお母さんからの電話でたまには見に行ってあげたらというようなことを言われたと書いてありました。たしかにそうかもしれませんが、息子さんに直接聞いたら、お母さんが見に行かなくてもさびしくなんかないと答えたそうです。
私もそのような経験があり、試合は土日曜の忙しいときしかないので、ほとんど行けませんでした。ところが、たまたま時間がとれそうなので行こうかと尋ねたら、「たまに来られると、むしろ緊張するから来なくていい」と言われて、とうとう1回も行きませんでした。おそらく、わが家の仕事をわかっていたから、あのような返事をしたのかと重いながら、この文章を読みました。
最近の子育ては、あまりにも手をかけすぎて、親子ともに疲れているのではないかとさえ思います。みんながしているからとか、情報によるとこのようにしなければならないとか、それに振り回されているような感じさえします。十人十色、いろいろなやり方があるので、いっしょに取り組めば、子育ても、親育ても、同じようなものです。
それにしても、「和田さんって、私よりも私のことを知ってるみたいで、玄関をガチャガチャッて開けたとき、私が沈んだ声で「お帰んなさい」なんて言うと、靴を脱ぐ前に、「どっか食いに行く?」って言う。私が疲れてることがわかるのね。もうありがたくてありがたくて。食べに行ったあと「ああ、おいしかった」って私が言うと、「レミのごはんのほうがおいしいよ」って言われちゃうの。」と書いてあり、まさに似た者夫婦だと思いました。
でも、それが長続きする夫婦かもしれません。やはり、お互いに思いやってるところがいいですね。
下に抜き書きしたのは、「おわりに」に書いてあったものです。
最初に「はじめに」のところにあったものを引用したので、やはり、この流れでいくと、「おわりに」で終わらないと締まりません。
そして、最初から最後まで、和田さんの話しが中心です。しかも、阿川佐和子との対談で、「和田さんは私のために生まれてきたのよ」と言い放ちますから、本当のいい夫婦だったと思います。これも、やはり、胃袋をつかまれるって、本当に幸せなことなんだと思いました。
(2025.3.30)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 私のまんまで生きてきた | 平野レミ | ポプラ社 | 2024年11月11日 | 9784591183793 |
|---|
☆ Extract passages ☆
だいすきな和田さんが亡くなって、もう5年も経っちゃった。今でも和田さんのことを考えない日はありません。会いたくて会いたくてたまらない日もある。そんなときは渋谷区の中央図書館に行くんです。そこの4階に、和田さんが書いた本とか、装丁した本、蔵書がたくさん置いてある。事務所で使ってたテーブルも椅子もある。「和田誠記念文庫」っていう場所なのね。そこで和田さんの本を開いていると心がすーっと落ち着いていくの。また和田さんに会えたような気持ちになるんです。本にはすごい力があるんだなあ。
(平野レミ 著『私のまんまで生きてきた』より)
No.2409『花と夢』
この本は、アジア文芸ライブラリーの最初の1冊で、この企画は、「文学を通じてアジアのこれからを考える」をテーマにしているそうです。
たしかに、アジアの作家の本を読む機会はほとんどなかったので、2024年4月より始まったアジア各地の同時代の文学作品を読めることは、たいへん意義のあることだと思います。
さて、この本の著者のツェリン・ヤンキーは、中国チベット自治区シガツェで1963年に生まれ、両親が忙しいこともあり語りのうまい祖母に育てられたそうです。ラサのチベット大学に在学中に『チベット日報』に投稿した小説が掲載されたり、その後も数々の賞を受賞したそうですが、教師の仕事が忙しく、しばらくブランクがあり、この長編小説『花と夢』を7年がかりで完成させました。
中国でチベット自治区ラサで刊行されたのが2016年で、特にコロナ禍のときには、インターネットにアップロードされたこの小説の朗読に耳を傾ける人も多かったといいます。まさにこの小説は、そのラサを舞台にして、ナイトクラブ「バラ」で働く、菜の花、ツツジ、ハナゴマ、プリムラという源氏名の4人の女性が主人公で、裏通りにある小さなアパートで共同生活をしながら支え合い生きる姿を描いています。
そういえば、この本にも出てきますが、世界最高所を走る青蔵鉄道に私も乗ってみたくて、中国の友人と1989年6月に行く計画を立てていたのですが、残念なことにその6月4日に天安門事件が起き、多数の一般民衆や解放軍兵士が死傷しました。もちろん、このようなときに行けるわけはなく、延期はしたものの、そのままになってしまいました。
今でも、本やテレビで青蔵鉄道が出てくると、つい引きつけられてきます。たとえば、西寧からゴルムドを経由し、少しずつ標高を上げて青海省とチベット自治区の境にある唐古拉峠(標高5,072m)を越えるところの山並みやヤクや羊が群れをなす大草原などを見ると、行ってみたいと思い続けています。そんなチベットを豚にした小説ですから、読んでみたくなるのも当然です。
しかし、今のチベットはだいぶ違うようです。まさに、ブラッド・ピット主役の映画、『セブン・イヤーズ・イン・チベット』を思い出しました。とくに、チベット僧が丹念に製作していたマンダラを蹴散らすようにして歩く解放軍を思い出し、それとは状況がまったく違うとはいえ、4人がみな性暴力やハラスメントなどを受けながらも生きていく姿に大きな力によって変わっていくことに悲しみを感じました。
もちろん、小説ですから、現実とは違うでしょうが、それでも今も輪廻転生や業報思想が生きていることを思い、人ってそんなに簡単には変われないということも感じました。あの手持ちのマニ車を回しながら歩く人たちや、額を土に打ち付けるように体全部を大地に投げ出す五体倒置を繰り返す姿などを私自身もネパールなどで見て、その信仰心の篤さを思い返しました。
それでも、「第6章ハナゴマ」のところで、ツツジがセラ寺の巡礼路を一歩一歩上がっていくことで、周囲の環境によって浄化されていくような姿に、これで良かったんだと思いました。生きるためにいろいろなことをしたとしても、このような気持ちになれたことに素直に喜ぶことができました。
下に抜き書きしたのは、そこの部分です。
小説というのは、全体を読まなければその感動は伝わってきません。
もし、興味を持ったら、自分でゆつくりと読んでみてもらいたいと思いました。
(2025.3.28)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 花と夢 | ツェリン・ヤンキー 著、星 泉 訳 | 春秋社 | 2024年4月20日 | 9784393455104 |
|---|
☆ Extract passages ☆
ああ、こんなにいい気分になったのは何年ぶりだろう。十三歳のときにこの都会にやってきてから今日に至るまで、鳥の鳴き声や自然の滝の音を耳にしたのは初めてだ。そこは狭苦しいナイトクラブとはまったく異なる世界だった。生えている草の一本一本や水の一滴一滴は、何と清らかで汚れがないのだろう。鳥たちは、何とのびのびのびとして自由なんだろう。巡礼路にはけばけばしいネオンサインも騒々しい音楽もない。鳥たちのさえずりは、インドラに仕える天界の楽団の奏でる音曲よりも美しい。枝ぶりのよい木々や勢いよく流れる滝の音は、さしもの楽団も気後れするほどと思われた。
(ツェリン・ヤンキー 著、星 泉 訳『花と夢』より)
No.2408『『ドラえもん』で哲学する』
著者は、大学のなかにとどまらず、商社マンやフリーター、名古屋市役所で公務員になったり、まさに移植の経歴があるからこそ、このような柔軟な本を書けるのではないかと思いました。
しかも、この本を書くために、改めて『ドラえもん』を1巻から45巻まで、全巻を読み直したそうです。そして、この本で取り上げはエピソードが、何巻にに書いてあるかも、巻末に掲載してあります。
孫といっしょ『ドラえもん』を見ていてよく出てくるのが、「どこでもドア」です。この本でも、「どこでもドアの魅力は、 これが本当のドアの形をしている点にもあります。私たちの身の周りにはたくさんのドアがあります。その向こうは見えませんが、それゆえに夢が広がるのです。これを開けた瞬間、見たこLもない景色が広がっていたらどうだろうかと。ドアの向こうは未知の世界です。そこが物理的にはつながっているはずのない場所だとしたら、興奮もひとしおでしょう。時速5キロにも満たないスピードでしか動けない人間が、未知の世界に思いを馳せ、今すぐにでもそこに行ってみたいと思う。そんな願いをかなえてくれるのは、どこでもドアにほかなりません。」と書いています。
そういえば、昨年、北海道の新富良野プリンスホテルに泊まったとき、そこのピクニックガーデンに「アンブレラスカイ」という空中にたくさんの色とりどりのカサを下げたところがありました。そこに「どこでもドア」に似たドアだけがありました。
おそらく、この日の午前中に、ラベンダで有名な「ファーム富田」に行き、広大なラベンダー畑と香りに触れてきたからかもしれませんが、ここから異次元空間に飛び出せそうな雰囲気があり、夢の世界にも行けそうな場所でした。
また、『ドラえもん』には、「スモールライト」や「ビックライト」もあり、物事を小さくしたり、大きくしたりできます。これがあれば、いろいろに使えそうですが、「基本的になにかを小さくするのとは違って、大きくするのには終わりがないのです。小さくする際は、なくなれば終わりです。でも、大きくする際には、どこまでもやれます。ここが問題です。際限なく大きくすると、大きくする行為は終わらなくても、話が終わってしまうのです。つまり、どこまでも、いつまでも続くということで、らちが明かないのです。」とあります。
たしかに、きりのないことをいつまでも続けるわけに行かず、むしろそこまでいってしまえば、大ごとになります。この世の中、なんどもほどほどがいいようです。
そういえば、『ドラえもん』の道具に「円ピツ」があり、それを使って紙に金額を書き込むだけでお金になるというものがありますが、もちろん、その書いた金額だけ働かなければならない仕組みになっています。
著者は、「お金の本質もまた縁であるように思えてきます。お金を払うことで、相手と何らかの関係ができるからです。まず、商品やサービスの提供を受けます。そしてその商品やサービスの対価として支払われたお金もまた別の形で、なにかの商品やサービスを得るために使われます。いわばお金とは人々の縁をつなぐための約束なのです。なぜ約束なのかというと、 お金自体がなにか具体的な効力を持っているわけではないからです。お金は食べることもできませんし、それで空を飛ぶこともできません。あくまで、そのお金の分だけなにかを食べることができる、あるいは空を飛んで旅行できるといった約束にすぎないのです。」と書いてあり、お金というものの本質的なことを現しています。
この本を読むと、『ドラえもん』に登場する未来の道具を切り口として、いろいろなテーマを考えて行く、つまりは哲学するということです。
下に抜き書きしたのは、第10章「望み――望みがかなう」に書いてありました。
『ドラえもん』の「うち出の小づち」は、労せずして得をしたりするものではなく、それに見合う努力や事情が必要です。つまり、小づちは仕事をするための道具ということです。
私も、よくこのような話しをしますが、子どもたちには『ドラえもん』の例を出して話すのもおもしろそうだと思いました。
これはJ・ロジャー・ルーシーという神父さんが書いたということです。
これを読むと、祈るということと、その願いが叶うということの違いを、神のはからいではないかと感じました。
(2025.3.25)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 『ドラえもん』で哲学する(PHP文庫) | 小川仁志 | PHP研究所 | 2024年12月16日 | 9784569904535 |
|---|
☆ Extract passages ☆
うちでの小づちは、ただでは望みをかなえてくれないのです。たとえば、ドラえもんが好物のドラやきを食べたいと望むと、10円が出てきます。そしてその10円が荷物の下に転がっていって、ひょんなことから引っ越しの手伝いをさせられます。そのお礼としてドラやきを振る舞らてもらえるという感じです。ドラえもんとのび太はなんだか得をした気がしないとこぼします。……
きわめつけはスネ夫です。うちでの小づちがあることを知った彼は、せめてのび太より背が高くなりたいと望みます。その時手をすべらせて、うちでの小づちが後ろに飛び、こともあろうかジャイアンにぶつかってしまいます。
怒ったジャイアンはスネ夫の頭を殴り、スネ夫の頭に大きなたんこぶができたことで、のび太より1センチほど背が高くなるのです。
(小川仁志 著『『ドラえもん』で哲学する』より)
No.2407『どんな時でも 人は笑顔になれる』
この本は、著者が帰天の10日前に校閲を終えられた遺作だそうです。読んで見ると、著者の言いたかったことが、たくさんつめられていると思いました。
著者は、家が浄土真宗だったそうですが、母の反対を押し切って、自分の意思で18歳のときに洗礼を受けたそうです。上智大学大学院を卒業後ノートルダム修道女会に入り、キリスト教教育一筋に歩まれ、2016年12月30日に逝去されたそうです。
また、マザー・テレサの通訳もされたことから、この本にもそのことが出てきて、そのときのエピソードも書いています。たとえば、「教会でのお話が終わった後、マザーは会場をお出になったところで「箱のような台を持ってきてほしい」とおっしゃいました。何かと思うと、マザーはその台の上に立ち、モニター越しに話を聴いていた会場の外の人たちに語りかけたのです。「あなた方は外で聴いてくださっていたそうで、どうもありがとう」そして、会場での講演内容をやや簡略化しながら、外でもお話を始められたのでした。マザーは、「あなた方は、たまたま会場の中に入れなかったけれど、あなた方も中にいる人と同じく話を聴きに来てくださったたいせつな方がたなのです」とおっしゃいました。」と書いてありました。
実は、だいぶ前のことですが、ブータンからカルカッタに飛行機で行き、そこから帰国する予定でした。でも、ブータンの小さな飛行場では、気候の関係で飛ばないこともあり、1日早くカルカッタまで来たのでした。そこで、友人と2人で、せっかくの機会なので、マザー・テレサの修道院に行こうとバスに乗ったのですが、あいにく地方に出かけていて、お会いできませんでした。
その帰り道、包帯の巻かれたすき間からウミが出ている手を差し出され、「バクシーシー」と喜捨を求められたのですが、なんとも言えない気持ちでした。
しかし、修道女たちは、その包帯を取り替え、また洗っていることを思うと、とても恥ずかしくなりましたが、私にはとてもできないことでした。この本を読みながら、そのことを思い出しました。
このエピソードにも、相手を分け隔てなく接することや、大きなやさしさを感じました。
この他に、ユダヤの古いことわざの話しも印象に残りました。それは、「ユダヤの古いことわざに、他人にすぐれようと思うな 他人とちがった人間になれ というのがあると聞きました。このような単純な言葉に、言いようのない新鮮さを覚え、日常生活を営んでいく上での励ましを受けるのは、世の中がそれだけ画一化し、人間の価値が比較の中にのみ見出されているからでしようか。たしかに比較という要素は、生活する上でなくてはならないものです。それがあるからこそ、自分が置かれた位置を知ることもでき、また競争心も湧いて、自分の能力の限界に挑むこともできようというものです。しかしながら、この比較も、人間一人ひとりは決して同じであり得ないという一つの「悟り」にも似たものなしに、ひたすら表面的な優劣に主眼を置くならば、それは、人間個々の可能性を伸ばすという教育の目的から遠く離れてしまいます。」と書いてあり、お釈迦さまも、よく比べるなと話したそうですが、教えというものは、どこか似ていると感じました。
私は、よく、信仰というものは、いろいろな違いはあっても、結局はひとつの山の頂上を目指すもので、その道はいろいろあると思ってます。人によっては、ゆっくりと九十九折りの道を進む人もいますし、急勾配を一気に進みたい人もいます。
だから、その違いを認め合うことが大切で、他人と違うからといって、責めることは間違いです。みんな違って、それが当たり前です。
下に抜き書きしたのは、第3章「祈ること、願いが叶うということ」に書いてあった詩です。
もともとは、ニューヨーク大学のリハビリテーション研究所の壁に一人の患者が書き残した詩だそうですが、著者が1990年の夏に、セントルイスのイエズス会の修道院で、この原文を見つけたそうです。
これはJ・ロジャー・ルーシーという神父さんが書いたということです。
これを読むと、祈るということと、その願いが叶うということの違いを、神のはからいではないかと感じました。
(2025.3.23)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| どんな時でも 人は笑顔になれる | 渡辺和子 | PHP | 2017年3月29日 | 9784569834719 |
|---|
☆ Extract passages ☆
大きなことを成しとげるために力を与えてほしいと神に求めたのに、謙遜を学ぶようにと弱さを授かった。
より偉大なことができるように健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱を与えられた。
幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。
世の人々の賞賛を得ようとして成功を求めたのに、得意にならないようにと失敗を授かった。
人生を享楽しようとあらゆるものを求めたのに、あらゆることを喜べるようにと生命を授かった。
求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。
神の意にそわぬものであるにもかかわらず、心の中の言い表わせないものは、すべて叶えられた。
私はあらゆる人の中で、もっとも豊かに祝福されたのだ。
(渡辺和子 著『どんな時でも 人は笑顔になれる』より)
No.2406『クマと人の長いかかわり』
最近、特に東北地方で市内に出てくる「アーバンベア」の問題が起こり、2023年度の流行語大賞にも選ばれる事態となっています。だから、いつも気にはしていたのですが、たまたま図書館でこの本を見つけ、即、借りてきました。383ページもありましたが、何度か読み返したところもあり、興味を持ちました。
題名の前に「世界を旅して見つめた」とあり、著者は科学ジャーナリストでロイター・ニュース・エージェンシーで地球規模の気候や環境問題を担当する記者だそうです。ただ、日本のツキノワグマを見に来てはいないそうですが、それ以外のクマは自分の眼で見てきているそうです。現在、世界には8種のクマがいますが、この本によると「現在、世界に残るクマは8種だけである。このうち、ヒグマ(Ursus arctos)、アメリカクロクマ(Ursus americanus)、パンダ(Ailuropoda melanoleuca)、ホツキョクグマ(Ursus maritimus)、は、自然界の象徴として愛されている。それ以外の、ツキノワグマ(Ursus thibetanus)、マレーグマ(Helarctos malayanus)、ナマケグマ(Melursus ursinus)、メガネグマ(Tremarctos oruatus)、あまり広く知られていない。」といいます。
ツキノワグマの学名は、日本というよりはもともと東アジアに多いクマという印象です。
このなかでも、特に攻撃的なクマは、インド亜大陸に棲むナマケグマで、「トラやヒョウと争わなければならないのだ。ヒグマやホッキョクグマは、それぞれ食物連鎖の頂上に君臨している。おとなのパンダを襲う捕食動物も、ほとんどいない。そしてメガネグマは木々のなかに隠れて身を守る。だがナマケグマは、危険が迫ったときには、毛をガサガサさせて、太く短い歯と鉤爪を武器に戦うしか術がないのではないか。ナマケグマは視力も聴力も弱いため、部族の人間とトラの区別がつかないのかもしれない。だから、縦縞模様の敵に対抗するための甚だしい攻撃性を、人間に対しても爆発させてしまうのだろう。」と、その理由を書いています。
いずれにしても、街中に出てくるようになったクマは、やはり怖い存在です。よくクマはかしこい動物だといわれますが、体の大きさに対する脳のサイズも大きいそうです。また、嗅覚がとても優れていて、人間の約2千倍もあり、嗅覚の敏感な大型犬ブラッドハウンドの7倍も鼻がきくといいますから、一度、人間の食べものをおいしいと感じれば、どうすればいいかさえわかるそうです。この本にも、キャンプ場でのクマ対策のいろいろを書いていますが、たとえキャンピングカーや小屋などに少しでも食料が残っていれば、それを嗅ぎ出すといいます。そして、クマ対策をしたごみ箱さえも、破壊するだけでなく、簡単には開けられないように工夫しても、手先を使って開けてしまうので、違う方法に変えざるをえないといいます。
まさに、いたちごっこならぬ、クマ対策の難しさです。
そういえば、クマのなかまにパンダもいて、この本に出てくる成都市近くの「成都パンダ繁育研究基地」に行ったことがありますが、ここにはたくさんのパンダがいて、野外で自由に動きまわるパンダを見ることができます。昔は、赤ちゃんパンダをだっこして写真を撮ることもできたそうですが、私が訪ねた2015年には、病気の危険もあるということで中止されていました。
この本で初めて知ったのですが、「パンダの出産では、ほぼ半分の確率で双子が生まれる。しかし、母親は、通常は1頭の子どもしか育てられない。野生下では、弱いほうの赤ちゃんを見捨てるのだ。「パンダの母親は本当に頑張り屋です。出産直後の24時間は、2頭とも生き延びさせようと必死になります。でも、そのあとはヘトヘトになってしまいます」と、張は説明する。「だから、1頭を育て、もう1頭を見捨てるのです」。臥龍の研究者たちは、あまりにもたくさんの赤ちゃんが生後わずか1日で放り出されることを知り、衝撃を受けた。張たちはこの問題を解決する方法を見いだすのに多くの労力を費やしたという。試行錯誤の末、赤ちゃんの免疫システムを強化し、張たちが育児方法を学ぶことで、双子を2頭とも救えることが判明した。現在では、飼育下の双子は決まったスケジュールでこっそり取り替えられ、母親が片方の世話をしている間、人間がもう片方の世話をする。母親はそのことにまったく気づかない。」と書いていました。
この張さんというのは、「パンダの父」ともいわれる方で、40年以上もパンダ繁殖に取り組み牽引してきた研究者、張和民氏です。
そういえば、私が訪ねたときも、大勢の来園者が訪れ、パンダの好きな竹も園内の通路脇に植えられていて、まさにパンダ尽しの施設です。私はたまたま一人で行ったので、ここだけはゆっくり見たいと思い、半日ほどいました。今でも、そのときに撮ったパンダの写真を見て、孫にも自慢してます。
下に抜き書きしたのは、第7章「氷上を歩くもの」に書いてあったものです。
最近は、テレビなどでも北極の氷がとけ出し、ホッキョクグマが絶滅するかもしれなというニュースを見ることがあります。この本によると、北極という言葉の語源は、英語で北極を意味する Arctic の語源は、ギリシャ語の arktos つまリクマだそうです。つまり、クマがいるからこそ北極なので、シロクマがいなければ他の生きものたちのつながりも消えてしまいます。だとすれば、その氷がとけ出す原因をつくった人間たちの責任はとても大きいと思います。
このチャーチルという町は、カナダのマニトバ州にあり、世界でもっとも手軽にホッキョクグマを見ることのできる場所だそうで、現在、世界のホッキョクグマは約2万6千等と推定されているそうです。これは、8種のクマのなかで、4番目に多い数です。
(2025.3.20)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| クマと人の長いかかわり | グロリア・ディッキー 著、水野裕紀子 訳 | 化学同人 | 2025年1月30日 | 9784759823998 |
|---|
☆ Extract passages ☆
チャーチルの町では、誰も家に鍵をかけない。くすんだ灰色と青のペンキで塗られたプレハブの家々は、徘徊するホッキョクグマに遭遇した不運な人がいつでも逃げ込めるように、鍵を開けっばなしにしてある。明らかに、泥棒よりもクマのほうが怖いということだ。錆の目立つ小型トラックや自動車も、すべて鍵が開いている。「とにかく、いつでも注意が必要なのよ」。長年この地に住み、ヘリコプターの運航管理をしているジョアン・ブラウナーが言った。「外出するときは、必ずピストルを持っていくの。家のベランダの上までクマが来たこともあるわ」。レストランには、建物を出る前に左右を見るように促すサインが貼ってある。車ではなく、クマがいないかを確認するためである。
(グロリア・ディッキー 著、水野裕紀子 訳『クマと人の長いかかわり』より)
No.2405『恋する仏教』
この本の題名を見たとき、この本には何を書いてあるのだろうと思いました。副題をみると、「アジア諸国の文学を育てた教え」とあり、読んでみようと思いました。
そういえば、スリランカの佛歯寺に行ったときに、お寺のなかのお堂のところに仏伝が描かれた額がずらっと並んでいて、説明はまったくわからなかったのですが、その絵を見ただけで理解できました。やはり、教えというものも、伝えるということがなければ広がりはないと思いました。
だとすれば、文学というスタイルをとって、教えが広がるというのはよくわかります。この本のなかに、「インド文学では掛詞が盛んに用いられていたため、仏教でも言葉遊びがしばしば利用されました。経典自身が用いていますし、仏教を題材とした文学作品でも利用されています。弁舌巧みな僧侶が一般信者相手におこなう説法や、芸人たちが仏教を素材として演じた芝居などでは、もちろん、洒落を散りばめて聴衆を楽しませていたようです。仏教関連の悲しい話、はらはらさせる話、滑稽な話、またそれらを題材にした文学作品や語りもの、歌舞や芝居なども歓迎されたでしょう。仏教に基づく文学や芸能が大いに発展したことも、仏教が国境を越えて広がっていった原因の一つです。そうした文学や芸能は、伝わっていった先々の国でさらに独自の展開をとげていきました。」と書いてあり、その拡がり具合がよくわかります。
この本では、具体的に和歌などの詩歌から文学作品まで取り上げて、原文やその和訳も掲載しているので、とてもわかりやすく、これなどはもう少し読んでみたいと思うものもありました。たとえば、白居易の『長恨歌』なども、有名なところは読んだ記憶がありますが、全体を通して読んだことはなく、さらにモデルになった楊貴妃についても、「皇后を亡くした唐の玄宗(在位712―756)は、第十八子の李瑁(りぼう)(?ー775)の妃であった楊玉環(719ー756)の美しさに魅せられ、離婚させていったん道教の寺に入れ、太真という名の女冠(女道士)とした後、後官に迎え入れて貴妃とします。以後、楊貴妃を溺愛して政治を怠り、貴妃の又従兄である楊国忠(?ー756)などの親族を登用したため、反発が高まって安禄山(703-757)が乱を起こし、洛陽を陥落させました。玄宗が長安を逃れて蜀に向かおうとしたところ、馬嵬の地まで来たところで兵士たちが騒乱の元である楊国忠などを殺したうえ、楊貴妃も殺すよう要求したため、玄宗は抵抗したものの、最後にはそれを認めます。反乱がおさまった後、長安に戻った玄宗は、楊貴妃の姿を絵に描かせ、朝夕眺めて暮らしたと伝えられています。」とあり、ある程度は知っていましたが、他人の奥方をめとったとは初耳です。
そういえば、昨年の診察になるまで、5千円札の肖像画に使われていて樋口一葉という筆名も、「当時貧乏であったため、一枚の葦の葉に乗って揚子江を渡って少林寺におもむき、面壁坐禅し過ぎて足が腐ってなくなったという伝説がある菩提達摩と同様、自分も「おあし(銭)」がないので達磨になぞらえて名乗っていた」と冗談のような話しも載っていて、真偽はともかくとしておもしろい話しだと思いました。
こういう話しはたくさんこの本に載っていて、たとえば「竹取物語」は維摩経を参考にして描いたとか、もしかすると、作者は僧正遍昭ではないかという説まで取り上げられていて、たしかに、駄洒落みたいなものも多く、それなりの天台宗の知識もなければ書けないとすれば、その可能性もあるかもしれないと思いました。
また、日本最古の歌集といわれる「万葉集」も、歌人のなかに百済が減亡した際に日本に逃れて来た渡来人の子孫もいて、この万葉集にも少しではありますが仏教の影響があるといいます。だとすれば、日本純粋の歌集とは言え切れず、東アジア文学比較研究が専攻の中西進氏のいうように、『万葉集』が韓半島(朝鮮半島)から渡来した百済人の影響を受けて誕生したという説も簡単には無視できないような気がします。また、中西氏は山上憶良も百済人の子孫である可能性が高いと発表しています。
このように考えて行くと、日本というのは、いろいろな意味で仏教の影響を受けていることは間違いなく、これからも多方面からのアプローチが必要だと感じました。
下に抜き書きしたのは、第4章「日本の恋歌・恋物語と仏教」に書いてあったものです。
私は植物が好きなので、いろいろな本を読みながらも、このようなところに一番最初に目が行きます。やはり、好きこそ物の上手慣れ、のようです。
(2025.3.16)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 恋する仏教(集英社新書) | 石井公成 | 集英社 | 2025年1月22日 | 9784087213454 |
|---|
☆ Extract passages ☆
インド仏教では、草本は感覚はあるものの心はないとされていました。中国仏教では、すべては心が生み出したものであるため、悟って仏となった人の目に見える草本は悟った存在とされましたが、日本では、草木が芽を出し、葉をつけ、花を咲かせ、実をならせるのは、発心し、修行し、悟って仏果を得る過程にほかならないとする草木成仏説が盛んになりました。その説が極端に進んだ『三十四箇事書』では、草木はもともと仏なのだから、改めて修行して仏になることはない、として草木成仏を否定するにまで至っています。
(石井公成 著『恋する仏教』より)
No.2404『フィールドワークってなんだろう』
私も植物が好きで、フィールドワークも楽しみに出かけていくのですが、正面切って『フィールドワークってなんだろう』っていわれると、野外に出て、調べることではないのと簡単に思ってしまいます。でも、この本を読むと、そんなに簡単なものでもなさそうで、つい最後まで読んでしまいました。
たとえば、この本に出てくる早池峰神社でのことですが、一人のおじさんがひょこっと著者の前にあらわれて、ここに祀られている施錠されているコンセイサマの話しをします。それを聞いて、「普通に考えれば、施錠をする意味は、賽銭泥棒などの「外」から不審者の侵入を防ぐためです。しかし、彼が語りだした論理は、「内」からの勢いを沈めるための"結界"だったのです。この結界の存在によって、コンセイサマという物質的存在は精神的な存在として私たちの前に現れます。もし結界がなければ、動き出さない=勢いがない、したがってご利益がないと感じてしまうでしょう。この内と外の逆転によって、コンセイサマは静から動へと勢いを伴ったものとして魂が込められたのです。」と書いてあり、まさに逆転の発想のような気分でした。
私の場合でも。施錠されていれば、そのなかにあるものを大切に守っているのだという印のように思っていました。だとすれば、先ずは話しを聞いてみないとわからないということになります。勝手に解釈しては、その意味も違ってくるということです。
また、このおじさんは、「ここの神様は一度の過ちなら許されるということで、訪れる人も多いみたいだよ」ともいいます。
たしかに、たった一度の過ちで、一生を棒に振るようなことが最近は多すぎます。もちろん、して悪いことをしたのだから、反省することは当然でしょうが、その後の人生をすべて台無しにすることはないと思います。立ち直りのきっかけをつくることも必要です。
ところが、このネット社会になり、いつまでもその一度の過ちを繰り返し掲載されると、立ち直りのきっかけすら失ってしまいます。人は、そんなにも強いものではありません。だとすれば、この早池峰神社のコンセイサマのように、許してくれる神様も必要だと私は思います。
そして、そのほうが、人としてのゆったりと生きられるし、優しくもできます。それが今求められていることではないかと、この本を読みながら思いました。
また、最近は生涯学習という言葉を安易に使っているような気がしますが、この本のなかに、「狭い意味の高校までの教育では正解を受け身のかたちで詰め込んでいきます。一方、大学以降の広い意味での教育は、自分で進んで行うもので、主体的で能動的なものです。一見するとフィールドワークは基本他人からお話を聞くというだけで受動的に見えますが、実は主体的なものが含まれています。なぜなら、これまで明らかでなかったことを、自ら明らかにしていくことはとても創造的だからです。自分でなんだろうと疑間をもって追求していくためには、自分で自分を再教育する必要があります。それは一生涯続く営みといえるでしょぅ。自分で考えることで世界は拡がっていきますが、自分だけの考え方では限界があります。そこで、フィールドワークによって、自分の考え方にショックを与えて、次元の違う視点を獲得するのです。」と書いてあり、なるほどと思いました。
つまり、学校での勉強とは違い、自分が主体的に学んでこそ生涯学習になるんです。子どものときにも経験しましたが、押しつけられて勉強しても、長続きはしません。自分がやろうと思わなければダメなんです。
だとすれば、先ず好きにならなければならないようで、私自身もこの『本のたび』をこんなにも長く続けていられるのも、結局は本を読むことが好きだからです。
下に抜き書きしたのは、第2章「一つの例から全体を問いなおす――ブラックスワンを探せ!」に書いてありました。
たしかに今はパソコンを使えば、手軽に資料を収集できるかもしれません。またAIを使えば、それなりの文章もできます。
しかし、考えてみれば、それらの資料や文章も、もともとは誰かが集めたり作成した文章です。つまり、みな二番煎じのものばかりです。だとすれば、No.2402『美術館・博物館の事件簿』で読んだコラージュみたいなもので、それを創作といえるかどうか、さまざまな問題を含んでいます。
たしかに、真似ることから始まりますが、それで終わってしまえば、ちょっと空しいような気がします。むしろ、自分だからこそできるということのほうが大事です。ある意味、独創性というのは、そこの部分がとても大事だとこの本を読みながら思いました。
(2025.3.12)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| フィールドワークってなんだろう(ちくまプリマー新書) | 金菱 清 | 筑摩書房 | 2024年10月10日 | 9784480684974 |
|---|
☆ Extract passages ☆
現在、ネットという強い味方があり、ちょちょっとググればそれこそ寝ながら検索し、いろいろなことを調べることができます。それなのに、なぜ時間とお金をかけて苦労して調査をするのでしょうか。それを一言でいえば、「ブラックスワン」を探すためです。直訳すれば黒い白鳥。ホワイトスワンつまり普通の白鳥は、ネットで検索すれば、すぐに見つけ出すことができます。しかし、ブラックスワンは検索ではでてきません。
また、 一羽でも黒い白鳥をみつけることができれば、白鳥はすべて白いとは言えなくなります。そのため、白鳥という概念そのものを考えなおす必要が生まれてきます。この概念を問いなおすほどのなにかを発見することが、苦労してフィールドワークする意味です。地道で苦労したデータを現場で拾い上げるフィールドワークは自らが持っている当たり前、難しい言葉でいえば「通念」を根本から問いなおします。それには若い感性を必要とします。
(金菱 清 著『フィールドワークってなんだろう』より)
No.2403『ヘタレ人類学者、砂漠をゆく』
2月11日の建国記念日の午後2時から、南陽市芸術文化協会の新春講演会が熊野大社證誠殿であり、そこで「笑顔が一番」という題で話しをしてきました。そのなかに、インドで暑かったことの話しをしたのですが、この本にも同じような体験が載っていました。
それは、「もう9月の半ばだというのに、暑さはさらに増しているかのようだ。いや、暑いというより、痛い。乾燥した空気と、肌に刺さるような直射日光。砂交じりの熱風。この街が元気なのは午
前中と夕方。日中はうだるような暑さのなか、街の人々も活動を減退させ、日陰をみつけだしては、横になったりしている。僕も午前中は、市街地の迷路のように入り組んだ路地裏の徘徊を大いに楽しんでいたが、日が高くなるにつれて動きが取れなくなり、街の中央にそびえ立つ城を見上げる城門前のルーフトップ・レストラン(要は屋上にある食堂)でライムソーダを飲みながら、「早く沈んでくれ!」と太陽に心から願い、ぐだぐだと無為な時間を過ごすのが日課となっていた。」とあります。
私もインドの飛行場に降り立ったとき、あの滑走路脇の広いコンクリートの上を歩いていると、同じような気持ちになりました。そういえば、インド人のなかには、裸足で歩いている人もいるので、私もまねして裸足で歩いてみたことがあるのですが、足の裏がやけどしそうになりました。だから、砂漠の世界では昼間灼熱地獄をつくり出す太陽より、夜に静かに照らしてくれるお月さまのほうがいいわけで、ちなみにイスラム教のシンボルは三日月と星です。
また、カビールという15世紀に活躍した宗教家は、神というのは世界中でいろいろな形をとったり、個別の呼び名で記述されたりしますが、もともとはひとつだといいます。「それらは「たったひとつのもの」がいろいろな姿で現れているだけであり、「神」は寺院の中や天界にいらっしゃるのではなく、その唯一無二の存在は、それぞれ個人の中に存在する、絶対的な真実だというのだ。だから、神話に描かれるような、人格を持った神々(ヴィシュヌ神とか、ラーマ王子とか)に対する焦がれる思いを信仰のベースにしたそれまでのバクティ思想とはだいぶん異なる、新たな宗教運動につながっていった。」といい、どちらかというと真言宗の大日如来に近い考え方のようです。
しかも、その存在は外にあるというよりは、「どんな人の中にもいる/ある」というから、ますます「梵我一如」の考え方に近いと思いました。
そういえば、第9章「感謝のない社会」のなかで、「僕がその都度彼らに「救い」の手を差し伸べ、金銭であろうが現物支給であろうが、彼らのために「してあげた」ことに対する、感謝の言葉を返されたことが、 一切なかったこと。懇願されてそれに応えても、お礼の言葉や態度が見受けられないこと。これが最も精神的な苦痛につながっていた。」と書いています。しかも、その後で、「これが彼らの社会だ。「ありがとう」がナイのではなく、あえてナイことにしている。それはタブーであり、感謝はしてはならないという鉄の掟なのだ。もう、訳がわからない。」といいますが、これこそ、仏教の布施の心です。
感謝するのは、むしろ手を差し伸べた人こそがするもので、気持ち的には「受け取ってくれてありがとう」ということです。だからこそ、功徳を積むことができます。むしろ功徳を積むことに協力してくれたようなものです。それこそが布施です。
私もインドで「ありがとう」と言われたことはありません。私のインドの友人は、現金であれモノであれ、布施できるだけのものを持っていることに感謝すべきで、それで功徳を積めるのだからありがたいといいます。この心こそ仏教の大切な教えではないかと感じました。だとすれば、感謝されないから無視されたという気持ちこそ、おかしな話しです。
下に抜き書きしたのは、「エピローグ」に書いてあったもので、トライブという少数民族のパーブーという若者の言葉です。
彼はこの話しの前に、フンコロガシがあんな忌み嫌われるウンコを宝物のように運んでいる気持ちがわかるか、と問われています。むしろわからないからこそ、不条理な部分や不完全さをさらけ出せるのかもしれません。
(2025.3.9)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| ヘタレ人類学者、砂漠をゆく | 小西公大 | 大和書房 | 2024年12月25日 | 9784479394419 |
|---|
☆ Extract passages ☆
「『わからない』ということの大切さを伝えたかったんだよ。『わからない』が全ての前提になってれば、僕らはさらけ出せるんだ。許せるんだよ、他人を。だって、どんな酷いことを言われたりされたりしても、なんでそいつがそんなことをしたのか、どうやったってわからないんだから。もちろん、わかろうとすることはできる。でも正解に至ることなんてできない。だから、最終的には「そういうものなのかな」と、受け流していく部分が必要になってくる。もっというと、『そんなお前でも、生きてるんだよな』という、あきらめのようなものになってくる」
(小西公大 著『ヘタレ人類学者、砂漠をゆく』より)
No.2402『美術館・博物館の事件簿』
前回読んだ『ナチスから美術品を守ったスパイ』の場合は、戦時下でのことなのであり得る話だと思ったのですが、美術館や博物館などの事件も平常時でも起こっていると知り、びっくりしました。まさか、あのぐらいきちんと正確に管理されていたとしても事件が起こるのは不思議と思うのですが、よくこの本を読んでみると、一般的な社会とそんなには違わないようです。
やはり、遺産相続で泥沼化したり、ちょっとした確認ミスが大きな問題になったりと、いろいろあるようです。
それと、『ナチスから美術品を守ったスパイ』でも読んだのですが、今現在も、ナチス略奪品の返還をめぐっての問題があり、「最近の欧米諸国の間では、略奪された文化財や美術品を被害者や原所有国に戻そうとする動きが広がっている。その発端は、第二次世界大戦中にナチスがユダヤ人から略奪した美術品の返還問題に関する欧米各国の対応の変化である。既に紹介したように、1998年、世界各地44か国の政府は、「各国はナテス略奪品の被害者やその遺族に返還するための制度や仕組みを設けるべく努力すること」などを「ワシントン原則」により合意した。これを契機に、欧米各国は、既存の法律の枠組みを超えて、道徳的な見地から被害者遺族の権利を守るための法制度を新たに設けた。2000年2月にイギリス政府が前述の略奪審査会を設置したのはこの一環である。」とあり、たしかに文化財とはいえ略奪されたものを展示するのは非難されるべきものです。
そういえば、昔の欧米の美術館や博物館は、帝国主義の時代に略奪してきた収蔵庫などといわれたこともありました。それが研究のためとはいえ、遺跡を壊したり、墓の中から発掘したものであれ、今の時代では考えられないことです。
また、贋作が本物として美術館や博物館に展示されれば、これも大きな問題になります。たとえば、この本では、徳島県立近代美術館が1999年にフランスのキュビズムの画家ジャン・メッツァンジェの油彩画「自転車乗り」を6,720万円で購入しました。これはドイツのウォルフガング・ベルトラッキの贋作の可能性が非常に高いそうです。しかも、一流の専門家が真作と認めていたのに、なぜだと思ってしまいます。まさに、騙す方が悪いのか、騙される方が悪いのか、です。
そういえば、何年か前に見た『嘘八百 京町ロワイヤル』で、古物商の則夫役を中井貴一、陶芸家の佐輔役を佐々木蔵之介が演じ、古田織部の幻の茶器「はたかけ」の贋作をつくり、目利きといわれる古物商たちも絡んで、コメディータッチで描いた映画を思い出しました。これはコメディーだからいいようなものの、公的機関の美術館まで騙されてはこまったものです。
この本では、「公立美術館が贋作を購入すると、公費が無駄になるうえ、真作と信じて観賞した多くの市民、研究者を欺くことになる」といいます。でも、有名なクリスティーズのオークションで落札したり、研究者が真作と確認したという証明書が付いていたりすれば、それほど疑問にも思いません。
『嘘八百 京町ロワイヤル』でも、著名な鑑定士がこれは間違いなく本物ですといえば、それで通ってしまう世界なのかもしれません。しかし、著者は、その作品の来歴の事前調査をすべきだったといいます。「来歴調査とは、購入予定の作品がどのような経緯で現在の売主に渡ったのかを調べ、それが盗難、略奪、不法輸入等の対象になっていないかを確認する作業のことで、現行のICOM職業倫理規程は博物館・美術館の義務と定めている。」といいます。
私はほとんど記憶になかったのですが、1974年4月、上野の東京国立博物館で「モナ・リザ展」が開かれ、50日間の会期中に約150万人もの人たちが来場したそうです。その初日に、「若い女性が「モナ・リザ」に赤いスプレー塗料を噴射するという事件が起きていた。犯人はその場で取り押さえられ、「モナ・リザ」は防弾ガラスに保護されていて被害はなかったので、展覧会は何事もなかったかのように続行された。事件は、「女性解放」を掲げたウーマンリブ(フェミニズム)の運動家、米津知子氏が起こしたものだった。「モナ・リザ」展は、安全上の理由で介助や付添いを必要とする障害者や高齢者等の入場を制限していたので、彼女はこの措置に抗議して「身障者を締め出すな」と叫んでスプレーを墳射したのだ。彼女自身も右足に障害を持っていた。大津知子氏ほ軽罪法違反(悪戯による業務妨害の罪)で起訴され、翌1975年、裁判所から科料3000円の判決を下された。」といいます。
この科料3000円にも驚きましたが、これなどをきっかけとして博物館・美術館などもバリアフリー化が進んだと書き加えています。
下に抜き書きしたのは、コラムに書いてあった「AIアートと美術館」に書いてあったもので、たしかにこれからの美術界においては、デジタルアートやAIアートなども非常に大切な部門になると思います。
特にこのAIアートは、他人の著作権を侵害するかどうかや、その確認の難しさもありそうです。
また、デジタルアートにしても、いくらNFT(ブロックチェーン技術を利用して作成された唯一無二のデータ)だとしても、そもそも実体がない作品をどのように保護するかも大きな問題です。
(2025.3.6)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 美術館・博物館の事件簿 | 島田真琴 | 慶應義塾大学出版会 | 2024年12月20日 | 9784766429992 |
|---|
☆ Extract passages ☆
最近、生成AIを活用したアート作品(AIアート)が増えている。「生成AI」とは、あらかじめ学習した既存の画像、音声等のデータをもとに、新しいコンテンツ(別の画像、音声等)を自動的に生成することができる人工知能(AI)のことをいう。 アーティストは、 生成AIに条件を与えて指示をすると、AIがこの指示に従って勝手に新しい画像等を生み出すので、これを新作の素材にしたりヒントにしたりすることができるのだ。
(島田真琴 著『ヘ美術館・博物館の事件簿』より)
No.2401『ナチスから美術品を守ったスパイ』
ナチスがフランスから美術品を持ち出し、貨車で運んだということは知っていましたが、これほど悪質に大量に略奪したということを初めて知りました。副題は「学芸員ローズ・ヴァランの生涯」ですが、この本で初めて知ったことです。
ヒトラーがこのような美術品を略奪したのは、ドイツ国のためということだそうですが、この本では「ヒトラーはその狂気の投影図のなかで、芸術を反ユダヤ主義やアーリア人の生存圏の拡大と同じくらい重視していた。ウィーン美術アカデミーの入学試験に三度も失敗した落ちこぼれ画家のヒトラーは、生活費を稼ぐために広告看板や絵葉書にパッとしない風景画を描いていた。彼にとって芸術は、美や瞑想、柔軟な感覚の源というより、むしろ、数あるもののなかの一つに対するたちの悪い執着や狂信的な妄想だった。そしてまた、ヴェルサイユ条約や自分を受け入れなかった美術アカデミーに対する恨みを晴らし、屈辱を消し去る手段だった。審美的な喜びというより、人種政策や領土拡張政策と同列の一つの構想だった。つまり、死ぬまで膨らませていく自己中心的な執着だ。」と書いています。
たしかに、ヒトラーが美術愛好家だったことも、この大戦で美術というものがいろいろな思惑から移動されてしまったようですが、それでも、移動できなかった大きな美術品や歴史的建造物などは爆撃されたり戦闘によって破壊されたりもしたと思います。
たとえば、現在も続いているウクライナとロシアの戦いでも、テレビなど放映されているだけでも、歴史的に貴重な文化遺産なども破壊されている様子がわかります。さらに、個人宅でもロシア兵によっていろいろな物が略奪され、故国に送られていることをネットでも伝えられています。
これらは、終戦近くなってからソ連兵がドイツに入ったときにも似たようなことがあり、この本には、「ローズがとりわけ気になっているのは、彫刻家、アルノー・ブレーカーがパリからベルリンに移送したロダンの二体の像、〈考える人〉と〈歩く男〉のブロンズ像の行方だった。ローズはこれらの像をベルリンのフランス占領地区に送ってからポツダムの倉庫に保管させていたが、そこからソ連軍が横取りし、モスクワに送っていた。ローズはオブソニムニコフ大佐に合法的な返還請求書を手渡した。ところが彼は、〈考える人〉は今もパリにあると反論した。「パリにはその像が三体ありますが、ソ連が持っていったものがオリジナルです」とローズは忍耐強く説明した。ソ連側の回答は期待できるものではなかった。そのロダンはいまだに見つかっていない。ローズは、赤軍から美術品を正式に返還してもらうことは一切期待できないことを悟った。彼女の返還請求は、十分な手がかりを得ることにしか役に立たなかった。ローズはもう、ソ連側には場所についてのどんな情報も知らせずに、違う行動をとろうと決心した。非公式の手法で裏切られることはめったにないのだから。」とあり、ほんとうにびっくりしました。
そのときも、今も、ほとんどかわらないやり方だったからです。
しかし、連合国側は「モニュメンツ・メン」という人たちを中心にして、国だけでなく、個人の美術品なども詳しく調べ上げて、根気よく返還をしていたことを知り、その違いに、またまたびっくりせざるを得ませんでした。
下に抜き書きしたのは、「岩塩坑の奥に金の光線」のところに書いてあったものです。
ドイツのヒトラーは、ベルリンの自分専用の掩蔽壕に立てこもっていたので、爆撃の音は聞こえてこなかったそうですが、それでも敗北は避けられないと悟ったといいます。そこで、アルタウスゼー岩塩坑に隠すよう命令を下しました。
では、どれほどの美術作品をフランスから持ち出したかというと、なかなか全体像は見えてきませんが、この本には「1941年初頭、ローズは、ユダヤ人が所蔵していたほとんどの大規模なコレクションが没収され、ジュ・ド・ポーム美術館に保管され、目録が作成され、その後、ドイツに送られたことを悟った。数十本もの輸送列車が数千個もの木箱を積んだ数百両の貨草を運んで、国境を越えていった。」とありました。
また、ヒトラーだけでなく、ゲーリングも同じように自分のものとした美術品を特別列車に積み込ませ、ベルヒテスガーデンに移送しました。
ただ、どちらの美術品も爆破されたり傷つけられたりせずに残ったことは、ある意味、後世の人たちにとっては幸いだったと思います。
(2025.3.3)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| ナチスから美術品を守ったスパイ | ジェニファー・ルシュー 著、広野和美 訳 | 原書房 | 2025年1月6日 | 9784562074907 |
|---|
☆ Extract passages ☆
ヒトラーにとって、瓦礫の下に埋もれた国民は戦争の巻き添えになった被害者にすぎなかった。彼は国民のことなど、結局どうでもよく、むしろ自分のコレクションの運命のほうがずっと気がか
りだった。ヒトラーは、リンツ美術館のために粘り強く獲得してきた自分の数万点の美術作品をアルタウスゼー岩塩坑に保護するようにという命令を出した。1944年5月から10月までの間に、ドイツ国の物質的資源や人材が枯渇していた頃、 1788点の作品がミュンヘンを発ち、危険な道を突き進んだ末に地下に埋められた。
(ジェニファー・ルシュー 著、広野和美 訳『ナチスから美術品を守ったスパイ』より)
No.2400『きっと「大丈夫。」』
著者は山形県河北町の生まれで、この本を書いていたときには聖路加国際病院の小児科に勤務しながら、日曜日には実家の谷地にある細谷病院で診療を続けていたそうです。
その話しを聞いて、読んでみようと思いました。さらに、現在はと気になり、ネットで調べてみると、平成16年に築100年の建物を新築し、内科だけでなく血液透析も始めたそうです。ただ、現在も谷地まで通っているかどうかはわかりませんでしたが、細谷病院のスタッフ一同の写真に本に載っていた著者に似た方が写っていました。現在の院長は臼井惠二さんだそうです。
しかも、そのホームページをみると、地域医療に貢献したいという気持ちが伝わってきて、私もこのような病院がかかりつけ医なら安心だと思いました。
そういえば、最近のコマーシャルで、「メメント・モリ」という言葉があり、それって何だろうと思っていたら、この本に『「メメント・モリ」という言葉があります。「死を思え」「いつかは自分が死ぬということを忘れるな」という意味のラテン語です。そんな言葉を意識して、「死を感じながら生きていくことがほんとうの生き方」と思っている医者がいても、世の中一般の人が、完璧に「死」と遠いところで暮らしていたのでは話が噛み合いません。医者は宗教者と同じようにいのちについて深く考えを思いめぐらす立場にいます。ただ病気を治すだけの職人ではないのです。その人の持っている技術やテクニックもさることながら、最終的には医者の人間性、「その人」こそが患者さんに深く「いのち」を考えてもらうために重要なのだと思います。」』と書いてあり、ゲームの名前に使うような言葉ではないと思いました。
よく、人は死ぬために生まれてきたとか、つねに死を意識しながら生きよ、などといわれますが、毎日そのように生きようとしたら息が詰まりそうです。むしろ、私は毎日を笑顔で楽しく暮らし、その喜びのなかにこそ人生があると思っています。
だって、「笑う門には福来る」という言葉があり、いつも笑っているからこそ福がやってくるという意味だと思います。
それでも、この本のなかにある、「癒やしや救い、あるいは生きがいというものは、人と人との関係の中で生まれるのだと思います。人間が人間のそばで生きているということの意味合いは、そういうところにあるはずです。メールゃツィッターだけでの関係は、血の通ったつながうにはなりにくいものです。だから、直接人と話をしたり、面と向かって人と会つたりするのは重要なことなのです。」と書いてあったりは、私もその通りだと思います。
最近は、年賀状などもメールやSNSで間に合わせてしまいがちですが、年に1度の挨拶ぐらいは何度でも読み返すことができるハガキもいいですし、何よりも手書きの温もりも感じます。
そういえば、著者は、「こころが大きく負の方向に揺れたとき、私はおいしいものを食べます。単純に「おいしい」と思って喜べるからです。そして、「なんとかしなきゃ」という気持ちになれます。悲しいことやつらいことを忘れるわけではないのですが、そういうことを正面から受け止めて、次への活力にするファイトがわいてきます。と書いていて、そういえば私もその口かもしれないと思いました。
もちろん、ただ、食べることが好きということもありますが、今日は和食にしようか、それともイタリアンにしようかなどと考えていると、思い悩んでいることも忘れてしまいます。だって、食べないでお腹が空きすぎるとますます考えがまとまらなくなるし、イライラすることもあります。やはり、先ずは食べることが先決で、食べてしまうとそれだけで満足し、なんとかなるだろうと思ってしまいます。
本当は、何を食べてもおいしいと思えることが大切だとはいいながら、やはり好きなものを食べるとついニコニコしてしまいます。
下に抜き書きしたのは、「ひとりになること」に書いてあったものです。
私も歩き遍路ではなかったのですが、2017年2月28日から3月15日まで、四国八十八ヵ所をお詣りしたことがあります。
そして、たしかに寺々でお詣りしたことも記憶に残っているのですが、それ以上にその道すがらに見た風景や花なども思い出され、今でもときどきはその時撮った写真を見ることがあります。それらを見ると、もう一度行きたいと思いますが、札所によってはすごい石段があったり山のなかだったりして、なかなか実現できないでいます。
(2025.2.28)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| きっと「大丈夫。」 | 細谷亮太 | 倖成出版社 | 2013年1月30日 | 9784333025916 |
|---|
☆ Extract passages ☆
お遍路をして歩いていると、自分自身が生きていることを強烈に感じます。それもひとりでではなく、地球の中でいろいろな動物とともに生きていることを実感できるのです。お遍路には、私にそういう思いを持たせる力がありました。
お遍路で歩ぃているときには、行った先々のお寺で鐘を撞き、ろうそくに火をともし、線香をあげてお経を読むというお勤めもとても重要です。しかし、ほんとうに大切なのは、そこの札所へ行くまでの道筋の時間ではないかという気がします。自分の祈りをお大師さまに聞けてもらうことも大事ですが、歩きながらいろいろなことを体全体で感じ取り、自分が今、宇宙の中のそういう時間を生きているんだと実感することが、より重要なのだと思います。
(細谷亮太 著『きっと「大丈夫。」』より)
No.2399『ウクライナはなぜ戦い続けるのか』
著者の高世仁氏は、山形県生まれだそうで、早稲田大学法学部を卒業後、日本電波ニュース社に勤務を経てテレビ制作会社「ジン・ネット」を設立しさまざまな番組を製作してきたそうで、現在はフリーです。
副題は「ジャーナリストが戦場で見た市民と愛国」で、なかなかテレビなどの報道では知り得ないウクライナの今を知りたくて、読み始めました。
私も「ブダペスト覚書」については知っていましたが、これは「ウクライナは1991年の独立時、旧ソ連の短距離戦術兵器や空中発射巡航ミサイルを含む約1800の核兵器を保有し、世界第3位の核兵器備蓄国だった。核拡散を恐れるアメリカの説得に応じ、ウクライナは核兵器を廃棄するためロシアに引き渡すこととし、その見返りとして、94年12月、米英露三国から安全保障(ブダペスト覚書)を取り付けた。覚書で三国は「ウクライナの領土保全ないし政治的独立に対して脅威を及ぼす、あるいは武力を行使することの自重義務を再確認」し、ウクライナに「経済的圧力をかけることを慎み」、ウクライナヘの「侵略行為」があった場合には、「同国に支援を提供するため、即座に国連安全保障理事会に行動を求める」ことを約束した。この結果、ウクライナは96年までにすべての核兵器をロシアに引き渡した。」ということで、米英露三国が覚書に署名しています。
しかし、そのロシアがウクライナに侵攻したわけですから、まさにとんでもないことです。
現実に、このような覚書が反故にされたなら、おそらく北朝鮮だって、もし核兵器を放棄でもしたら、攻め込まれるかもしれないと考えるのは当然です。約束などは、あってないものだと考えるかもしれません。
私としては、むしろこのような不信感こそが怖いと思います。
でも、過去の歴史において、ロシアだけでなく、多くの国でも不戦条約を結んでおきながら、自国に有利だと思うと、戦争に突入したわけですから困ったものです。むしろ、国連安保理こそが、このような約束を率先して守るべきなのに、安保理常任理事国がそれを守らないのですから、世界中に不信感が生まれるのは当然です。
もうひとつ、私が驚いたのは、まさか日本と遠く離れているので、あまり関係性はないと思っていましたが、じつは北方領土に住むロシア人住民、約1万8千人のおよそ4割はウクライナ系だと知ったことです。この本によると、「ロシア帝国時代、ウクライナ地方の貧困と人口圧は大量の国内移民を生んだ。とくに1880年代から20世紀初めにかけて、膨大な農民がウラル山脈以東へと移民している。シベリア鉄道が1903年に完成していたが、多くは海路でオデーサ港からはるばるスエズ運河、インド洋を越え、数千キロ離れたウラジオストク港へとたどり着いた。1914年には、ロシア極東地方にロシア人の2倍にあたる200万人のウクライナ人が定住していた。移住から年月がたち、ほとんどは自らをロシア人と意識しているというものの、数多くのウクライナ人の子孫たちが現在も日本の対岸に暮らしているというのは興味深い。」と書いています。
今回のロシア侵略で、ウクライナの人たちも、日本の「北方領土」については日本を支持しますという意見が多く聞かれ、ウクライナ最高会議でも、北方領土を日本領だと決議したそうです。
つまり、自分たちと同じように、ロシアによる一方的な併合だと感じたようです。
また、今回の侵略で、ロシアは「花びら地雷」を使っているそうですが、これは、「人命を奪わない程度の、足首や膝から下がもげる怪我を負わせる。戦場では、地雷で負傷した兵士を応急処置し搬送する人員をとられ、作戦が大きく妨げられる。この対人地雷の効果が、昨年6月以降のウクライナの反転攻勢をロシア軍が阻止できた要因の一つになったともいわれている。戦場を離れても、医療や社会復帰のための資源や人員が社会に負担となってのしかかる。さらに、障害を負った本人と周りの人々の戦意を削ぎ、厭戦気分を助長する。戦死よりも大きな物理的、心理的ダメージを敵に与えることを目的に考案された、悪意に満ちた地雷である。」というから、恐ろしい地雷です。
同じ人間が考えたと思うと、人間というのは、恐ろしい存在だと思います。
下に抜き書きしたのは、第12章「銃後で"日常"を戦う市民たち」のなかに出てくるものです。
じつは、ロシア侵攻後に流行っているものに「スタンダップ・コメディ」というのがあり、これは日本の漫談のようなことを1人でする即興話芸だそうです。たとえば、綾小路きみまろのような漫談に近いかもしれません。そういえば、現大統領のゼレンスキーもかつてはコメディアンとして、観客の前で話芸を披露していたことは有名な話しです。
今は、戦争下なので戦争そのものも笑いのネタになっているそうで、私も聞いてみたいような気がします。そして、笑顔というのは、万国どこでも必要なことだと痛感しました。
(2025.2.25)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| ウクライナはなぜ戦い続けるのか | 高世 仁 | 旬報社 | 2024年12月25日 | 9784845119561 |
|---|
☆ Extract passages ☆
格好の笑いのネタにされるのは、まずロシアやプーチン大統領だが、国連、バイデン大統領、赤十字やNGOもこき下ろされ、ゼレンスキーを含むウクライナの政治家までもが容赦なく笑いのめされる。
コメディアンたちは、「戦時下のいま、なぜコメディーなのか」とよく尋ねられるという。それに対してある芸人は「戦争下だからこそ、笑うことで正気をとりもどし、楽観的になって抵抗を続けていける」という。観客にとって笑いは「感情のチャージ(充電)」「傷ついた心への薬」。戦争の現実に押しつぶされそうになる自分を笑いで支えるのも、戦時下の「ニューノーマル」のようだ。コメディアンたちは笑いを必要とする人に届けることを自分たちの「戦い」と捉えており、ボランティアで学校や避難所で演じるほか、兵士を慰間するため前線にまで赴いている。
(高世 仁 著『ウクライナはなぜ戦い続けるのか』より)
No.2398『こだわりが強すぎる子どもたち』
著者は、「うちの子は強いこだわりがあって、食べ物の好き嫌いもひどくて育てにくい」と感じたら、PANS(パンズ)/PANDAS(パンダス)かもしれないといいます。
私は、このPANS/PANDASという病気を知らなかったのですが、脳の炎症が原因なので、その炎症を抑える食事と生活環境を変えることで症状を改善できるそうです。私は子育てをすませ、むしろ孫たちに関心が移っているので、今の子育てというのは大変だなというのが第一印象でした。
その炎症を取り去るのは、家庭で9割もできると第3章「親子でPANS/PANDASをやっつける方法」というのが書いてあり、①環境を整える、②食事を改善する、③お腹をととのえる、④ミトコンドリアの働きをサポート、⑤解毒する、⑥免疫アップ、で、ここまでは家庭できるそうです。それから先は感染症治療になります。
しかし、この家庭でできることを全てしようとすると、大変なストレスになりそうです。住環境も匂いのあるものはダメとか石けん系の洗剤や柔軟剤も子どもの脳に影響があるといわれれば、使えるものがほとんどなくなります。また、食べものでも、グルテンフリーやカゼインフリー、さらに糖質も青魚もといわれれば、何を食べたら良いのか悩んでしまいそうです。
たしかに、「魚を食べるときは、まな板にのるサイズのものを食べる、と覚えておきましょう。具体的にはイワシ、サバ、アジ、サンマ、アユ、ニジマス、サーモン(サーモンは大きいですが、生存期間が短いため)や、シラスなどの小魚もおすすめです。」とか、「小松菜やブロッコリーなどの緑黄色野菜に多く含まれているのが「葉酸」です。葉酸はビタミンB群の一種ですが、脳の神経伝達物質の代謝に使われます。そのため、葉酸が不足すると、脳の神経伝達物質の代謝経路が回らなくなってしまうので、集中力が落ちる、不安になる、記憶力が低下する、気力が落ちることも……。」などは、すぐ納得できましたが、それ以外の私の好きなもののほとんどはねられてしまいそうです。
たしかに日常生活においても、注意しなければならないことは、たくさんあります。しかし、これもダメ、あれもダメといわれると、だんだんと窮屈になり、身動きが取れなくなってしまいます。毎日、病院で入院生活をしているわけではないので、ラフに考えることも大切だと私は思います。
でも、ある程度は、自分の孫たちには気を付けてほしいことがたくさん書いてあり、伝えていければと思いました。
下に抜き書きしたのは、「プロローグ」のなかに書いてあったものです。
このPANS/PANDASという病気をまったく知らなかったのですが、これからもその実体を把握するのは、専門医でもなければ難しいと思います。
だとすれば、私のような素人が読むよりは、お医者さんにこそ読んでほしいと思いました。
(2025.2.22)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| こだわりが強すぎる子どもたち | 本間良子・本間龍介 | 青春出版社 | 2024年10月30日 | 9784413233781 |
|---|
☆ Extract passages ☆
すべての子どもは、自分の能力を発揮できるポテンシャルを持って生まれてきます。それなのに、そのポテンシャルに気づいであげられない。その結果、本当の意味での「個性」は消えてしまっているのではないでしょうか。
その子どもの苦しみを理解し、解決の糸口をぜひ見つけてほしい。そして、子どものポテンシャルに気づいてあげてほしぃ……。これは、急務です。
もう一度、お伝えします。コロナ後、世界中の子どもたちの間で急増しているPANS/PANDAS。今現在苦しんでいる子どもたち、そしてこの先も苦しみ続ける子どもたちを一人でもなくし、子どもたちの本来の能力が発揮できますように!
(本間良子・本間龍介 著『こだわりが強すぎる子どもたち』より)
No.2397『面白すぎる天才科学者たち』
No.2396『神が愛した天才科学者たち』を読んで、たしか、似たような題名の本があったことを思い出し、まだ読んでいない棚から引っ張りだして読みました。
この本も、世界の著名な科学者17人について、科学的な業績だけでなく、「ダメ要素こそ人の魅力」とばかりに、意外な一面まで取り上げています。そして、「坊ちゃん育ち」か「たたき上げ系」かと、「家庭的」か「浮気性」かという二次元チャートをつくっています。
家庭的か浮気性かと取り上げることでもわかりますが、たとえば、アルベルト・アインシュタインの目次には「実は女グセが悪い暴言家」とあったり、ニールス・ボーアは「心ここにあらず、でも物理学界でも家庭でも良きパパ」とか、ちょっと週刊誌的な評価になっています。だから、取っつきやすいという一面はあります。
『神が愛した天才科学者たち』では、日本人は湯川秀樹と野口英世の二人が取り上げられていましたが、この本では南方熊楠一人で、目次には「日本のレオナルド・ダ・ヴィンチ、奇人ぶりも超人的」と書いてあります。両著に出てくるのは、ニュートン、ダーウィン、アインシュタイン、ファラデー、ラボアジェの5人です。この5人は間違いなく天才科学者です。
この本に取り上げられた科学者で印象に残っているのは、やはり南方熊楠です。今のネイチャーと単純に比べることはできないにしても、日本人で最多の約50報が載っていて、今でもその記録は破られていないそうです。この本のなかで、「今でこそ、その業績を評価されている熊楠ですが、当時の評価は気の毒だと感じてしまいます。実際、柳田國男も彼のことを「巨人が縛られたような状態」と評しています。確かに、時代が早すぎたばかりに、そのオ能は無視されていました。もし当時の日本が彼を受け入れていれば、もっと恵まれた研究や生活が送れたかもしれないのに、と。でも、熊楠の長女である南方文枝さんは誰にも東縛されずに、一途に好きな学問の世界を生き抜いた父は、幸せな生涯を送つた、という趣旨のことをインタビューで語っています。」と書いてあり、おそらく人の評価などまったく気にせず、好きな学問に邁進していたのかもしれません。
また、外国人で面白いと思ったのは、リチャード・ファインマンです。私も「ご冗談でしょう、ファインマンさん」(上巻下巻、岩波現代文庫)を読んだことがありますが、とても面白かったです。まさに、「なぜだろう?」といつも好奇心いっぱいの子どものような人で、この本にも「終始、「頑固な子供」であり続けました。好きなものは好き、でも気に入らないものは絶対に嫌。彼にとって気にくわないモノは徹底して拒否します。物理学者であり夏目漱石の門下生であった寺田寅彦は、「好きなもの イチゴ珈琲花美人 懐手して宇宙見物」という素敵な短歌を残しています。」と書いています。
そういえば、寺田の本で、「懐手して宇宙見物」というのが みすず書房の「大人の本棚」シリーズにあるそうですが、まだ読んだことがないので、機会があれば読みたいと思っています。
また、寺田が椿の落下を研究していたころ、「花は樹にくっついている間は植物学の問題になるが、樹を離れた瞬間から以後の事柄は問題にならぬそうである。学問というものはどうも窮屈なものである」と語っていたそうです。
私にとっての寺田寅彦は、科学者というよりは、随筆家のような印象の方が強いみたいです。
下に抜き書きしたのは、マイケル・ファラデーについての話しです。
彼は病弱の鍛冶職人の父の子で、大学どころか小学校へもまともに通うことができず、13歳で製本屋に奉公に出ました。でも、この製本屋で働くことで、いくつもの幸運が重なったといいます。だから、なるべくして大科学者になったというか、すごい強運を持って生まれたというか、そこが人生の面白いところです。
(2025.2.19)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 面白すぎる天才科学者たち(講談社+α文庫) | 内田麻理 | 講談社 | 2016年3月17日 | 9784062816526 |
|---|
☆ Extract passages ☆
そんなフアラデーの奉公先は製本屋でした。これからお話ししますが、彼の人生は大科学者になるために、「これでもか」というくらい、いくつもの幸運が重なっています。運も実力のうちなのでしょう。製本屋で働くことになったのがまず彼の幸運の始まり。当時、本は高価だったのでファラデーが買うことができるようなものではありませんでした。でもファラデーはそのような高価な「商品」だった本を無料で読めるような環境を得て、科学の本を読みあさるのです。でも、ひょっとしたらファラデーの奉公先が製本屋だったのは、向学心旺盛な彼自身の選択だったのかもしれません。
そして二つめの幸運。製本屋の客の一人が、ファラデーの科学への傾倒ぶりに感心して、王立研究所のデーヴイの講演のチケットをプレゼントしてくれたのです。
(内田麻理 著『面白すぎる天才科学者たち』より)
No.2396『神が愛した天才科学者たち』
世界の著名な科学者や発明家、16人についてエピソードや略年譜などを掲載しながら書き記したものです。
この本に出てくるような天才科学者は有名ですから、ほとんど知ってはいましたが、唯一、知らなかったのはロシアの化学者、メンデレーエフです。彼は原子量の大きさの順に並べた元素の性質が周期的に変化する周期律を発見した方で、ほんらいならノーベル賞級の発見でしたが、当時のノーベル賞は欧米白人社会中心だったそうで、ロシア人ということもあり、選考会でたった1票差でフランスのモアッサンに敗れたそうです。そういえば、自然科学分野で東洋人初の受賞は1949年の湯川秀樹博士でしたから、やはり時代的なものもあったようです。
彼は化学者として一流で、各地の大学で教授をしていますが、ペテルブルク大学で左翼学生運動を支持し連座して大学をやめたそうです。この本には、「彼が左翼学生を支持した理由は、シベリアに育った子ども時代に求めることができる。メンデレーエフの祖父は、 シベリア初の新聞社を興した言論人で、自由の徒であった。このような家系の影響を強く受け、メンデレーエフは、生来、自由主義者であった。さらに、幼少時代、シベリアに流された科学者から科学教育の手ほどきを受けた体験から、政治犯への同情と共感の思いが底流にあったことも見逃せない。だが、左翼学生への支持は彼の立場を決定的に不利にし、ロシア科学アカデミーの会員にも選出されなかった。」そうです。
しかし、彼は当時のロシア科学界では、ただひとりヨーロッパ科学のレベルに達していたし、周期表を発見し、さらに技術百科事典の刊行、 コーカサス油田やドネツ炭田の調査なども行い、ロシア国には多大なる貢献もしました。そこで、ロシア政府は、1893年には度量衡局総裁に就任させるなど、それなりの計らいをしたようです。
そういえば、天才はひとりでなれるものではなく、多くの方たちの後ろ盾も必要です。たとえば、野口英世の場合は母親で、「村の危機を一人で救ったエピソードでわかるように、野口の母シカは、実際にはかなり行動力のある人だった。ぐうたらな夫、病弱な祖母、子ども二人をかかえて夜昼となく働きながら、清作へのいじめを阻止すべく小学校へ乗り込み、いじめっ子と直談判した。清作が高等小学校へ進学を希望していることを小林栄に伝え、学費の援助まで引き出したのもシカだし、野口が医師をめざしたときも、そのことで小林に相談をもちかけている。世界のノグチヘのレールを実際に敷いたのは、小林先生でも渡部医師でもなく、母シカかもしれない。」と書いていますが、たしかにそのような面は否定できません。
ここで「村の危機を一人で救ったエピソード」というのは、1868年に会津若松城が落城したときに、その勢いにまかせて「官軍はとなりの翁島(今の猪苗代町、野口の出生地)を焼き払おうとしたとき、必死に官軍に願い出て村を焼減から救ったのが、まだ16歳のシカであった。」というものです。
下に抜き書きしたのは、パスツールの狂犬病ワクチンについての話しです。
じつは、私もマダガスカルに行くとき、向こうには野犬が多いから狂犬病ワクチンをしていったほうがよいといわれ、調べてみたことがあります。そのときは、狂犬病ワクチンが16,500円で、それを2回受けなければならないということでした。破傷風は3,850円で、これも2回ですから7,700円です。何度もマダガスカルに行っている方に聞いたら、人を噛むほど元気のよう犬はいないということで、そのときは破傷風のワクチンだけ打ちました。
この本を読むと、狂犬病にかまれても、早めにワクチンを接種すれば助かるそうですが、破傷風にかかると、亡くなる割合が非常に高い病気だそうです。しかも傷口から罹患してから発症するまでの潜伏期間は、短い人で3日、長い人では3週間程度もあるそうで、やはり、こちらを接種しておいてよかったと思いました。
でも、パスツールは電子顕微鏡がなければこの狂犬病ウイルスを見ることはできないのに、「病気には原因がある」という科学的な考え方で狂犬病ワクチンをつくったのですから、すごいことです。
電子顕微鏡は、1932年にドイツのクノールとルスカによって作られたので、パスツールは生きているうちには見ることができなかったようです。
(2025.2.16)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 神が愛した天才科学者たち(角川ソフィア文庫) | 山田大隆 | 角川学芸出版 | 2013年3月25日 | 9784044094461 |
|---|
☆ Extract passages ☆
実際のワクチンは、狂大病に感染した患者から採取した未知の病原体を、ウサギの脊髄に植え、それを乾燥したものからつくった。
これは本物の狂犬病ウイルスより弱い毒性をもち、狂犬に咬まれて潜伏期にあるうちに注射すると抗体ができ、本来の狂犬病ウイルスを殺すしくみである。
ちなみに、ジェンナーの種痘法(1796年)は、種の違う病原体の利用法だったが(牛痘ウイルスの抗体で人痘ウイルスを殺す)、パスツールのやり方は、本物の毒性を薄めたものを接種して、人体に強制的に抗体をつくらせ、それで侵入したウイルスを殺すやり方だった。
狂大病ワクチンを接種した患者は、劇的に回復した。パスツールは救世主となったのである。
(山田大隆 著『神が愛した天才科学者たち』より)
No.2395『私的な書店』
ひとりの韓国の女性が、本が大好きということで、本屋を開くまでの物語です。副題は「たったひとりのための本屋」で、カウンセリングをしながらその人のための本を選ぶという書店です。
このような本屋さんは聞いたことも観たこともありませんでしたが、思い出したのは、北海道砂川市にある「いわた書店」の「1万円選書」という取り組みです。この『本のたび』のNo.2027『一万円選書』でも取り上げましたが、ポプラ新書の「一万円選書: 北国の小さな本屋が起こした奇跡の物語」の著者、岩田徹さんです。
そのときも書きましたが、1万円で本屋さんが選んでくれ本を送ってくれるというサービスで、でも、本というのは、自分で読みたい本を自分で選ばなければおもしろくないのではないかと思いました。なぜ自分で選ばずに他の人に選んでもらうのか不思議でした。
しかも、この私的な書店は、本を処方するプログラムとして3万ウォンから5万ウォンを支払うということです。3万ウォンといってもピンとこないので今日現在の日本円の換算で、3,200円ほどです。5万ウォンなら5,530円ほどになります。この料金は、1対1で話しをする1時間、「サルビア喫茶店」の新鮮な茶葉で淹れたお茶1杯、たったひとりのために選書した1冊と手紙、包装代と配送費が含まれるそうです。だとすれば、3万ウォンから安いし、5万ウォンならそこそこではないかと思いました。
いわた書店の岩田徹さんの場合は、応募者のカルテをもとに、1万円分の本を選んで届けるサービスです。でも、最近になって思うのは、どのような本を読んでみたいかわからない方には、必要なサービスかもしれないと考えるようになりました。
私の場合は、本屋さんでも図書館でも、ほとんど苦もなく簡単に本を選びます。理系も文系の本も、なんでもいいから選ぶのも楽なんです。
この本のなかに、「私は、こんなに素晴らしいものを自分だけが知っているのはもったいない、と思うようになりました。本と出会うことでどんなに人生が豊かになるか、それを伝えたかったのです。本を一冊読んだからといって、突然人生が変わるわけではありませんが、それでも本を読むことで、より良い自分になれる可能性はあります。本はまさに「種」なのです。どんな実がなるのかは誰にもわかりませんが、たとえ芽が出なかったとしても、「種」がなければその機会さえありません。本を読むということは、人生に「可能性」を植えることだと言えます。」と書いてあり、そういえば、私がこの『本のたび』をつくったときも、たしかこのような気持ちがあったように思います。
この上の『本のたび』について書いたところに、「今時の若者はあまり本を読まないということを聞き、こんなにも楽しいことをなぜしないのかという問いかけから掲載をはじめました」と書いています。その気持ちは今も変わらないのですが、街中の本屋さんはめっきり少なくなりました。たしかに通販も楽ではいいのですが、本を選ぶ楽しさは実際の本屋さんが一番です。1冊1冊、棚から引っ張り出して内容を確認してから選ぶのが楽しいのです。たまには、じっくり読んで初めてよくわかるものもあるし、何度読んでもなかなか理解できないこともあります。でも、本棚に並べて置いて、時間が経ってから読み直すと、意外とおもしろかったりするとうれしくなります。
私も、本はほんとうにワンダーランドだと思っています。
下に抜き書きしたのは、「それでも」に書いてあったものです。
いくら本が好きだと言っても、それが仕事になれば、まったく別です。私も本は好きですが、本屋をしたいとはまったく思ったこともありません。ただ、私設の図書館を開きたいと思ったことはあります。それも、自分の好きな植物関係の図書を中心に集めて、開放するというものです。しかし、場所の確保と管理の大変さで、諦めました。
また、若い時は本を1日中ずっと読んでいたいと思い、それなら灯台守ならできるかもしれないと考えたこともあります。しかし、今ではその灯台守も、ほとんどがリモートで管理するようになったそうで、ならなくてよかったと思います。
ある植物好きの方から、植物好きが高じて山草屋になったけれど、流行り廃りがあったり、愛好者も高齢化するなど、やはり好きなことを仕事にすると大変だと聞かされ、この本屋さんの話しを思い出しました。
楽しみは、自分で稼いで、それを使って楽しむのが一番ではないかと思っています。
(2025.2.13)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 私的な書店 | チョン・ジヘ 著、原田里美 訳 | 葉々社 | 2024年11月22日 | 9784910959054 |
|---|
☆ Extract passages ☆
固定の営業時間を決めていなかったので、問い合ゎせがくれば朝でも夜でも、平日、週末関係なく、いつでも返せるように二十四時間体制で待機していました。自分の時間を捻出するために考えた「予約制」に、むしろ足を引っ張られていたのです。会社で働いていたときは、自分が担当する仕事だけをしっかりやればよかったのですが、掃除から精算、税務業務までのすべてをひとりで処理しなければなりませんでした。やることは多いのに時間が足りないのだから、他に選択肢はありません。休みを返上する以外には。
(チョン・ジヘ 著『私的な書店』より)
No.2394『在野と独学の近代』
この本の副題は「ダーウィン、マルクスから南方熊楠、牧野富太郎まで」と書いてあり、それぞれに思い出の方たちばかりです。
というのは、2017年9月5日に、エジンバラ植物園を訪ね、その標本館でシャクナゲの標本をさがしていると、そこの研究者がダーウィンの標本を持ってきて、見せてくれました。そこには、1831年から1836年にかけて、ビーグル号に乗って世界を回ったときに採取したと書いてあり、これは今も覚えているぐらい衝撃的でした。マルクスは、学生時代に左翼系の教授が課外授業として資本論の読書会に誘われて読みました。また、南方熊楠は上野の東京国立科学館で神仏分離のときの資料を見て感動しましたし、牧野富太郎は昨年のNHKの朝の連ドラ「らんまん」で取り上げられ、植物監修者に誘われて四国のロケ現場まで行き、いろいろなところを見てまわりました。
それらを思い出しながら読むと、牧野富太郎は東京大学に所属はしていましたが、在野の植物愛好家たちと交流があり、その縁からたくさんの標本が集まってきたようです。そう考えれば、いわば大学に所属し研究をする人たちとは一線を画します。
そういう意味では、この本のなかにあった「牧野に情熱と植物への愛があったのはまちがいなく、親切かつ正確に教えてくれることがアマチュア植物愛好家たちの信頼につながった。とはいえ、それだけでは情報の集積点となることは不可能だったろう。重要なのは、東大に所属しているという牧野の身分にほかならなかった。大学業界では、身分の低い講師にすぎなかったかもしれない。しかし、アマチュアの目からすれば、牧野は東大所属の立派な研究者で、尊敬すべき存在であった。……牧野が1927年に理学博士号をもらっている点も注目される。これに対して熊楠は「ドクトルとかプロフェッサー」といったひとたちを毛嫌いしていた。しかし、博士号という箔付けは、ときに重要なものとなる。牧野はそのことをよく理解していたのである。」ということは、私も大切なことだったと思います。
朝の連ドラ「らんまん」のなかでも、牧野本人が私はこだわらないという台詞がありましたが、妻のスエ子さんは、大喜びだったと語っています。おそらく、これが本音で、あのシーンは、現在の小石川植物園の本館前でロケをしたそうです。
さらに、現在は植物分類をDNA解析による系統関係の研究、つまり新分類体系であるAPGシステムが主流ですが、それでも本の名前は、「新分類 牧野日本植物図鑑」です。ただ、2017年に出版されたものでは、著者や編集は邑田仁(東京大学大学院理学系研究科教授)と米倉浩司(東北大学植物園助教)となっています。
つまり、分類が大幅に変更されてもなお、牧野氏の名前が入っていることに驚きますが、私もアマチュアのひとりとして、名前が残っていることにいいことだと思っています。
また、三田村鳶魚の研究のところでも、「鳶魚の側でも、「世の学者は手で書くが、俺は足で書く」と述べ、各地の旧家を訪ねては古文書を見せてもらっていた。幕末に御殿女中をしていた村山ませ子のもとに6~7年も通って聞き取りをしたほか、元与力の原胤昭(たねあき)、元広島藩主の浅野長勲(ながこと)らにも情報を提供してもらった。江戸の話を鳶魚が聞き取りできたのは、その熱心さや知識にくわえて、武上の家系という出自によって、「仲間」とみなされたのもあるだろう。また親しくしていた古書店の吉田書店(現在の台東区台東にあった。熊楠のところにも販売書目を送っていた)を通して、写本、日記、道中記を入手した。吉田書店はこれらを、江戸からつづく古い屋敷がなくなるとき、廃品回収業者を通して集めていた。とくに関東大震災後は、旧大名家をはじめとした旧家の上蔵が壊れるなどして、多数の資料が市中に出回ったという。官学の教授たちとは、情報収集法において、とてつもない距離があったのである。」とあり、アマチュアだからこそできる資料収集法だと思いました。
やはり、鳶魚がいうように、「世の学者は手で書くが、俺は足で書く」という気概も必要だと感じました。
下に抜き書きしたのは、終章「アマチュア学者たちの行方」に書いてありました。
私の知り合いにも大学などの研究機関に所属している研究者もいますし、定年退職後にフルで足まめに出かけて研究をしている人たちもいます。それでも、日本では、やはりプロの研究者でないとできないことがたくさんあります。ただ、私の場合は、プロの研究者たちと出かけることが多く、その恩恵に浴することもあり、アマチュアでいることを楽しんでいます。
そういう意味では、しばられることは何もないので、自分が思うままに突き進むことができ、最後は自分が納得できればよれでよし、と思っています。
(2025.2.10)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 在野と独学の近代(中公新書) | 志村真幸 | 中央公論新社 | 2024年9月25日 | 9784121028211 |
|---|
☆ Extract passages ☆
いまの日本では、プロの研究者とアマチュアの研究者の区別は簡単で、大学や研究所といった機関に所属しているかどうかで見分けられる。両者の区分は厳密で、アマチュアをわざわざ研究者ではなく、「研究家」と呼ぶことすらあるほどだ。周囲から「違う」と認識されているのみならず、本人のアイデンティティ的にも異なっている。両者のあいだには明確な階層の違いがあり、日本ではアマチュアの地位が極端に低いように感じる。それに対してイギリスでは、現在もアマチュア研究者たちの存在感が大きい。アマチュアが変に萎縮したり、逆に自意識が強くなりすぎたりもしていない。アマチュアとプロの垣根が低いのである。
(志村真幸 著『在野と独学の近代』より)
No.2393『風景をつくるごはん』
この本の出版社は農文協ですが、正確には「一般社団法人 農山漁村文化協会」というそうで、今まで本の内容と出版社との関係などあまり気にも留めませんでした。それでも、この副題の「都市と農村の真に幸せな関係とは」をみると、こういう出版社だからこその本のように思えてきました。
この本の題名の『風景をつくるごはん』という意味は、「良好な農村環境、農村社会を象徴するものとしての「風景」、消費者の意志や選択次第でそれが変化するということを表わす「つくる」という能動的な動詞、そして消費者が選ぶ対象となる野菜などの食品である「ごはん」から成っている。目的、手段、対象が入っている名前である。」といいます。
そして、著者の今住んでいる徳島での基本ルールとして、
1.基本は徳島県内産の食材
2.選べるときはなるべく過疎地域のもの
3.できるだけ産直市で購入
4.調味料など難しい場合は四国内
5.加工品は天日干しや伝統的手法のもの
6.旅行先で買ったものはOK(むしろ積極的に)
7.それ以外は栽培過程に配慮がなされたもの
と食べ方を明文化しています。
著者は、イタリアとのつながりがあり、日本の農村とイタリアの農村との比較などもあり、とてもおもしろく読みました。やはり、1カ所から見て掘り下げることもいいとは思いますが、違った角度から見てみることも必要なことです。たとえば、イタリアで長ネギが替えなかったという話しをのせていますが、「産直では、土地と季節に縛りがあり、並んでいる野菜は限られている。たとえば冬には大根、白菜、水菜、ホウレンソウといった野菜しか並んでいない。そうするとおのずと、並んでいる野菜を見ながら「今日は大根をどうやって食べようか」と考えるのである。「カレーが食べたいからジヤガイモとニンジンと……」という食べ方ではなく、そこに並んでいるものからメニューを発想する。メニューの大元を決めるのは私ではなく、土地と季節である。おそらくかつての暮らしはこうだったのだろう。私たちはいつの間にか人間が食べたいもの、あるいは栄養学的に見て食べるべきものからメニューを決めることが当たり前になっていたのだとあらためて気づかされた。」と書いています。
たしかに、私も野菜などを買いに、JAの愛菜館に行きますが、季節によってすごく種類のあるときと、生産者が違っていてもほとんど同じものしか並んでいないときがあります。むしろ、欲しいと思って立ち寄ってもないときもあり、珍しい野菜を見つけて、どのようにして食べるのかと考えさせられるときもあります。
おそらく、農家さんたちも、なるべく違った野菜を栽培して差別化を図ろうとしているようで、行くのも楽しくなります。しかも、今の時代は、パソコンなどで簡単にレシピが手に入るので、ある意味、料理の幅が広がってきているような感もあります。
下に抜き書きしたのは、第10章「社会のシステムを変えるための小さな行動」に書いてあったものです。
私の若いころに見た映画には、タバコを吸うシーンはかなりありましたが、今では映画だけでなく、テレビや雑誌などでもほとんど見なくなりました。昔は、部屋がタバコの煙で充満していても、誰も文句のいう人はいなく、むしろ当たり前のような風景でした。それが今では、建物の目立たないところに設置された喫煙所で、こそこそと吸うしかないような状況です。
おそらく、タイムマシーンで昭和前期の時代から今の時代に来ることができれば、タバコだけでなく、いろいろなものが様変わりしているはずです。急に変わったのは気づきやすいのですが、徐々に変化したものはなかなか分からないものです。ということは、いかに社会のシステムを変えるのは難しいといっても、みんなで少しずつ変えることは可能です。
このたとえは、私にとっては目から鱗でした。変えるのが大変なことほど、これからはこのようになってほしいと強く思うなら、なんとかなりそうです。
(2025.2.7)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 風景をつくるごはん | 真田純子 | 農文協 | 2023年10月5日 | 9784540231247 |
|---|
☆ Extract passages ☆
すべての人の行動や価値観が変化したわけではないが、たばこをめぐる「社会の価値観」は完全に変化しているのである。その過程では、たとえば駅情内や列車での禁煙化の拡大など具体的な規制、増税など吸わないことへのインセンティブがつけられた。そのほか、人びとの意識づけとしてパッケージヘの注意書き、テレビやラジオ、雑誌等でのCMの規制などが行なわれた。特に意識づけに関する取り組みはそれぞれは効果が見えにくいものであるが、それらの積み重ねで、たばこのィメージは変わったのである。
(真田純子 著『風景をつくるごはん』より)
No.2392『マンゴーの歴史』
この本は、『「食」の図書館』シリーズの1冊で、調べてみると、私はこのシリーズを8冊、バニラ、イチジク、ココナッツ、ベリー、豆、食用花、トマト、コーヒー、サラダの各歴史ですが、「お茶の歴史」も読んでみたいと思いました。
しかも、写真やイラストがカラーで紹介されていて、読むだけでなく見る楽しみもあります。
初めてマンゴーを食べのは、だいぶ昔の話しになりますが、息子たちと種までしゃぶるようにした食べた記憶があります。そして、初めてマンゴーの木を見たのはインドで、まさか街路樹にもなっていることをそのときに知りました。マンゴー園については、お釈迦さまがこのなかで説法をしたという記録もあり、知識としては知っていましたが、見るのは初めてでした。
そういえば、ネパールの友人宅にホームスティしたときには、私がマンゴー好きだと知り、毎朝、生のマンゴーを絞ったジュースを買いに行ってくれました。当然ながら、マーケットでは、マンゴーがあれば必ず買って帰りましたが、日本で買うよりは格段に安かったことを覚えています。
この本の最初のところにマンゴーの起源が載っていて、「6,000万年前のマンゴーの葉の化石と現代のマンゴー種の比較から、古民族植物学者らは、マンゴーの起源がインド北東部にあると結論づけている。その実が、そこからインド南部や東南アジアヘと広がったのだ。紀元前1,500年ごろの石うすや陶器、また、同時期にインド亜大陸で栄えた最古の文明、ハラッパーの遺跡で発掘された品々から、微量のマンゴーが見つかっている。マンゴーの繊維は、遺跡発掘現場で出土した人間の歯からも検出された。」ということでした。
そういえば、マンゴーという言葉は、ケララ州の「マームカーイ」と発音することから、さらに「マーンガ」と変化し、16世紀にポルトガル人がケララ州に入植しこの果物と出会い、彼らはそれを「マンゴー」と呼んだそうです。私がケララ州にいったときは2018年9月だったので、まだマンゴーのシーズンではなく、植物園がココナッツを飲ませてもらいました。
この本のなかで、玄奘三蔵の話もあり、「中国から訪れていた僧侶の玄奘(602~664)は、ハルシャの時代の仏教大学ナーランダ僧院に「直射日光をさえぎる濃い木陰を居住者にもたらすマンゴーの森」があったと記している。マンゴーはインド中に生えていたと彼は言う。」とありましたが、私がナーランダ遺跡に行ったときには、その近くにはマンゴーの森はなかったようです。
また、仏教の寓話には、マンゴーを果実や木の話しが多く、お釈迦さまもよくマンゴーの木の下で説法をしたそうです。そこで、私も岩波文庫の「ブッダ最後の旅: 大パリニッバーナ経」中村 元訳、を読みながら、その場所を歩いたことがあります。そこには、マンゴー園もあり、いくつかの場所で写真を撮ったことがあります。
下に抜き書きしたのは、第7章「マンゴーと比喩と意味」に書かれていたもので、ガンディーらしい比喩だと思い、ここに取り上げました。
この他にも、「マンゴーの木はすぐには実をつけない。マンゴーのような木に何年もの世話が必要であるのに、まさに木のような存在でありながら、かくも長いあいだ教育を受けさせてもらえなかった女性に対して、いったいどれほどの思いやりある支援が必要となることか。」という言葉も残っていて、いかにインドの人たちにとってマンゴーは身近な果物だったのだと知りました。
(2025.2.3)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| マンゴーの歴史 | コンスタンス・L・カーカー/メアリー・ニューマン 著、大槻敦子 訳 | 原書房 | 2024年11月30日 | 9784260057660 |
|---|
☆ Extract passages ☆
マハトマ・ガンディーは人生の大半でおいしいマンゴーを楽しんでいた。みずからのメッセージを伝えるための比喩として、幾度となくマンゴーの実や木を用いている。
マンゴーの苗を植えて2~3日水を与えなかったらどうなるか、あるいは苗の周りに垣根を作ったらどうなるかを考えてほしい。(中略)マンゴーの木は伸びて大きくなるにつれ、低く頭を垂れる。同様に、強者も力を増すにつれて、いっそう謙虚に、いっそう敬虔になるべきだ。
(コンスタンス・L・カーカー/メアリー・ニューマン 著『マンゴーの歴史』より)
No.2391『銀座で逢ったひと』
この本の著者と一字違いの人を知っているので、そのような縁から図書館で借りてきました。そして読んでみると、ほんとうにおもしろく、その交友の広さにもびっくりしました。
もともと、この本は、「銀座百店」に連載された同じタイトルのエッセイ(2018年1月号から2021年3月号まで)のなかから37編を選んで加筆修正してまとめたもので、さらに「誠の人、情の人 十八代目中村勘三郎」を収録したそうです。
そういえば、この冊子を銀座の伊東屋でもらったことがあり、ホテルで読んだこともあります。しかしその内容はほとんど覚えていませんが、無料だったことだけはしっかりと記憶しています。
印象的だったのは、宗教にも詳しい哲学者の梅原猛さんに、著者は輪廻転生について聞いてみたことがあるそうです。そのとき、『「それは必ずあるな。人間、ぐっすり眠って目が醒めても、昨日のことを忘れてへんやろ。それと同じで、生まれ変わっても前世の記憶があるから、ピアノがだれよりも早く上達したり、絵がうまく描けたりする者がおる。いくら習ってもあかんやつは、生まれ変わりのまだ浅い人間やな」この話には深く納得がいって、天才と言われる方々を見聞きするたびに、梅原さんの熱っぽくあたたかな声音と、はにかみながらも自信に満ちた表情がなつかしく思い浮かぶ。』と書いてありました。
おそらく、このような曖昧ことを文章にするのはなかなかできないことで、話しのなかだからこそ、気楽に答えられたのではないかと思います。
そういえば、私の知り合いのインド人は、知識もあり高学歴でもありますが、この輪廻転生を信じています。むしろ疑ったこともないようで、だからこそ生きものを殺すことはしません。そういう意味では、輪廻転生という考え方は、やさしさでもあります。だから、私も信じているというよりは、そのように信じることで、いろいろな生きものに優しく柔軟に対処できるような気がします。
著者は、古今亭志ん朝さんの歯切れがよく、威勢もよい江戸前落語が好きだったそうで、多くの落語ファンの方たちもいつかは親譲りの「フラ」を聴いてみたいと思っているのではないかといいます。
この「フラとは、父志ん生のような瓢逸な芸風を指すのだろう。あるとき、志ん朝さん自身がこんなふうに言うのを聞いた。「なんであんなに、え―、とか、ん~とか、考える間が多いの? もしかして、忘れたのを思い出してる時間なの? って、息子じゃなきゃ訊けないようなことを親父に訊いたんです。そしたら「ん~、そりゃあね、なんだよ、え~ほら、俺が、ん~っていうと、お客が、なんですか? って感じで乗り出してくる。そこで一言、さっとかわす。その駆け引きがおもしれえんだよ」って言ってましたね。でも、これ若い芸人にはできません」ということです。
そういえば、笑点という番組で、喜久蔵が志ん生のまねをするときがあり、それも芸なのかな、と思っていましたが、この話で納得しました。
やはり、このようなひょうひょうとした話しをするには、若くてはできませんし、相当な修練を重ねないとだめだと思います。おそらく、ただ忘れたのではないかと思われるだけかもしれません。
私も年を重ね、話しをしてくれと頼まれたときには、このような間合いの取り方ができるようになりたいと思います。
下に抜き書きしたのは、「二代目尾上松緑さんの木札」にあったものです。
やはり芸人というのは、いつまでたっても完成したとは思わないようで、だからこそ日々精進するのかもしれません。
この言葉を聞いて、元気で一生懸命に修練しているときが一番いいのではないかと思いました。誰でもいつかは体力が落ち、したくてもできなくなるのが人間です。やはり、下手でも何でも、できるときを大切にしたいと思います。
(2025.1.31)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 銀座で逢ったひと | 関 容子 | 中央公論新社 | 2021年9月25日 | 9784120054662 |
|---|
☆ Extract passages ☆
やがてお茶が運ばれると、自ら気を取り直して私の観劇歴を訊ねてくれた。そこで『天下茶屋』『申酉』『江戸の夕映』の話をする。松緑さんがだんだん膝を乗り出してきて、「う―ん、あのころは俺もまだ若くて、元気溌剌だったからなぁ。しかし未熟だった。今ならもっと上手にできるけど、そうなると身体が利かない。うまくいかないものだねぇ」
カラカラと快活に笑って、少しの間だけ昔に戻ったようだった。
(関 容子 著『銀座で逢ったひと』より)
No.2390『谷崎『陰翳礼讃』のデザイン』
副題が「デザイナー谷崎潤一郎の暗さへの称賛」で、著者自身も鉱業デザイナーだそうで、デザイン事務所に勤務したりして、現在は和光大学名誉教授です。
だからこそ、『陰翳礼讃』で取り上げられた陰影というものをデザイナーの立場からどのように見えるのかと興味がありました。
ところが、この『陰翳礼讃』を読んだことがなく、これを機会に読んでみると、初めのところに、電気や瓦斯や水道なとの取り付けに日本座敷と調和するように句法するのがなかなか難しいという話しが出てきます。
まさに日本家屋に西洋の設備をうまく取り入れることから、新たなデザインが生まれます。そういう意味では、おもしろそうです。
たとえば、谷崎潤一郎が関西に引っ越した1927年ころは、電力会社と「一戸一灯契約」だったそうで、それは電球が電力会社からのレンタルで、電気の供給口は電灯用のソケット1つだけ、というものだったそうです。だから、それを各部屋に移動したり、アイロンを使う場合などはその1つのソケットにつないで使っていたそうです。このような状況だったからこそ、松下幸之助は1918年に1家で電球と電気器具を童子に使える「アタッチメントプラグ(アタチン)」をつくり、それが成功の礎になったそうです。
そのことを、この本では、「まだ若かった松下幸之助が、成功を遂げる礎にもなった小さな器具の開発は、彼特有の技術、すでにあるものに一寸だけ機能をつけ加えて、だった。普及した電球は壊れて廃棄される。その壊れた電球のネジ部分を手にいれ、それをソケットに組み込んだ。すでに一流のメーカーが生産していた電球の捻じ込み部分の性能は約束されていたから、故障がなく、しかも格安の商品になった。アタチンは売れに売れた。この「アタチン」の延長に松下を飛躍的に有望なメーカーにした二股ソケットが生まれる。」と書いています。
私は二股ソケットが飛躍的に売れたことが松下電機の礎だと思ってましたが、そうではなかったようで、壊れた電球のネジ部分をソケットに改良したそうで、この発想はいま考えてもすごいことです。
もちろん、『陰翳礼讃』を書いた谷崎には、それを使うというような発想よりは、それを見せない工夫こそが大切だったのではないかと思います。まだ『陰翳礼讃』を全部は読んでいないので、これから読んで、どのように感じるかは、もし機会があれば、そのときにでも書いてみたいと思います。
それにしても、明治時代というのは、一気に西洋文化が入ってきたことから、それを巧みに受け入れることに工夫も必要だったと思います。
この本のなかで、「和洋折哀へのもう一つの答えは、ヨーロッパ体験を生かさなければならない、という留学生達の自負があったからだ。だが日本人が暮らせる住空間は単に模倣だけではすまないことも分かっていた。というのはヨーロツパで日本人が驚いたのは、靴を脱がずに部屋で生活することだったにちがいない。ベットに入るまで靴を履いたまま暮らすなどと想像さえしなかった。」とあり、それをうまく折衷するのにスリッパを使ったとあり、今ではどこの家庭でも使っているものが、そのような工夫から生まれたと知りました。
下に抜き書きしたのは、第4章「カタカナで持ち帰ったモダン」に書いてありました。
ほとんどの文章は、『陰翳礼讃』からの抜書きですが、後ろの1節が著者の説明です。さらに、金継ぎなどで新品よりも美しい茶碗を生み出し評価したとありますが、たしかにそういう一面はあると思いますが、それ以上に大切にしたいということもあったようです。
というのは、昨年の10月4日に、静嘉堂文庫の「眼福 大名家旧蔵、静嘉堂茶道具の粋」を観てきましたが、いかに茶入を大切にしていたかを知りました。たとえば、そのなかにあった徳川家康から伊達政宗にわたった「唐物肩衝茶入 銘 山井」には、たくさんの添え物がありました。まるで宝物を大切に保管するために、何重もの箱をつくり、貴重な布地に包んでいました。
その展示物を観て、茶道具というのは、その故事来歴がものをいうという意味が、よくわかりました。
(2025.1.28)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 谷崎『陰翳礼讃』のデザイン | 竹原あき子 | 緑風出版 | 2024年11月5日 | 9784846124113 |
|---|
☆ Extract passages ☆
「われわれの喜ぶ『雅致』と云うものの中には幾分の不潔、かつ非衛生的分子がある」と言う時、その「不潔」とは、無常の時の流れの中で日々失われてゆく人々の生活の痕跡であり、モノと人との間の親しげな「関係」の蓄積である。それこそが、即ち「陰翳」となる。まだ人の口の垢に十分に汚れていない新語は、語の相互の微妙な調和の中で、不用意に浮き立って、全体の統一感を損なってしまう。それは新鮮なだけに不安定で、生活の実際を潜り抜けて角を落としていない分、手触りが悪く、前後の語との間に軋みを生じさせるものである」(『陰騎礼讃』)。不潔とは我々の生活の痕跡、だからこそ、それは陰影となるというのは、茶碗のひびも生活の痕跡だから陰影の一つになるとも受け取れる表現だ。谷崎は、直接金継ぎに付言していないが、金継ぎなどで、新品よりも美しい茶碗を生み出し評価してきた「茶の湯」は、室町時代の富と権力を見せびらかしたい男の趣味だった。
(竹原あき子 著『谷崎『陰翳礼讃』のデザイン』より)
No.2389『クマにあったらどうするか』
一昨年あたりから市街地にクマが出没するようになり、マスコミなどでもしばしば取り上げられましたが、特に昨年後半から、秋田県などではスーパーに立てこもったことで、殺さざるを得なくなりました。ところが、まったくクマをテディベアーと勘違いするかのような人たちが、県や市町村などに苦情電話が寄せられ、本来の業務に支障が出るほどだったそうです。
すると、秋田県知事が、「お前の所に今(クマを)送るから住所を送れ」と言ったそうで、またネットで騒動になりました。
この本にも書いてありましたが、本当の手負いのクマは逃げる力が残っていないので、「そうすると、生きようとしたら相手を倒すしかないんです。相手を倒してでも生きようという、その怖さをハンターの人らは知らないで、手負いでもう動かないから死んでいると安易に考えてしまう。鉄砲撃ちの場合は特に、自分の撃った弾で死んでいるという先入観があって、それがまた危険なんですよ。」といいます。だとすれば、ハンターも命がけなのですが、2018年に砂川市の要請でヒグマを駆除した猟友会会員が猟銃所持許可が取り消されました。その処分取り消しを求めてではその訴えが認められたのですが、2024年10月18日に札幌高裁で1審の判決を取り消し、請求が棄却されました。そのことから、北海道の猟友会では、もうヒグマの駆除はできないという声明を出しましたが、昨年の12月21日に、クマの人的被害が多発していることから、鳥獣保護管理法改正案として市街地でも緊急狩猟を拡大することにしたそうです。
この本は、アイヌ民族の最後の狩人である姉崎等さんが語り、それを片山龍峯さんが聞き書きしたもので、ヒグマの話しではありますが、ツキノワグマでもにたような生態を持っているのではないかと思います。最近のクマは冬眠をしないとはいうものの、春になればまたクマの話しが出てくると思い、読むことにしました。
そもそもこの本は、2002年4月に木楽舎から刊行されたそうで、文庫化されるときに再編集し、第1刷が2014年3月10日で、現在第17刷だそうです。ということは、かなりの反響があり、多くの人たちに読まれているようです。
この本のなかで何度か出てきますが、人を襲ったクマは、人の弱さを知ってしまい、何度も襲うそうで、奥山に放獣してもまた人を襲うから、姉崎さんは「殺す以外にない」と言い切ります。よく、素人はかわいそうだから山に返してといいますが、この本を読んで人を襲ったクマを返すのは絶対にしてほしくないと思いました。
ここに、この本のキモを書いてしまうのもどうかとおもうのですが、昨今のクマ騒動をみていると、せめてこのぐらいは知っておいてほしいと思い、抜書きしました。
姉崎さんがすすめる「クマに会ったらどうするか」10ヵ条ですが、
【まず予防のために】
1. ペットボトルを歩きながら押してペコペコ嗚らす。
2. または、木を細い棒で縦に叩いて音を立てる。
【もしもクマに出会ったら】
3. 背中を見せて走って逃げない。
4. 大声を出す。
5. じっと立っているだけでもよい。その場合、身体を大きく揺り動かさない。
6. 腰を抜かしてもよいから動かない。
7. にらめっこで根くらべ。
8. 子逹れグマに出会つたら子グマを見ないで親だけを見ながら静かに後ずさり(その前に母グマからのバーンと地面を叩く警戒音に気をつけていて、もしもその音を聞いたら、その場をすみやかに立ち去る)。
9. ベルトをヘビのように揺らしたり、釣り竿をヒューヒュー音を立てるようにしたり、柴を振りまわす。
10. 柴を引きずって静かに離れる(尖った棒で突かない)。
と書いてありました。
このなかで興味を引いたのが、クマはヘビが嫌いだということで、この本のなかに、「タラ(※背負い縄のこと)を投げつけるのも生きたヘビを投げたような形になるから彼らは嫌うんだと思います。登別のクマ牧場の中でもそういう実験をしたことがあって、クマは跳び上がって逃げますからね。あとは特にそんなに嫌うものはないと思います。」と書いてありました。
姉崎さんが山の中でクマが知らないで通って、そこにヘビがいたことに気づき、「ウオーッ」と怒ってバシンと何度も叩いたそうです。あの大きな足で踏みつけられたらそれだけでも死んでしまうのに、何度も叩いたというから相当怖かったのではないかと話していました。
下に抜き書きしたのは、第4章「アイヌ民族とクマ」のなかに書いてあったものです。
私も小さいときに負傷したカラスを飼ったことがあり、賢いことはわかりますが、そのカラスとアイヌの人たちは助け合っていたというから驚きました。私の場合はキズが治るまでということだったので、外に離しましたが、しばらくは近くの樹々の上で、学校から帰ってくるとカァーカァーと挨拶してくれていました。
その後、自宅の屋根の上で、ホウノキの実を転がして遊んでいるのを見たこともあり、下に落ちる寸前に飛んで来て拾うと、その実を見せびらかすように近くを飛ぶこともありました。
だから、ここに書いてあることも、すぐに納得しました。
ちなみに、「――」の部分は片山龍峯が聞いて、そのあとの部分は姉崎さんが離したところになります。
(2025.1.25)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| クマにあったらどうするか(ちくま文庫) | 姉崎 等(語り手)、片山龍峯(聞き書き) | 筑摩書房 | 2014年3月10日 | 9784480431486 |
|---|
☆ Extract passages ☆
――山に入ってカラスが騒ぐと、クマとかシカがいると言われていますが。
カラスが騒ぐと、クマがいるとか、獲物がいるという見方は、アイヌ民族が考えたことなんです。もともと猟をやっているから気がついたんだろうね。
――獲物をとったあと、カラスにどんなものを残すのですか。
肺臓とかその他の人間が食べられないところがありますね。それらをカラスに平均に当たるように細かく刻んでおいて、そこらの本の伎に1切れ1切れ刺しておくんですよ。
――それは姉崎さんの先輩の人たちから聞いたんですか、それとも自然に覚えたんですか。
それは話で聞いていました。カラスにおこぼれを与えることで、カラスも喜んで教えてくれるんだ、と。鉄砲撃ちが鉄砲を出していると、カラスは来ないのが普通なんですよ。ところがクマ猟に行くときは、カラスに銃を向けることは絶対にしないから、猟のハンターが弁当を出して食べているとカラスは鳴いて欲しがる。鳴いていると少しおこぼれを置いておく。するとカラスが後をついて歩くようになるんですよ。……
カラスは夏中ずっと、冬になるまで山にいるから、どのクマが来て、どこに穴籠りをするか知っているんです。クマは一度にさっと穴に隠れちゃうわけじゃないから、穴を掘るのに暇をかける。十日以上も暇がかかるから、カラスはそれを見てちゃんと覚えているわけですよ。そうすると、この近くにクマが隠れているって鳴くんです。
(姉崎 等(語り手)、片山龍峯(聞き書き) 著『クマにあったらどうするか』より)
No.2388『定年後が楽しくなる脳習慣』
最近、脳についてとても興味があり、図書館から借りてきました。読んでおもしろいかどうかがわからないのは、なるべくなら図書館から借りるようにしています。というのは、途中でおもしろくなければ読まなくてもよいと思うのは、自腹を切っていないからです。
つまり、気楽に読めるのです。ということは、性格的にケチなのかもしれません。
よく、好きこそ物の上手なれ、といいますが、たしかに好きなことだと長続きしますし、何よりも楽しくやれることが一番です。この本のなかに、「人は「できないこと」に「嫌い」というレッテルを貼る傾向があります。実際は「できない」というのは、脳のその部分が育っていないだけのことですが、「できる」状態にもっていくよりも前に「嫌い」の一言で片づけてしまうほぅが楽なのです。しかし、それを繰り返せば世の中は嫌いなことだらけになり、伸びるはずの脳も成長をやめてしまいます。……「好き」という感情をもって臨んだことのほうがより効果的に上達します。逆に「嫌い」と感じたものへの上達がなかなかうまくいかないのは皆さんも経験されていることでしょう。学生のときも、好きな先生の授業のほうが嫌いな先生の授業よりも耳に入ってきたはずです。「好き」という感情で始めたものごとが、その後も順調に上達していくのは、脳の成長システムと深くかかわっているからなのです。」と書いてあり、当たり前のことですが、まさにその通りです。
そもそも、やってみないことには「できる」とか「できない」ということもわかりませんし、ある程度の時間をかけてやってみないとどんなことでもわかりません。
だとすれば、好きだと思ってやることも大切なことで、そのほうが楽しいと思います。嫌々やれば、できることでさえも、途中で挫折してしまいます。
人って、たしかに脳で考え、脳で感じて、すべてそこが肝心かなめのところです。ある人がチェンソーで指を切ってしまったそうですが、あるとき、ないはずの指先が痛いと感じたそうです。なくなっても感じということは、おそらく、脳でそのように感じてしまったということのようです。
もちろん、いくら痛いといわれても、ないところのものを治療はできませんから、医者にも行かなかったそうですが、しばらく経ってから痛みはなくなったそうです。この話しを聞いたときには、人というのは脳がすべてを取り仕切っているのだと思いました。
だから著者は、「嫌い」「面倒くさい」「つまらない」などのネガティブな感情は脳にとっては有害だといいます。まさに、「負の感情で自分を攻撃すれば雪崩式に脳が劣化していくシステムが存在していると私は考えています。その代表的な例が、脳の神経細胞が死減していき、脳が萎縮し、記憶障害などを発症する認知症です。」と書いています。
だとすれば、ネガティブな感情で生活するよりは、ポジティブな感情で毎日生活することを脳が求めているということになります。
つまり、私が笑顔でいることがさらに笑顔になる秘訣だと多くの人たちに話していますが、そうすればさらに笑顔の輪が広がります。
下に抜き書きしたのは、第4章「祈る力」に書いてあったものです。
たしかに、祈るということは大切なことですが、目に見えないことを説明するのはとても難しいことです。だいぶ前に、アメリカの医学雑誌に載っていた「カリフォルニア大学医学部の心臓外科の専門医が行った研究」で、場所はサンフランシスコ総合病院の集中治療室ですが、無差別に400人の患者を2組に分け、高度な心臓の治療を行ったそうです。そこで1組の200人についてだけ、その治療が成功し、もとの健康な体に戻れるようにと、アメリカ全土から無作為に選んだ人々に1日3回のお祈りをささげてもらったそうです。そして、別な組の200人については祈らないということで、その結果も載っていました。
それを聞いたときも、たしかに祈るということの不思議さを感じましたが、ここに抜き書きしたものもなるほどと思いました。
(2025.1.23)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 定年後が楽しくなる脳習慣(潮新書) | 加藤俊徳 | 潮出版社 | 2018年4月20日 | 9784267021299 |
|---|
☆ Extract passages ☆
祈りの形に目を向けると、両手を合わせて瞑目していることがほとんどです。両手を合わせることで何が起こるのでしょう。人は両手で火を使い、道具を使いこなすことで進化してきました。両手を合わせた瞬間、左脳と右脳の「両脳覚醒」が起こります。普段私たちは、体の中心を意識しません。手を合わせることで、「両脳覚醒」とともに体の正中線に意識が向けられます。脳の正中線上には、自律神経の中枢で、ホルモン産生の現場の視床下部があり、松果体や下垂体などホルモンと神経の中枢が位置しています。これだけを考えても、祈りには脳を動かす原理が隠されていると考えることは容易です。
実際に、脳の働きを知らなくとも、両手を体の正中に合わせ目を開じるだけで、外の世界をオフにして「自己」に戻ることができます。
(加藤俊徳 著『定年後が楽しくなる脳習慣』より)
No.2387『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』
図書館から借りてきて、この本を読むまではまったく気づかなかったのですが、読み始めてすぐに、No.2361『国道沿いで、だいじょうぶ100回』を読んだことを思い出しました。
内容は違いながら、出てくる人たちは家族で、行動パターンもほとんど同じような感じでした。それでも、引きつけられるから、不思議なものです。しかも、ページの間に写真がはさまれているのも同じで、今回は東京駅の前で、3人で笑っている写真でした。
その写真を撮ったのがカメラマンの幡野広志さんで、血液ガンなのに、その明るい前向きの言葉が素敵でした。幡野さんが「生牡蠣だって食中毒になるかもしれないけど、みんな食べてるでしよ?おいしいものにはリスクがあって、楽しいことにもリスクがあるんだよ」と言うと、著者は「幡野さんは楽しい方を選んでるんですね」と言います。すると幡野さんは「うん。外で好きな人に会って、好きなことして、好きな写真撮って。それで寿命が多少縮んでも、あんまり気にしないな」とガハハと豪快に笑うんです。
わたしも、こういう生き方には大賛成で、甘いものは身体に悪いといわれても、毎日お抹茶をいただきながら和菓子を食べています。それをSNSに流すと、そんなに毎日甘いものを食べて大丈夫ですかというコメントをいただくのですが、病院で生活するような節制をして、長生きするよりも好きなものを食べて、楽しいことをして生きたいと思ってます。
幡野さんも、病院の減菌室にいるような生活なんて、そんなの、つまらん人生ですよといいます。私もそう思います。
著者自身、中学2年のときに父親が急性心筋梗塞で亡くなり、高校1年生のときに意識不明の重体で6時間もの大手術で一命をとりとめ、下半身の感覚をすべて失い、車イスの生活になり、2年間も入院したそうです。そんなこんなでなかなか勉強ができず、母親のことを考え関西学院大学の「社会起業学科」を志望校に選んだそうですが、模試の結果は合格確率5%以下だったそうです。
それでもあきらめきれず、たまたま知り合いの接骨院の院長先生に英語を教えてもらうことになり、先ずは500の英文を全部暗記しろといわれました。ところが文法がまったく理解できず、また院長先生に相談すると、「わからん文法はその本で調べろ」と言われます。そして、「そんで、俺に説明できるようになれ」と言います。著者は、わたしが理解したならば、それでいいのではないかというと、先生は、「アホか。患者に説明できないけど、参考書読んだから大丈夫ですっていう医者に、手術させるか?」と言い放つのです。
これは名言です。知識というのは他の人に説明できるようになり、理解が深まります。
私もお茶を習っていたときには、初めのころはなぜこのような所作が必要なのか理解できなかったのですが、たまたま先生がいないときに代わりに教えたりすると、すっと理解できました。つまり、人に教えることで、わかることもあります。
だから、この話しをみて、なるほどと思いました。そして、本をただ読んだだけでは理解できないことも、このような『本のたび』に書きとめたり、人に話したりすると、よく覚えています。だから、よく家内にも話すのですが、それも大切なことだと思います。
そして、高校3年生の秋ころにはこの500の英文をすべて暗記し、その他の教科は漫画「ドラゴン桜」(講談社)の全巻セットを渡され、それを読んだそうで、それで志望大学の学科に合格したというからすごいと思います。
やはり、できるとかできないとかいう前に、やってみることです。
下に抜き書きしたのは、「奈美にできることはまだあるかい」に書いてあったものです。
著者の4歳下の弟、良太は生まれつきダウン症という染色体の異常で知的障害もあり、いっしょに滋賀県のおごと温泉旅館に1泊したときの話しです。これを読みながら、いろいろな障がいもその人の個性だと思いました。
(2025.1.20)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった | 岸田奈美 | 小学館 | 2020年9月28日 | 9784093887786 |
|---|
☆ Extract passages ☆
良太の場合鍵付きロッカーやボタン式の水道の仕組みがわかりづらいので、ひとりで大浴場に行くのはちょっとむずかしい。
それで、露天風呂付きの部屋にしたのだが、良太は朝も夜もずーっと、プカプカ浮いていた。海坊主のようだった。
さらに感動したことがあった。良太は本当に、みようみまねでちゃんと生きてきたんだなと思った。
わたしが浴衣着てるの見て、自分で浴衣を着ていた。
わたしが懐石料理のお鍋をつくってるのを見て、自分でお鍋をつくっていた。
経験がないことも、おそれず、挑戦する。失敗するはずかしさとかも、良太にはない。
もっと身近なたとえをすれば。言葉が通じない国に行ったとしても、良太はうまくやっていけるんだろうな。頼もしいな。
(岸田奈美 著『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』より)
No.2386『編集を愛して』
副題が「アンソロジストの優雅な日々」で、著者はこのアンソロジーを、「そう。詩歌集ゃ詞華集とあるように、もともとは詩歌を集めたものから始まっているようなのだ。日本で言えば、「万葉集」がそうだ。そして、「古今和歌集」も『百人一首」もアンソロジーの一つだろう。最近は少なくなったが、文学全集、教養全集、一人の作家の選集・短編集・エッセイ集のようなタイプのアンソロジーが多くの読者を獲得した時代もあった。その後、あるテーマに沿って、いろんな書き手の小説やエッセイを集めたものが、多様なジャンルで編まれるようになった。」と書いていて、その前に辞書の抜書きをしています。
そういえば、その後に、「音楽業界の人の話だと、日本ほどコンピレーション、とりわけベストアルバムが好きな国はないという。あるアーティストのファンは折々のニューアルバムをすべて買った上にベストも購入する。それなりに好きな人は、ベストアルバムだけを買う。こうして、人気アーティストのベストアルバムはミリオンセラーになるのだ。こうしたアンソロジー好き、コンピレーション好きという傾向は、日本文化に根ざしたもののような気がしている。食文化にたとえれば、会席料理や幕の内弁当の考え方と通底しているのだ。ちょっとずついろんなものを味わいたいという欲求から始まり、それらをコンパクトに収めようとするところまで、似通っているではないか。」とも書き、なるほどと思いました。
しかし、今や時代がかわり、音楽も好きな曲をスマホで単品買いするようになりました。あるいは、CDが出ないものもあり、スマホで聴いた曲をそのままスマホで買うことも多いようです。そうなると音楽環境もだいぶ違ってきます。
私自身のことを考えても、昔は音楽ジャンルのベストアルバムなどをたくさん集めましたし、全集本も揃えたりしました。そういえば、学生の時、神保町に本と引き換えできるパチンコ屋があり、それで昭和45年から発酵された筑摩書房「日本文学全集 全70巻」を揃えたこともありました。
しかし今は、置く場所のことや管理も難しいので、なるべく図書館で借りてくることにしましたが、昔は私設図書館をつくりたいというのも夢のひとつでした。
だから、迷うことなく、この本も借りてきましたが、借りてきた後で山新の読書欄(2025年1月12日朝刊)にこの本が取り上げられていたので、びっくりしました。そういえば、昨年末に読んだ No.2379『庭に埋めたものは掘り起こさなければならない』齋藤美衣著、も同じ読書欄に載ってました。もともと、ベストセラーになったり、誰かが取り上げたから読むということはほとんどありません。
さて、著者は、今まで500冊近くの本に関わってきたそうで、その本のなかには、私が読んだものも多くありました。たとえば、井上ひさし『吉里吉里人』や『ちくま文学の森』などはすぐ思い出しましたが、まだまだありそうです。
この本のなかに、著者自身のことで、「僕は、貧乏性というか、転んでもタダでは起きないというか、せこい性格なのだ。例えば、四月の初めに通勤途上でオートバイに接触し、道路に叩きつけられた時も、とっさに思ったのは「ああ、これであの原稿書けていない言い訳ができる」だった。背骨の横突起骨折で痛みが4週間もとれなかったのだから、言い訳ぐらいでは割が合わないのだが。仕事をしていて辛くなったり、人間関係で面倒になったりしても、どこかで楽しまなければ損だと思うのだ。」とあり、そういえば、私もそうかもしれないと感じました。
でも、そのような貧乏性も楽しんでいて、たとえばトイレットペーパーをこれだけ少なく使えば、10年ぐらい経つと木の1本分ぐらいにはなるかもしれないなどと思っています。たしかにせこいかもしれませんが、湯水のように使うことは、私にはできそうもありません。
下に抜き書きしたのは、第4章「人を集めて何かを編む」のなかの「路上観察学への招待」に書いてあったものです。
私もその当時の写真を見てびっくりしましたが、あの無用にも思える階段を初めて見たときの印象が書いてあり、ちょっと懐かしく思いました。
私も写真を撮るのでよくわかりますが、同じものを見ていても、その切り取り方でだいぶ印象がかわるので、目玉の修練は大切です。でも、その目の付け所が編集でも生かされているように思います。
(2025.1.17)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 編集を愛して | 松田哲夫 | 筑摩書房 | 2024年10月5日 | 9784480816948 |
|---|
☆ Extract passages ☆
街を歩くのに理屈はいらない。軽やかな足どりと旺盛な好奇心があればいいのだ。
しかし、都市というヒトやモノの洪水の中から、面白いものを探しだそうと思ったら、少しばかり日玉の鍛練が必要だ。それには、まず、なるべく沢山歩くことが一番なのだが、ただ闇雲に歩いていても、日玉が活性化するわけではない。時には、秀れた都市ウォッチャーたちの目玉の動かし方に学ぶことも必要らしい。……
この学が対象とするのは、路上から観察できる木林羅万象。特に、その中のズレたもの、おかしなもの、不思議なものを主に探索するので、"学"というよりは街歩きが一層おいしくなる、都市の新しい遊び方とも言える。
(松田哲夫 著『編集を愛して』より)
No.2385『大観音の傾き』
この小説は、河北新報の2024年4月7日から9月29日までの毎週日曜朝刊に連載されたものです。
私はこの表紙の写真を見て、会津若松の大観音ではないかと思ったのですが、小説のなかに出てくるショッピングモールがそこにはないので、よく観音さまの顔を見ると違っていて、おそらくは仙台大観音ではないかと思い至りました。そこだとすぐ近くにイオン仙台中山店があるので、小説のなかに登場する地形と似通っています。
私は何度も仙台には行っているのですが、一度もそこには行ったことがなく、先月の12月にも近くまで行き、行って見ようかと思ったのですが、仙台に住む孫の学校からの帰宅時間が迫っていたので、行くことはできませんでした。
でも、考えてみれば、これは小説なので実在の仙台大観音とは違うはずで、河北新報によれば「仙台に実在する高さ百メートルの大観音をモチーフとした小説です。毎週日曜、読書面(「東北の文芸」面)での連載となります。樋口佳絵さんご担当の挿絵にも、ぜひご注目いただけたらと思っています。」とあり、あくまでも架空の話しということです。
それにしても、実在の観音さまが本当にあった東日本大震災のときに傾いたという話しをその地方紙に載せていいのかと思いました。しかも、12月21日に河北新報社本社ホールで、大観音の傾きトークイベントがあったそうで、翌日の河北新報の朝刊に載っていました。そのときは、挿絵担当の樋口佳絵さんも参加され、著者の山野辺さんが作品の1部を朗読したそうです。この本には、挿絵はありませんので、機会があれば河北新報の挿絵を見てみたいと思ってます。
もともと著者は福島県の生まれで、宮城県で育ったので、この小説に登場する地域はなじみのあるところばかりです。
印象に残ったのは、沢井さんが、故郷の双葉の話しをしたときに、「途切れてしまった常磐線も、いずれ復旧するはず。除染も進んで、また街に人が住めるときがくるかもしれない。両親はいま郡山にいるんだけど、暮らしも落ち着いてきたから、もう戻ることはないだろうって言ってる。わたしもきっと、ここで生きていくんだろうなあ。だけど、故郷の街が少しでも復活してくれたらっていう願いもあるよ」と言い、主人公の修司は、「話を聞きながら、いつか自分も常磐線に乗って、その地を訪ねてみたいと感じていた。」と考えます。
実は、私もこの復旧した常磐線に乗りたいと思って、昨年の10月2日に「ひたち13号」に乗ることにしました。このときは大人の休日倶楽部パスを利用して、米沢駅から仙台駅まで乗り、そこから秋田新幹線で秋田駅に行き、翌日の「いなほ8号」に乗り、新潟駅から東京駅に行き、乗る予定でした。ところが羽越本線が豪雨のために不通になり、しかたなく、いったん青森駅から東京駅まで戻り、さらに品川駅から常磐線に乗り、仙台駅までというコースに変更さぜるをえませんでした。まさに、常磐線に乗るためだけのとんでもないコース変更でした。それでも双葉付近を通るときには、私自身の知り合いもいたことがあり、そのときのテレビで見た震災の記憶が蘇りました。
下に抜き書きしたのは、今の若者たちがなかなか異性と知り合う機会がなかったり、結婚できないという心情をとらえていると思ったフレーズです。
そして、最後に思い切って「今度の七夕、よかったら一緒に行きませんか」と誘うと、「ほかに一緒に行く人がいるんだ」と断られてしまいます。それをきっかけにして、町外れの忘れられたようなところで、一人で暮らすことを決断します。そこでこの小説が終わってしまいます。
小説というのは、あまり抜書きするようなところもなく、これを選びましたが、本来は読んでいただくのが一番です。
ぜひ機会があればお読みいただければと思います。
(2025.1.14)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 大観音の傾き | 山野辺太郎 | 中央公論新社 | 2024年12月10日 | 9784120058608 |
|---|
☆ Extract passages ☆
誰かと親しい問柄になりたいと望みつつ、ずっとかなえられずにいた。学生時代に、いいなと思う人は何人かいたけれど、傷ついたり傷つけたりすることへの恐れもあったし、どうせ自分なんか駄目だと卑下する思いもあった。距離を縮めることができず、もしかして、と可能性の萌芽を感じたときにはむしろ自分のほうからとっさに遠ざかってしまったものだった。おのれへの自信がもてず、だから人に対して臆病になってしまう。そんな自分の弱さが身にしみて、苦しく感じる夜もある。変化を求める情念が、行き場を見いだせないまま胸の奥にくすぶっていた。
(山野辺太郎 著『大観音の傾き』より)
No.2384『tupera tupera のアイデアポケット』
著者のtupera tuperaというのは、2人組のクリエイティブユニットだそうで、絵本だけでなく、イラストや商品の企画デザイン、さらにはテレビや演劇の仕事もしているそうで、まさにマルチな活動をしているそうです。
この本では、本をつくるアイデアの出し方として、「中川 この本をつくるにあたって、これまでの作品を改めて振り返ってみたら、私たちのアイデアの出し方は大きく2つあるなと思いました。……中川 「コトバ」。言葉あそびやダジャレ的なもの。つくるもののタイトルなど、言葉あそびから入るものがあります。亀山 その考え方は、絵本でもたくさんあるよね。もう一つは? 中川 「カタチ」。ふつうに形を見るだけじゃなくて、ちょっと見立てる。「あれ?。これってこっちの角度から見るとこんなふうに見えない?」ということを考えたりして。亀山 なるほど。おもに「コトバ」と「カタチ」というのが僕たちのアイデアの出し方の大きなポイントです。」と「はじめに」のところで書いています。この中川と亀山というのが著者の名前で、その掛け合いのなかで話しが進みます。
つまり「コトバ」と「カタチ」から入るということですが、これはとても参考になると思います。子どもたちと遊んでいると、どこでもできるのが「しりとり」で、著者たちも『うんこしりとり』という絵本を作っています。そこでは「こいぬのうんこ→こうしのうんこ→こどものうんこ→こうちょうのうんこ→こっそりうんこ→こおったうんこ→こいのぼりのうんこ……」と続くそうです。「こ」というのは意外とつくりやすいし、子どもたちにとっては「うんこ」のつくドリルなどがあるぐらいなじみのキーワードです。
このような文字遊びは、車などの移動中でもなんの準備がなくてもできるので簡単ですが、「カタチ」のあるものは大きさにもよりますが、どこでもできるとは限りません。でも、この本を読むと、たとえば私も子どものころには河原で何かに似ている石を探して遊んだり、木の枝を使って、何かを見立てて遊んだ記憶があります。ただ、今は勝手に河原から石を拾うことも野山で植物を採取することもなかなかできない時代です。
だとすれば、この本に書いてあることで遊ぶことはできます。たとえば、このなかの「仕事であそぶ」にあったものですが、それは西鉄久留米駅近くのフリースペース、久留米シティプラザという激情の1階部分だそうです。そこに「カタチの森」ということで、「亀山 丸三角四角のカタチを組み合わせて、動物や植物を表現しています。「カタチ」というのは人間のそれぞれのカタチ、関係のカタチということも意味していて。老若男女、多種多様な使い方ができるいろんなカタチがこの空間から生まれたらと。中川 この柱のように立っている三角柱が回るんですよ。そろえる面の角度に
よって風景が変わります。動物型の家具もデザインしました。親子連れが食事をしたり絵本を読んだり、中高生が宿題をしにきたり、イベントに使われることもあるし、商店街の会合をすることも。地域の人たちによって、カタチの森がどんどん育っていってくれたらと思います。」と書いてあり、これからのフリースペースも誰かが企画をして作ってしまうというよりは、地域の皆が参加してみんなで作り上げるということがこれからは大切だと感じました。
下に抜き書きしたのは、「参加が楽しくなる ワークショップ」にあったものです。
これは、茶道のなかにもあり、お茶って強い縛りのなかで作法していると思う方も多いと思いますが、時には暑くてとか寒くてどうしようもないときがあります。そんなときには、融通無碍で流れを変えてしまうこともあります。また、昔はなかったんでしょうが、クリスマス茶会というのを何度もしていて、お菓子も「聖夜」という菓銘を使うこともあります。
つまりは今の時代に合わせることも必要で、これからはもしかして、ハロウィンに仮装をしてお茶会をするようになるかもしれません。
(2025.1.12)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| tupera tupera のアイデアポケット | tupera tupera | ミシマ社 | 2024年10月23日 | 9784911226100 |
|---|
☆ Extract passages ☆
亀山 そして、キーワードから自由にイメージを広げて、ベースのトットラに色を塗ったり顔を描いたりして各自仕上げていきます。
中川 最初のくじ引きで自分がつくる方向性を勝手に決められちゃうことで、みんな迷いなくつくり始めます。自由でなんでもいいよと言われても何つくっていいかわからないですよね。適度な縛りがあるからこそ、個性が出しやすく、自分の想像を超えるものができあがります。
(tupera tupera 著『tupera tupera のアイデアポケット』より)
No.2383『インドの正体』
おそらく、一般の人たちにとっては、インドというと思い出すのはお釈迦さまが生まれたところとか、マハトマ・ガンディーがインドの独立をしたこととかではないかと思います。あるいは、今、世界一の人口を抱える国というもあるかもしれません。また、旅行好きな人たちにとっては、インドというのは好き嫌いのはっきりと分かれる国というのもあり、私はどちらかというと好きで、5~6回ぐらいは行ったと思います。
そのなかでも一番印象に残っているのは、2012年12月5日から13日までのインド仏跡の旅で、これは岩波文庫から出ている『ブッダ最後の旅 大パリニッバーナ経』中村 元 訳、を読みながら、その足跡を追う旅でした。ときどき通訳の方をお願いし、なるべく一人で旅をしましたが、いろいろな出会いがありました。
それ以前にもインドにネパールの友人と仏跡をまわったことがあり、もし、彼がいなければ今ここにいないというような経験もしました。だから、インドの怖さとか不思議さとかも知ってしまうと、インドを理解するのは一筋縄ではいかないと思います。そういう気持ちもあって、この本を読むことにしました。
今でも、インド人にとってはマハトマ・ガンディーは、「インドには誇るべき思想や理念のシンボルがある。インドの政治指導者たちが、事あるごとに世界に向けて強調するのが、「ガンディーの国」というアピールだ。非暴力を実践した平和主義者であり、宗教間の融和を説いたマハトマ・ガンデイーは、インドのモラル、良心を体現する偶像として位置づけられている。1998年の核実験、中国やパキスタンに対する軍事力増強と対決姿勢、モディ政権下のヒンドウー・ナショナリズムとマイノリティ弾圧といった動きは、これとまったく矛盾するように思えるかもしれない。」ということです。
私も行ってみて分かったのですが、「ガンディーの日」があり、毎年10月2日は国家の父マハトマ・ガンディーの生誕記念日で、休日になっていました。私はこの日に南インドにいたのですが、お店が休みなので買いものも食べることもできず困りました。その日のテレビを見ていると、今でも絶大な人気があり、モディ首相なども初代首相のネルーの宥和的な政策を否定してますが、ガンディーには限りない称賛を与えているのです。
たしかに、世界各地で戦争や紛争が起こっている状況からみると、今こそガンディーのような平和主義者がいてほしいと思いますが、ではインドでは紛争がないのかというとそうではなく、先の抜書きのなかにもあるように、差し迫った問題もあります。
よく、インドというと、日本人は「カースト」の国だという認識もありますが、じつは、「インドにおけるカーストは「生まれ」であり、ひとびとは長く、みずからの置かれたその「生まれ」を甘受して暮らしてきた。それはさまざまな矛盾を抱えた巨大な国のなかで、社会を安定化させる装置として、つまり社会秩序として機能してきたのではないか。だとすれば、現代のわれわれの目線からは、議会や政府の失政、あるいは不作為に映る貧困や差別が、インドの誇る民主主義制度と共存してきたとしても不思議はない。」と著者も書いていますが、私の理解では家業と深く結びついていて、それに護られているという側面もあります。
たとえば、クリーニング屋はクリーニング屋になる、運転手は運転手になる、というように、いわば決められていることで将来の生きる術を身につけるということです。ただし、現実問題としてお金や食物などを人からもらって生活する人たちにとっては、そこから抜け出すことは非常に難しいのです。なりたい仕事につくということは、いろいろな障がいがあり、大変なことで、だからもともとなかったITなどの仕事は、そのようなしがらみがなく、誰でもなれるので人気があるのです。自分のカーストから抜け出ることもできます。ただ、結婚とかになると、憲法では禁止されていても、現実にはあると聞いたことがあります。
だから、私の知り合いは、これではとても結婚できないと思い、国外に出たのですが、子どもが生まれると、仕方ないということで認められて帰国しました。その子どもたちも成人しましたが、今でもときどきその違いを感じることがあると話してくれたことがあります。
下に抜き書きしたのは、第4章「インドをどこまで取り込めるか?」にあったものです。
おそらく、最近のインドを取り上げるときに多いのがこのような話しで、特にこれからはインドを抜きにして国際関係を論ずることは難しいと思います。そういう意味では、とてもわかりにくい国ではありますが、しっかりと理解しておかなければならないと思います。
(2025.1.9)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| インドの正体(中公新書ラクレ) | 伊藤 融 | 中央公論新社 | 2023年4月10日 | 9784121507938 |
|---|
☆ Extract passages ☆
実際のところ、この20年ほどの世界は、全体としていえば、インドの望むような多極化に向かった。アメリカの覇権はもはや絶対的なものではなくなったが、中国がアメリカの地位に取って代わったわけでもない。かつての栄光を夢見るプーチンのロシアは、ウクライナで無謀な戦いをはじめたが、アメリカと西側世界は、これを簡単に蹴散らすことができなかった。各国の国力が拮抗し、せめぎあいがつづく世界で、どの国にとっても、インドの戦略的価値が増大した。
これまでにインドは世界のすべての主要国、新興国と「戦略的パートナーシツプ」関係を宣言し、関係を拡大深化してきたが、いずれもインドが頼んだのではなく、各国から「言い寄られた」、という印象が強い。どの国も交渉で大幅な譲歩をしてでも、インドを引き込むことに躍起になった。
(伊藤 融 著『インドの正体』より)
No.2382『面白くて眠れなくなる理科』
「面白くて眠れなくなる」というのは、私の興味のある理科に関してはそうでしたが、あまり関心のないことについては読んでいても眠くなることもありました。
それでもぜんぶ読んでしまうと、なるほどという気持ちになり、このように難しいことを簡単に説明してもらうとわかりやすいと思いました。そういえば、井上ひさしの座右の銘である「むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく、ふかいことをおもしろく、おもしろいことをまじめに、まじめなことをゆかいに、そしてゆかいなことはあくまでゆかいに」という言葉を思い出しました。
たとえば、今まで「溶ける」ということに関しても、なんとなくわかっているような気持ちでいましたが、「溶けること(溶解)は自然現象の中で大きな役目を果たしており、人間の生活と生産の中でも、さまざまな形で利用されています。家庭生活における「溶解」の大きな利用の一つは、食物の味つけに食塩や砂糖を使うことです。食塩や砂糖が水に溶けなければ、辛い、甘いなどの味は感じられません。漬け物に食塩を使うのは、水に溶けた食塩が微生物の繁殖や植物の組織に及ぼす微妙な働きを利用しています。また、着物や服のえりなどの汚れをベンジンでふき取るのは、からだから出る皮脂がベンジンに溶けることを利用しています。」と書いてあり、まさに溶けるということはとても大切なことだと理解できます。
よく、地球は水の惑星、という表現がありますが、水が「非常に多くの種類の物質を溶かす性質を持っていること」だからで、そのことがすべての生命の誕生に寄与していると考えることができます。このように考えると、「溶ける」ということがいかに大切なことかということがわかります。
どうも、私はアイスクリームが溶けるのと、生命体が誕生するのと同じレベルだとはなかなか信じられませんでした。でもよく考えてみると、溶けるということだけを考えれば、同じことです。
この本のなかで、磁石について書いてありましたが、「磁石の「磁」は、もともとは中国で「慈」という字でした。「慈石」とよんでいたのです。「慈」は「慈しむ」という言葉通り「大切にする、いとおしむ、かわいがる」という意味です。磁石が鉄を引きつける様子を、まるで母親が子どもを抱くようにやさしくかわいがっている様子にたとえたのです。」とあり、なるほどと思いました。
「磁」と「慈」はよく似ていますが、このような関連性があるとは思いもしませんでした。ところが、聞いてみると、なるほどというよりは、これで一生忘れることもないはずです。
下に抜き書きしたのは、Part 2「世界はふしぎに満ちている」のなかの「人類の工夫の所産――イネ」に書いてあったものです。
だいぶ前に、地元のJA婦人部の方々にイネの話しをしたことがありましたが、そのときのことを思い出しました。まさにイネは、品種改良の歴史でもあります。もともとは熱帯の植物ですから、寒いところは苦手なのですが、今では北海道でも栽培できるようになりました。ところが、最近の猛暑の影響などで不作が続き、これからは、もう一度暑さに強い品種を目指して品種改良をしなければならないそうです。
このような話しを聞くと、イネも人間との関わりで右往左往しているのではないかと思ってしまいました。
(2025.1.6)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 面白くて眠れなくなる理科(PHP文庫) | 左巻健男 | PHP研究所 | 2016年8月15日 | 9784569765945 |
|---|
☆ Extract passages ☆
野生のイネは自分の花粉がめしべについても受精せず、ほかのイネの花粉がめしべにつくと受精する「他家受粉」という性質を持っています。これは常にほかのイネの花粉がついて種子が雑種になるようになっているのです。
そのほうがいろいろな性質の種子ができ、環境の変動や病害虫などが原因で一斉に死に絶えるリスクが小さくなります。つまり、どれかが生き残るという点で、野生のイネにとっては大切なことなのです。
しかし、イネを栽培する人類にとっては、やっかいな性質といえます。なぜなら、雑多な種子ができてしまい、均一な性質の種子ではなくなるからです。
長い栽培の歴史の中で、この性質は完全になくなり、花が咲くとすぐに自分の花粉がめしべにつく「自家受粉」をして受精し、種子ができるようになりました。
そのため、すべてが同じ性質を持つイネになり栽培しやすくなりましたが、そのぶん環境の変動や病害虫などに弱くなったともいえるのです。
(左巻健男 著『面白くて眠れなくなる理科』より)
No.2381『人生のことはすべて山に学んだ』
私も高校生のころは山岳部だったので、毎週のように山に登っていました。そして登る時間がとれなくなってからは、ビーパルなどを読んで、野外生活の楽しさなどを知識として味わっていました。
これらの本は、自宅を改築したときに大量に処分してしまい、ほとんど残っていませんが、今でも椎名誠さんの本に書かれたイラストなどを思い出します。どちらかというとほのぼのとして、ヘタウマの絵が多かったようです。
また、似たような題名の本で、ロバート・フルガムの「人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだ」などもありますが、いろいろな場所で学ぶこともできますし、自分の好きなところで学ぶということも大切なことです。
この本は、もともとは海竜社から2015年11月に刊行された単行本「人生のことはすべて山に学んだ 沢野ひとしの特選日本の名山50」を改題し、加筆修正して文庫化したものです。生まれは1944年ですから、私より5歳ほど上ですが、「文庫本あとがき」で「さてこの十年ほど山から下りて里のあたりをぶらぶら歩いている。設備の良くなったテント場で、息子や孫たちと、2、3日滞在している。滞在中、山里の歴史を聞いたり本で調べたりすると、これまで知らなかった土地の文化に驚く。長野県は満州開拓団が多かったことを知り、その碑も各地にある。若い頃は山の頂上にしか興味がなく、クライミングに夢中になっていた。だが歳を取ると、しだいに山の麓のことを知りたくなってくる。」と書いています。
また、私のような歳になってくると、「山のコラム9」のなかに書いてあった「山で事故が起こるのは、登りより下る時のほうが比べられないほど多い。体が萎えてくる頃の転落事故が後をたたない。山では最後の平らな道へ下りてくるまで油断しないことだ。……下りで膝が震えだしたら、ストックが役に立つ。カーボン素材を使った軽量モデルがたくさん出ているが、中高年登山者にとっては必携品と言えよう。さらに膝のサポーターも強い味方になる。この2つであと10年先まで山でがんばれるはず。」とあり、私ももう少しはがんばれそうと思いました。
そういえば、昨年の7月に大雪山の旭岳の麓を歩きましたが、もしやと思い持っていった膝サポーターが、とても役立ちました。これはだいぶ前に整形外科に受診したときにもらったもので、たしかに膝が痛くなったときには有効です。もともと小さいので、リックに入れて行っても邪魔にはなりません。
そのときも感じたのですが、著者も「山登りの良いところは、 へとへとになっても一歩前に進めば、いつかかならず頂上が現れることだ。誰に対しても裏切ることなく達成感を山は与えてくれる。杖をついて登ってきた年輩者のザックを見知らぬ人がいたわるようにして下ろしている。小屋付近からの眺望は、どっしりと雪を被った富士山や南アルプス、大菩薩峠に奥秩父、奥多摩とまるで山々が「見てください」と自慢げに連なっている。」書いていますが、たしかに一歩一歩で風景が変わり、お花畑を進んでいると、自然と歩けます。
ただ気を付けなければならないのが、宿に着いてから痛みが出てくることです。だから、最近はなるべく長距離は歩かず、時間も早めに下山するようにしています。そして、もしもう少し先に行きたければ、翌日に体力の回復を待って行くようにしています。やはり、絶対に無理はしないことです。
下に抜き書きしたのは、第5章「宝物が隠されている山」にあった言葉で、たしかにそうだと思いました。
私は、最近は一人旅をする機会が多くなり、それもなるべくなら電車に乗ってみたいと思うようになりました。電車だと勝手に目的地に運んでもらえるし、その土地の人たちが乗ってくると方言なども聞くことができます。駅弁を食べる楽しみもあります。風景を眺めながら本を読むこともできます。
一人旅は、誰にも邪魔されずに自分の時間を持つことができます。
ますます、限りある時間を、有効に大切に使いたいと思ってます。
(2025.1.3)
| 書名 | 著者 | 発行所 | 発行日 | ISBN |
|---|
| 人生のことはすべて山に学んだ(角川文庫) | 沢野ひとし | KADOKAWA | 2015年7月25日 | 9784041092064 |
|---|
☆ Extract passages ☆
都会の喧噪と騒音に慣れた者にとって山は沈黙の世界だ。山に入るとその静けさに耳を傾ける。鳥のさえずり、林を抜ける風の音、植物の匂い、岩のざらつきと、五感が鋭くなってくる。とりわけ一人の時は、自然の持っている緊張と穏やかさが刻々に増大していく
バス停を下りて歩きだすと林の匂い、水の匂い、針葉樹の松の匂い、やがて森林地帯を越えると、硫黄や鉱物、さらに3000mの頂上に立つと大袈裟だが宇宙の匂いさえする。
(沢野ひとし 著『人生のことはすべて山に学んだ』より)
◎紹介したい本やおもしろかった本の感想をコラムに掲載します!
(匿名やペンネームご希望の場合は、その旨をお知らせください。また、お知らせいただいた個人情報は、ここ以外には使用いたしません。)
 タイトル画面へ戻る
タイトル画面へ戻る
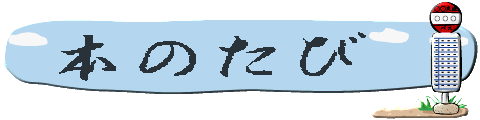
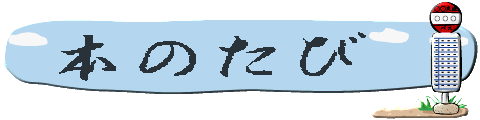
 タイトル画面へ戻る
タイトル画面へ戻る